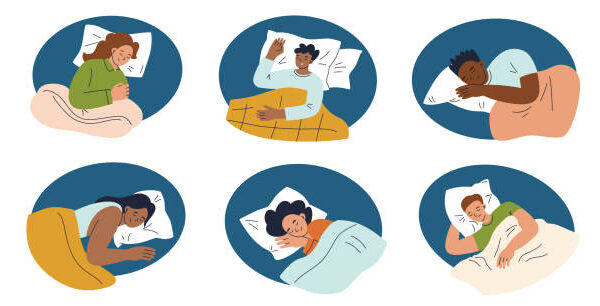「ちょっとしたことで怒りっぽくなる」「気持ちを抑えられずイライラが止まらない」──そんな状態が続くと、自分を責めたり人間関係に悪影響が出たりしてしまいます。
イライラは誰にでもある自然な感情ですが、ストレス・睡眠不足・ホルモンバランスの乱れ・自律神経の不調などが重なると、日常生活に支障をきたすほど強くなることがあります。
中には、うつ病や不安障害、双極性障害など心の病気のサインとして現れるケースもあるため注意が必要です。
本記事では、イライラが止まらないときの原因と考えられる病気、すぐに実践できるセルフケア方法、生活改善の工夫、そして専門家に相談すべきタイミングまで詳しく解説します。
「どうしても抑えられないイライラ」に悩んでいる方が、自分を責めずに安心して対処できるきっかけになるようまとめました。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。
イライラが止まらないときに考えられる原因

イライラは誰にでも起こる自然な感情ですが、止まらないほど強く続く場合には心身の不調や病気が隠れていることもあります。
原因は一つに限らず、ストレスや生活習慣の乱れ、ホルモンバランスの変化、さらには精神的な疾患など多岐にわたります。
ここでは、イライラが続くときに考えられる代表的な要因を整理して紹介します。
- 仕事や人間関係などの強いストレス
- 睡眠不足や疲労の蓄積
- ホルモンバランスの乱れ(月経・更年期など)
- 自律神経の乱れによる心身の不調
- うつ病・不安障害・双極性障害など精神的な疾患
- 血糖値の乱高下や栄養不足の影響
- 薬・アルコール・カフェインなど刺激物の影響
自分に当てはまる原因を知ることが、適切な対処につながります。
仕事や人間関係などの強いストレス
最も多い原因の一つはストレスです。
仕事での過重労働や人間関係のトラブル、家庭内の緊張状態などが積み重なると、心に余裕がなくなりイライラが爆発しやすくなります。
ストレスは自律神経を乱し、交感神経が過剰に働くことで常に緊張した状態をつくります。
その結果、小さな出来事にも敏感に反応してしまうのです。
ストレスを完全になくすことはできませんが、適度に発散し緩和する方法を持つことが大切です。
睡眠不足や疲労の蓄積
睡眠不足や疲労もイライラを強める大きな要因です。
眠りが浅い、睡眠時間が短い、休んでも疲れが取れないといった状態では、脳の感情コントロール機能が低下します。
そのため些細なことでも怒りや不安を感じやすくなります。
また、体の疲れが溜まると心にも余裕がなくなり、イライラの悪循環が生じます。
質の良い睡眠と休養を意識的に取ることは、心の安定に直結します。
ホルモンバランスの乱れ(月経・更年期など)
特に女性に多いのがホルモンバランスの変化によるイライラです。
月経前症候群(PMS)や更年期には、女性ホルモンの変動によって気分が不安定になりやすくなります。
また、出産後の産褥期にも同じような症状が出ることがあります。
これらは病気ではなく生理的な変化ですが、本人にとっては大きな負担です。
生活習慣の改善や婦人科での相談が、不快なイライラを和らげるきっかけになります。
自律神経の乱れによる心身の不調
自律神経失調は、イライラの背景にある代表的な要因です。
ストレスや生活リズムの乱れによって交感神経と副交感神経のバランスが崩れると、心身に不調が現れます。
動悸や息苦しさ、頭痛や胃腸の不快感に加え、感情が不安定になりイライラしやすくなります。
特に不眠や食欲不振と一緒に現れる場合は注意が必要です。
自律神経を整えるために、規則正しい生活やリラックス法の実践が効果的です。
うつ病・不安障害・双極性障害など精神的な疾患
イライラが続く背景には心の病気が隠れている場合もあります。
うつ病では気分の落ち込みだけでなく、焦りや怒りとして表れることがあります。
不安障害では常に緊張しているため、些細な刺激でイライラしやすくなります。
双極性障害では気分の波の一部として怒りっぽさが出ることもあります。
こうした場合は自力での改善が難しく、専門家のサポートが必要です。
血糖値の乱高下や栄養不足の影響
血糖値の変動は感情に大きな影響を与えます。
空腹時や甘いものを摂った後に血糖値が急激に下がると、強いイライラや不安を感じやすくなります。
また、鉄分やビタミンB群、オメガ3脂肪酸などの不足も、脳の働きを乱し感情コントロールを難しくします。
食事内容を見直すことは、不安やイライラを和らげる上で欠かせない視点です。
規則正しい食生活を意識し、栄養バランスを整えることが重要です。
薬・アルコール・カフェインなど刺激物の影響
一部の薬や嗜好品もイライラの原因になります。
例えばステロイド薬や一部の治療薬には副作用として気分の変動があります。
また、カフェインやアルコールは神経を刺激し、一時的に気分が高まってもその後の落ち込みや不安を強めることがあります。
過剰摂取は感情のコントロールを難しくするため、量を見直すことが必要です。
もし服薬や嗜好品の影響が疑われる場合は、医師や専門家に相談することが安心です。
イライラが止まらないときのセルフケア方法

イライラを完全になくすことはできませんが、セルフケアを取り入れることで気持ちを落ち着け、悪循環を断ち切ることが可能です。
感情を抑え込むのではなく、適切に発散しリセットする工夫が大切です。
ここでは、日常生活で手軽に取り入れられる代表的なセルフケア方法を紹介します。
- 深呼吸・瞑想・マインドフルネスを実践する
- 軽い運動やストレッチで気分をリセット
- 生活習慣を整える(睡眠・食事・運動)
- 感情を書き出して客観視する
- 音楽・趣味などで気持ちを切り替える
- 自然に触れる・日光を浴びる
- 「できること」だけに集中する
これらの方法を続けることで、イライラが起きにくい心身の状態を整えることができます。
深呼吸・瞑想・マインドフルネスを実践する
深呼吸は副交感神経を優位にし、体の緊張をほぐす効果があります。
「4秒吸って、6秒で吐く」を数分繰り返すだけで心拍数が落ち着き、イライラが和らぎます。
また、瞑想やマインドフルネスは「今ここ」に意識を集中させ、過去や未来への不安から解放されやすくなります。
一日の隙間時間に取り入れるだけでも効果が期待でき、習慣化することで感情のコントロール力が高まります。
特別な道具を必要としないため、すぐに始められる点も大きなメリットです。
軽い運動やストレッチで気分をリセット
イライラしているときは交感神経が優位になり、体が緊張しています。
その状態をほぐすには軽い運動やストレッチが効果的です。
散歩やジョギング、ヨガなどは脳内のセロトニン分泌を促し、心を落ち着けます。
体を動かすことで「怒りのエネルギー」が発散され、気持ちを切り替えやすくなります。
特に仕事や家庭で座りっぱなしの人は、こまめに体を動かす習慣をつけると良いでしょう。
生活習慣を整える(睡眠・食事・運動)
乱れた生活習慣は、イライラの大きな原因となります。
睡眠不足は脳の感情コントロール機能を低下させ、怒りやすくなります。
食事は血糖値を安定させるようバランスを意識し、過度なカフェインやアルコールは控えることが大切です。
また、適度な運動を取り入れることで自律神経が整い、気持ちが安定しやすくなります。
規則正しい生活リズムを作ることが、イライラの予防につながります。
感情を書き出して客観視する
イライラしているときは頭の中で感情がぐるぐる回り続けます。
そんなときは紙に書き出すことで客観視しやすくなります。
「なぜ怒っているのか」「本当はどうしたいのか」を文字にするだけで冷静さを取り戻せます。
書いた後に「これは本当に大きな問題か?」と振り返ると、不要な怒りに気づくこともあります。
感情を外に出す手段として、とても効果的な方法です。
音楽・趣味などで気持ちを切り替える
音楽や趣味は、イライラした気持ちをリセットする効果的な方法です。
好きな音楽を聴く、楽器を演奏する、絵を描く、料理をするなど、自分が没頭できることを取り入れてみましょう。
感情のエネルギーをポジティブな活動に変えることで、心が軽くなります。
イライラを我慢するよりも、自然に切り替えられる時間を持つことが大切です。
自分に合った趣味を日常に組み込むことが、心の安定につながります。
自然に触れる・日光を浴びる
自然との触れ合いは心を落ち着ける効果があります。
公園を散歩する、木々の緑を見る、川の音を聞くなどは、脳をリラックスさせイライラを和らげます。
また、日光を浴びるとセロトニンが分泌され、気分が安定しやすくなります。
特に朝日を浴びることは体内時計を整え、睡眠の質改善にもつながります。
自然や光を取り入れる習慣は、心身のバランスを取り戻す大切なセルフケアです。
「できること」だけに集中する
イライラしているときは「やるべきこと」に圧倒されていることが多いです。
そんなときは「いま自分ができること」に意識を絞ることが有効です。
目の前の小さなタスクに集中することで、余計な不安や怒りに振り回されにくくなります。
「全部やらなければ」と考えるのではなく、「今日はここまでできた」と区切ることが大切です。
完璧を求めず一歩ずつ進む姿勢が、心を安定させる支えになります。
イライラを悪化させないための生活の工夫

イライラを感じたときに一時的に発散するだけでなく、悪化させない生活習慣を整えることが大切です。
日常の小さな工夫によって心身のバランスを取り戻し、イライラが蓄積しにくい状態をつくることができます。
ここでは、イライラを長引かせず、予防するために役立つ具体的な生活の工夫を紹介します。
- カフェイン・アルコールを控える
- SNSやネガティブ情報から距離を置く
- 完璧主義を手放す思考の工夫
- 小さな成功体験を積み重ねる
- 休養日を意識的に設ける
- バランスの良い栄養を意識する
これらの工夫を取り入れることで、イライラの連鎖を断ち切りやすくなります。
カフェイン・アルコールを控える
カフェインやアルコールは一時的に気分を高める作用がありますが、その後の反動で不安やイライラを強めることがあります。
カフェインは交感神経を刺激し、神経を過敏にさせて睡眠の質を下げるため、感情コントロールが難しくなります。
アルコールも同様に、酔いが冷めた後に気分の落ち込みや焦燥感を引き起こしやすいです。
イライラを予防するには、摂取を控えたり時間帯を工夫することが効果的です。
特に就寝前は避けることで睡眠の質が向上し、感情の安定につながります。
SNSやネガティブ情報から距離を置く
SNSやニュースからの情報は、便利である一方でネガティブな影響を与えることも少なくありません。
他人と自分を比較して劣等感を抱いたり、ネガティブなニュースに触れて気分が沈むことがあります。
イライラを防ぐためには「情報を取る時間を決める」「見ない時間をつくる」といった工夫が有効です。
必要な情報だけを取捨選択することで、心を守ることができます。
特に就寝前はSNSから距離を置くことで、睡眠の質も向上し、翌日の感情安定にもつながります。
完璧主義を手放す思考の工夫
イライラを抱える人の多くは完璧主義の傾向を持っています。
「こうでなければならない」と思い込みが強いと、少しの失敗やズレで強いストレスを感じやすくなります。
そこで「できる範囲でいい」「今日はここまでで十分」と自分に声をかけることが大切です。
柔軟な考え方を持つことで心に余裕が生まれ、イライラの予防につながります。
思考のクセを見直すことは、長期的に感情を安定させるための重要な一歩です。
小さな成功体験を積み重ねる
大きな目標にばかり意識を向けると、できない自分にイライラしやすくなります。
そこで有効なのが小さな成功体験を意識的に積み重ねることです。
「今日は散歩できた」「書類を仕上げられた」など些細なことで十分です。
成功体験を重ねることで自己肯定感が高まり、感情の安定につながります。
自分を認める習慣ができると、イライラが起こりにくい心の状態を育てられます。
休養日を意識的に設ける
毎日忙しく過ごしていると心身が疲れ果て、イライラが爆発しやすくなります。
そこで意識的に休養日を設けることが重要です。
「何もしない日」をあえて作り、好きなことやリラックスできる時間に充てることで、心がリセットされます。
働きすぎや家事・育児の負担を抱え込みすぎないように、休むことも自分を守る行動です。
休養は贅沢ではなく、感情を安定させるための必要な習慣と考えましょう。
バランスの良い栄養を意識する
食生活は心の状態に大きな影響を与えます。
血糖値が急激に上下するような食事は感情の不安定さを招き、イライラを増幅させる原因になります。
野菜・タンパク質・炭水化物をバランス良く摂ることが重要です。
特にビタミンB群や鉄分、オメガ3脂肪酸は神経の安定に役立ちます。
規則正しい食事を意識することで、イライラしにくい心身を作ることができます。
専門家に相談すべきタイミング

イライラは誰にでもある感情ですが、一定のラインを超えると専門家の助けが必要になります。
「性格だから仕方ない」「自分でなんとかしなければ」と我慢し続けると、心身に深刻な影響を与えることがあります。
ここでは、専門家への相談を検討すべき代表的なサインを紹介します。
- イライラが2週間以上続いている場合
- 仕事や家庭生活に大きな支障が出ている場合
- 暴言・暴力など衝動的な行動が出ている場合
- 強い不安や抑うつを伴っている場合
- 「自分では抑えられない」と感じる場合
思い当たる点があるときは一人で抱え込まず、心療内科や精神科、カウンセリングなどの専門機関へ相談することが大切です。
イライラが2週間以上続いている場合
誰でも一時的にイライラすることはありますが、2週間以上続く場合は注意が必要です。
慢性的なイライラは自律神経や脳の働きに影響を及ぼし、放置すると心の病気に発展するリスクもあります。
一時的なものかどうかを見極めるためにも、一定期間以上続く場合は専門家に相談してみましょう。
早期に対応することで、改善も早くなります。
仕事や家庭生活に大きな支障が出ている場合
日常生活に支障が出ている場合は、専門家に相談すべき重要なサインです。
例えば、仕事で集中できない、同僚や家族に当たり散らしてしまう、家事や育児ができないなどが挙げられます。
生活への影響が広がる前にサポートを受けることで、早い段階で改善につなげられます。
「自分が悪い」と責めるのではなく、適切な治療や支援を受けることが解決の近道です。
暴言・暴力など衝動的な行動が出ている場合
イライラが強まると、衝動的な行動につながることがあります。
暴言を吐いて人間関係を悪化させたり、物に当たる、他人や自分を傷つける行動に至る場合は非常に危険です。
このような状態は本人だけでなく周囲にも大きな影響を与えます。
衝動的な行動が見られるときは、早急に専門家へ相談することが安全のためにも重要です。
強い不安や抑うつを伴っている場合
イライラに加えて強い不安や抑うつを感じている場合も要注意です。
これはうつ病や不安障害などの心の病気が背景にある可能性があります。
「気分が落ち込む」「将来に希望を持てない」などの状態が続く場合、専門的な治療が必要です。
イライラだけでなく他の症状も伴っているときは、我慢せず専門家に相談することが大切です。
「自分では抑えられない」と感じる場合
最も重要なのは、本人が「もう自分ではコントロールできない」と感じているかどうかです。
自分なりの工夫をしても改善が見られないとき、それは専門的支援が必要なサインです。
医師やカウンセラーと一緒に原因を探り、適切な治療法を選ぶことで安心を取り戻せます。
「助けを求めること」は弱さではなく、回復へ向けた大切な一歩です。
考えられる病気と治療の選択肢

イライラが長期間続く場合や、日常生活に大きな支障を与えている場合には、心や体の病気が隠れている可能性があります。
単なる性格や気分の問題と捉えるのではなく、医学的に説明できる背景があることも少なくありません。
ここでは、イライラの背後にある代表的な疾患と、それに対する治療の選択肢について解説します。
- うつ病や不安障害によるイライラ
- 双極性障害での気分の波
- 更年期障害・ホルモンバランスの影響
- ADHDや発達特性による衝動性
- 治療法(薬物療法・心理療法・カウンセリング)
原因を正しく見極めることが、適切な治療やセルフケアにつながります。
うつ病や不安障害によるイライラ
うつ病と聞くと「気分の落ち込み」が中心と思われがちですが、実際にはイライラや怒りっぽさとして症状が現れることもあります。
特に男性や若い世代では「抑うつ」より「怒り」として表出するケースが少なくありません。
また、不安障害では常に緊張状態が続くため、心が休まらず、些細な刺激でイライラを感じやすくなります。
このような場合、自分を責めるのではなく病気の一部と理解し、専門家の治療を受けることが大切です。
薬物療法や心理療法で改善が見込めるケースは多くあります。
双極性障害での気分の波
双極性障害は、気分の高揚(躁状態)と落ち込み(うつ状態)が周期的に現れる病気です。
躁状態のときには活動的になりすぎたり衝動的になったりし、その延長でイライラや攻撃的な言動が出ることがあります。
一方でうつ状態に入ると強い無気力や抑うつに苦しむため、本人も周囲も対応が難しくなります。
気分の波によるイライラは本人の努力ではコントロールが難しく、適切な治療と周囲の理解が必要です。
専門医による診断と治療計画のもと、気分を安定させる薬や心理的サポートを組み合わせることが推奨されます。
更年期障害・ホルモンバランスの影響
特に女性の場合、更年期障害やホルモンバランスの乱れがイライラの大きな原因になります。
女性ホルモンの分泌が減少する時期には、自律神経が乱れやすくなり、感情の起伏が激しくなることがあります。
「何にイライラしているのかわからない」と感じるほど、コントロールが難しいのが特徴です。
婦人科でのホルモン補充療法や漢方薬の利用、生活習慣の見直しによって改善できる場合があります。
一人で悩まず、女性特有の症状に詳しい専門医に相談することが安心です。
ADHDや発達特性による衝動性
ADHD(注意欠如・多動症)やその他の発達特性を持つ人は、感情のコントロールが難しい場合があります。
特に衝動性が強いと、イライラがすぐに表に出てしまったり、言葉や行動に結びつきやすくなります。
本人も「わかっているのに抑えられない」と苦しむことが少なくありません。
発達特性によるイライラは性格の問題ではなく脳の働きに関係しているため、専門的な理解が必要です。
カウンセリングや環境調整、場合によっては薬物療法が役立つこともあります。
治療法(薬物療法・心理療法・カウンセリング)
イライラの背景に病気がある場合、専門的な治療が効果的です。
薬物療法では抗うつ薬、抗不安薬、気分安定薬などが用いられ、脳内のバランスを整えることで感情の起伏を緩和します。
心理療法では認知行動療法(CBT)やカウンセリングを通じて、思考や行動のパターンを見直す支援を受けられます。
また、セルフケアと組み合わせることでより高い改善効果が期待できます。
「我慢するしかない」と思い込まず、治療という選択肢があることを知ることが大切です。
家族や周囲ができるサポート

イライラが止まらない状態は、本人だけでなく家族や周囲にも大きな影響を与えます。
しかし、適切なサポートがあれば安心感が生まれ、回復を後押しすることができます。
逆に接し方を誤ると、本人がさらに孤立感を深めてしまうこともあるため注意が必要です。
ここでは、家族や周囲ができる具体的なサポート方法を紹介します。
- 否定せずに気持ちを受け止める
- 安心できる環境を一緒に整える
- 無理に克服させようとせず寄り添う
- 受診を勧めるときの声かけの工夫
- 支える側もセルフケアを大切にする
支える人が正しい姿勢を持つことで、本人にとって大きな安心感につながります。
否定せずに気持ちを受け止める
本人が「イライラして辛い」と打ち明けたときに否定しないことが大切です。
「気にしすぎ」「我慢すればいい」と言ってしまうと、本人はさらに追い詰められてしまいます。
「そう感じているんだね」「大変だね」と共感を示すことで、安心感が得られます。
否定ではなく受け止める姿勢が、信頼関係を強めてサポートの土台になります。
安心できる環境を一緒に整える
生活環境は感情に大きく影響します。
静かで落ち着ける空間をつくる、家事や育児の負担を分担するなど、環境面での配慮が本人を助けます。
また、生活リズムを整えるサポートも効果的です。
「一緒に散歩しよう」「早めに寝よう」といった声かけは無理なく行動につなげやすくなります。
周囲が協力して安心できる環境を整えることは、回復の大きな支えになります。
無理に克服させようとせず寄り添う
「早く治さなきゃ」「気合で乗り越えよう」といった無理強いは逆効果です。
本人はすでにコントロールできないことに苦しんでおり、強制的な言葉はプレッシャーになります。
大切なのは「無理しなくていいよ」「少しずつでいいよ」と寄り添う姿勢です。
小さな前進を一緒に喜ぶことで、安心感と自己肯定感が高まります。
伴走するように支えることが最も効果的です。
受診を勧めるときの声かけの工夫
イライラが続き生活に支障が出ている場合、専門家の受診が必要になることがあります。
その際「病気だから病院へ行け」と強い口調で言うと抵抗感が生まれます。
「一緒に相談してみない?」「少し楽になる方法を探そう」と優しく声をかけることが効果的です。
本人が「自分の意思で相談してみよう」と思えるように促す工夫が大切です。
同行してあげることで安心感も増します。
支える側もセルフケアを大切にする
家族や周囲が疲弊してしまうとサポートを続けられません。
サポートする側も休養や趣味の時間を確保し、自分の心を守ることが必要です。
無理をして支えると共倒れになる可能性もあるため、支援を分担することが重要です。
「自分も大切にすること」が、結果的に本人の支えにもなります。支える人が元気でいることは、最良のサポートになります。
よくある質問(FAQ)
Q1. イライラが止まらないのは病気のサインですか?
一時的なイライラであれば、ストレスや疲れによる自然な反応の場合が多いです。
しかし、2週間以上イライラが続く、日常生活に大きな支障が出る、衝動的な行動が出るといった場合は病気のサインである可能性があります。
うつ病や不安障害、双極性障害、自律神経失調症、更年期障害などでもイライラは症状として現れることがあります。
性格や気の持ちようではなく、医学的な背景があることも多いため、我慢せず専門家に相談することが大切です。
Q2. 生理前や更年期でイライラするのはどうしたらいい?
女性ホルモンの変化によるPMS(月経前症候群)や更年期障害では、感情の起伏が強くなりイライラが止まらなくなることがあります。
この場合、生活習慣の改善(睡眠・食事・運動)やストレス発散法の実践が役立ちます。
さらに、婦人科でホルモン補充療法や漢方薬を相談できる場合もあります。
「体の仕組みによるもの」と理解し、必要に応じて医療機関でケアを受けることが症状緩和につながります。
Q3. 子育てや家庭でイライラしてしまうときの対処法は?
子育てや家庭生活は心身の負担が大きく、イライラが積もりやすい場面です。
完璧を目指さず「できなくてもいい」と思うこと、家事や育児を分担することが有効です。
また、自分の時間を意識的に確保することも重要です。
イライラを我慢するのではなく、深呼吸や散歩、趣味などで気分を切り替える習慣を持ちましょう。
サポートを求めることは決して甘えではなく、健全な選択です。
Q4. 薬を使わずにイライラを抑えることはできますか?
軽度のイライラであれば、セルフケアで抑えられることもあります。
深呼吸や瞑想、生活リズムを整える、栄養バランスを見直すなどが効果的です。
一方、中等度以上で生活に大きな支障がある場合は、薬物療法が必要になることもあります。
「薬を使わずに改善したい」と思う場合でも、まずは専門家に相談し、安全な方法を一緒に検討するのがおすすめです。
Q5. 病院に行くなら心療内科と精神科どちらがよいですか?
心療内科は体の症状(頭痛・胃痛・不眠など)と心の不調が絡むケースに向いており、精神科は主に心の病気全般を専門とします。
イライラが強く日常生活に影響している場合は、どちらを受診しても適切な診断と治療が受けられます。
迷った場合はまず心療内科に相談し、必要に応じて精神科へ紹介してもらうのが安心です。
いずれも「心の専門家に相談する」という行動自体が重要です。
Q6. 食べ物やサプリでイライラを改善できますか?
食事やサプリはイライラ対策に役立つ場合があります。
血糖値を安定させる食事(野菜・タンパク質・複合炭水化物)は感情の安定に効果的です。
また、鉄分・ビタミンB群・オメガ3脂肪酸は神経伝達に関わり、不足するとイライラが強まりやすくなります。
サプリや漢方を活用する人もいますが、効果には個人差があるため、気になる場合は医師や薬剤師に相談するのがおすすめです。
Q7. イライラが睡眠障害や頭痛と関係することはありますか?
イライラと睡眠障害・頭痛は深く関係しています。
睡眠不足が続くと脳の感情コントロール機能が低下し、怒りやすくなります。
また、緊張や自律神経の乱れは頭痛を引き起こす原因にもなります。
逆に頭痛や不眠が続くことでイライラが増幅する悪循環に陥ることもあります。
根本的な改善には、睡眠環境の調整やストレスケアが欠かせません。
イライラが止まらないときはセルフケア+必要に応じて専門家へ

イライラは誰にでもある感情ですが、長引いたり強すぎたりする場合は心身の不調や病気が背景にある可能性があります。
セルフケアで改善できることもありますが、無理に我慢せず、必要に応じて専門家に相談することが大切です。
自分を責めるのではなく、環境を整えたり適切な支援を受けたりすることで、安心して生活を取り戻すことができます。
「イライラが止まらない」と感じたときは、セルフケア+専門家の助けをバランスよく取り入れていきましょう。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。