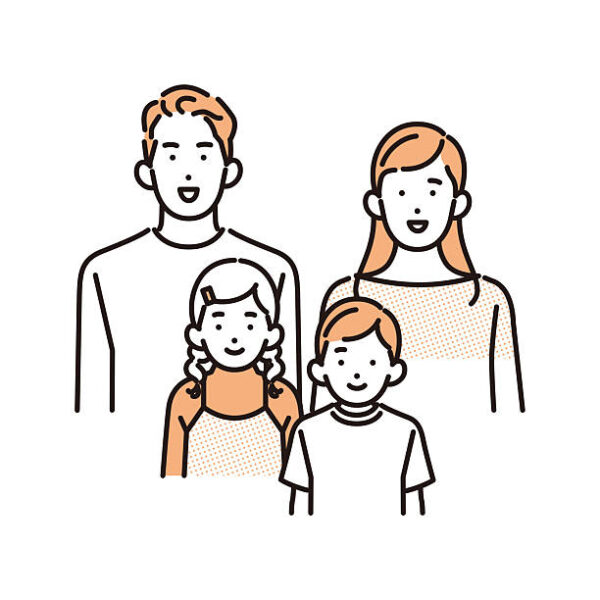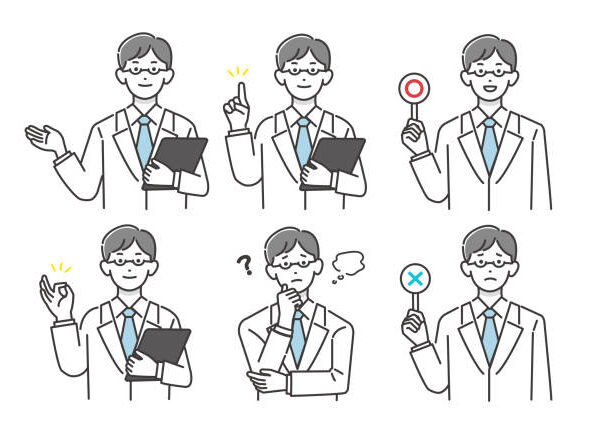うつ病や適応障害で休職や給付金の申請をする際、欠かせないのが診断書です。
しかし「初診でもすぐに診断書を出してもらえるのか」「費用や日数はどのくらいかかるのか」と不安に思う方は多いでしょう。
診断書は医師の判断や症状の状況によって即日発行されるケースもあれば、複数回の診察が必要な場合もあります。
この記事では、うつ病・適応障害の診断書が必要な場面、即日発行の可否、費用やもらうためのポイントを分かりやすく解説します。
会社や学校への提出、保険申請などで診断書が必要な方は、ぜひ参考にしてください。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。
うつ病や適応障害で診断書はすぐにもらえる?

うつ病や適応障害の診断書は必ずしも初診で即日発行されるわけではありません。
医師の判断や症状の程度によっては、初診当日に発行されることもあれば、数回の診察を経てからになる場合もあります。
ここでは、診断書をもらえるタイミングや条件について詳しく解説します。
- 初診当日に発行してもらえるケース
- 数回の診察を経てから発行される場合
- 診断書発行に必要な診断基準と医師の判断
- 即日発行を希望するときの伝え方
診断書を確実に受け取るためには、事前準備と医師への伝え方が大切です。
初診当日に発行してもらえるケース
初診当日に診断書が発行されるのは、症状が明らかであり緊急性が高い場合です。
例えば、強い抑うつ症状で日常生活に著しい支障が出ているケースや、職場から至急診断書を提出するよう求められている場合などです。
医師が「休養が必要」と判断すれば、初診でも即日診断書を作成してもらえることがあります。
ただしこれはあくまで例外的対応であり、すべての医療機関で保証されるものではありません。
予約時に「初診で診断書が必要」と伝えておくと、対応してもらいやすくなります。
数回の診察を経てから発行される場合
多くの場合、診断書は複数回の診察を経てから発行されます。
精神科や心療内科では、診断のために症状の持続期間や経過を観察する必要があるからです。
例えば、一時的なストレス反応なのか、うつ病や適応障害と診断できる状態なのかを区別するためには、2回以上の受診で経過を確認するのが一般的です。
そのため、初診当日には問診や心理検査が中心で、診断書は次回以降の発行になることもあります。
提出期限がある場合は、初診の際に「診断書はいつごろ出していただけますか」と確認しておくと安心です。
診断書発行に必要な診断基準と医師の判断
診断書の発行は医師の診断基準に基づいて行われます。
うつ病ではDSM-5やICD-10といった国際的診断基準に沿い、気分の落ち込みが2週間以上続いているか、意欲低下や集中力の低下が見られるかなどを確認します。
適応障害の場合は、特定のストレス要因と症状の関係性、日常生活や仕事への影響の度合いが重視されます。
医師は問診、症状の経過、心理検査の結果を踏まえて診断を下し、必要と判断したときに診断書を発行します。
したがって、患者が希望しても基準を満たさなければ即日発行は難しいことがあります。
即日発行を希望するときの伝え方
診断書を早く必要とする場合は、医師や受付に希望を明確に伝えることが重要です。
例えば「会社から今日中に診断書の提出を求められている」「休職手続きに明日まで必要」といった具体的な理由を説明しましょう。
また、診断書の用途(会社提出用・保険用・学校提出用など)を伝えておくと、医師も対応しやすくなります。
ただし、症状が診断基準に達していない場合は、正式な診断書の代わりに「通院中である旨の証明書」や「経過観察中である旨の文書」が発行されることもあります。
事前に電話で「初診で診断書をお願いできますか」と問い合わせておくことも、スムーズに進めるための有効な方法です。
診断書が必要となる代表的なケース

うつ病や適応障害の診断書は、さまざまな場面で必要になります。
特に社会生活や仕事、学業を継続するための手続きでは、診断書が求められるケースが少なくありません。
ここでは、診断書が必要となる代表的なケースを紹介します。
- 休職や復職の申請に必要な場合
- 大学や高校など学校への提出
- 傷病手当金・保険金の申請
- 試験や資格試験の受験延期・免除
- 就職・転職活動での配慮申請
どのケースにおいても、医師が記載する診断書は客観的な証明となり、各種制度やサポートを利用するための重要な役割を果たします。
休職や復職の申請に必要な場合
最も多いのが職場に提出するための診断書です。
うつ病や適応障害によって仕事を続けることが難しいとき、休職を申請するには診断書が欠かせません。
診断書には「病名」や「療養が必要な期間」などが記載され、会社はこれを根拠に休職を認めます。
また、休職から復職する際にも「就業可能である」という医師の診断書を提出する必要がある場合があります。
診断書があることで、従業員は法的に守られながら安心して休養や復帰ができる環境を得ることができます。
大学や高校など学校への提出
学生生活においても診断書が必要な場面があります。
授業に出席できない日が続く場合や、試験を欠席するときに診断書を提出することで、欠席が正当な理由として認められることがあります。
また、長期的な休学や復学を申請する際も診断書の提出が求められることがあります。
精神的な不調は周囲から理解されにくいこともあるため、診断書があることで客観的に証明でき、学生本人や保護者の負担を減らすことにつながります。
学校側も診断書を根拠に支援を検討しやすくなるため、早めに準備することが重要です。
傷病手当金・保険金の申請
経済的な支援を受けるために診断書が必要となるケースもあります。
健康保険から支給される傷病手当金を受給するには、医師の診断書(意見書)が欠かせません。
また、民間の医療保険や生命保険で給付金を請求する際にも、診断書の提出が必要となります。
保険会社が指定する書式に記入してもらうケースが多いため、事前に必要な書類を揃えて医師に依頼する必要があります。
診断書がなければ給付金は受け取れないため、経済的支援をスムーズに得るためには欠かせない手続きです。
試験や資格試験の受験延期・免除
重要な試験や資格試験を控えている場合にも診断書が役立ちます。
精神的な不調で受験が困難になったとき、診断書を提出することで受験日程の延期や振替が認められることがあります。
大学入試や資格試験の一部では、受験免除や追試の申請に診断書の提出が必須となっています。
診断書は「受験できなかった理由」を客観的に証明するものとなり、学生や受験者が不利な扱いを受けないための大切な手段です。
試験の主催者ごとにルールが異なるため、事前に確認し、必要に応じて早めに診断書を依頼しておくと安心です。
就職・転職活動での配慮申請
就職や転職の際に、配慮を求めるために診断書が必要になる場合もあります。
例えば、障害者雇用枠での応募や、働き方に制限があることを企業に伝える場合、診断書が客観的な証明として活用されます。
「長時間労働が困難」「ストレス負荷の高い業務を避けたい」といった配慮を求めるときに、診断書は大きな役割を果たします。
企業側も診断書を根拠にして、配置や勤務形態を調整することができます。
安心して新しい職場に挑戦するためにも、必要に応じて診断書を準備しておくとよいでしょう。
診断書の発行にかかる費用と日数

診断書の発行には費用と日数がかかります。
うつ病や適応障害の診断書は、保険診療外の扱いとなるため、料金は医療機関ごとに異なります。
また、発行までにかかる日数も「即日」から「数日後」まで幅があります。
ここでは、診断書の費用や発行スピード、郵送対応の有無などについて解説します。
- 診断書の一般的な費用相場(3,000円〜5,000円程度)
- クリニックや病院による費用の違い
- 発行までにかかる日数(即日〜数日)
- 郵送対応の有無と追加料金
費用や日数はケースによって変動するため、事前確認が安心につながります。
診断書の一般的な費用相場(3,000円〜5,000円程度)
診断書の一般的な費用は3,000円から5,000円程度が目安です。
これは自由診療扱いとなるため、健康保険は適用されません。
休職や復職のための診断書、学校への提出用、保険申請用など、用途によって料金が変わる場合があります。
また、同じ診断書を複数枚発行してもらう場合には、1枚ごとに追加料金がかかることが一般的です。
クリニックや病院のホームページに料金が掲載されていることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
クリニックや病院による費用の違い
診断書の費用は医療機関によって差があります。
個人経営のクリニックでは比較的安価で3,000円前後のことが多いですが、大きな総合病院では5,000円以上かかる場合があります。
また、保険会社や学校など指定の書式に記入してもらう場合は、通常の診断書よりも高額になるケースがあります。
「意見書」や「診断証明書」といった形式になると、8,000円から1万円近く請求されることも珍しくありません。
提出先が指定する書類がある場合は、料金の違いも含めて依頼前に確認することが大切です。
発行までにかかる日数(即日〜数日)
診断書の発行にかかる日数は、即日から数日程度が一般的です。
初診当日に症状が明確であり、医師がすぐに診断できる場合は、その日のうちに診断書をもらえることがあります。
一方で、医師が慎重に診断する必要がある場合や、書類が複雑な場合は数日から1週間程度かかることもあります。
また、病院によっては診断書の作成を事務部門が行うため、医師の記載後に事務処理で日数を要することもあります。
期限が迫っている場合は「いつまでに受け取れるか」を必ず確認しておきましょう。
郵送対応の有無と追加料金
診断書は郵送で受け取れる場合もありますが、追加料金がかかるケースが多いです。
特に再発行や遠方からの依頼では、窓口受け取りが難しいため郵送対応を選ぶ人が増えています。
郵送料や事務手数料として500円〜1,000円程度の追加費用がかかるのが一般的です。
また、簡易書留や宅配便を利用する病院もあり、安全性と確実性を重視した対応がなされます。
受け取り方法についても、依頼時に確認しておくと手続きがスムーズになります。
診断書をスムーズにもらうための準備

診断書をスムーズに発行してもらうためには、事前の準備がとても大切です。
準備が不十分だと、医師に症状が正しく伝わらなかったり、書類の形式が違って再発行が必要になったりすることがあります。
診断書は提出先によって書き方や条件が異なるため、準備を整えてから受診することで手続きがスムーズに進みます。
- 症状・困りごとをメモにまとめておく
- 職場や学校に必要な書式や条件を確認する
- 診断書が何に必要なのかを明確に伝える
- Web予約やLINE予約を活用する
以下では、診断書を依頼するときに役立つ準備の具体的なポイントを解説します。
症状・困りごとをメモにまとめておく
診断書を依頼する前に、現在の症状や困っていることをメモにまとめておくことが重要です。
例えば「2週間以上気分の落ち込みが続いている」「眠れず疲労感が取れない」「職場でのミスが増えている」といった内容です。
医師は短い診察時間で患者の状態を把握しなければならないため、事前に整理した情報があると診断がスムーズになります。
また、メモがあることで本人も伝え漏れがなくなり、診断書の内容に正確に反映されやすくなります。
医師に簡潔に説明できる準備が、診断書を早くもらう第一歩になります。
職場や学校に必要な書式や条件を確認する
診断書は提出先によって必要な形式や内容が異なります。
会社によっては「休職開始日と期間の明記」が必要な場合があり、学校では「授業を欠席した理由の証明」が求められることもあります。
また、保険会社では指定の書式があり、通常の診断書では認められないこともあります。
こうした条件を確認せずに依頼すると「書き直し」が必要となり、時間や費用のロスにつながります。
受診前に会社・学校・保険会社の条件をチェックしておくことがスムーズな対応につながります。
診断書が何に必要なのかを明確に伝える
診断書を依頼するときには、用途を医師に明確に伝えることが大切です。
「休職のため」「復職のため」「保険金申請のため」「学校への欠席届のため」など、目的によって診断書に記載すべき内容が変わるからです。
用途が不明確なまま依頼すると、必要な項目が抜け落ちて再発行が必要になることがあります。
また、用途を伝えることで、医師も診断のポイントを把握しやすくなり、適切な診断書を発行できます。
「誰に提出するか」と「どんな内容が必要か」を整理して伝えることが重要です。
Web予約やLINE予約を活用する
スムーズに診断書をもらうためには、予約方法も工夫するのがおすすめです。
最近ではWeb予約やLINE予約に対応しているクリニックも増えており、診断書が必要な旨を事前に入力して伝えることができます。
予約時点で「初診で診断書を希望」と伝えておけば、診察の流れが調整され、当日スムーズに発行される可能性が高まります。
また、オンライン問診票で症状や困りごとをあらかじめ入力できるクリニックもあり、診断の効率化につながります。
予約段階で診断書希望を伝える工夫が、無駄な待ち時間や手続きの手間を減らすポイントになります。
診断書を後から依頼するケース

診断書は必ずしも診察当日に依頼しなければならないわけではありません。
後日改めて依頼することも可能であり、状況によっては再診や電話、郵送などさまざまな方法で手続きできます。
ただし、依頼の仕方や受け取り方法によっては追加費用や日数がかかるため、事前に確認しておくことが大切です。
- 再診時に依頼する流れ
- 電話やオンラインで依頼できるか
- 郵送や窓口での受け取り方法
- 再発行や追加発行の注意点
ここでは、診断書を後から依頼する際の具体的な流れと注意点を解説します。
再診時に依頼する流れ
診断書を後から依頼する最も一般的な方法は再診の際にお願いすることです。
初診では診断が確定せず、経過観察が必要と判断されるケースも多いため、再診で改めて依頼する流れは自然です。
再診時に依頼する場合、医師が前回の診察記録をもとに診断を補足できるため、より詳細で正確な診断書を書いてもらえるメリットもあります。
また、休職期間の延長や復職判断など、時期に応じて必要となる内容を反映した診断書を作成してもらえる点も利点です。
受診のたびに診断書を依頼できる仕組みを理解しておくと、計画的に手続きが進めやすくなります。
電話やオンラインで依頼できるか
近年は電話やオンラインで診断書を依頼できる医療機関も増えています。
通院が難しい場合や忙しくて時間が取れない場合には、電話で「診断書をお願いしたい」と伝えることで依頼できるケースがあります。
また、オンライン診療や専用のWebフォームを導入しているクリニックでは、インターネット経由で診断書を依頼することが可能です。
ただし、初診からの期間が短い場合や、診断内容の確認が必要な場合は、医師の判断で来院を求められることもあります。
電話やオンライン対応は便利ですが、すべての病院が対応しているわけではないため、事前確認が欠かせません。
郵送や窓口での受け取り方法
診断書は郵送や窓口で受け取ることができます。
窓口受け取りは直接来院して受け取る方法で、即日対応や緊急時には便利です。
一方で、遠方に住んでいたり多忙で通院が難しい場合には、郵送で送ってもらえる医療機関もあります。
郵送の場合は郵送料や事務手数料が追加で発生するのが一般的で、数百円から千円程度かかることもあります。
安全性を確保するため簡易書留などで送付されるケースも多いため、依頼時に受け取り方法を確認しておくと安心です。
再発行や追加発行の注意点
診断書を紛失した場合や複数枚必要な場合には再発行や追加発行を依頼できます。
ただし、再発行には新たに費用がかかるのが一般的で、1通あたり数千円が請求されます。
また、内容が更新される場合(休職延長など)には新しい診断が必要となり、診察を受けてからの発行となるケースもあります。
保険申請や会社提出用など複数の用途に使う予定がある場合は、初めから必要な枚数を伝えておくと効率的です。
再発行は簡単にできるものではないため、診断書を受け取ったら大切に保管することが重要です。
診断書の内容と記載の仕方

うつ病や適応障害の診断書の内容は一律ではなく、用途や提出先によって書かれ方が変わります。
「病名」が明記される場合もあれば、「状態」や「症状」といった表現でまとめられることもあります。
また、会社提出用と保険申請用、学校提出用とでは求められる記載内容に違いがあるため注意が必要です。
- 「病名」ではなく「状態」が書かれるケース
- 会社提出用・保険用・学校用で内容が異なる
- 休職期間の記載方法
- 診断書に病名が書かれるリスクとプライバシー
ここでは、診断書の書き方やプライバシー面での注意点について詳しく解説します。
「病名」ではなく「状態」が書かれるケース
診断書には必ずしも「病名」が書かれるわけではありません。
精神科や心療内科では、患者のプライバシー保護や社会的な影響を考慮して「状態」や「症状」が記載されることがあります。
例えば「うつ病」とは書かずに「抑うつ状態」「気分障害のため安静加療を要する」などと表現される場合です。
これにより、診断書を提出する相手に病名が伝わらず、余計な誤解や偏見を避けられるメリットがあります。
病名の有無は医師の判断や提出先の条件に左右されるため、事前に希望を伝えることが重要です。
会社提出用・保険用・学校用で内容が異なる
診断書の内容は提出先によって大きく異なります。
会社提出用では「休職の必要性」「復職の可否」などが記載されるのが一般的です。
保険用では病名の明記が求められることが多く、指定の書式に沿って症状の経過や治療方針が細かく書かれます。
学校提出用では「授業や試験に出席できない理由」として「安静加療を要する」といった簡潔な記載が多いです。
診断書の内容は用途に合わせて変わるため、提出先が何を求めているかを把握し、医師に正確に伝えることが大切です。
休職期間の記載方法
診断書では休職期間の記載が非常に重要なポイントです。
「◯月◯日から◯月◯日まで休養を要する」と具体的に日付を入れる場合もあれば、「一定期間の加療を要する」と抽象的に書かれる場合もあります。
会社が休職を認めるかどうかはこの記載に大きく左右されるため、休職の開始日や期間の明記が求められることが多いです。
ただし、精神疾患は回復の見通しが立てにくいため、最初は「2週間程度」や「1か月程度」と短めに記載され、必要に応じて延長の診断書を追加する流れになることもあります。
医師と相談しながら現実的な休職期間を設定することが、無理のない復帰につながります。
診断書に病名が書かれるリスクとプライバシー
診断書に病名が書かれることには、プライバシー上のリスクがあります。
「うつ病」「適応障害」と明記されると、職場や学校に知られたくない情報が伝わってしまう可能性があります。
また、病名によっては誤解や偏見を招き、職場での立場に影響することも懸念されます。
そのため、医師によっては「抑うつ状態」「心身の不調のため加療中」といった表現で配慮してくれるケースがあります。
病名の記載を避けたい場合は、診断書作成前に医師へ相談することが大切です。
診断書がもらえない場合の理由と対処法

診断書は必ずしも希望すればすぐにもらえるわけではありません。
医師の判断や診察の内容によっては、診断書を発行してもらえないこともあります。
その場合には理由を理解し、適切な対応を取ることが大切です。
- 医師が病状を確認できない場合
- 初診のみでは判断が難しい場合
- 依頼内容が不適切な場合
- 別の病院やクリニックに相談する選択肢
ここでは、診断書をもらえない代表的な理由と、その際の対処法について解説します。
医師が病状を確認できない場合
診断書は医師が医学的に診断できる根拠があるときにのみ発行されます。
そのため、診察の際に症状が十分に確認できなかった場合には、診断書の発行を断られることがあります。
例えば「数日間だけ気分が落ち込んだ」といった一時的な症状では、医学的に病名を付けるのが難しいこともあります。
この場合は、症状を具体的にメモして伝えることや、体調の変化を日記形式で記録しておくと有効です。
医師に客観的な情報を提供することで診断がつきやすくなり、診断書発行につながる可能性が高まります。
初診のみでは判断が難しい場合
精神科や心療内科では、初診だけで診断書を発行できないことがあります。
これは、うつ病や適応障害といった精神疾患は診断に一定の時間と経過観察が必要だからです。
医師はDSM-5やICD-10といった診断基準に照らし合わせて判断しますが、初診時にはまだ情報が不十分なことが多いです。
「少なくとも2週間以上の抑うつ状態」といった条件を満たさないと診断が難しい場合もあります。
この場合は、再診を重ねて経過を示すことで、診断書が発行されやすくなります。
初診で断られても諦めず、複数回通院する姿勢が大切です。
依頼内容が不適切な場合
診断書の用途や依頼内容が不適切だと、医師は発行を断ることがあります。
例えば「会社を辞めたいから診断書が欲しい」「試験を免除してほしいのでとにかく病名を書いてほしい」といった依頼は不適切とされます。
診断書は医学的事実を記録するものであり、患者の希望に合わせて都合よく書き換えることはできません。
不適切な依頼をすると、医師との信頼関係を損なうことにもつながります。
診断書は客観的証明であることを理解し、正しい目的で依頼することが大切です。
別の病院やクリニックに相談する選択肢
どうしても診断書をもらえない場合には、別の医療機関に相談するという選択肢もあります。
医師によって診断方針や判断の基準が異なるため、他院であれば診断書を発行してもらえるケースもあります。
ただし、病院を転々として診断書だけを求める行為は「ドクターショッピング」とされ、逆に信頼を損ねる可能性があります。
新しい病院を受診する際には、過去の診療記録や症状の経過をしっかり伝えることが重要です。
信頼できる医師と出会い、症状を正しく理解してもらうことが、診断書を得るための近道になります。
医師に相談すべきタイミング

うつ病や適応障害は早めの受診が回復につながります。
「まだ大丈夫」と我慢してしまう人も多いですが、症状を放置すると悪化して長期化するリスクがあります。
医師に相談すべきサインを見極めることで、必要なときに適切な支援を受けることが可能になります。
- 気分の落ち込みが2週間以上続いている
- 仕事や学校に行けないほどの不調がある
- 不眠や食欲低下が続いている
- 集中力低下や頭が働かない感覚がある
ここでは、医師に相談すべき代表的なタイミングについて解説します。
気分の落ち込みが2週間以上続いている
気分の落ち込みが2週間以上続いている場合は、うつ病の可能性があるため受診を検討すべきです。
一時的な落ち込みであれば自然に回復することもありますが、2週間以上続くと精神疾患の兆候である可能性が高まります。
特に「何をしても楽しく感じられない」「朝起きられない」「気持ちが晴れない」といった状態が続いている場合は注意が必要です。
放置してしまうと症状が悪化し、日常生活や社会生活に大きな影響を及ぼすことがあります。
早めに専門医に相談することが、症状の悪化を防ぐ第一歩です。
仕事や学校に行けないほどの不調がある
仕事や学校に行けないほどの不調が続いている場合は、医師に相談するべき重要なサインです。
体が重くて出勤できない、学校に行くことを考えるだけで強い不安や憂うつを感じるといった状態は、適応障害やうつ病の典型的な症状です。
この段階で無理に頑張ろうとすると、さらに状態が悪化して長期の休養が必要になることもあります。
また、欠勤や欠席が続くことで仕事や学業に支障が出て、自己評価の低下や孤立感が強まる可能性もあります。
社会生活に影響が出始めた段階で相談することが、回復を早めるための大切なポイントです。
不眠や食欲低下が続いている
不眠や食欲低下が続く場合も、医師に相談すべき重要なサインです。
睡眠が十分に取れないと疲労が蓄積し、体力や集中力が低下して日常生活に支障をきたします。
また、食欲が落ちることで栄養不足となり、心身のバランスをさらに崩してしまうことがあります。
これらの症状が1週間以上続くと自然回復が難しいことも多く、うつ病や適応障害の診断基準にも当てはまる可能性があります。
生活の基本である睡眠と食事に異常が出ているときは、早めの受診を検討することが大切です。
集中力低下や頭が働かない感覚がある
集中力の低下や頭が働かない感覚が続く場合も、医師に相談が必要です。
仕事でミスが増えたり、勉強が手につかなくなったりするのは、単なる疲労ではなく精神疾患のサインであることがあります。
特に「考えがまとまらない」「本を読んでも内容が頭に入らない」「同じ作業に時間がかかる」といった状態が続くと注意が必要です。
こうした状態は自己判断で改善するのが難しく、放置すると自信喪失や更なる気分の落ち込みにつながります。
思考や集中に支障が出てきたと感じたら、早めに医師へ相談することで適切な治療を受けられます。
よくある質問(FAQ)

Q1. 初診でも診断書をすぐに出してもらえますか?
初診でも診断書が発行されることはありますが、必ずではありません。
症状が明らかであり、医師が休養の必要性を認めた場合には即日発行されることがあります。
例えば、強い抑うつ症状や不安障害が見られ、日常生活や仕事への影響が大きいと判断されたケースです。
一方で、精神科や心療内科では初診だけでは情報が不十分とされ、経過を観察してから診断書を発行する方針の医師も多いです。
診断書がすぐ必要な場合は、予約や受付の時点で「初診で診断書が必要」と伝えておくことが大切です。
Q2. 適応障害でも休職の診断書は発行されますか?
適応障害であっても、休職に必要な診断書は発行されます。
適応障害は特定のストレス要因によって心身に不調が現れる病気で、仕事や学校生活に支障が出る場合があります。
医師が「休養が必要」と判断すれば、うつ病と同様に診断書を発行してもらえます。
ただし、症状が軽度の場合には「通院加療を要する」といった表現になることもあります。
症状の程度や生活への影響をしっかり伝えることが、適切な診断書の発行につながります。
Q3. 診断書の費用はどのくらいかかりますか?
診断書の費用は一般的に3,000円から5,000円程度です。
これは健康保険の対象外となる自由診療扱いのため、医療機関ごとに金額が異なります。
また、保険会社指定の書類や意見書など、通常より詳細な書式を求められる場合には8,000円から1万円近くかかることもあります。
診断書を複数枚依頼する場合にも追加費用がかかるため、必要な枚数をあらかじめ確認しておきましょう。
費用は病院のホームページや受付で事前に問い合わせておくと安心です。
Q4. 診断書は必ず病名が書かれますか?
診断書に必ず病名が書かれるわけではありません。
プライバシー保護の観点から、「うつ病」や「適応障害」と明記せず、「抑うつ状態」「加療を要する状態」といった表現を用いることもあります。
一方で、保険会社に提出する診断書では病名の記載が必須となる場合が多いです。
提出先によって求められる内容が異なるため、用途を事前に医師へ伝えることが大切です。
病名の有無について希望がある場合は、診断書作成前に医師に相談しましょう。
Q5. 診断書を断られた場合はどうすればいいですか?
診断書を断られることもありますが、理由を確認することが大切です。
初診のみでは診断が確定できない場合や、医学的根拠が不十分な場合には発行されないことがあります。
この場合は再診を重ねて症状の経過を示すことで、診断書が発行されやすくなります。
どうしても必要な場合には、他のクリニックや病院に相談するのも選択肢の一つです。
重要なのは正しい理由で診断書を依頼し、信頼できる医師と相談を重ねることです。
診断書はケースによって即日も可能、事前準備が大切

診断書は症状や医師の判断によって即日発行されることもあれば、数回の診察後になる場合もあります。
用途や提出先の条件をあらかじめ確認し、症状を整理して伝えることがスムーズな発行につながります。
また、費用や発行日数についても事前に確認しておくことで、手続きに余裕を持つことができます。
必要なときに確実に診断書を入手するためには、事前準備と医師への正しい伝え方が欠かせません。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。