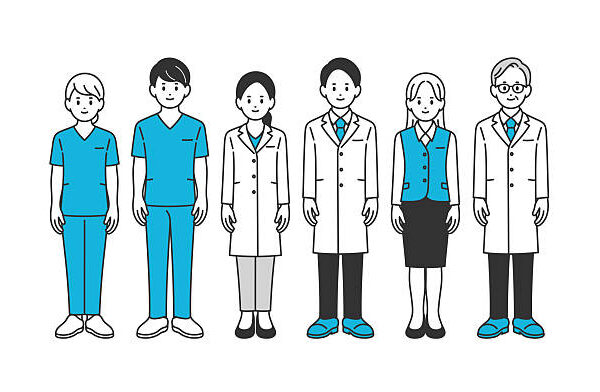「一人でいると不安で落ち着かない」「常に誰かと一緒にいないと怖い」──大人になってから一人でいられないと感じるのは、不安障害のサインかもしれません。
不安障害は過剰な不安や恐怖が長期間続く心の病気で、パニック障害や広場恐怖、対人不安などと関係することがあります。
大人になってから発症するケースも少なくなく、仕事や家庭生活に支障が出ることもあります。
本記事では「一人でいられない」と感じる背景や原因、セルフケアでできる対処法、そして専門家に相談すべきタイミングについて解説します。
不安を一人で抱え込まず、正しい理解とサポートを得ることで安心して生活できるようになる第一歩を紹介します。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。
不安障害とは?

不安障害とは、日常生活に支障が出るほどの強い不安や恐怖が長期間続く心の病気です。
一時的な不安であれば自然に収まりますが、慢性的に続く場合は生活全般に悪影響を与えることが少なくありません。
ここでは、不安障害の基本的な特徴や「一人でいられない」と感じる背景について整理して解説します。
- 大人に多い不安障害の特徴
- 「一人でいられない」と感じる背景
- 不安障害とパニック障害・広場恐怖の関係
- 日常生活に及ぼす影響
不安障害を正しく理解することが、適切な対処の第一歩になります。
大人に多い不安障害の特徴
大人の不安障害は、仕事や家庭など責任や役割が増える時期に発症しやすいのが特徴です。
プレッシャーが大きくなると「失敗したらどうしよう」「一人では対応できない」という不安が強まります。
さらに大人は症状を周囲に隠そうとする傾向があるため、発見や支援が遅れることも少なくありません。
症状は性格の問題ではなく脳や自律神経の働きによるもので、適切な治療で改善が期待できます。
責任世代に多いという特性を理解し、早めの対処を意識することが重要です。
「一人でいられない」と感じる背景
不安障害では「一人でいると不安に押しつぶされる」という感覚を持つ人が多くいます。
背景には「もし体調が急に悪化したら」「助けてくれる人がいなかったら」という恐怖が潜んでいます。
また、孤独感や見捨てられ不安といった心理的要因も強く影響します。
そのため常に誰かと一緒にいたい衝動が強まり、日常生活に制限がかかることがあります。
原因は一人ひとり異なりますが、心の仕組みを理解することが不安の軽減につながります。
不安障害とパニック障害・広場恐怖の関係
パニック障害や広場恐怖は、不安障害と深く関連しています。
パニック障害では突然の発作により「一人でいると助けてもらえない」という恐怖が強まります。
広場恐怖は「逃げられない場所」にいることへの不安が特徴で、一人での外出や留守番が難しくなることがあります。
これらの症状が重なると「一人でいられない」という状態がさらに強化されます。
自己判断で放置せず、専門家に相談することで改善の可能性が広がります。
日常生活に及ぼす影響
不安障害が進行すると生活全般に大きな支障を及ぼします。
買い物や通勤、外出などの日常行動が制限され、社会生活や家庭生活に影響が出ます。
さらに「不安が来るかもしれない」という予期不安が強まり、行動範囲がどんどん狭まってしまうことがあります。
その結果、家族や友人への依存が強まり、人間関係のバランスを崩すことも少なくありません。
正しい理解とケアによって生活の質を取り戻すことが重要です。
「一人でいられない」状態の原因

不安障害において「一人でいられない」という感覚は珍しくありません。
その背景には心理的な要因から脳や自律神経の働きまで、さまざまな原因が絡み合っています。
一人でいると不安が高まったり恐怖を感じたりするのは、単なる性格ではなく医学的にも説明できる現象です。
ここでは、一人でいられなくなる代表的な原因について解説します。
- 強い不安感や恐怖感による依存
- 過去のトラウマや体験の影響
- 孤独や見捨てられ不安の心理的要因
- 自律神経や脳の働きの不調
- 愛着スタイル(依存・不安型)の影響
原因を理解することは、適切な対処や専門家への相談につながります。
強い不安感や恐怖感による依存
強い不安や恐怖が続くと、人は安心を求めて他者に依存しやすくなります。
「一人でいると不安が爆発する」「そばに誰かがいれば安心できる」という感覚は、不安障害でよく見られる特徴です。
これは自己防衛的な反応であり、脳が「安全を確保する手段」として他者の存在を必要としているのです。
依存は一時的に不安を和らげますが、長期的には「一人では過ごせない」という制限を強める原因となります。
少しずつ一人の時間を慣らす工夫や安心できる習慣を持つことが回復の一歩になります。
過去のトラウマや体験の影響
幼少期や過去にトラウマ体験があると、一人でいることに強い不安を感じることがあります。
事故や病気、災害、家庭内の不和など「一人のときに怖い経験をした」記憶は、その後の生活にも影響を残します。
脳は危険を回避するために過去の体験を参照し、「一人=危険」という認識を強めてしまうのです。
トラウマの影響は無意識に働くため、自分では理由がわからないまま「一人が怖い」と感じることもあります。
専門家のサポートを受けながら過去を整理することが、不安軽減の助けになります。
孤独や見捨てられ不安の心理的要因
孤独感や見捨てられ不安は、「一人でいられない」と感じる大きな心理的要因です。
「誰からも必要とされないのでは」「一人になったら見捨てられるのでは」という恐れが強く、他者への過剰な依存を生みます。
この状態は人間関係に悪影響を与えることもあり、周囲とのバランスを崩す原因となります。
孤独は誰にでもある感情ですが、強すぎる場合は不安障害の一部として扱われることもあります。
安心できる人とのつながりを持ちながら、少しずつ自立心を育てることが大切です。
自律神経や脳の働きの不調
不安障害には自律神経や脳の働きの乱れが深く関わっています。
自律神経が乱れると心臓の動悸や呼吸の乱れが起こり、「一人では危険かもしれない」という恐怖を増幅させます。
また、脳内の神経伝達物質(セロトニンやドーパミン)のバランスが崩れることで、不安が抑えにくくなることも知られています。
こうした身体的要因は本人の意志ではコントロールできず、「一人では不安」という感覚につながります。
医学的な治療や生活習慣の改善が有効となるケースです。
愛着スタイル(依存・不安型)の影響
心理学では、人にはそれぞれの愛着スタイルがあり、不安型や依存型の人は「一人でいること」が苦手とされています。
幼少期に安定した愛着を得られなかった場合や、人間関係で不安を抱える傾向がある場合、常に他者とのつながりを必要とすることがあります。
このスタイルは性格ではなく学習された心のパターンであり、努力やサポートで変えていくことが可能です。
愛着スタイルを理解することで「自分のせいではない」と受け止めやすくなり、適切な対応ができるようになります。
専門家の支援を得ながら新しい関係性を築くことが、不安の改善につながります。
一人でいられない大人に見られるサイン
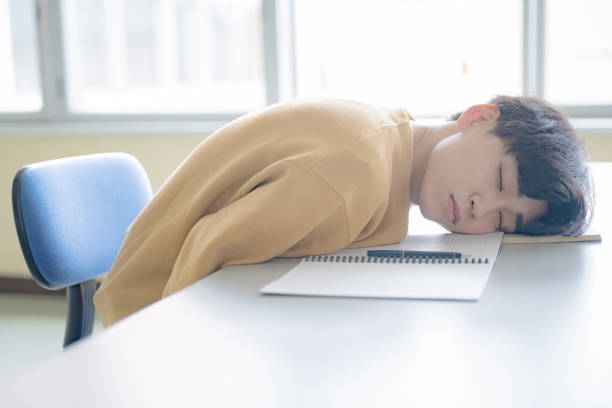
不安障害を抱える大人には、「一人でいられない」という特徴的な行動や感覚が現れることがあります。
本人は理由を説明できなくても、日常生活の中で不安が強まる場面が繰り返し起こるのが特徴です。
こうしたサインを見逃さずに理解することで、早期の対応や適切なサポートにつなげることができます。
- 常に誰かと一緒にいたい衝動
- 夜間や静かな時間に強まる不安
- 外出や留守番ができない
- 依存的な行動や過剰な確認
- 孤独になることへの強い恐怖感
ここでは、「一人でいられない」大人に見られる代表的なサインを解説します。
常に誰かと一緒にいたい衝動
不安障害のサインとしてよく見られるのが「常に誰かと一緒にいたい衝動」です。
仕事や趣味の時間でも、一人になると不安が強まるため、常に人と関わりを持とうとします。
電話やメッセージで常に連絡を取ろうとする行動もこの特徴の一部です。
本人にとっては「安心するために必要な行動」ですが、周囲には依存的に映ることがあります。
一時的な行動ではなく習慣化している場合、不安障害を疑うサインとなります。
夜間や静かな時間に強まる不安
多くの人が日中は活動や人との交流で気を紛らわせていますが、夜間や静かな時間になると不安が強まる傾向があります。
「一人でいると考えが止まらない」「不安が増幅して眠れない」といった訴えが典型的です。
特に寝室や自宅で一人になると強い孤独感や恐怖を感じやすく、就寝前にパニック発作が出る人もいます。
これは心が休まらない状態を意味しており、睡眠障害や生活リズムの乱れにつながる危険があります。
夜に不安が増す場合は、専門的なケアが必要になるサインです。
外出や留守番ができない
「外出や留守番ができない」のも、一人でいられない大人に見られる代表的なサインです。
買い物や通勤といった日常的な行動であっても、一人では強い不安に襲われ行動が困難になります。
また、家族が外出すると「一人にしないでほしい」と訴えるケースも少なくありません。
これは現実的な危険がなくても、不安が強まることで体が反応してしまうためです。
生活に大きな制限を与えるため、改善に向けたサポートが不可欠です。
依存的な行動や過剰な確認
不安が強いと依存的な行動が見られるようになります。
例えば「今どこにいるの?」「何時に帰ってくるの?」といった過剰な確認を繰り返すのが典型です。
本人は安心を得るために行っているのですが、周囲にとっては負担になることもあります。
また、依存的な行動は人間関係に緊張をもたらし、悪循環に陥ることもあります。
「確認しないと落ち着かない」という状況が続く場合、専門的な治療の必要性が高まります。
孤独になることへの強い恐怖感
「一人でいると孤独感が耐えられない」という強い恐怖感も特徴的なサインです。
これは単なる寂しさではなく、存在の不安や見捨てられ感と直結している場合が多いです。
孤独に対する恐怖が強いと、社会的な行動が制限され、精神的な負担がさらに増します。
この状態は自己判断で改善するのが難しく、本人を強く追い詰めてしまうことがあります。
孤独感が耐えられないほど強い場合は、早期に専門家へ相談することが重要です。
自分でできるセルフケア・対処法

「一人でいられない」という不安を少しずつ和らげるためには、セルフケアを取り入れることが効果的です。
完全に克服するのは難しくても、自分で工夫を積み重ねることで不安を軽減し、安心できる時間を増やすことができます。
ここでは、日常生活で無理なく実践できるセルフケアの方法を紹介します。
- 深呼吸やマインドフルネスで落ち着く
- 段階的に「一人の時間」を慣らしていく
- 安心できるアイテム(音楽・香り・ペット)を利用する
- 規則正しい生活で自律神経を整える
- 「安心できる人」との連絡手段を確保する
- 不安日記をつけて客観視する
無理にすべてを行う必要はなく、自分に合った方法から取り入れることが大切です。
深呼吸やマインドフルネスで落ち着く
深呼吸やマインドフルネスは、不安を感じたときにすぐ取り入れられるセルフケアです。
「4秒かけて息を吸い、6秒かけて吐く」呼吸法を繰り返すと、副交感神経が優位になり体がリラックスします。
またマインドフルネスは「今この瞬間」に意識を向ける方法で、過去や未来の不安から一時的に距離を取ることができます。
頭の中が不安でいっぱいになったときほど効果的で、習慣化することで不安のコントロール力が高まります。
特別な道具は不要で、誰でもすぐに始められる点も大きなメリットです。
段階的に「一人の時間」を慣らしていく
「一人でいると不安になる」人にとって、いきなり完全に一人で過ごすのは難しいものです。
そのため、段階的に一人の時間を増やす工夫が効果的です。
最初は数分だけ一人になる、その後は少しずつ時間を延ばしていくという方法で、心が慣れていきます。
「今日は5分頑張れた」と小さな達成感を積み重ねることが、自信につながります。
無理をせず自分のペースで挑戦することが、不安を軽減する近道です。
安心できるアイテム(音楽・香り・ペット)を利用する
一人でいるときの不安を和らげるために、安心できるアイテムを取り入れるのも効果的です。
好きな音楽を流す、アロマやお香で心を落ち着ける、ペットと一緒に過ごすなどが代表例です。
これらは「安心感を与えてくれる存在」として機能し、不安でいっぱいの気持ちを和らげます。
視覚・聴覚・嗅覚といった感覚を活用することで、不安の集中を分散させる効果もあります。
自分に合ったアイテムを見つけておくと、一人時間を過ごす助けになります。
規則正しい生活で自律神経を整える
不安を軽減するためには、生活リズムの安定が欠かせません。
特に睡眠不足や栄養の偏りは自律神経を乱し、不安を悪化させる原因になります。
毎日同じ時間に寝起きする、栄養バランスの取れた食事をする、適度に体を動かすことが基本です。
生活の土台を整えることで、自律神経が安定しやすくなり、不安も和らぎやすくなります。
小さな習慣の積み重ねが、不安をコントロールする力を高めます。
「安心できる人」との連絡手段を確保する
一人でいるときの不安を和らげる方法として、信頼できる人との連絡手段を持っておくことが役立ちます。
「困ったときはすぐ連絡できる」と思えるだけで、不安が軽減されることがあります。
実際に連絡しなくても「つながりがある」という感覚が安心材料になります。
ただし過剰に依存しすぎると逆効果になるため、バランスを意識することも大切です。
サポート体制を確保しておくことは、心の安全ネットになります。
不安日記をつけて客観視する
不安日記をつけることで、自分の気持ちを客観的に整理できます。
「いつ」「どんな状況で」「どれくらいの不安を感じたか」を書き出すことで、不安のパターンが見えてきます。
書き出す作業自体が気持ちの整理になり、不安を軽減する効果もあります。
また後から読み返すことで「前より不安が減っている」と気づき、自信につながることもあります。
日記はセルフモニタリングの一環として、不安を管理する有効なツールです。
専門家に相談すべきタイミング

「一人でいられない」という不安は誰にでも起こり得ますが、一定のラインを超えたときには専門家に相談することが大切です。
自分なりの工夫やセルフケアで改善が見られることもありますが、長引いたり悪化したりする場合は専門的な治療が必要です。
ここでは、専門家への相談を検討すべき代表的なサインを紹介します。
- 一人で過ごすことが日常的に困難な場合
- 不安発作やパニック症状を伴う場合
- 仕事や家庭生活に支障が出ている場合
- 「消えたい」と思うほどの強い不安がある場合
- セルフケアを続けても改善が見られない場合
一つでも当てはまる場合は我慢せず、心療内科や精神科、カウンセリングなどに早めに相談することが推奨されます。
一人で過ごすことが日常的に困難な場合
一人で過ごせない状態が日常化している場合は、専門家に相談する大きなサインです。
「常に誰かがいないと落ち着かない」「一人だと不安で何もできない」という状況が続くと、生活の自由度が大きく制限されます。
この状態を放置すると依存傾向が強まり、さらに不安が悪化するリスクがあります。
専門家に相談することで、原因を見極め、少しずつ一人で過ごせる力を取り戻すための方法を一緒に考えることができます。
自分の力だけで解決しようとせず、安心できるサポートを受けることが重要です。
不安発作やパニック症状を伴う場合
「動悸がする」「呼吸が苦しい」「めまいがする」といった身体的な症状を伴う不安発作は、専門的な治療が必要です。
特にパニック発作は突然起こるため、一人でいるときに発症することへの恐怖が「一人でいられない」という感覚をさらに強めます。
セルフケアだけでは発作をコントロールするのは難しく、薬物療法や認知行動療法が有効な場合があります。
繰り返す発作を放置すると生活範囲が狭まり、社会的な孤立につながる可能性があるため、早めに受診することが望まれます。
仕事や家庭生活に支障が出ている場合
不安によって日常生活や仕事に大きな影響が出ている場合も、専門家に相談すべきタイミングです。
出勤できない、家事や育児が進まない、人間関係に摩擦が生じるといった支障は、放置するとますます不安を悪化させる要因になります。
「頑張れば何とかなる」と我慢し続けることは、悪循環を招くだけです。
生活に支障が出ていると感じたら、自分を責めるのではなく専門的な支援を取り入れることが回復の近道になります。
早い段階で相談することで、仕事や家庭を守りながら改善につなげられます。
「消えたい」と思うほどの強い不安がある場合
「消えてしまいたい」「この不安から逃れたい」と感じるほどの状態は、非常に危険なサインです。
これは強い不安や抑うつが背景にある可能性が高く、自分の力だけでの改善は困難です。
このような状態を放置すると、自傷や自殺念慮につながるリスクがあります。
少しでも「危ない」と感じたら、すぐに専門機関に連絡することが必要です。
緊急の場合は医療機関や相談窓口、地域の支援サービスを活用しましょう。
セルフケアを続けても改善が見られない場合
セルフケアを継続しても改善が見られない場合も、専門家に相談する必要があります。
深呼吸や生活改善といった工夫をしても不安が和らがない場合、脳や自律神経のバランスに医学的な治療が必要な可能性があります。
薬物療法や心理療法を組み合わせることで、セルフケアでは得られなかった効果が期待できるケースも多いです。
「自分は努力が足りない」と責めるのではなく、治療によって改善できる症状であると理解することが重要です。
相談をきっかけに、新しい解決方法を見つけることができます。
治療法とサポートの選び方

「一人でいられない」と感じるほどの不安は、専門的な治療やサポートを受けることで改善できる可能性があります。
セルフケアも大切ですが、それだけでは不十分なケースも多く、医学的・心理的な支援を取り入れることが回復への近道です。
ここでは代表的な治療法と、家族や周囲によるサポートの選択肢について紹介します。
- 薬物療法(抗不安薬・抗うつ薬)
- 認知行動療法(CBT)による不安への対処
- カウンセリング・心理療法
- グループ療法やピアサポート
- 家族やパートナーのサポートの重要性
複数の治療や支援を組み合わせることで、不安を軽減し「一人で過ごす力」を少しずつ取り戻すことが可能です。
薬物療法(抗不安薬・抗うつ薬)
薬物療法は、不安障害の治療で多く用いられる方法の一つです。
抗不安薬は急激に高まった不安を抑える作用があり、抗うつ薬は長期的に不安や抑うつを軽減する効果があります。
特に「一人でいると不安で動悸や発作が起きる」という場合、薬の力を借りることで生活がしやすくなるケースが多いです。
ただし依存のリスクや副作用の可能性もあるため、医師と相談しながら用量や期間を調整することが大切です。
薬はあくまで補助であり、心理療法や生活改善と組み合わせることでより高い効果を得られます。
認知行動療法(CBT)による不安への対処
認知行動療法(CBT)は、不安障害に非常に効果的とされる心理療法です。
「一人でいると危険だ」という考え方を少しずつ修正し、現実的な視点で不安を和らげる練習をします。
また、段階的に一人で過ごす練習を取り入れることで「できた」という成功体験を積み重ね、不安に対する耐性を高めます。
薬に頼らず不安をコントロールできる力を育てられるため、再発予防にもつながります。
専門の心理士や医師と一緒に進めることで、実生活に役立つスキルを身につけられます。
カウンセリング・心理療法
カウンセリングや心理療法は、気持ちを整理し不安の背景を理解するために有効です。
安心できる環境で思いを話すことで、孤独感が軽減されるだけでなく、自分では気づかなかった思考パターンを見直すきっかけになります。
特に「一人でいると見捨てられる気がする」といった深い心理的要因には、専門家の伴走が役立ちます。
心理療法には支持的療法や精神分析的療法などさまざまな方法があり、個人に合った形で選択されます。
話すことで心が整理されるだけでも、不安が軽減することは珍しくありません。
グループ療法やピアサポート
同じ悩みを持つ人と交流できるグループ療法やピアサポートも効果的です。
「自分だけではない」と感じられることで安心感が生まれ、不安を客観的に捉えやすくなります。
グループでの体験共有は、自分では思いつかなかった対処法を学ぶ機会にもなります。
また、孤独感を和らげ「一人でも大丈夫」という感覚を少しずつ育てる助けになります。
地域のサポート団体やオンラインコミュニティを活用するのも一つの方法です。
家族やパートナーのサポートの重要性
家族やパートナーの理解と支援は、回復に欠かせない要素です。
「大丈夫だよ」「一緒に乗り越えよう」という言葉や態度は、本人に安心感を与えます。
ただし無理に克服させようとせず、本人のペースを尊重することが大切です。
また、受診に同行する、安心できる環境を整えるなど具体的な支援が大きな助けになります。
支える側もセルフケアを大切にしながら、長期的な支援を続けることが望まれます。
家族や周囲ができる支援

「一人でいられない」と感じる不安は、本人だけではなく家族や周囲のサポートによって和らげることができます。
しかし接し方を誤ると、本人がさらに孤立感や無力感を強めてしまうこともあります。
適切なサポートを意識することで安心感が生まれ、回復の大きな後押しになります。
ここでは、家族や周囲ができる具体的な支援の方法について解説します。
- 否定せずに不安を受け止める
- 安心できる環境を整える
- 無理に一人にさせず段階的に支える
- 専門機関の受診を一緒に促す
- 支える側もセルフケアを大切にする
支える人自身も無理をしすぎないことが、長期的なサポートの鍵になります。
否定せずに不安を受け止める
本人が「一人でいるのが怖い」と訴えたときに否定しないことが最も重要です。
「気にしすぎ」「大人なのに情けない」といった言葉は、本人の自尊心を大きく傷つけてしまいます。
代わりに「そう感じているんだね」「大丈夫、一緒に考えよう」と受け止める姿勢が安心感を与えます。
不安の感情自体はコントロールできないため、理解を示すことが信頼関係を深める第一歩です。
受容的な態度は、本人が安心してサポートを受け入れる基盤になります。
安心できる環境を整える
環境の整備は不安を和らげる大きな支えになります。
静かで落ち着ける空間を作る、生活リズムを安定させるサポートをすることが効果的です。
たとえば「一緒に寝る前のリラックスタイムを持つ」「外出に付き添う」といった小さな工夫も役立ちます。
本人が安心して過ごせる環境は、不安を減らすと同時に「一人でも大丈夫かもしれない」という自信につながります。
環境の工夫は本人だけでなく、家族の安心感にもつながります。
無理に一人にさせず段階的に支える
「一人でいられるように」と無理に突き放すことは逆効果です。
段階的に一人の時間を増やすことで、少しずつ不安に慣れていくことが可能です。
最初は短時間から始め、「数分なら一人で大丈夫だった」という経験を積み重ねることが重要です。
家族がそばにいながら本人が安心して挑戦できる環境を作ることが、最も安全な方法です。
無理をさせず、成功体験を支える姿勢が回復を後押しします。
専門機関の受診を一緒に促す
不安が長引いたり生活に支障が出ている場合は、専門機関の受診が必要です。
ただし「病気だから病院に行け」と強く言うと本人は抵抗を感じやすくなります。
「少し楽になる方法を一緒に探してみない?」「相談してみたら気が楽になるかも」といった声かけが効果的です。
家族が受診に同行するだけでも安心感が高まり、受診へのハードルが下がります。
本人の気持ちを尊重しながら優しく勧めることが大切です。
支える側もセルフケアを大切にする
家族や周囲が疲れ切ってしまうと、長期的な支援は難しくなります。
支える側も休息や趣味の時間を持ち、自分自身の心を守ることが必要です。
サポートを一人で抱え込まず、他の家族や支援機関と分担することも大切です。
支える人が元気でいることが、本人にとっても安心材料になります。
「自分を大切にしながら支える」という意識が、健全なサポートの基盤になります。
よくある質問(FAQ)

Q1. 不安障害で大人になってから「一人でいられない」と感じることはありますか?
はい、大人になってから不安障害を発症し「一人でいられない」と感じる人は少なくありません。
社会的な責任や家庭の役割が増えることでストレスが積み重なり、不安が慢性化して発症するケースがあります。
特に30代以降は「もし自分に何かあったら誰が助けてくれるのか」という恐怖心が強まりやすく、一人になることに強い不安を抱えることがあります。
これは性格の問題ではなく、脳や自律神経のバランスが関係する医学的な症状です。
大人であっても発症することは珍しくなく、適切な治療を受ければ改善が期待できます。
Q2. 自力で改善できる人もいますか?
軽度の不安であればセルフケアで改善できる人もいます。
深呼吸やマインドフルネス、生活習慣の改善、段階的に一人の時間を慣らす練習などが有効です。
ただし、不安が2週間以上続いたり生活に大きな支障が出ている場合は、自力での改善は難しいことが多いです。
自分を責めずに「自分の努力が足りないのではなく治療が必要な状態」だと理解することが大切です。
セルフケアと専門家のサポートを組み合わせるのが、もっとも現実的で効果的な方法です。
Q3. パニック障害と「一人でいられない」状態はどう違う?
パニック障害は突然の動悸や呼吸困難などの発作が特徴で、「一人だと助けてもらえない」という恐怖心が「一人でいられない」という状態につながります。
一方、不安障害での「一人でいられない」は、発作がなくても「孤独や不安に押しつぶされる」という慢性的な不安が背景にあります。
つまりパニック障害は急性的な発作がきっかけで不安が高まり、不安障害は持続的な不安感そのものが影響している点に違いがあります。
両者は併発することもあるため、症状を見極めるには専門的な診断が必要です。
Q4. 家族がどう対応すればいい?
家族は否定せず不安を受け止め、安心できる環境を整えることが重要です。
「大げさだ」「気にしすぎ」と言ってしまうと本人はさらに孤立してしまいます。
「一緒に考えよう」「そばにいるから大丈夫」という姿勢が安心感を与えます。
また、無理に一人にさせるのではなく、少しずつ挑戦を支援する伴走型のサポートが効果的です。
必要に応じて受診を優しく勧め、同行することも大きな支えになります。
Q5. 病院に行くとどんな治療が受けられる?
病院では薬物療法や心理療法を中心とした治療が行われます。
抗不安薬や抗うつ薬は不安の強さを和らげ、生活を安定させる役割を果たします。
また、認知行動療法(CBT)では不安を生み出す考え方を修正し、実生活で不安に対応する方法を学びます。
必要に応じてカウンセリングやグループ療法も併用されます。
医師やカウンセラーと相談しながら自分に合った治療法を見つけることが改善につながります。
Q6. 漢方やサプリで不安を軽減できる?
漢方やサプリメントは不安の軽減に役立つ場合もあります。
たとえば漢方では「柴胡加竜骨牡蛎湯」や「加味逍遙散」が用いられることがあります。
サプリではGABA、トリプトファン、マグネシウム、ビタミンB群などが神経の安定に寄与するとされています。
ただし効果には個人差があり、医学的な治療の代替にはなりません。
試す場合は医師や薬剤師に相談し、安全性を確認することが重要です。
Q7. 不安が強いときにすぐできる対処法は?
すぐにできる不安対処法としては、呼吸法・グラウンディング・安心アイテムの活用などがあります。
呼吸法では「4秒吸って6秒吐く」を繰り返すことで自律神経が整い、不安を和らげます。
グラウンディングでは「今見えるもの・触れている感覚」に集中することで、過度な不安から意識を切り替えることができます。
また、お気に入りの音楽を聴いたりアロマを使ったりすることで安心感を得られる人も多いです。
「すぐに取り入れられる工夫」を持っておくと、不安が高まったときの安心材料になります。
不安障害で「一人でいられない」大人はセルフケア+専門家の支援を

「一人でいられない」という状態は、不安障害の重要なサインである可能性があります。
セルフケアで不安を和らげることはできますが、それだけでは十分でない場合もあります。
必要に応じて専門家の支援を取り入れることで、不安を軽減し生活の質を取り戻すことが可能です。
自分を責めるのではなく、支援を受けながら少しずつ「一人でも安心できる自分」を育てていきましょう。
セルフケアと専門的な治療をバランスよく組み合わせることが、回復への大切なステップです。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。