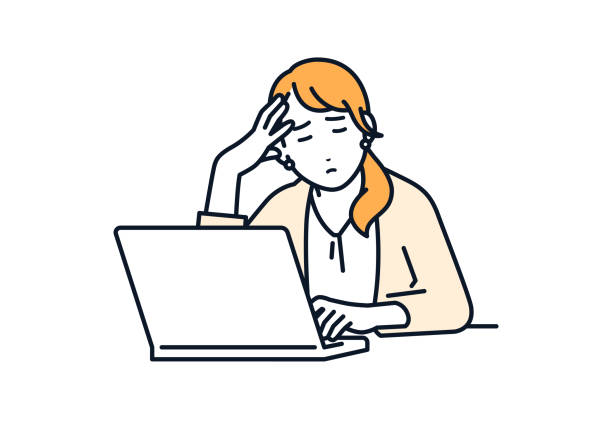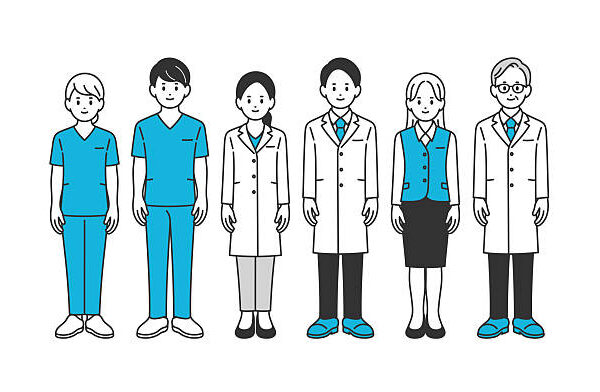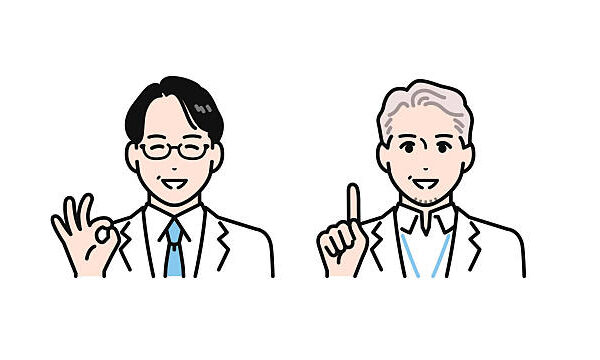双極性障害は「躁」と「うつ」という気分の波を繰り返す精神疾患で、1型と2型では症状の現れ方に違いがあります。
そのため、接し方を誤ると本人の症状を悪化させたり、支える側が疲弊して共倒れになってしまうことも少なくありません。
家族や恋人、職場の人が「どう接すればいいのか分からない」と悩むのは自然なことです。
本記事では「双極性障害1型 接し方」「双極性障害2型 接し方」を中心に、それぞれの特徴や適切な関わり方を解説します。
さらに、家庭・恋人関係・職場での具体的な対応方法や、支える側が共倒れを防ぐためのセルフケア、相談先についても紹介します。
正しい理解と接し方を身につけることで、本人の回復を支えると同時に、周囲も無理なく安心して関わることができます。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。
双極性障害1型の接し方

双極性障害1型は強い躁状態が現れるのが特徴で、本人だけでなく周囲の人にとっても対応が難しい場面が多くあります。
躁のときは活動的すぎてトラブルを招きやすく、うつのときは重度の落ち込みが続くため、両方の状態に合わせた接し方が必要です。
ここでは、双極性障害1型の人に接する際に意識すべき具体的なポイントを紹介します。
- 躁状態のときの関わり方(刺激しすぎない・見守りが基本)
- 抑うつ状態のときの接し方(安心感を与え、無理をさせない)
- トラブル防止のための具体的配慮(お金・人間関係・社会生活)
- 家族や恋人が注意すべきポイント
双極性障害1型では「症状を理解し、過度に振り回されないこと」が大切な姿勢となります。
躁状態のときの関わり方(刺激しすぎない・見守りが基本)
躁状態では気分が高揚し、多弁や浪費、衝動的な行動が目立ちます。
このときに正面から強く否定すると、かえって反発を招きやすくなります。
基本は刺激を与えすぎず、見守る姿勢を取ることです。
無理に行動を止めようとせず、必要であれば医師や専門家に相談して調整を依頼しましょう。
環境を静かに保ち、トラブルを避ける工夫を周囲が行うことが有効です。
抑うつ状態のときの接し方(安心感を与え、無理をさせない)
躁状態の後には強いうつが訪れることが多く、本人は強い無気力や自責感に苦しみます。
このときに「頑張れ」「早く元気になって」と声をかけるのは逆効果です。
必要なのは安心感を与え、休める環境を整えることです。
「そばにいるよ」「ゆっくりで大丈夫」といった受け止める姿勢が本人の安心につながります。
家族や恋人は焦らず、治療を継続できるよう支えることが大切です。
トラブル防止のための具体的配慮(お金・人間関係・社会生活)
躁状態では金銭感覚が乱れたり、対人関係で衝突が増えることがあります。
そのため、金銭管理を家族が一時的に代行するなど、トラブルを防ぐ仕組みを作ることが有効です。
また、SNSや人間関係での過度な交流を制限し、不要なトラブルを避ける工夫も必要です。
社会生活では、仕事量を調整したり、休職を検討することも再発予防に役立ちます。
本人の自由を奪うのではなく、安全を守るための一時的なサポートとして配慮することが大切です。
家族や恋人が注意すべきポイント
家族や恋人は「病気の症状」と「本人の性格」を分けて考えることが重要です。
躁やうつの行動をそのまま「本人の意思」と捉えてしまうと、関係が悪化しやすくなります。
また、支える側が疲れすぎないようセルフケアを行うことも欠かせません。
必要に応じて第三者の支援を受け、「一人で支えすぎない」意識を持つことが、長期的な関係を守るカギになります。
双極性障害1型では、症状の激しさを理解しつつ、冷静にサポートする姿勢が求められます。
双極性障害1型の接し方

双極性障害1型は、強い躁状態と重いうつ状態が繰り返される病気です。
躁のときは活動的になりすぎてトラブルを招きやすく、うつのときは強い落ち込みに苦しむため、周囲の適切な接し方が欠かせません。
ここでは、双極性障害1型の人と関わる際に押さえておきたい接し方の基本を解説します。
- 躁状態のときの関わり方(刺激しすぎない・見守りが基本)
- 抑うつ状態のときの接し方(安心感を与え、無理をさせない)
- トラブル防止のための具体的配慮(お金・人間関係・社会生活)
- 家族や恋人が注意すべきポイント
接し方を工夫することで、本人の回復を支え、周囲も疲弊せずに関わることができます。
躁状態のときの関わり方(刺激しすぎない・見守りが基本)
躁状態では気分が高揚し、活動量が増え、衝動的な行動や浪費が目立ちます。
このときに強く止めようとしたり、激しく叱責すると、逆に反発を招いてトラブルが悪化することがあります。
大切なのは、刺激を与えすぎず見守る姿勢を保つことです。
環境を静かに整え、必要があれば医師に相談して薬の調整を検討してもらいましょう。
躁状態では本人に「自覚がない」ことが多いため、冷静に対応することが重要です。
抑うつ状態のときの接し方(安心感を与え、無理をさせない)
躁状態の後には強いうつ状態が訪れることが多く、本人は深い無気力や自責感に苦しみます。
このときに「頑張れ」「気の持ちようだ」といった言葉をかけるのは逆効果です。
必要なのは、安心感を与え、無理をさせないことです。
「そばにいるよ」「焦らなくて大丈夫」といった受け止める言葉が本人を支えます。
周囲は焦らず、治療や休養を継続できる環境を整えることが大切です。
トラブル防止のための具体的配慮(お金・人間関係・社会生活)
躁状態では金銭トラブルや人間関係の衝突が起きやすくなります。
そのため、一時的に金銭管理を家族がサポートする、SNSの使い方を制限するなどの工夫が役立ちます。
また、仕事や学業では、業務量を減らしたり休職を検討するなど、無理をさせない環境づくりが必要です。
「本人の自由を奪う」のではなく「安全を守るための一時的な配慮」と捉えることが重要です。
こうした工夫が、再発や大きなトラブルの予防につながります。
家族や恋人が注意すべきポイント
家族や恋人は、症状と性格を切り分けて考えることが大切です。
躁やうつの行動をそのまま「本人の意思」と受け取ってしまうと、関係が悪化するリスクがあります。
また、支える側が無理をしすぎて疲れ切ってしまうのも避けなければなりません。
セルフケアを行い、必要に応じて第三者の支援を受けることは、本人を支える上でも重要です。
冷静さを保ち、病気の特性を理解したうえで接することが、信頼関係を守りながら支えるポイントとなります。
双極性障害2型の接し方

双極性障害2型は、軽躁状態と抑うつ状態を繰り返すことが特徴です。
1型ほど激しい躁状態はありませんが、抑うつが長く続く傾向があり、本人も周囲も疲弊しやすい病気です。
接し方のポイントは「軽躁に振り回されないこと」と「抑うつに寄り添うこと」です。
ここでは、双極性障害2型の人と関わる際に意識すべき具体的な対応について解説します。
- 軽躁状態への対応(勢いに巻き込まれない)
- 抑うつ状態が長引くときの支え方
- 「気分の波」を理解し、ペースを合わせる工夫
- 接する側のストレス管理
双極性障害2型では、症状の変化を理解しながら柔軟に接することが大切です。
軽躁状態への対応(勢いに巻き込まれない)
軽躁状態では、普段より活動的になったり、社交的になったりと一見「元気そう」に見えることがあります。
しかし、その勢いに周囲が巻き込まれると、無理な計画や過度な行動に付き合うことになり、後で本人も疲れ果ててしまいます。
「元気だから大丈夫」ではなく「病気の一部」と理解することが大切です。
本人の提案や行動に対しては冷静に判断し、必要があればやんわり制止したり医師に相談することも考えましょう。
軽躁状態に巻き込まれないことが、症状の悪化を防ぐ第一歩です。
抑うつ状態が長引くときの支え方
双極性障害2型はうつ症状が長引く傾向があり、本人は無気力や絶望感に苦しむ時間が多くなります。
このときに「早く元気になって」「頑張って」と励ますのは逆効果です。
必要なのは安心感を与え、無理をさせない支え方です。
「休んでいてもいい」「できることから少しずつでいい」といった受け入れる言葉が本人の心を軽くします。
また、治療の継続をサポートし、生活リズムを安定させる工夫を一緒に行うことが有効です。
「気分の波」を理解し、ペースを合わせる工夫
双極性障害2型では、気分の波に合わせて生活リズムを調整することが大切です。
軽躁と抑うつを繰り返すため、周囲は「波がある病気」であることを理解し、一定のペースを本人に押し付けないようにしましょう。
例えば、軽躁のときに予定を詰め込みすぎず、抑うつのときには小さな目標にとどめるなど、柔軟な対応が必要です。
「今日は無理でも、明日は少しできるかもしれない」といった視点を持つことで、本人の自己否定感を和らげられます。
気分の波を前提に生活を整えることは、再発予防にもつながります。
接する側のストレス管理
双極性障害2型の人を支える周囲は、自分のストレス管理を怠らないことが重要です。
長引く抑うつや突然の軽躁に付き合ううちに、支える側も疲れ切ってしまうことがあります。
そのため「一人で抱え込まない」意識を持ち、信頼できる人やカウンセラーに相談する習慣をつけましょう。
趣味や休養の時間を持つことも、支える力を長く保つために欠かせません。
接する側が健康を守ることが、本人の安定を支える土台になります。
家族ができる支援

双極性障害を抱える本人にとって、家族の存在は大きな支えになります。
しかし、支え方を誤ると症状が悪化したり、家族自身が疲弊して「共倒れ」になるリスクもあります。
ここでは、家族ができる具体的な支援方法と、その際に意識すべきポイントを解説します。
- 否定せずに話を聞き、感情を受け止める
- 症状の変化を観察し、治療に協力する
- 共倒れを防ぐためのセルフケア
「無理をしない」「一人で抱え込まない」ことが、家族にとって最も大切な支援の姿勢です。
否定せずに話を聞き、感情を受け止める
家族ができる最も基本的な支援は、本人の気持ちを否定せずに受け止めることです。
躁状態や抑うつ状態では、普段なら言わないような言葉や行動が出ることがあります。
そのときに「そんなこと考えるのはおかしい」「気にしすぎだ」と否定してしまうと、本人はますます孤立感を深めてしまいます。
「そう感じているんだね」「つらい気持ちがあるんだね」と共感を示すだけで、本人は安心を得られます。
解決策をすぐに提示する必要はなく、まずは安心して気持ちを話せる環境を整えることが大切です。
症状の変化を観察し、治療に協力する
双極性障害は、症状の波がある病気です。
そのため、家族が日々の様子を観察し、変化を見逃さないことが重要です。
「睡眠時間が極端に減っている」「急に活動的になった」「強い落ち込みが続いている」といったサインを記録しておくと、診察時に役立ちます。
本人が治療に前向きになれないときも、通院や服薬をサポートすることが必要です。
ただし、過度に管理しすぎると本人が負担に感じることもあるため、バランスを意識して協力することが大切です。
共倒れを防ぐためのセルフケア
家族が支える上で忘れてはならないのが、自分自身のセルフケアです。
「自分が頑張らなければ」と無理をし続けると、家族が心身を壊して共倒れになってしまいます。
趣味やリフレッシュの時間を持つ、信頼できる人に気持ちを話す、カウンセリングを受けるなど、自分を守る工夫が必要です。
また、地域の家族教室やサポート団体を活用するのも有効です。
家族が健康でいることが、本人の安定と回復を支える最も大切な基盤になります。
恋人として接する場合のポイント

双極性障害を抱える恋人を支えるとき、愛情と現実のバランスを取ることがとても大切です。
気分の波によって関係が不安定になりやすく、支える側も「どう接すればいいのか分からない」と悩むことがあります。
ここでは、恋人として無理なく寄り添うための具体的なポイントを解説します。
- 「病気」と「性格」を切り分けて考える
- 無理に励まさず、寄り添う姿勢
- 将来の関係を考える上で大切な視点
恋人関係を長く続けるためには、正しい理解と適切な距離感が欠かせません。
「病気」と「性格」を切り分けて考える
双極性障害の症状が出ているときの言動を、そのまま「性格」や「本心」と受け取ってしまうと関係が悪化しやすくなります。
躁状態での衝動的な発言や、抑うつ状態での否定的な言葉は、病気の影響であることが多いのです。
「これは病気の症状であって、その人自身の本質ではない」と切り分けて考えることで、余計な衝突や傷つきを防ぐことができます。
病気を理解する姿勢は、恋人にとっても安心感につながります。
無理に励まさず、寄り添う姿勢
抑うつ状態のときに「元気を出して」「もっと頑張ろう」と励ますのは逆効果になることがあります。
本人はすでに「頑張れない自分」に苦しんでいるため、励ましの言葉がプレッシャーになるのです。
大切なのは、無理に元気づけるのではなく寄り添う姿勢です。
「そばにいるよ」「話したくなったら聞くよ」といった安心感を与える言葉が有効です。
沈黙の時間を共有するだけでも、恋人にとっては大きな支えになります。
将来の関係を考える上で大切な視点
双極性障害は長期的に付き合っていく病気であり、恋人関係にも影響を及ぼします。
そのため、将来を考えるうえで病気の理解とサポート体制が重要になります。
結婚や同居を考える場合には、生活リズムや経済面への影響も含めて話し合う必要があります。
「病気があるから無理」と諦めるのではなく、「どう工夫すれば一緒に歩めるか」を考える姿勢が大切です。
恋人同士がお互いの負担にならないよう、適度な距離感を持ちつつ協力し合うことが、長く関係を続けるための鍵となります。
職場での接し方と配慮

双極性障害を抱える社員にとって、職場での理解とサポートは症状の安定に大きく影響します。
一方で、職場が適切に配慮できないと本人が無理を重ねて悪化したり、周囲が負担を感じて人間関係が悪化することもあります。
ここでは、職場で取り入れられる具体的な配慮と接し方のポイントを紹介します。
- 業務の調整(過負荷を避ける)
- 休職・復職への理解と支援
- 職場全体での情報共有と理解促進
組織全体が柔軟に対応することで、本人の働きやすさと周囲の安心感を両立できます。
業務の調整(過負荷を避ける)
双極性障害を持つ社員にとって、過度な業務負担は症状の悪化につながります。
躁状態では一時的にエネルギーが高まり「できる」と思って無理を引き受けてしまうことがあり、後に抑うつ状態で大きな反動が来ることがあります。
そのため、上司や同僚は「一時的な元気さ」に惑わされず、業務量を安定的に調整することが大切です。
具体的には、納期に余裕を持たせたり、分担を明確にすることで本人と周囲双方の負担を減らせます。
業務の無理を防ぐことは、本人の健康維持と組織全体の効率向上につながります。
休職・復職への理解と支援
双極性障害は休職と復職を繰り返すことも少なくありません。
職場に戻る際、いきなりフルタイムで働くと再び悪化するリスクが高まります。
そのため、段階的な復職(短時間勤務や業務内容の調整)を取り入れることが望ましいです。
また、復職直後は「周囲に迷惑をかけているのでは」と本人が不安を感じやすいため、上司や同僚が理解を示すことが重要です。
柔軟な支援体制が整っていることで、本人は安心して仕事に取り組め、再発防止にもつながります。
職場全体での情報共有と理解促進
特定の上司や同僚だけが理解していても、職場全体に共有されていなければサポートは不十分です。
必要に応じて人事や産業医を交え、業務上の配慮点をチーム全体で確認しておくことが大切です。
「どう声をかければいいか」「どの業務を任せるべきか」といった共通理解があれば、対応に一貫性が生まれ、本人も安心できます。
また、職場研修やメンタルヘルス教育を導入し、双極性障害に対する偏見や誤解をなくすことも効果的です。
全体での理解促進は、本人の働きやすさと組織の健全な環境づくりの両方に貢献します。
共通して大切な接し方の基本

双極性障害は1型・2型いずれも気分の波を繰り返す慢性的な病気であり、接し方には共通して押さえるべき基本があります。
家族や恋人、職場など立場は違っても、本人の状態を理解し、治療を続けられる環境を整えることが大切です。
また、支える側が孤立せずサポートを受けることも欠かせません。
- 病気を理解し「波があること」を受け入れる
- 治療(薬物療法・心理社会的支援)の継続を支える
- 周囲も相談機関やカウンセリングを活用する
これらの基本を意識することで、本人と周囲双方の負担を軽減し、安定した関係を築くことができます。
病気を理解し「波があること」を受け入れる
双極性障害では躁と抑うつの波が繰り返し訪れます。
周囲が「なぜ急に元気になったのか」「どうして急に落ち込むのか」と混乱すると、対応に疲れてしまいがちです。
大切なのは「波がある病気」だと理解し、症状を性格や意思と切り離して受け止めることです。
本人に対して「また落ち込んでいる」「さっきまで元気だったのに」と否定的な言葉をかけないよう注意しましょう。
波を前提に生活を調整することで、無理なく長期的な支援を続けることができます。
治療(薬物療法・心理社会的支援)の継続を支える
双極性障害の安定には、薬物療法と心理社会的支援の継続が不可欠です。
躁のときは「もう薬はいらない」と考えて服薬を中断することがあり、再発のリスクが高まります。
家族や恋人、職場は「治療の継続が回復につながる」と理解し、必要に応じて受診や服薬をサポートしましょう。
ただし過度に監視すると本人のストレスになるため、「一緒に確認する」「受診を応援する」といった協力的な関わり方が効果的です。
治療を支えることは、再発防止と安定した生活の維持に直結します。
周囲も相談機関やカウンセリングを活用する
双極性障害を支える側も孤立しないことが大切です。
家族教室や支援団体、保健センターなどの相談機関を利用することで、正しい知識や実践的なアドバイスを得られます。
また、支える人自身がカウンセリングを受けて気持ちを整理することも効果的です。
「自分も相談していい」と思えるだけで心が軽くなり、無理なく本人に寄り添えるようになります。
周囲が安心できる環境を持つことが、本人の安定にも大きくつながります。
よくある質問(FAQ)

双極性障害の接し方について、多くの人が抱く疑問に答えます。
1型と2型の違いや、躁・うつそれぞれの対応、家族や職場での配慮など、具体的なポイントを理解しておくことは支える上でとても大切です。
Q1. 双極性障害1型と2型で接し方はどれくらい違う?
1型と2型では症状の特徴が異なるため、接し方にも違いがあります。
1型は躁状態が強く出るため「刺激しすぎない・暴走を防ぐ」対応が必要です。
一方で2型は抑うつが長引きやすいため「安心感を与え、無理をさせない」関わり方が重要です。
つまり、1型は衝動を抑えるための見守り、2型は長期的な落ち込みに寄り添う姿勢がポイントになります。
両者に共通して大切なのは「病気の波を理解し、性格とは切り離して接する」ことです。
Q2. 躁状態のときに注意すべき行動は?
躁状態では、浪費・多弁・衝動的な行動が出やすいため注意が必要です。
このときに強く止めたり叱責するのは逆効果で、反発を招きやすくなります。
金銭管理を一時的にサポートしたり、不要な人間関係のトラブルを避けるために環境を調整することが効果的です。
また「元気そうだから大丈夫」と放置せず、必要なら医師に相談して薬の調整を依頼することも大切です。
冷静に見守りつつ、安全を守る工夫を取り入れましょう。
Q3. 抑うつ状態のときはどう声をかける?
抑うつ状態のときは「頑張って」「早く元気になって」と励ますのは避けましょう。
本人はすでに「頑張れない自分」に苦しんでおり、励ましがプレッシャーになることがあります。
代わりに「そばにいるよ」「ゆっくりで大丈夫」といった安心感を与える言葉が有効です。
また、沈黙を共有するだけでも本人にとっては支えになります。
声かけよりも「安心できる環境を整える」ことを意識しましょう。
Q4. 家族が疲れてしまったらどうすればいい?
家族が限界を感じたときは、まず自分の休養を優先することが大切です。
「逃げたい」「もう無理」と感じるのはSOSのサインであり、無理を続けると共倒れにつながります。
信頼できる友人や支援団体に相談する、カウンセリングを受けるなど外部の力を借りましょう。
家族が健康でいることは本人の回復を支えるためにも欠かせません。
「自分を守ることも支援の一部」と意識することが重要です。
Q5. 職場でできる最小限の配慮は?
職場では業務の過負荷を避ける配慮が基本です。
短時間勤務や業務分担の調整を行い、急な休職や復職にも柔軟に対応できる体制を整えましょう。
また「励まし」よりも「無理をさせない」姿勢が求められます。
産業医や人事と連携し、チーム全体で対応方法を共有することも有効です。
特定の人に負担を集中させず、職場全体で支える仕組みを作ることが重要です。
双極性障害1型・2型に合わせた接し方で支え合う

双極性障害は1型と2型で症状や特徴が異なるため、接し方にも違いがあります。
1型では躁状態の暴走を防ぐ工夫、2型では抑うつへの寄り添いが特に重要です。
共通して大切なのは「病気の波を理解し、無理なく支えること」です。
また、家族や恋人、職場など支える側もセルフケアや相談先を活用し、共倒れを防ぐ姿勢を持つことが必要です。
双極性障害は一人で抱える病気ではなく、本人と周囲が協力して支え合うことで安定した生活につながります。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。