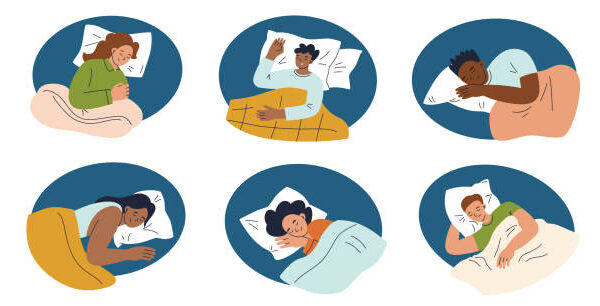うつ病は本人だけの問題ではなく、家族・恋人・職場など周囲の人にも大きな影響を与える病気です。
最初は「支えてあげたい」という思いから寄り添っていても、長期間続くと疲労やストレスが積み重なり、支える側が限界を迎えることもあります。
その結果、周囲まで心身を消耗し、いわゆる「共倒れ」の状態に陥ってしまうケースも少なくありません。
しかし、支える側が疲れてしまうのは決して冷たいことではなく、自然な反応です。
大切なのは「支える側もサポートを受けながら無理なく関わること」であり、それが結果的に本人の回復にもつながります。
本記事では「うつ病 周りが疲れる」「うつ病 共倒れ」をテーマに、家族・恋人・職場ごとに周囲が疲れる理由、共倒れを防ぐ考え方、支える側のセルフケアと相談先まで詳しく解説します。
「どう接したらいいのか分からない」「自分も限界かもしれない」と悩む方に、実践的なヒントをお届けします。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。
うつ病は本人だけでなく周囲にも影響する

うつ病は本人の心身に大きな負担を与える病気ですが、家族・恋人・職場など周囲の人にも影響を及ぼします。
支える側は「なんとか力になりたい」と思う一方で、長期的なサポートにより精神的・身体的に疲弊してしまうことも少なくありません。
ここでは、なぜ周囲が疲れてしまうのか、その背景や典型的なシーンを解説します。
なぜ周囲が疲れるのか?心理的・身体的負担の理由
うつ病の人を支える周囲が疲れる理由には、心理的な負担と身体的な負担の両方があります。
心理的な負担としては、本人の落ち込みや不安に寄り添う中で、支える側も感情的に巻き込まれてしまう点が挙げられます。
「自分の声かけが逆効果になっていないか」「支えきれない自分は冷たいのではないか」といった罪悪感や無力感が積み重なり、精神的に疲弊するのです。
一方で身体的な負担としては、夜眠れない本人に付き合ったり、家事や生活面の負担が増えることで、支える人自身の生活リズムが崩れてしまうケースがあります。
こうした心身両面の疲労が重なることで、周囲も限界を迎えるリスクが高まります。
「共倒れ」が起きる仕組みと背景
共倒れとは、うつ病の本人だけでなく、支えている周囲の人まで心身の不調に陥る状態を指します。
その背景には「本人を助けたい」という思いから無理を続けてしまう構造があります。
例えば家族は、本人の世話や感情のサポートを最優先するあまり、自分の休養や健康管理を後回しにしがちです。
恋人の場合は「自分しか支える人がいない」という責任感から孤立し、強いプレッシャーを抱えやすくなります。
職場では、同僚や上司がフォローを続ける中で業務負担が増し、組織全体が疲弊していくことがあります。
このように、本人を思う気持ちが強いほど周囲が無理をし、結果的に「共倒れ」が生じやすいのです。
周囲が疲れを感じやすい典型的なシーン
周囲が疲れを強く感じるシーンにはいくつかのパターンがあります。
家庭では、本人の気分の波に振り回され、予測できない行動に対応し続けることが精神的負担になります。
恋人関係では、デートや将来の話ができず、孤独感や不安が募るケースがよく見られます。
職場では、休職や業務の遅れをカバーするために残業が増えたり、人間関係の緊張が高まったりします。
また、支える側が「自分の努力が報われていない」と感じると、無力感や疲労が一気に増します。
こうした典型的なシーンを理解することは、共倒れを防ぐ第一歩になります。
家族が疲れるケースと対応策

うつ病の本人を支える家族は、最も身近な存在であるがゆえに心身の負担を抱えやすい立場です。
毎日の生活を共にしているため、家事や育児などの現実的な負担に加え、感情面のサポートも担わなければならず、気づかぬうちに疲れが蓄積していきます。
ここでは、家族が疲れてしまう典型的な状況と、その対応策について解説します。
- 家事・育児・介護が重なり負担が増える
- 感情の起伏に振り回されるつらさ
- 家族が限界に近づいているサイン
- 共倒れを避けるために家族ができる工夫
家族の疲れを理解し、適切に対応することは「共倒れ」を防ぐうえで重要なポイントです。
家事・育児・介護が重なり負担が増える
うつ病の本人が十分に家事や生活の役割を果たせなくなると、その負担は家族に集中します。
家事・育児・介護などが重なれば、支える側は心身ともに疲弊してしまいます。
「自分が頑張らなければ」と無理を続けると、家族自身の生活リズムが崩れ、心の余裕を失いやすくなります。
こうした状況では、行政の家事支援サービスやファミリーサポート、親族や友人の協力を得ることが有効です。
一人で背負い込まず、役割を分担することが長期的な支援を続けるカギとなります。
感情の起伏に振り回されるつらさ
うつ病の症状には感情の起伏の激しさが含まれることがあります。
無気力で一日を過ごすこともあれば、突発的に怒りや涙があふれることもあります。
家族はその変化に振り回され、「どう接したらよいのか分からない」と悩み、心理的に疲れてしまうのです。
対応策としては、本人の感情に過度に反応せず「病気の症状」と切り離して考えることが大切です。
また、家族教室やカウンセリングなど専門家の支援を活用し、感情の受け止め方を学ぶことも役立ちます。
家族が限界に近づいているサイン
支える家族自身が限界に近づいているサインを見逃さないことも重要です。
代表的なサインには「眠れない」「イライラが止まらない」「涙が自然に出る」といった心身の不調があります。
さらに「もう顔を見るのもつらい」「逃げたい」といった感情が芽生えたときは危険信号です。
これらのサインが現れたら、家族も休息を取る・信頼できる人に相談するなど、自分を守る行動を優先する必要があります。
家族が倒れてしまっては、本人を支えることもできません。
共倒れを避けるために家族ができる工夫
うつ病のケアを続ける中で共倒れを防ぐ工夫は欠かせません。
まず、自分自身の趣味やリラックス時間を確保し、心を回復させる習慣を持つことが大切です。
また、行政の支援サービスや専門医のサポートを活用し、負担を一人で抱え込まない工夫をしましょう。
「自分も支援を受けていい」という意識を持つことが、長期的に支え続けるための基盤になります。
家族が健康を保つことが、本人の回復にも直結することを忘れずに取り組むことが重要です。
恋人が疲れるケースと対応策

うつ病のパートナーを支える恋人は、強い愛情や責任感から全力で寄り添おうとします。
しかし、長期的なサポートは孤独感や不安定さを生み、恋愛関係そのものに影響を及ぼすことがあります。
ここでは、恋人が疲れてしまう典型的な状況と、関係を長く続けるための対応策を解説します。
- 支える側が孤独を感じる理由
- 恋愛関係が不安定になるパターン
- 無理に支えすぎない接し方
- 長く関係を続けるための工夫
「愛しているからこそ支えたい」という気持ちと「自分も疲れてしまう」という現実のバランスを取ることが大切です。
支える側が孤独を感じる理由
恋人がうつ病になると、支える側は強い孤独感を抱きやすくなります。
本人が気分の落ち込みから会話を避けることが増えるため、コミュニケーション不足に陥りやすいのです。
「自分の気持ちを話せない」「相談できる人がいない」と感じ、次第に孤立していきます。
また、周囲に病気のことを打ち明けられず一人で抱え込むケースも多く、精神的な疲労が蓄積します。
孤独を防ぐには、信頼できる友人やカウンセラーに自分の気持ちを共有することが効果的です。
支える側が孤立しない環境を持つことが、長期的な関係維持につながります。
恋愛関係が不安定になるパターン
うつ病は恋愛関係にも影響を与えます。
例えば、相手が突然連絡を絶ったり、約束を守れなくなることがあります。
支える側は「嫌われたのでは」「自分のせいでは」と不安を感じ、関係が不安定になります。
また、性的な関心の低下や愛情表現の減少も起こりやすく、パートナーとしての距離感に戸惑うことがあります。
このような変化は病気の症状によるものであり、必ずしも愛情の欠如ではないと理解することが大切です。
冷静に捉えることで、不必要な誤解や衝突を防げます。
無理に支えすぎない接し方
恋人を支えるときに注意したいのは、無理に背負い込みすぎないことです。
「自分が頑張れば相手は治る」と考えると、支える側が疲弊し共倒れのリスクが高まります。
大切なのは、病気の治療は医師や専門家の役割であり、恋人は安心できる存在として寄り添うことです。
「できること」と「できないこと」を区別し、過度に責任を抱えないようにしましょう。
一緒に病院に行く、生活の一部を支援する程度にとどめ、自分の生活や健康を犠牲にしないことが大切です。
無理をしない接し方こそが、長期的な支えにつながります。
長く関係を続けるための工夫
恋人として関係を続けるためには、互いのバランスを意識する工夫が必要です。
例えば、定期的に自分の時間を確保し、趣味や休養で心をリフレッシュすることが有効です。
また、病気のことを一人で抱え込まず、第三者や専門機関に相談する習慣をつけましょう。
「支える」だけでなく「一緒に休む」「共に小さな目標を立てる」といった関わり方も効果的です。
恋人関係は病気によって形を変えることもありますが、その中で無理なく継続できる方法を見つけることが重要です。
お互いの健康を守ることが、信頼と関係の継続につながります。
職場が疲れるケースと対応策

うつ病は家庭だけでなく職場にも大きな影響を与える病気です。
特に同僚や上司は、業務のしわ寄せや人間関係の摩擦によって疲弊してしまうことがあります。
「どこまでフォローすべきか」「本人にどう接するべきか」が分からず、職場全体のストレスが増すことも少なくありません。
ここでは、職場で疲れが生じやすい典型的なケースと、対応策について解説します。
- 休職や遅刻・欠勤による業務のしわ寄せ
- 同僚や上司が抱えるストレス
- 職場でできる配慮と工夫
- 産業医や人事部門への相談の重要性
職場が適切に対応することで、本人と周囲の両方の負担を軽減することができます。
休職や遅刻・欠勤による業務のしわ寄せ
うつ病の社員が休職や遅刻・欠勤を繰り返すと、その分の業務が周囲にしわ寄せされます。
同僚は残業や担当業務の増加に直面し、結果的にストレスや疲労が蓄積してしまいます。
また、欠勤が予測できない場合は、業務計画の調整が難しくなり、組織全体の効率低下にもつながります。
対応策としては、業務を特定の人に集中させず、チーム全体で分担できる仕組みを作ることが重要です。
さらに、本人が休職に入る場合は、早めに役割を調整することで負担を最小限に抑えられます。
同僚や上司が抱えるストレス
うつ病の社員を支える立場にある同僚や上司も強いストレスを抱えることがあります。
「どう声をかけたらよいのか分からない」「配慮しなければならないが業務も進めなければならない」といった板挟みの状況が続くのです。
また、業務フォローに加え、精神的なサポートを担うことになり、疲労感や無力感が強まります。
このような状況を放置すると、職場全体の人間関係が悪化するリスクがあります。
同僚や上司自身も相談できる環境を整えることが、ストレスを軽減するカギとなります。
職場でできる配慮と工夫
うつ病の社員を支えるために、職場ができる配慮はいくつかあります。
まずは無理に「励まそう」とするのではなく、本人の体調や気分に応じて業務を調整することが大切です。
時短勤務やリモートワークを導入し、復職後も徐々に業務に慣れられる環境を作るのも効果的です。
また、チーム内で情報を共有し、特定の人に負担が集中しない仕組みを作ることが必要です。
小さな工夫でも、本人と周囲の双方のストレスを減らすことにつながります。
産業医や人事部門への相談の重要性
職場でうつ病に対応する際には、産業医や人事部門への相談が欠かせません。
専門的な視点から本人の健康状態を把握し、業務量や勤務形態の調整についてアドバイスを受けることができます。
また、上司や同僚が抱えているストレスについても、産業医や人事が調整役となることで軽減されます。
「本人にどう接すればいいか分からない」と感じたら、一人で悩まず専門部署に相談することが重要です。
適切なサポート体制を整えることが、職場全体の健全な環境づくりにつながります。
支える側が限界を感じるサイン

うつ病の人を支える家族や恋人、職場の同僚など支える立場にある人も、知らず知らずのうちに心身を消耗しています。
「まだ大丈夫」と思っていても、限界が近づくと身体や言葉、感情にサインが現れます。
ここでは、支える側が限界を迎えつつあるときに見られる代表的な兆候について解説します。
- 「疲れた」「もう無理」と口にすることが増えた
- 自分の生活や健康が犠牲になっている
- 怒りや苛立ちが抑えられなくなる
- 無気力や不眠など二次的な症状が出ている
これらのサインに早めに気づき、自分自身のケアを優先することが「共倒れ」を防ぐ第一歩です。
「疲れた」「もう無理」と口にすることが増えた
支える立場の人が「疲れた」「もう無理」と頻繁に口にするようになったら要注意です。
これは心身のエネルギーが限界に近づいているサインであり、すでに強いストレスを抱えていることを示しています。
最初は愚痴として口にしていても、繰り返すうちに本音となり、支える意欲が低下していきます。
この状態を放置すると、支える側自身が燃え尽き症候群のようになり、うつ状態に陥る危険もあります。
「口に出している時点でSOS」と捉え、休養や相談を検討することが大切です。
自分の生活や健康が犠牲になっている
うつ病の人を支えるあまり、自分の生活や健康を犠牲にしているケースも多くあります。
睡眠時間を削って世話をしたり、食生活が乱れる、仕事を後回しにするなどが続くと、支える側が先に倒れてしまいます。
「自分がやらなければ」という気持ちは大切ですが、無理をしすぎると長続きしません。
支える側も健康を保つことが、結果的に本人を支えることにつながります。
生活や健康を犠牲にしていると感じたら、役割を分担したり外部のサポートを導入することが必要です。
怒りや苛立ちが抑えられなくなる
支える立場の人が怒りや苛立ちをコントロールできない状態になったら、それは限界が近いサインです。
最初は小さな苛立ちでも、疲れが積み重なることで「どうして分かってくれないのか」「もう嫌だ」と強い怒りに変わることがあります。
怒りを本人にぶつけてしまうと、関係が悪化し、本人の症状がさらに悪化する可能性もあります。
苛立ちが募ったときは、自分の中に余裕がなくなっている証拠です。
感情を抑えられない状態になったら、一度距離をとり休養を取ることが必要です。
無気力や不眠など二次的な症状が出ている
支える側に無気力や不眠といった二次的な症状が出るのも危険信号です。
「やる気が出ない」「趣味に興味が持てない」「夜眠れない」などは、ストレス過多による心身のSOSです。
この状態が続くと、支える側自身がうつ状態に陥るリスクがあります。
無気力や不眠が見られたら、休息や医療機関での相談を検討する必要があります。
本人を支えるためにも、自分の心と体の健康を守ることが最優先です。
共倒れを防ぐために大切な考え方

うつ病の人を支える家族や恋人、職場の同僚などは、「共倒れ」というリスクを常に抱えています。
共倒れとは、本人を支える側まで心身の健康を失ってしまう状態であり、本人にとっても支える人にとっても望ましくありません。
そのためには、支える姿勢や考え方を見直すことが不可欠です。
- 完璧に支えようとしない
- 第三者の力を借りることは恥ではない
- 本人と「距離を取る」選択も必要な場合がある
「支える側が健康でいること」が、最終的には本人の回復を助ける最も大切な要素になります。
完璧に支えようとしない
うつ病の人を支えるとき、「自分がしっかり支えなければならない」という気持ちが強すぎると、支える側が消耗してしまいます。
完璧に支えようとするほど、相手の改善が見られなかったときに「自分のせいだ」と感じてしまい、無力感や罪悪感に苦しむことになります。
大切なのは「自分にできること」と「自分ではできないこと」を切り分けることです。
治療や病状の改善は医師や専門家の役割であり、家族や恋人は安心できる環境を整える存在であれば十分です。
支えることに全力を注ぎすぎず、無理のない範囲で関わることで、長期的にバランスのとれたサポートが可能になります。
第三者の力を借りることは恥ではない
第三者の力を借りることをためらう人は少なくありません。
「家族なのだから自分が支えなければ」「恋人として弱音を吐けない」と考える人も多いですが、それは共倒れを招く大きな要因になります。
カウンセラー、医師、地域の支援機関、友人や親族など、頼れる人やサービスは数多く存在します。
支える側が相談することで気持ちが軽くなり、冷静に対応できる余裕が生まれます。
「助けを求めること」は弱さではなく、自分と本人を守るための賢明な選択です。
第三者の力を取り入れることが、共倒れを防ぎ、本人の回復にもつながります。
本人と「距離を取る」選択も必要な場合がある
うつ病の人を支える中で、一時的に距離を取ることも必要な場合があります。
四六時中そばにいると、支える側の心が休まらず、イライラや疲労が限界に達してしまうからです。
物理的に距離をとって休養したり、感情的に深く入り込みすぎない工夫をすることは、支える人自身を守るために有効です。
一見冷たいように感じるかもしれませんが、自分が健康を保つことが最終的には本人のためにもなります。
「一緒にいる時間」と「自分の時間」のバランスを取りながら関わることが、共倒れを防ぐ現実的な方法です。
距離を取る勇気も、長期的に関係を続けるうえで大切な選択肢のひとつです。
家族・恋人・職場ができる具体的なサポート

うつ病の人を支えるときに大切なのは、「無理なく続けられる支援」を行うことです。
本人の症状や状況に合わせたサポートを行うことで、支える側の負担を減らしつつ、本人に安心感を与えることができます。
ここでは、家族・恋人・職場が実践できる具体的なサポート方法を紹介します。
- 否定せずに話を聞き、感情を受け止める
- 必要以上に抱え込まず「小さなサポート」にとどめる
- 職場での理解促進(情報共有・業務調整)
- 一緒に医療機関や相談先につなげる
周囲が適切に関わることで、本人の回復と共倒れ防止の両方につながります。
否定せずに話を聞き、感情を受け止める
うつ病の人が悩みや不安を口にしたときに、否定せずに受け止めることは非常に重要です。
「そんなこと気にしすぎ」「頑張れば大丈夫」といった言葉は、本人を追い詰めてしまう可能性があります。
まずは「そう感じているんだね」「つらかったね」と共感を示し、安心できる場を提供することが支えになります。
解決策を急いで提示する必要はなく、ただ気持ちを吐き出せること自体が回復の一歩になります。
否定せずに耳を傾ける姿勢は、家族・恋人・職場に共通する基本的なサポート方法です。
必要以上に抱え込まず「小さなサポート」にとどめる
支える側が必要以上に抱え込むと、心身に大きな負担がかかり共倒れにつながります。
そのため「すべてを解決する」必要はなく、できる範囲の小さなサポートにとどめることが大切です。
例えば「一緒に食事をとる」「病院に行く日をリマインドする」など、無理なくできる行動を積み重ねるだけで十分です。
支える側が元気でいることが、長期的な支援を続ける条件になります。
本人に寄り添いながらも、自分の生活や健康を優先することを忘れないようにしましょう。
職場での理解促進(情報共有・業務調整)
職場では、情報共有と業務調整が重要なサポートとなります。
上司や同僚が本人の状況を把握し、業務を適切に分担することで過度な負担を防ぐことができます。
また「励まし」よりも「無理をさせない環境づくり」が求められます。
復職の際には、短時間勤務や段階的な業務復帰を取り入れるとスムーズに職場へ戻りやすくなります。
産業医や人事部門と連携しながら、チーム全体で支える姿勢を持つことが大切です。
一緒に医療機関や相談先につなげる
うつ病の人が自分から医療機関に行く決断をするのは簡単ではありません。
そのため、家族や恋人が「一緒に行こう」と声をかけ、同行することが有効です。
一人では不安でも、信頼できる人と一緒なら受診のハードルが下がります。
また、職場の場合も産業医や外部の相談窓口へつなげるサポートが役立ちます。
本人に「助けを求めてもいい」という安心感を与えることが、回復の大きな一歩となります。
相談や受診につなげる役割は、周囲だからこそできる大切なサポートです。
支える側のセルフケアと相談先

うつ病を支える家族や恋人、職場の人たちにとって、「自分を守ること」は決してわがままではありません。
むしろ支える側が健康を保つことで、本人へのサポートを無理なく続けることができます。
そのためにはセルフケアと相談先の活用が欠かせません。
- 自分の時間や趣味を大切にする
- カウンセリングや家族教室を活用する
- 公的支援窓口やピアサポートを利用する
- 医療機関での「家族外来」を検討する
支える側が健やかでいることは、本人の回復を支える基盤となります。
自分の時間や趣味を大切にする
うつ病の人を支えていると、自分の生活や楽しみを後回しにしてしまうことがよくあります。
しかし、それでは支える側が疲弊してしまい、共倒れのリスクが高まります。
読書や映画鑑賞、運動、友人との時間など、自分がリフレッシュできる時間を意識的に確保しましょう。
「自分の時間を持つこと」に罪悪感を抱く必要はありません。
むしろ、自分を整えることが本人を支える力につながります。
日常生活に小さな楽しみを取り入れることが、セルフケアの第一歩です。
カウンセリングや家族教室を活用する
カウンセリングや家族教室は、支える側にとって有効な支援手段です。
専門家に話を聞いてもらうことで、抱えている不安やストレスを安心して吐き出せます。
また、家族教室では同じ立場の人と交流できるため、「自分だけではない」と感じられるのも大きなメリットです。
病気の正しい知識や対応方法を学ぶことができ、無理のない関わり方を身につけられます。
カウンセリングや教室は、家族全体のストレス軽減にもつながります。
支える側が安心できる環境を持つことは、共倒れを防ぐ重要なポイントです。
公的支援窓口やピアサポートを利用する
公的支援窓口やピアサポートの活用も、支える人にとって心強い選択肢です。
地域の保健センターや「こころの健康相談統一ダイヤル」、自死予防の「いのちの電話」などは、匿名で利用できる安心感があります。
また、ピアサポートは「同じ経験を持つ人」による支援であり、共感や実践的なアドバイスを得ることができます。
周囲に話しにくい悩みも、専門の相談窓口やピアサポーターであれば安心して話せます。
こうしたサポートを利用することは弱さではなく、自分と本人を守るための積極的な行動です。
医療機関での「家族外来」を検討する
最近では、うつ病の本人だけでなく家族を対象にした「家族外来」を設けている医療機関も増えています。
家族外来では、医師や専門スタッフから直接アドバイスを受けることができ、支えるうえでの疑問や不安を相談できます。
また、家族自身のストレス状態をチェックしてもらえるため、必要に応じて治療やケアを受けることも可能です。
「支える側も医療の対象になれる」という意識を持つことが大切です。
家族外来を利用することで、無理なく支え続けるための知識と安心感を得ることができます。
本人の治療と並行して、家族が支援を受けることが共倒れ防止の大きな力となります。
よくある質問(FAQ)

うつ病の人を支えている家族や恋人、職場の人が抱きやすい疑問に答えます。
「疲れてしまう自分は冷たいのでは?」「どこまで支えればいいの?」といった悩みを解消することで、共倒れを防ぎ、無理のない支援につながります。
Q1. うつ病の人を支えていて疲れるのは冷たい?
冷たいのではなく自然な反応です。
うつ病を支えることは大きな心理的・身体的エネルギーを必要とし、長期化すると疲れを感じるのは当然のことです。
疲れると感じる自分を責める必要はなく、「支える側にも限界がある」と認識することが大切です。
むしろ、自分の疲れに気づくことが共倒れを防ぐ第一歩になります。
Q2. 共倒れを防ぐ第一歩は何?
一人で抱え込まないことが第一歩です。
家族や恋人、職場だけで解決しようとすると、支える側が疲弊しやすくなります。
医師やカウンセラー、公的支援窓口など外部の力を借りることで、負担を分散できます。
「助けを求めるのは弱さではない」と意識することが、共倒れ防止の大切な出発点です。
Q3. 家族が限界に感じたらどうすればいい?
家族が限界を感じたときは、まず自分を優先して休むことが必要です。
「逃げたい」「もう無理」と感じるのはSOSのサインです。
親戚や地域の支援サービスに頼る、カウンセリングを受けるなど、外部の手を借りて負担を減らしましょう。
家族が健康を守ることは、本人を支えることと同じくらい重要です。
Q4. 恋人がうつ病で、支えるのが苦しいときの対応は?
恋人を支えるときは、「無理に頑張りすぎない」ことが大切です。
恋人の病気を背負い込もうとすると、関係が破綻しやすくなります。
病気の治療は医師の役割であり、恋人は「安心できる存在」であれば十分です。
自分の生活や健康を犠牲にせず、距離を保ちながら寄り添う姿勢を意識しましょう。
Q5. 職場でどこまで配慮すべき?
職場での配慮は「業務上の合理的な調整」にとどめることが基本です。
具体的には、短時間勤務や業務量の調整、復職支援のための段階的復帰などが挙げられます。
一方で、過度な個人的支援を同僚や上司が担う必要はありません。
産業医や人事部門と連携し、組織全体でサポートできる仕組みを作ることが重要です。
Q6. 支える側がカウンセリングを受けてもいい?
もちろん受けて構いません。
むしろ、支える側がカウンセリングを受けることはとても有効です。
専門家に気持ちを話すことでストレスが軽減し、冷静な対応ができるようになります。
「自分のために相談するのは贅沢では?」と思う必要はありません。
支える側が健やかでいることが、本人を守る最大の力になります。
うつ病は「支える人」も守ることが大切

うつ病は本人だけでなく、支える家族や恋人、職場の人にとっても大きな負担となります。
共倒れを防ぐためには、支える側が自分の心身を守りながら無理なく関わることが欠かせません。
完璧を目指さず、第三者や公的支援の力を借りながら支えることで、長期的な支援が可能になります。
「支える人も支えられていい」という意識を持ち、周囲のサポートを取り入れることが本人の回復にもつながります。
うつ病は一人で抱える病気ではなく、支える人も共にケアを受けながら向き合うことが大切です。