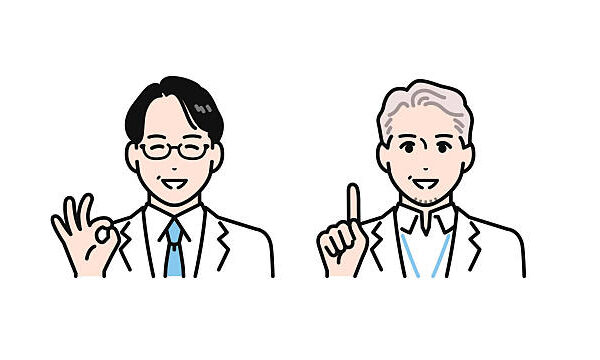双極性障害(躁うつ病)は、気分が高揚する「躁状態」と、落ち込む「うつ状態」を繰り返す精神疾患です。
「どんな性格の人がなりやすいのか?」という疑問は多くの人が抱くテーマですが、実際には性格だけで発症が決まるわけではなく、遺伝的要因やストレス、環境要因なども大きく関わります。
本記事では、双極性障害になりやすい性格の特徴、背景にある原因やリスク、さらに予防や対処法まで詳しく解説します。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。
双極性障害になりやすい性格の特徴

双極性障害は「躁状態」と「うつ状態」を繰り返す精神疾患ですが、その発症には性格傾向も一定の影響を与えると考えられています。
もちろん性格だけで病気が決まるわけではなく、遺伝や脳内の働き、環境要因が複雑に絡み合っています。
しかし、特定の性格的特徴を持つ人はストレスの影響を受けやすく、発症や症状の悪化につながるリスクがあるのです。ここでは、双極性障害になりやすいとされる性格の特徴を5つ紹介します。
- 感受性が強く影響を受けやすい
- 完璧主義や責任感が強い
- 衝動的で行動に波が出やすい
- 自己評価の変動が大きい
- 人間関係に敏感でストレスを抱えやすい
それぞれの詳細について確認していきます。
感受性が強く影響を受けやすい
双極性障害になりやすい人の特徴としてまず挙げられるのが「感受性の強さ」です。
周囲の環境や人の言葉、ちょっとした出来事に大きく影響を受けやすいため、気分が急に高揚したり落ち込んだりする傾向があります。
芸術的才能や創造性と結びつく一方で、ネガティブな刺激にも敏感に反応しやすく、精神的な疲弊を招きやすい点がリスクになります。
感受性が強い人は長所も多いですが、ストレスや不安が積み重なると、双極性障害の症状を悪化させるきっかけとなる可能性があります。
完璧主義や責任感が強い
双極性障害の発症リスクが高い性格傾向として「完璧主義」や「強い責任感」も挙げられます。
常に自分に厳しく「完璧にやらなければならない」と考える人は、達成できなかったときに強い自己否定感を抱きやすくなります。
また、責任感が強すぎると無理をしてでも目標を達成しようとし、心身に過剰な負担をかけてしまいます。
これが躁状態を引き起こしたり、その反動でうつ状態に陥ったりする要因となることがあります。自分を追い込みすぎない工夫が必要です。
衝動的で行動に波が出やすい
双極性障害に関連する性格の一つに「衝動性」があります。
気分の変化に伴って、計画性よりもその時の感情に基づいて行動してしまう傾向があり、買い物の浪費や突発的な決断に結びつくことがあります。
このような行動の波は本人も制御しにくく、躁状態では過活動や不眠、うつ状態では極端な無気力につながります。
衝動性自体はエネルギッシュな面を持つ長所でもありますが、双極性障害のリスクを高める性格的要因になり得るのです。
自己評価の変動が大きい
「自分は何でもできる」という自信にあふれる時期と、「自分はダメだ」と過度に落ち込む時期の差が大きい人も、双極性障害のリスクが高いといわれます。
自己評価の変動が激しいと、ちょっとした成功や失敗に一喜一憂しやすく、気分の安定を保つことが難しくなります。
この心理的な波は双極性障害の特徴である気分の極端な変動と結びつきやすく、発症や悪化の背景要因になると考えられています。安定した自己肯定感を持つためのサポートが重要です。
人間関係に敏感でストレスを抱えやすい
人間関係に敏感で、他人の反応や評価を強く気にする人も双極性障害になりやすい傾向があります。
小さな誤解や人間関係の摩擦でも深く傷つきやすく、それが強いストレスとなって心のバランスを崩してしまうのです。
特に「嫌われたのではないか」「役に立てていないのでは」といった思い込みは、不安や落ち込みを助長します。
人間関係のストレスは躁状態やうつ状態を引き起こす要因にもなるため、適切な距離感を持ち、ストレスを減らす工夫が必要です。
性格だけではない!双極性障害の原因

双極性障害は「なりやすい性格」があるとよく言われますが、実際には性格だけで発症が決まるわけではありません。
遺伝的要因、脳の神経伝達物質の異常、強いストレスや生活環境、さらには睡眠リズムの乱れなど、複数の要因が重なり合って発症すると考えられています。
そのため、単に「性格の問題」と片付けてしまうのは誤解です。ここでは、双極性障害の原因として注目される代表的な4つの要因について詳しく解説します。
- 遺伝的要因と家族歴
- 脳内神経伝達物質のアンバランス
- 強いストレスやライフイベント
- 睡眠リズムの乱れとの関係
それぞれの詳細について確認していきます。
遺伝的要因と家族歴
研究によると、双極性障害は遺伝的要因の影響を強く受けることが分かっています。
家族や近親者に双極性障害やうつ病などの気分障害を持つ人がいる場合、発症リスクが高まるとされています。
ただし「必ず遺伝する」というわけではなく、あくまで発症しやすい素因を持つという意味です。
遺伝的リスクを持っていても、適切な生活習慣やストレス管理を行うことで発症を防げる可能性があります。
つまり、家族歴は重要な要因ですが、それだけで決まるものではありません。
脳内神経伝達物質のアンバランス
双極性障害は脳の働きと深く関係しています。
特にセロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリンといった神経伝達物質のバランスが崩れることが、躁状態やうつ状態の引き金になると考えられています。
これらの物質は「感情」「行動」「意欲」に大きな影響を与えるため、アンバランスが生じると気分の波が極端になりやすくなります。
この脳内の変化は本人の意思ではコントロールできないため、医学的な治療(薬物療法など)が必要になるケースが多いのです。
強いストレスやライフイベント
双極性障害の発症や悪化には、ストレスが大きく関与します。例えば、進学・就職・結婚・転職・離婚・大切な人の死など、大きなライフイベントは心に強い負担をかけます。
こうしたストレスは誰にでも影響を与えますが、もともと気分障害の素因を持つ人にとっては発症や再発の引き金となりやすいのです。
また、日常的なストレス(人間関係の不和や仕事のプレッシャー)が積み重なることも症状を悪化させます。
ストレスをうまく軽減することが予防にもつながります。
睡眠リズムの乱れとの関係
双極性障害と深い関わりがあるのが「睡眠リズムの乱れ」です。
不眠や過眠、昼夜逆転などの生活習慣は、気分の安定に大きな影響を与えます。
特に躁状態の前には睡眠時間が極端に短くなる傾向があり、逆にうつ状態では過眠が目立つことがあります。
睡眠の乱れは脳内の神経伝達物質にも悪影響を与え、症状を悪化させる要因となります。
そのため、双極性障害の治療や予防において「規則正しい睡眠習慣を守ること」は非常に重要なポイントとされています。
双極性障害と間違えやすい性格傾向

双極性障害は「気分の波が大きい病気」として知られていますが、実際には性格的な特徴や他の心理的傾向と混同されやすいのが特徴です。
HSP(繊細な気質)やパーソナリティ障害、一時的な気分の浮き沈みと誤解されるケースが少なくありません。
これらは一見すると似ているように見えますが、背景や持続性、生活への影響に明確な違いがあります。
ここでは、双極性障害と混同されやすい代表的な傾向について解説します。
- HSP(繊細な気質)との違い
- パーソナリティ障害との区別
- 一時的な気分の波との見極め
それぞれの詳細について確認していきます。
HSP(繊細な気質)との違い
HSP(Highly Sensitive Person)は、刺激に敏感で人の感情や環境の変化に強く反応する気質を持つ人を指します。HSPの人も気分の浮き沈みを経験しやすいですが、その根本は「外部刺激への過敏さ」であり、脳内の神経伝達物質の異常とは異なります。一方、双極性障害は医学的に認められた気分障害であり、躁状態とうつ状態が周期的に繰り返され、生活や社会機能に大きな影響を及ぼします。つまり、HSPは性格的な傾向であるのに対し、双極性障害は治療が必要な病気である点が大きな違いです。
パーソナリティ障害との区別
双極性障害と混同されやすいもう一つの特徴が「パーソナリティ障害」です。特に境界性パーソナリティ障害(BPD)は感情の起伏が激しく、人間関係が不安定になりやすいため、双極性障害と間違われることがあります。しかし、双極性障害は明確に躁状態とうつ状態が周期的に現れるのに対し、パーソナリティ障害は慢性的かつ持続的に感情が不安定である点が異なります。また、治療方法も異なり、双極性障害では薬物療法が重要ですが、パーソナリティ障害では心理療法が中心となります。正確な診断には専門医の評価が不可欠です。
一時的な気分の波との見極め
誰にでも「今日は気分がいい」「なんとなく落ち込む」といった気分の変化はあります。
しかし、それは一時的で日常生活に大きな支障を与えることは少ないものです。
一方、双極性障害の気分の波は数日から数週間、場合によっては数か月単位で続き、仕事や学業、人間関係に深刻な影響を及ぼします。
また、躁状態では浪費や過活動、不眠といった行動の変化が現れる点も特徴です。
つまり「普通の気分の波」と「双極性障害の気分変動」は、その持続性と生活への影響度合いで明確に区別できます。
双極性障害を悪化させやすい性格的傾向

双極性障害は性格だけで発症する病気ではありませんが、特定の性格傾向を持つ人は症状を悪化させやすいといわれています。
我慢強く無理を重ねる人、周囲に気を遣いすぎる人、そして自分の不調を口に出せない人は、知らず知らずのうちに心身に負担をかけ、症状を長期化・重症化させるリスクがあります。
ここでは、双極性障害を悪化させやすい性格的傾向を3つ取り上げ、それぞれの特徴と注意点を解説します。
- 我慢強く無理を重ねやすい
- 周囲に気を遣いすぎる
- 自分の不調を人に言えない
それぞれの詳細について確認していきます。
我慢強く無理を重ねやすい
双極性障害を悪化させやすい性格の一つに「我慢強さ」があります。
本来は美徳とされる資質ですが、限界を超えて無理を続けることで心身に大きな負担を与えます。
特に責任感が強い人は「休んではいけない」「周囲に迷惑をかけてはいけない」と考え、体調が悪化しても頑張りすぎる傾向があります。
その結果、躁状態を誘発したり、エネルギーを使い果たした反動でうつ状態が深刻化することがあります。
我慢するのではなく、適切に休むことが重要です。
周囲に気を遣いすぎる
人間関係において過剰に気を遣うタイプの人も、双極性障害を悪化させやすい傾向があります。
他人の期待に応えようと無理をしたり、断れない性格のためにストレスをため込みやすいのです。
特に躁状態の時はエネルギーが高まり「やります」と引き受けすぎてしまい、その反動でうつ状態が一気に訪れることがあります。
周囲に配慮することは大切ですが、自分の限界を意識し「できないことは断る勇気」を持つことが、病気の悪化を防ぐためには欠かせません。
自分の不調を人に言えない
双極性障害を抱える人の中には「弱みを見せたくない」「心配をかけたくない」と考え、不調を周囲に伝えられない人が少なくありません。
しかし、不調を隠していると治療や支援を受けるタイミングを逃し、結果的に症状を悪化させてしまうリスクが高まります。
また、自分だけで抱え込むことで孤独感や自己否定感が強まり、回復が遅れることもあります。
調子が悪いときは「言いにくいけれど少し辛い」と伝えるだけでも十分です。小さな共有が大きな支えにつながります。
双極性障害と日常生活への影響

双極性障害は気分の波が大きく、躁状態と抑うつ状態を繰り返す病気です。
そのため、症状は本人の心身だけでなく、日常生活のさまざまな領域に影響を及ぼします。
仕事や学業のパフォーマンス、恋愛や結婚生活の安定、家族や友人との関係など、社会的な生活全般に強く関わってくるのです。
ここでは、双極性障害が与える代表的な日常生活への影響について3つの視点から解説します。
- 仕事や学業への影響
- 恋愛や結婚生活への影響
- 家族関係や人間関係への影響
それぞれの詳細について確認していきます。
仕事や学業への影響
双極性障害は仕事や学業に大きな影響を及ぼします。躁状態のときはエネルギーが高まり、過剰な仕事量を引き受けたり、集中力が散漫になったりすることがあります。
一見すると「積極的で能力が高い」と評価されることもありますが、その裏には無理を重ねている場合が多く、反動として強い抑うつ状態に陥るリスクがあります。
うつ状態に入ると欠勤や不登校が増え、パフォーマンスが大きく低下します。この繰り返しは本人の自信を失わせ、キャリア形成にも悪影響を与えます。
恋愛や結婚生活への影響
恋愛や結婚生活においても双極性障害の影響は無視できません。躁状態では衝動的な行動が増え、浪費や浮気などトラブルにつながることがあります。
一方、抑うつ状態では自己否定感が強まり、パートナーとの関係に不安を抱えやすくなります。
この気分の波は相手に理解してもらうのが難しく、誤解や摩擦が生じやすいのです。
ただし、病気の特性をお互いに理解し合い、無理のない生活リズムを共有することで、安定した関係を築くことも可能です。理解と協力が鍵となります。
家族関係や人間関係への影響
双極性障害は家族関係や人間関係にも深い影響を与えます。
気分の波が大きいため、周囲が戸惑ったり不安を抱えたりすることが少なくありません。
躁状態のときは言動が攻撃的になる場合があり、家族や友人との摩擦を生みやすくなります。
逆に抑うつ状態では孤立感が強まり、周囲との関係が希薄になりやすい傾向があります。
結果として「信頼を失うのでは」と不安を抱えるようになり、人間関係の悪循環に陥ることがあります。家族や周囲の理解とサポートが欠かせない部分です。
双極性障害の予防・セルフケア

双極性障害は遺伝的要因や脳内の働きなど、完全に予防することが難しい側面があります。
しかし、日常生活の工夫やセルフケアによって、発症リスクを下げたり、症状の悪化や再発を防ぐことは可能です。
特に「生活リズムの安定」「ストレス管理」「十分な睡眠」「アルコールや刺激物のコントロール」は、予防と症状の安定に大きく関わる重要なポイントです。
ここでは、日常で取り入れやすいセルフケア方法を4つ紹介します。
- 規則正しい生活リズムを保つ
- ストレスマネジメント(運動・呼吸法)
- 睡眠習慣を整える
- アルコールや刺激物を控える
それぞれの詳細について確認していきます。
規則正しい生活リズムを保つ
双極性障害の予防と安定には「生活リズムの一定化」が欠かせません。
毎日の起床・就寝時間をそろえ、食事や活動のタイミングを一定にすることで、自律神経やホルモンのバランスが整いやすくなります。
特に不規則な生活は躁状態やうつ状態のきっかけになりやすいため、生活のリズムを守ることは再発予防にも直結します。
無理に活動を増やす必要はなく、「同じ時間に起きる・寝る」といった基本を徹底することが、安定した生活の基盤となります。
ストレスマネジメント(運動・呼吸法)
双極性障害の症状はストレスに敏感に反応するため、ストレスマネジメントが重要です。
適度な運動(ウォーキングやヨガなど)は、心身をリフレッシュさせ、ストレスホルモンを軽減します。
また、深呼吸や瞑想、マインドフルネスなどの呼吸法を取り入れることで、自律神経を整え、不安や緊張を和らげる効果が期待できます。
大切なのは「日常的に続けられる方法」を取り入れることです。
小さな工夫を積み重ねることで、ストレスに強い心身をつくることができます。
睡眠習慣を整える
双極性障害は「睡眠リズムの乱れ」と強く結びついています。
躁状態の前には睡眠時間が短くなり、うつ状態のときには過眠に陥るケースが多く見られます。
そのため、毎日の睡眠習慣を整えることは再発予防に直結します。就寝前はスマホやパソコンを控え、リラックスできる環境を整えることが効果的です。
また、日中に適度な運動や日光を浴びることで自然な眠気を促しやすくなります。
睡眠を軽視せず、「眠りの質」を意識することが大切です。
アルコールや刺激物を控える
アルコールやカフェインなどの刺激物は、気分の波を大きくする要因となることがあります。
アルコールは一時的に気分を高める作用がありますが、その後に強い落ち込みを招くことが多く、症状の悪化や再発のリスクを高めます。
カフェインも睡眠の質を下げ、生活リズムを乱す原因となるため注意が必要です。
完全に禁止する必要はありませんが、「摂取量を減らす」「夜は控える」といった工夫が予防につながります。
生活習慣を見直すことは、小さな一歩でも大きな効果をもたらします。
双極性障害の治療とサポート

双極性障害は一時的な気分の浮き沈みではなく、医学的な治療が必要な精神疾患です。
そのため、本人の努力や生活習慣の改善だけでは十分ではなく、専門的な医療サポートを受けることが重要です。
治療は薬物療法を基本に、心理療法や家族療法を組み合わせ、再発を防ぐための長期的なケアが行われます。
ここでは、双極性障害の治療とサポートの主要な方法を4つの観点から解説します。
- 薬物療法(気分安定薬・抗精神病薬)
- 認知行動療法など心理療法
- 家族療法と周囲の理解
- 再発予防のための継続的ケア
それぞれの詳細について確認していきます。
薬物療法(気分安定薬・抗精神病薬)
双極性障害の治療の中心は薬物療法です。代表的なのが気分安定薬(リチウム、バルプロ酸など)で、躁状態やうつ状態の波を抑え、再発を防ぐ効果があります。
また、躁状態が強い場合には抗精神病薬、うつ状態が深刻な場合には抗うつ薬が補助的に使われることもあります。
ただし、抗うつ薬は躁転(うつから躁への切り替わり)を引き起こすリスクがあるため、専門医の管理が不可欠です。
薬物療法は長期にわたる継続が前提であり、自己判断で中止せず、医師の指示に従うことが大切です。
認知行動療法など心理療法
薬物療法に加え、心理療法も有効です。特に「認知行動療法(CBT)」は、自分の思考の偏りを見直し、症状を悪化させる思考パターンを修正するのに役立ちます。
また「対人関係・社会リズム療法(IPSRT)」は、生活リズムを整えながら対人関係のストレスを減らし、再発を防ぐ効果が期待されています。
心理療法は「病気を理解する力」を高め、自分で症状をコントロールするスキルを養う点でも重要です。
薬物療法と併用することで治療効果が高まります。
家族療法と周囲の理解
双極性障害は本人だけでなく、家族や周囲にも大きな影響を与えます。そのため「家族療法」や「心理教育(ペイシェント・エデュケーション)」が有効です。
家族が病気の特性や症状のサインを理解することで、悪化を未然に防ぐことができます。
また、家族の過度な期待や誤解が本人を追い詰めることを避け、サポートの仕方を学ぶ機会にもなります。
周囲の理解と協力は、本人の安心感を支える大きな柱となり、治療継続や社会復帰を後押しします。
再発予防のための継続的ケア
双極性障害は再発率が高いため、治療は「治す」より「コントロールして安定させる」ことが重視されます。
そのためには、定期的な通院や服薬管理に加え、生活リズムの安定、ストレスコントロール、睡眠習慣の改善などが必要です。
また、再発の前兆(気分の高揚、不眠、倦怠感など)に早めに気づくことが大切で、家族や支援者がサインを共有しておくと安心です。
双極性障害と長く付き合うには、本人・家族・医療機関が連携し、継続的なケアを行うことが不可欠です。
家族や周囲ができる接し方

双極性障害の本人にとって、家族や周囲の接し方は症状の安定や回復に大きな影響を与えます。
誤った対応をしてしまうと、本人を追い詰めたり、症状を悪化させてしまうリスクがあります。
大切なのは「否定せず受け止めること」「症状に応じた声かけ」「医療機関への適切なサポート」です。ここでは、家族や周囲ができる具体的な接し方を3つの視点から解説します。
- 否定せず受け止める姿勢
- 躁状態・うつ状態での声かけの工夫
- 医療機関への受診をサポートする
それぞれの詳細について確認していきます。
否定せず受け止める姿勢
双極性障害の本人は、気分の波によって自分でも感情や行動をコントロールできないことがあります。
そのため、家族が「なぜそんなことをするの」「気持ちの持ちようだ」と否定的な言葉を投げかけると、本人はさらに自己否定感を強め、孤立を深めてしまいます。
大切なのは「否定せずに受け止める姿勢」です。「辛いよね」「大変だったね」と共感を示すことで、本人は安心感を得られます。
理解されていると感じることが、症状の安定や治療への前向きな姿勢につながります。
躁状態・うつ状態での声かけの工夫
双極性障害は躁状態とうつ状態で接し方を変える必要があります。
躁状態のときはエネルギーが過剰で衝動的な行動に出やすいため、「落ち着いて」と制止するのではなく、「一緒に考えよう」と穏やかに伝えることが有効です。
一方、うつ状態のときは「頑張って」や「元気を出して」と励ますのではなく、「そばにいるよ」「無理しなくていいよ」と安心感を与える言葉を選びましょう。
症状に応じた声かけが、本人の気持ちを安定させる大きな支えになります。
医療機関への受診をサポートする
双極性障害は本人が自覚していても、医療機関への受診に抵抗を感じることがあります。
「病気だと思われたくない」「薬に頼りたくない」と考える人も少なくありません。
家族や周囲にできることは、無理に受診を強要するのではなく、「一緒に行こうか」「相談するだけでも安心できるかもしれない」と優しく促すことです。
付き添って受診することは本人にとって大きな安心になります。
また、受診後も通院や服薬を続けやすい環境を整えることが、治療の継続につながります。
医師に相談すべきサイン

双極性障害は、症状の程度や現れ方によっては本人や家族だけで対応するのが難しくなることがあります。
特に「気分の波が強く生活に支障を与えている」「衝動的な行動や浪費が目立つ」「自傷や強い希死念慮がある」といったサインは、早急に医師へ相談すべき重要なポイントです。
ここでは、医療機関を受診する目安となる代表的なサインを3つ取り上げ、それぞれ解説します。
- 気分の波が生活に支障を与えている
- 衝動的な行動や浪費が増えている
- 自傷や強い希死念慮が見られる
それぞれの詳細について確認していきます。
気分の波が生活に支障を与えている
双極性障害の特徴である気分の波が強まり、仕事や学業、家庭生活に支障をきたしている場合は、医師に相談するべきサインです。
躁状態では集中力が続かず、無計画に物事を進めて失敗につながることがあります。
逆にうつ状態では倦怠感や意欲の低下から、出勤・登校が困難になるケースも多く見られます。
このように生活に大きな影響が出ている場合、本人の努力だけでは改善が難しいため、医療機関での適切な診断と治療が必要です。
早めの受診が回復への第一歩になります。
衝動的な行動や浪費が増えている
躁状態が強まると、衝動的な行動が目立ち始めます。高額な買い物やギャンブル、無謀な投資など浪費につながる行動は、本人や家族の生活に深刻な影響を及ぼします。
また、対人関係においても衝動的な発言や行動がトラブルを招き、社会生活に悪影響を及ぼすことがあります。
これらの行動は本人の意思だけで制御するのが難しいため、医師に相談して適切な治療を受けることが必要です。
衝動性は双極性障害の重要な症状の一つであり、放置は危険です。
自傷や強い希死念慮が見られる
双極性障害のうつ状態が悪化すると、「死にたい」「消えてしまいたい」といった強い希死念慮が現れる場合があります。
さらに、自分を傷つける自傷行為に至るケースもあり、非常に危険な状態です。
このようなサインが見られる場合は、一刻も早く医療機関に相談する必要があります。
本人が受診を拒んでいても、家族が代わりに医師へ相談することも可能です。
安全を確保し、命を守るためにも、強い希死念慮や自傷があるときは専門家の支援を受けることが最優先です。
よくある質問(FAQ)

Q1. 双極性障害は性格で決まるのですか?
双極性障害は「性格で決まる病気」ではありません。
感受性が強い、完璧主義、衝動性が高いといった性格傾向はリスク因子の一つですが、発症の直接的な原因ではないのです。
実際には遺伝的要因や脳内の神経伝達物質のアンバランス、ストレスや生活習慣の乱れなど、複数の要因が重なって発症します。
そのため「性格のせい」と捉えるのは誤解であり、むしろ正しい理解と医療的なサポートが必要です。
性格は背景の一部にすぎず、病気は体質や環境によっても大きく左右されます。
Q2. 双極性障害になりやすい人の共通点は?
双極性障害になりやすい人には、いくつかの共通点が見られます。代表的なのは「感受性が強い」「完璧主義」「衝動的」「人間関係に敏感」といった性格傾向です。
これらの特徴を持つ人はストレスの影響を受けやすく、気分の波が大きくなることがあります。
ただし、これらの性格を持っていても必ず双極性障害になるわけではなく、遺伝的素因や環境要因が重なることで発症リスクが高まるのです。
共通点はあくまで「なりやすい傾向」であり、性格と病気を同一視しないことが大切です。
Q3. ストレスで双極性障害は悪化しますか?
はい、ストレスは双極性障害を悪化させる大きな要因です。
仕事や学校、家庭でのプレッシャー、人間関係のトラブル、ライフイベント(転職・結婚・離婚・喪失体験など)は、躁状態やうつ状態を引き起こす引き金になることがあります。
特にストレスが長期的に続くと、再発のリスクが高まるため注意が必要です。
そのため治療やセルフケアにおいては「ストレスマネジメント」が欠かせません。
リラクゼーションや運動、趣味の時間を持つことが、症状安定につながります。
Q4. 家族に双極性障害の人がいる場合どう支えればいい?
家族に双極性障害の人がいる場合、最も大切なのは「否定せず受け止める姿勢」です。
「気の持ちようだ」や「頑張れ」といった言葉は逆効果になることがあります。
躁状態のときは行動を制止するのではなく、冷静に一緒に考える姿勢を持ち、うつ状態のときは安心感を与える言葉を選ぶことが重要です。
また、無理に治そうとせず、医療機関への受診や治療の継続を優しくサポートすることも求められます。
家族自身も相談機関を利用し、支える負担を一人で抱え込まないことが大切です。
Q5. 完治する病気ですか?
双極性障害は「一度治療すれば完全に治る」という意味での完治は難しい病気です。
しかし、適切な薬物療法や心理療法を継続し、生活リズムを整えることで、症状を安定させながら日常生活を送ることは十分可能です。
再発を防ぐためには長期的なケアが必要ですが、多くの人が治療とサポートを受けながら仕事や家庭生活を維持しています。
つまり「完治」ではなく「寛解(症状が落ち着いた状態)」を目指し、病気と上手に付き合っていくことが現実的なゴールとなります。
双極性障害は「性格だけでなく環境や体質」が影響する

双極性障害は「性格が原因」と誤解されがちですが、実際には遺伝的要因や脳内の働き、生活環境やストレスなど多くの要因が複雑に絡み合って発症します。
性格的な特徴は発症リスクを高める一因にすぎません。
大切なのは「性格の問題ではない」と正しく理解し、本人や家族が必要以上に自責感を抱かないことです。
早期に医療機関へ相談し、治療やセルフケア、周囲のサポートを組み合わせることで、安定した生活を取り戻すことができます。理解と支援こそが回復の第一歩です。