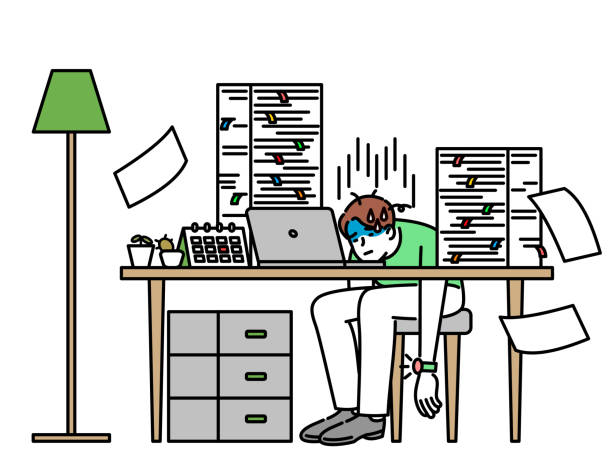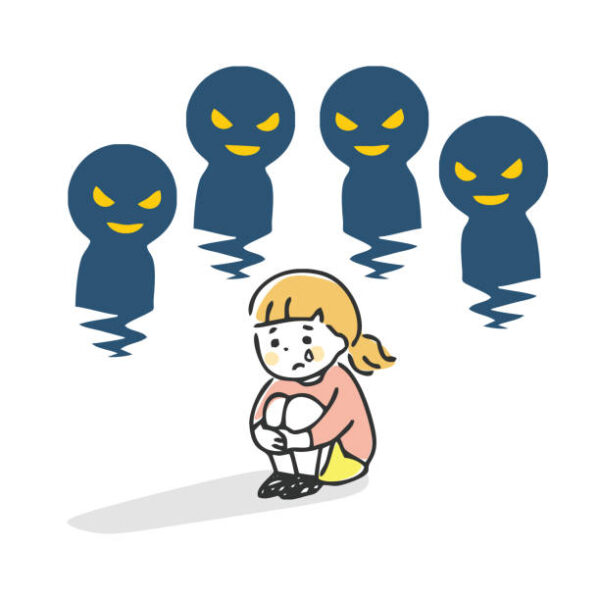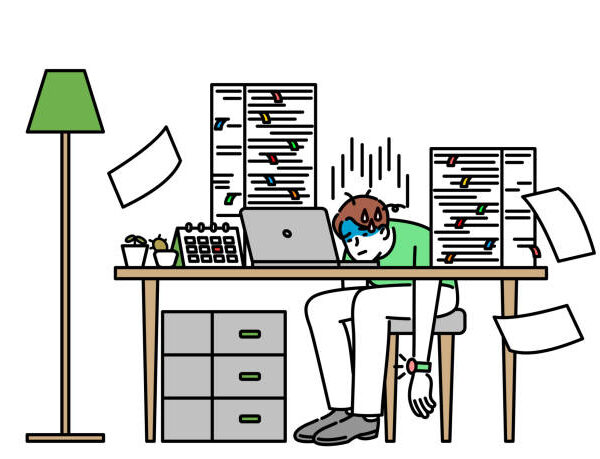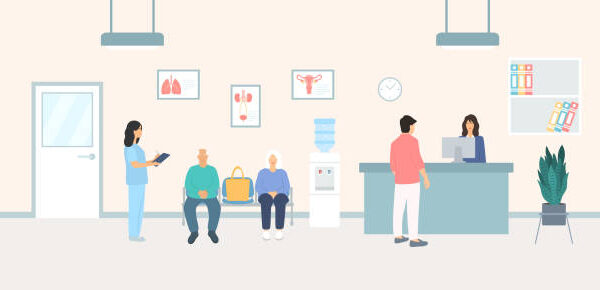「もう会社に行けない」「今すぐ休みたい」と感じたとき、即日で休職できるのかどうかは多くの人が悩むポイントです。
心身に限界を感じながらも、会社への連絡や診断書の準備、休職手続きの流れがわからず不安を抱える方は少なくありません。
実際には診断書があれば即日休職が可能なケースもあれば、まずは有給休暇や欠勤で対応し、後日診断書を提出して休職へ切り替える流れもあります。
この記事では、会社を今すぐ休みたいときの対応方法、即日休職の条件、診断書の取得方法、そして経済的に利用できる制度まで分かりやすく解説します。
「今日から会社に行けない」と思ったときにどう動けばいいかを知ることで、安心して休養に専念できるようになります。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。
会社を今すぐ休みたいと感じるのはどんなとき?

「会社に行けない」と強く感じる背景には、心身の限界や職場環境の問題など、いくつかの共通する要因があります。
一時的な疲労であれば休養で改善することもありますが、続いている場合は深刻なサインです。
ここでは、会社を今すぐ休みたいと感じる代表的なケースについて解説します。
- 強いストレスで出勤ができないとき
- 体調不良や精神的な限界を迎えているとき
- 職場の人間関係やハラスメントが原因の場合
- 無理に働き続けると病状が悪化するリスク
このような状況では、無理に我慢するよりも、適切な休養や専門的なサポートを受けることが大切です。
強いストレスで出勤ができないとき
過度なストレスによって「会社に行くのが怖い」「出勤を考えると動悸や吐き気がする」といった状態になることがあります。
これは心身が限界を迎えているサインであり、無理に働き続けると症状が悪化してしまう危険があります。
強いストレスが続くと集中力の低下や睡眠障害が起こり、仕事のパフォーマンスにも影響が出てしまいます。
こうした場合は「怠けている」のではなく、体が休養を求めている自然な反応です。
出勤が困難になるほどのストレスを感じたら、休職や受診を真剣に検討するべきタイミングです。
体調不良や精神的な限界を迎えているとき
体調不良や精神的な疲労が限界を超えたとき、人は「会社に行けない」と感じるようになります。
例えば、頭痛や胃痛、強い倦怠感、睡眠障害などが長引くと、心身ともに働く余力を失ってしまいます。
また「もう頑張れない」「何をしても楽しくない」と感じるようになったら、うつ病や適応障害の初期症状である可能性もあります。
こうした状態を放置すると、長期的な休職や重度の病気につながるリスクが高まります。
心身の限界を迎えているサインに気づいたら、早めに休養や受診を検討することが大切です。
職場の人間関係やハラスメントが原因の場合
上司や同僚との人間関係の悪化、パワハラやセクハラといったハラスメントは、会社に行きたくない大きな理由になります。
人間関係のストレスは、心身に深刻なダメージを与え、強い不安や恐怖感を引き起こします。
特に「顔を見るだけで胃が痛む」「職場に入るだけで体調が悪化する」といった状態は危険信号です。
無理に耐え続ければ、うつ病や不安障害などの精神疾患に発展することも少なくありません。
職場環境が原因で出勤困難になっているときは、休職や配置転換、専門機関への相談を考えることが必要です。
無理に働き続けると病状が悪化するリスク
「会社に行きたくない」と思いながら無理に働き続けると、心身の病状が悪化するリスクがあります。
疲労やストレスを蓄積したまま仕事を続けると、ある日突然動けなくなる「燃え尽き症候群」や重度のうつ病につながる可能性があります。
また、軽い不調の段階で休めば短期間の休養で回復できることも、限界まで我慢すると長期休職や退職につながることがあります。
「もう限界だ」と感じたときは、心身を守るために立ち止まる勇気が必要です。
無理をして取り返しのつかない状態になる前に、休職や受診を選択することが重要です。
即日休職が可能になる条件

会社を今すぐ休みたいと感じたときでも、全てのケースで即日休職が認められるわけではありません。
即日休職を実現するには、医師の診断書や会社の制度など、いくつかの条件を満たす必要があります。
ここでは、即日で休職が可能になる代表的な条件について解説します。
- 医師が「就業困難」と判断した場合
- 初診で診断書を発行してもらえた場合
- 会社に休職制度が整っている場合
- まずは有給休暇・欠勤でつなぐケース
これらを理解しておくことで、いざというときに冷静に行動しやすくなります。
医師が「就業困難」と判断した場合
即日休職の最も重要な条件は、医師が「就業困難」と判断し診断書を発行してくれることです。
会社は本人の申告だけではなく、医師による客観的な証明をもとに休職を認めます。
診断書には「抑うつ状態により休養を要する」「当面の就業は困難」といった表現が記載されるのが一般的です。
この診断書があることで、会社は即日でも休職を承認することが可能になります。
まずは専門医に相談し、診断書を得ることが即日休職の大前提です。
初診で診断書を発行してもらえた場合
症状が明らかで重い場合には、初診でも診断書を発行してもらえるケースがあります。
「強い気分の落ち込み」「出勤しようとすると体調が悪化する」「不眠や食欲不振が続いている」といった状況は、医師が休職の必要性を即日判断できる典型的な症状です。
ただし、軽度の症状や診断基準に満たない場合は、初診では診断書が出ず、数回の通院を経て発行されることもあります。
即日休職を希望する場合は、予約の段階で「診断書が必要」と伝えておくとスムーズです。
初診で診断書を得られるかどうかは症状の重さと医師の判断に左右されます。
会社に休職制度が整っている場合
会社側に休職制度が整っていることも、即日休職を実現する条件のひとつです。
大企業や公務員の場合、就業規則に「休職制度」が明記されており、診断書の提出によって速やかに休職が承認されます。
一方で、中小企業やベンチャー企業では休職制度が不十分で、診断書を出しても休職ではなく欠勤扱いになるケースもあります。
そのため、会社の就業規則や労務制度を事前に確認しておくことが大切です。
休職制度の有無によって、即日休職が可能かどうかが変わることを理解しておきましょう。
まずは有給休暇・欠勤でつなぐケース
診断書が間に合わない場合や休職制度が整っていない場合は、まず有給休暇や欠勤でつなぐ方法があります。
当日は「体調不良のため休みます」と連絡を入れ、後日診断書を提出して休職に切り替える流れが一般的です。
この場合、有給休暇が残っていれば給与が支払われるため、経済的な不安を軽減できます。
有給が残っていない場合でも、診断書を提出すれば休職扱いに変更してもらえるケースもあります。
すぐに診断書が手に入らないときは、有給や欠勤を使って休養しながら準備を進めることが現実的です。
会社を今すぐ休むための手順

「もう出勤できない」と感じたときは、正しい手順で会社を休むことが大切です。
感情のままに無断欠勤してしまうと、後々トラブルになったり、休職が認められなかったりする可能性があります。
ここでは、会社を今すぐ休むための基本的な流れを解説します。
- 上司や人事に体調不良を理由に連絡する
- 心療内科・精神科を受診して診断書を依頼する
- 診断書を会社に提出して正式に休職に切り替える
- 診断書が間に合わないときの対応方法
- 退職ではなく「休職」を選ぶメリット
焦らずに順を追って行動することが、安心して休養を始めるための第一歩になります。
上司や人事に体調不良を理由に連絡する
まずは直属の上司や人事部に「体調不良のため休む」と連絡することが重要です。
休職の手続きを始める前に、欠勤の理由を明確に伝えておくことで、無断欠勤と誤解されるのを防げます。
このとき「精神的に限界です」と言いにくい場合は「体調不良」と伝えても構いません。
大切なのは、会社に「出勤が難しい状況である」と知らせることです。
連絡を入れるだけでも気持ちが少し楽になり、次のステップへ進みやすくなります。
心療内科・精神科を受診して診断書を依頼する
会社を正式に休職するためには、医師の診断書が必要です。
そのため、できるだけ早く心療内科や精神科を受診しましょう。
予約が必要な場合が多いですが、事情を伝えると即日診察に対応してくれる場合もあります。
診察では「会社に行こうとすると動悸がする」「眠れない」「気分の落ち込みが続く」など、具体的な症状を伝えることが大切です。
医師が就業困難と判断すれば、診断書を即日発行してもらえる可能性があります。
診断書を会社に提出して正式に休職に切り替える
診断書を受け取ったら、速やかに会社へ提出して休職手続きを進めます。
提出先は人事部や直属の上司が一般的で、会社の規定によって異なります。
診断書には「休職が必要な期間」が記載されており、その期間をもとに会社が休職を承認します。
診断書のコピーは自分用に残しておくと、後日の手続きや傷病手当金の申請時に役立ちます。
診断書を提出することで、休職が正式に認められ、安心して療養に専念できる環境が整います。
診断書が間に合わないときの対応方法
初診では診断書が出ない場合や、発行までに数日かかることもあります。
その場合は、有給休暇や欠勤を使って数日間休み、診断書ができ次第提出する方法があります。
会社によっては「後日提出でも可」とする場合があるため、連絡時に確認しておくと安心です。
診断書がなくても「体調不良で休む」と伝えておけば、無断欠勤にはなりません。
診断書が遅れる場合は焦らず、まずは休むことを優先することが大切です。
退職ではなく「休職」を選ぶメリット
「もう会社に行けない」と思ったとき、すぐに退職を選ぶのではなく、まずは休職を検討することをおすすめします。
休職であれば、健康保険の傷病手当金を受け取れる可能性があり、経済的な支援を受けながら療養できます。
また、休職は復職を前提とした制度のため、体調が回復すれば元の職場に戻ることも可能です。
一方で退職を選んでしまうと、収入の確保が難しくなり、生活が不安定になるリスクがあります。
まずは「休職」で心身を整えることが、将来の選択肢を広げるためにも有効です。
診断書が即日発行されるケースとされないケース

診断書は必ずしも初診で即日発行されるとは限らず、医師の判断や症状の程度によって対応が分かれます。
「どうしても今日から休みたい」という状況でも、医師が十分に診断できない場合は数回の受診が必要になることもあります。
ここでは、診断書が即日発行される場合とされない場合の違いについて整理します。
- 初診当日に診断書が発行されるケース
- 数回の診察が必要とされる場合
- 医師が症状を確認できないとき
- 「抑うつ状態」と書かれるケースもある
即日発行の可能性を高めるには、症状を具体的に伝えることが大切です。
初診当日に診断書が発行されるケース
症状が重く、医師が明らかに就業困難と判断した場合には、初診当日でも診断書を発行してもらえることがあります。
例えば「出勤しようとすると強い吐き気や動悸がある」「睡眠がほとんど取れない」「涙が止まらず仕事に集中できない」といった状態は、医師が即日で休職を勧める典型例です。
診断書には「抑うつ状態」「就業困難」などの文言が記載され、休職期間もあわせて示されることが一般的です。
即日で診断書をもらうためには、予約や受付の時点で「診断書が必要」と伝えておくことがポイントです。
明確な症状を示すことで、初診でも診断書が発行されやすくなります。
数回の診察が必要とされる場合
初診だけでは判断できず、数回の診察を経てから診断書が発行されることもあります。
これは、うつ病や適応障害の診断基準に「症状が2週間以上続く」などの条件があるためです。
医師としても限られた診察時間で判断するのはリスクがあるため、経過を見ながら慎重に診断する必要があります。
この場合は、まず有給休暇や欠勤で休み、再診時に診断書を依頼する流れになります。
即日発行されないからといって諦めず、通院を継続することが診断書取得につながります。
医師が症状を確認できないとき
本人の訴えと実際の症状が一致せず、医師が症状を十分に確認できない場合には、診断書の発行が見送られることがあります。
例えば「とてもつらい」と口頭では説明していても、診察時に具体的な症状が見られなければ、医師は就業困難と判断できません。
この場合は、症状の記録をメモに残したり、家族の証言を添えたりすることで診断の補助資料になります。
医師が根拠を確認できれば、次回以降に診断書を発行してもらえる可能性が高まります。
症状を客観的に伝える工夫が、診断書発行のカギになります。
「抑うつ状態」と書かれるケースもある
診断書に必ず病名が記載されるわけではなく、「抑うつ状態」「心身の不調」といった表現に留められることもあります。
これは会社に病名を知られたくない場合や、医師がプライバシーに配慮した場合に選ばれる表現です。
ただし、保険や公的手続きで利用する診断書では、正式な病名の記載が必要になることがあります。
提出先によって必要な記載内容は異なるため、用途を明確にして依頼することが大切です。
「病名を伏せたい」と思う場合は、発行前に医師へ相談しておくと安心です。
診断書が間に合わないときの選択肢

「今日から会社に行けない」と思っても、診断書がすぐに手に入らないことがあります。
初診では医師が慎重に診断を行うため、すぐに診断書を発行してもらえないケースも珍しくありません。
しかし、診断書が間に合わないからといって無理に出勤する必要はなく、いくつかの代替手段があります。
- 有給休暇で一時的に休む
- 欠勤として処理されるリスク
- 診断書を後日提出できる場合
- 無断欠勤との違いを理解する
診断書が発行されるまでの間をどう過ごすかを知っておくことは、安心して休養するために重要です。
有給休暇で一時的に休む
診断書がすぐに手に入らないときは、有給休暇を利用して一時的に休む方法があります。
有給休暇は労働者の権利として認められているため、理由を詳しく説明しなくても「体調不良のため」と伝えるだけで取得できます。
この方法であれば、診断書がなくても正当な休みとして処理され、給与も支払われるため経済的な安心感があります。
ただし、有給休暇の日数には限りがあるため、長期的な休職が必要な場合には後から診断書を提出して正式な休職に切り替える必要があります。
まずは有給で休み、後から診断書を準備するのが現実的な対応です。
欠勤として処理されるリスク
有給休暇が残っていない場合は、診断書が出るまで「欠勤」として扱われることがあります。
欠勤扱いになると給与は支払われませんが、後から診断書を提出することで「欠勤」から「休職」に切り替えられる場合もあります。
ただし、診断書が出る前に長期間欠勤が続くと「自己都合の欠勤」とされるリスクがあるため注意が必要です。
会社によっては、欠勤が長引くと人事評価や今後の雇用に影響を与える可能性もあります。
診断書が出るまでの短期間であれば欠勤も選択肢ですが、早めに受診して正式な休職に切り替えることが大切です。
診断書を後日提出できる場合
会社によっては「診断書を後日提出すればよい」としてくれる場合があります。
特に急な体調不良や精神的な限界によって即日休む必要があるときには、この対応が認められることもあります。
この場合、当日は「体調不良で休む」と連絡し、後日診断書が発行されたタイミングで提出すれば問題ありません。
ただし、会社の就業規則によっては「所定の期日までに提出が必要」と定められていることもあるため、確認が必要です。
後日提出が可能かどうかを事前に確認し、期限を守ることが安心につながります。
無断欠勤との違いを理解する
診断書がなくても、必ず会社に「休みます」と連絡を入れておくことが大切です。
連絡をせずに休むと「無断欠勤」とされ、信頼を大きく損ねてしまうリスクがあります。
一方で「体調不良で休む」と伝えておけば、たとえ診断書が後日になっても正当な理由として認められる可能性が高くなります。
無断欠勤は懲戒処分や解雇の対象になる場合もあるため、必ず最低限の連絡は入れておくことが重要です。
診断書が間に合わなくても、無断欠勤との違いを理解して行動することで自分を守ることができます。
即日休職で利用できる制度

会社を即日休職した場合、経済的な不安を軽減するために活用できる制度があります。
主に健康保険による支給や公的制度、会社独自の福利厚生などを組み合わせることで、安心して療養に専念できる環境を整えることが可能です。
ここでは、即日休職に役立つ代表的な制度について解説します。
- 健康保険の傷病手当金(給与の約3分の2が支給)
- 障害年金との違いを理解する
- 失業給付との併用はできる?
- 自立支援医療制度で医療費を軽減する
- 会社の福利厚生や産業医制度を活用する
制度を正しく知り、適切に申請することで、安心して休職生活を送ることができます。
健康保険の傷病手当金(給与の約3分の2が支給)
休職中の生活を支える最も代表的な制度が「傷病手当金」です。
これは健康保険に加入している人が、業務外の病気やケガで働けなくなった場合に利用できる給付金です。
支給額は給与の約3分の2で、最長1年6か月まで受け取ることが可能です。
支給を受けるには、医師の診断書と会社の証明書が必要になるため、休職が決まったら早めに申請準備を進めることが大切です。
傷病手当金は休職中の収入を補う重要な制度であり、経済的な安心を得るために欠かせません。
障害年金との違いを理解する
傷病手当金と混同されやすい制度に「障害年金」があります。
障害年金は、病気やケガによって長期間にわたり働くことが困難になった場合に支給される年金制度です。
うつ病や適応障害も対象となる場合がありますが、傷病手当金のようにすぐ受け取れるものではなく、申請から審査・決定まで時間がかかります。
また、障害年金は「長期的な就労困難」が条件であり、短期的な休職には利用できません。
傷病手当金は短期的な収入補填、障害年金は長期的な生活保障という違いを理解しておきましょう。
失業給付との併用はできる?
休職中は「失業給付」との併用はできません。
失業給付(雇用保険の基本手当)は、退職して働く意思と能力がある人に支給される制度です。
休職中は雇用契約が続いているため、失業状態とはみなされず、失業給付を受けることはできません。
ただし、退職後に病気で働けない状態が続いている場合は「受給期間延長」の手続きを行うことで、回復後に失業給付を受けられる場合があります。
休職と失業給付は仕組みが異なるため、自分の状況に合わせてどの制度が使えるかを確認することが大切です。
自立支援医療制度で医療費を軽減する
精神科や心療内科に通院する場合には「自立支援医療制度」を利用することで、医療費の自己負担を軽減できます。
この制度を使うと、医療費の自己負担が通常の3割から1割に軽減されます。
対象は、うつ病や適応障害などで継続的に治療が必要な人です。
申請は自治体の福祉課などで行い、医師の診断書が必要になります。
休職中の通院費を抑えるためにも、自立支援医療制度の活用は非常に有効です。
会社の福利厚生や産業医制度を活用する
会社によっては独自の福利厚生や産業医制度を利用できる場合があります。
福利厚生としてカウンセリングサービスや復職支援プログラムを用意している企業もあります。
また、産業医による面談を通じて、復職に向けた準備や勤務条件の調整が行われることもあります。
こうした制度を利用することで、職場復帰がスムーズになり、再発防止にもつながります。
会社独自の制度を確認し、利用できる支援を積極的に活用することが回復への近道です。
会社に診断書を提出するときの注意点

診断書を会社に提出する際には、正しい手順と注意点を理解しておくことが重要です。
診断書は単なる書類ではなく、休職の可否や給与・手当の支給に直結する大切な証明書です。
提出の仕方を誤ると、プライバシーが守られなかったり、休職が認められなかったりするリスクがあります。
- 診断書は人事部や直属の上司に提出する
- 病名が記載される場合のプライバシー対応
- 提出期限を守らないと不利になるリスク
- コピーを残しておく重要性
以下では、それぞれの注意点を詳しく解説します。
診断書は人事部や直属の上司に提出する
診断書は通常、人事部または直属の上司に提出するのが一般的です。
ただし、会社によっては提出先が明確に規定されている場合もあるため、就業規則や人事担当者に確認することが必要です。
直属の上司に提出する場合でも、最終的には人事部が管理を行うことが多く、両方に提出を求められるケースもあります。
診断書は個人情報を含む重要な書類ですので、封筒に入れる、メールではなく直接手渡すなど、取り扱いに配慮しましょう。
正しい提出先と方法を守ることが、スムーズに休職を認めてもらうための第一歩です。
病名が記載される場合のプライバシー対応
診断書には病名が記載される場合がありますが、必ずしも明示されるとは限りません。
医師の判断によっては「抑うつ状態」「心身の不調により加療中」といった表現が使われることもあります。
もし会社に病名を知られたくない場合は、事前に医師に相談して表現を調整してもらうことが可能です。
一方で、保険申請などの場合は病名が必要とされるケースが多く、用途によって診断書の内容が変わります。
プライバシー保護の観点から、診断書にどのような内容が書かれるかを確認し、必要に応じて希望を伝えることが大切です。
提出期限を守らないと不利になるリスク
診断書の提出期限を守らないと、休職が認められず欠勤扱いになるリスクがあります。
会社は就業規則で「診断書を◯日以内に提出」と定めている場合が多く、期限を過ぎると無断欠勤とみなされる可能性があります。
また、診断書が遅れると傷病手当金の申請手続きにも影響し、経済的に不利益を被ることもあります。
診断書がすぐに発行されない場合は、事前に「後日提出になる」と会社へ伝えておくと安心です。
提出期限を守ることは、会社との信頼関係を維持し、手続きを円滑に進めるための基本です。
コピーを残しておく重要性
診断書を会社に提出する前に、必ずコピーを取って手元に保管しておくことが大切です。
診断書は再発行が可能ですが、手間や費用がかかり、内容が微妙に変わってしまうこともあります。
また、会社で紛失されてしまった場合や、後で申請書類を作成するときにコピーが役立つこともあります。
特に傷病手当金や保険金の申請では、診断書の内容を確認する必要があるため、控えを残しておくと安心です。
コピーを残しておけば、自分の記録としても活用でき、トラブル防止につながります。
即日休職と退職の違い

「会社を今すぐ辞めたい」と思ったとき、休職と退職のどちらを選ぶかで将来への影響は大きく変わります。
休職は一時的に仕事を離れて療養するための制度であり、退職は雇用契約そのものを終了させる手続きです。
両者の違いを理解して選択することが、安心して心身を回復させるために重要です。
- 休職は復帰を前提とした制度
- 退職は雇用契約が終了するためリスクもある
- 経済的な支援を受けられるかどうかの違い
- まずは休職で心身を回復させる選択が望ましい
以下で、それぞれの違いを詳しく解説します。
休職は復帰を前提とした制度
休職は「一定期間働けないが、回復すれば復帰すること」を前提とした制度です。
心身の不調で働けないとき、医師の診断書を提出することで休職が認められます。
休職期間中は雇用契約が維持されるため、会社に在籍したまま治療や休養に専念できます。
復職時には診断書を再度提出し、医師と会社の承認を得て仕事に戻る流れが一般的です。
休職は「一時的な休み」であり、雇用を維持したまま心身を立て直せる大きなメリットがあります。
退職は雇用契約が終了するためリスクもある
退職は雇用契約そのものが終了するため、復帰の道がなくなるリスクがあります。
「もう会社に行けない」と感じたとき、勢いで退職を選んでしまう人もいますが、その後に「やっぱり働きたい」と思っても戻ることはできません。
また、退職後は社会保険や住民税の負担が発生し、経済的な不安が増すこともあります。
体調が回復するまでに再就職先を探すのは難しく、生活が不安定になりやすい点にも注意が必要です。
退職は最終手段であり、安易に選ぶと大きなリスクを抱える可能性があります。
経済的な支援を受けられるかどうかの違い
休職と退職では、受けられる経済的支援に大きな違いがあります。
休職中であれば健康保険から「傷病手当金」が支給され、給与の約3分の2を最長1年6か月受け取ることが可能です。
一方で、退職した場合は傷病手当金を継続して受け取れるケースもありますが、条件を満たさないと打ち切られることもあります。
また、退職すると雇用保険の「失業給付」の対象になりますが、病気で働けない間はすぐに受け取れません。
経済的な安心を確保するなら、まず休職を選ぶ方が現実的です。
まずは休職で心身を回復させる選択が望ましい
強いストレスや体調不良で会社に行けないときは、すぐに退職するよりも「休職」で回復を優先する方が望ましいです。
休職であれば雇用を維持しつつ、医師のサポートを受けながら安心して治療や休養に専念できます。
心身が安定してから、復職するか転職するかを冷静に判断する方が将来の選択肢も広がります。
一方で、退職は後戻りできないため、判断は慎重に行う必要があります。
「今すぐ辞めたい」と思ったときこそ、まずは休職で立ち止まり、自分を守ることが大切です。
復職時に必要な診断書について

休職から復帰する際には、多くの会社で「復職用の診断書」の提出が求められます。
これは従業員が本当に働ける状態に回復しているかを確認するためであり、会社の安全配慮義務を果たす意味でも欠かせません。
復職診断書は、休職開始時の診断書とは異なり「働けるかどうか」に重点が置かれています。
- 復職許可診断書を求められるケース
- 「就業可能」の記載が必要な理由
- 医師と会社が共同で復職の可否を判断する
- フォローアップ診断書が必要になる場合
ここでは、復職時に必要となる診断書のポイントを詳しく解説します。
復職許可診断書を求められるケース
休職を終えて復帰する際、会社から「復職許可診断書」の提出を求められることが一般的です。
これは本人の体調が職務に耐えられる状態かどうかを、医師の意見で確認するためです。
特にメンタルヘルスが理由で休職していた場合は、再発防止や職場への影響を考慮して、必ず診断書を提出させる企業も多くあります。
診断書には「通常勤務が可能」「制限付きで勤務可能」などの具体的な所見が書かれます。
復職許可診断書は、本人の意思だけでなく会社の判断を支える重要な証明書です。
「就業可能」の記載が必要な理由
復職時の診断書で最も重視されるのは「就業可能」という表現です。
単に「症状が改善している」と記載されていても、会社は復職を認められない場合があります。
「通常勤務可能」「制限付き勤務可能」などの明確な記載があって初めて、会社は正式に復職を承認できます。
この記載がないと「本当に業務を行えるのか」が不明確となり、復帰の判断が遅れてしまいます。
診断書に「就業可能」の文言が含まれているかは、復職の可否を大きく左右するポイントです。
医師と会社が共同で復職の可否を判断する
復職の可否は医師の診断書だけで決まるのではなく、会社の判断も加わります。
医師が「復職可能」と記載しても、会社側が職務内容や職場環境を考慮し「復帰はまだ難しい」と判断することもあります。
逆に「制限付きであれば復職可能」と医師が記載した場合、会社が時短勤務や軽作業などを調整して復帰を認めるケースもあります。
このように、本人・医師・会社の三者が協力して復職の可否を決めることが重要です。
復職は医師の判断だけではなく、会社との合意のうえで成立することを理解しておきましょう。
フォローアップ診断書が必要になる場合
復職後も状況に応じて「フォローアップ診断書」を提出するよう求められることがあります。
例えば「3か月後に再度診察を受け、その結果を会社に報告する」といった条件付きで復職が認められるケースです。
この場合、定期的に医師に通院し、継続的に勤務が可能かどうかを診断してもらう必要があります。
フォローアップ診断書は、再発を防ぎながら安心して働き続けるための仕組みでもあります。
復職後の安定した就労のために、追加の診断書が必要になるケースがあることを覚えておきましょう。
よくある質問(FAQ)

Q1. 今日から会社に行けない場合、即日休職できますか?
今日から会社に行けないと感じた場合でも、条件が整えば即日休職は可能です。
会社を休職するためには、医師の診断書が必要となるのが一般的です。
症状が重く、医師が就業困難と判断した場合は初診当日でも診断書を発行してもらえることがあります。
ただし、症状が軽度で診断を確定するには時間が必要な場合、再診を経て診断書が出るケースもあります。
即日休職を希望する場合は、まず会社に体調不良で休む旨を伝え、速やかに心療内科や精神科を受診することが大切です。
Q2. 初診でも診断書をもらえますか?
初診でも診断書を発行してもらえる場合がありますが、必ずしも全員が即日発行されるとは限りません。
強いストレスや不眠、出勤困難などが明らかであれば、医師がその場で休職を勧め診断書を発行するケースもあります。
一方で、症状がはっきりせず判断材料が不足している場合は、数回の診察を経てから発行されることもあります。
診断書がすぐに必要なときは、予約や受付時に「初診で診断書が必要」と伝えておくとスムーズです。
医師の判断次第ですが、伝え方を工夫することで即日発行の可能性を高められます。
Q3. 診断書がないまま休んだらどうなりますか?
診断書がない状態で会社を休むと、欠勤扱いとなるリスクがあります。
無断欠勤と判断されると人事評価や信頼に悪影響を及ぼす可能性が高まります。
ただし、事前に「体調不良のため休む」と連絡しておけば、後日診断書を提出することで休職に切り替えてもらえる場合があります。
診断書が間に合わないときは、有給休暇を使って対応する方法も有効です。
診断書がなくても必ず連絡は入れ、後日提出で対応できるかを会社に確認しておきましょう。
Q4. 有給休暇と休職の違いは?
有給休暇と休職は大きく仕組みが異なります。
有給休暇は労働者の権利として付与されるもので、理由を問わず休め、その間は給与も支払われます。
一方で休職は、心身の不調で働けないときに医師の診断書を提出して認められる制度です。
休職中は給与が支払われないことが多いですが、健康保険から傷病手当金を受け取れる場合があります。
有給は短期的な休み、休職は長期療養のための制度という点を理解して選択しましょう。
Q5. 診断書に病名を書かれたくない場合はどうすればいいですか?
診断書に必ず病名を書かなければならないわけではありません。
医師に相談すれば「抑うつ状態」「心身の不調のため加療中」といった表現にしてもらえる場合があります。
特に会社提出用では、病名よりも「休職が必要かどうか」が重視されます。
ただし、保険申請や公的手続きに使う診断書では病名の記載が必須となる場合があります。
用途に応じて診断書を分けてもらえるか医師に相談してみると安心です。
Q6. どのくらい休職できますか?
休職期間は症状の程度や会社の規定によって異なります。
診断書にはまず「2週間〜1か月程度」と短めに記載されることが多く、必要に応じて延長されます。
会社によっては「最長3か月」「最長1年6か月」と上限が定められていることもあります。
延長する際には、再度診断書を提出する必要があります。
休職期間は一度で確定するのではなく、医師と相談しながら段階的に決めていくのが一般的です。
即日休職は診断書と正しい手続きがカギ

「会社を今すぐ休みたい」と思ったとき、休職を認めてもらうためには診断書が欠かせません。
初診で発行される場合もあれば、数回の通院が必要な場合もあるため、まずは受診することが第一歩です。
診断書が間に合わないときは有給休暇や欠勤で対応しつつ、後日提出して休職に切り替えることが可能です。
また、傷病手当金や自立支援医療制度などの支援を活用すれば、経済的な不安も軽減できます。
焦らず正しい手続きを踏むことで、安心して心身の回復に専念することができます。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。