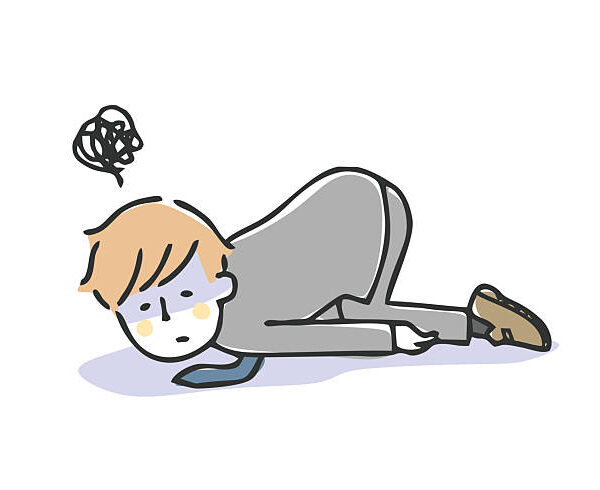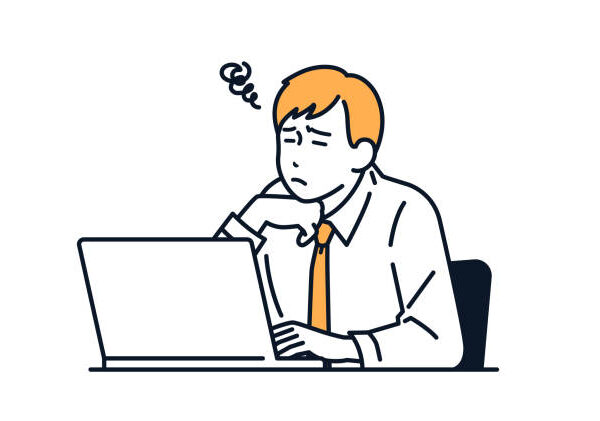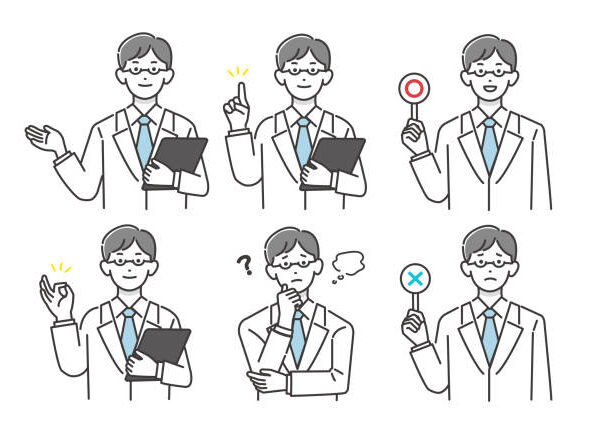適応障害は、強いストレスが原因となって心身に不調が現れる疾患です。
仕事や人間関係のトラブルなどがきっかけとなり、気分の落ち込みや不安、不眠、集中力の低下といった症状が続くことがあります。
しかし「どのように診断されるのか」「うつ病や不安障害との違いは何か」と疑問に思う方も少なくありません。
この記事では、適応障害の診断方法や診断基準、検査の流れ、さらに診断を受けるべきサインについて詳しく解説します。
早めに適切な医療機関で相談することで、正しい治療や休養につながり、回復への第一歩を踏み出すことができます。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。
適応障害の診断方法

適応障害の診断は、ストレス要因と症状の関連を明らかにすることを中心に行われます。
医師は問診や心理検査、必要に応じた身体検査を通じて、他の精神疾患や身体疾患との違いを見極めます。
診断は一度の診察だけでなく、経過を観察しながら総合的に判断されることも多いです。
ここでは、具体的な診断方法について詳しく解説します。
- 問診(症状や生活状況の聞き取り)
- 心理検査(質問票や心理テスト)
- 身体検査(血液検査・脳検査による除外診断)
- 他の精神疾患(うつ病・不安障害など)との鑑別
複数の方法を組み合わせることで、より正確に診断が行われます。
問診(症状や生活状況の聞き取り)
問診は適応障害の診断で最も重要なプロセスです。
医師は患者の症状がいつから始まったのか、どのようなストレス要因と関係しているのかを丁寧に聞き取ります。
例えば「仕事での人間関係」「家庭内トラブル」「進学や転職」など、環境の変化やストレスが背景にあることが多いです。
また、気分の落ち込み、不安、不眠、食欲低下などの精神的・身体的症状についても詳しく確認します。
問診で得られた情報をもとに、医師はストレス要因と症状の因果関係を把握し、診断の基盤とします。
この段階で「ただの疲れ」や「うつ病との違い」を見極めることが大切です。
心理検査(質問票や心理テスト)
心理検査は、症状の程度や心理的な傾向を客観的に評価するために行われます。
代表的なものに質問票(自己記入式のアンケート)や心理テストがあります。
不安や抑うつの程度を数値化することで、症状の重さや治療の必要性を判断する材料になります。
心理検査は診断の補助として用いられ、問診で得られた主観的な情報を客観的に裏付ける役割を果たします。
また、継続的に検査を行うことで、治療効果の経過を追跡することも可能です。
心理検査は絶対的な診断基準ではありませんが、診断の信頼性を高める重要なツールといえます。
身体検査(血液検査・脳検査による除外診断)
身体検査は、適応障害に似た症状を示す他の病気を除外するために行われます。
例えば、甲状腺機能の異常や貧血、脳の疾患が不安や抑うつに似た症状を引き起こすことがあります。
そのため血液検査や脳波、MRIなどを実施し、身体的な病気が背景にないかを確認します。
この「除外診断」によって、精神的なストレスが主因であると判断された場合に適応障害と診断されるのです。
身体検査は必ず行われるわけではありませんが、症状が複雑な場合や身体疾患の可能性がある場合には重要な役割を果たします。
正確な診断のために、医師の判断で必要に応じて実施されます。
他の精神疾患(うつ病・不安障害など)との鑑別
鑑別診断も適応障害の診断に欠かせません。
適応障害はうつ病や不安障害と症状が重なる部分が多く、誤診されやすい疾患です。
例えば、うつ病では原因が明確でなくても抑うつが続く一方、適応障害は特定のストレス要因が症状の引き金となっています。
また、不安障害では持続的な強い不安が特徴ですが、適応障害ではストレス要因が取り除かれると症状が軽快しやすい傾向があります。
このように症状の経過や背景を丁寧に見極めることで、正しく診断されます。
鑑別診断は治療方針の決定にも直結するため、医師と十分に相談しながら進めることが大切です。
適応障害の診断基準

適応障害の診断基準は、国際的に定められたガイドラインに基づいています。
代表的なのはアメリカ精神医学会が定めるDSM-5と、世界保健機関(WHO)が定めるICD-10やICD-11です。
これらの診断基準は医師が適応障害を判断する際の重要な指標となります。
また、症状の発症時期や持続期間も診断において重視されます。
ここでは、DSM-5、ICD-10/ICD-11、診断期間の観点から基準を解説します。
- DSM-5における診断基準
- ICD-10/ICD-11における診断基準
- 診断期間と症状の持続性
正しい診断基準を知ることは、適応障害を他の疾患と区別し、治療につなげるうえで不可欠です。
DSM-5における診断基準
アメリカ精神医学会が発行するDSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル)では、適応障害は明確に定義されています。
主な基準は、特定のストレス因子が出現してから3か月以内に症状が出現することです。
症状には気分の落ち込み、不安、行動の変化などが含まれ、社会的・職業的機能に支障をきたすことが条件とされています。
また、症状が他の精神疾患(うつ病、不安障害、PTSDなど)で説明できないことも診断の前提です。
さらに、ストレス因子が解消された後、症状が6か月以上持続しないことが診断基準に含まれています。
これらの基準に当てはまる場合に、医師は「適応障害」と診断します。
DSM-5は世界的に広く用いられているため、診断の国際的な共通基準といえます。
ICD-10/ICD-11における診断基準
世界保健機関(WHO)が定めるICD-10およびICD-11でも、適応障害は独立した診断カテゴリーとして規定されています。
ICD-10では、特定のライフイベントや環境の変化によって症状が引き起こされ、通常3か月以内に発症することが条件とされています。
ICD-11ではさらに詳細化され、「ストレス因子に対する不適応反応」として定義され、日常生活や社会的機能に明確な支障を与えることが要件とされています。
また、うつ病や不安障害など、他の精神疾患により説明できないことが強調されています。
これにより、ストレス要因との因果関係が特に重視される点が特徴です。
国際的に使用されるICDは医療機関だけでなく、保険や研究分野でも利用されるため、診断の裏付けとして重要な役割を果たします。
診断期間と症状の持続性
診断期間と症状の持続性は、適応障害を判断する際の大きなポイントです。
DSM-5やICDの基準に共通しているのは「ストレス因子から3か月以内に発症する」点です。
また、ストレス因子がなくなった場合、症状は6か月以内に改善することが前提とされています。
もし症状が6か月以上続く場合は、うつ病や不安障害など他の精神疾患を疑う必要があります。
この「発症時期」と「持続期間」は、適応障害を他の病気と区別するための大切な基準です。
医師は症状の経過を観察しながら診断するため、診断が即日確定しない場合もあります。
診断基準を正しく理解することで、自分の症状が適応障害に当てはまるのかを判断しやすくなります。
適切な診断を受けることが、早期治療と回復への近道です。
診断にかかる時間・費用

適応障害の診断を受ける際には、どのくらい時間がかかるのか、費用はどの程度必要なのかを知っておくと安心です。
診断は一度の受診で終わる場合もあれば、経過観察を経て確定することもあります。
また、診断書を発行してもらう場合は別途費用がかかるため、あらかじめ把握しておくことが大切です。
ここでは診断にかかる時間と費用の目安を3つの観点から解説します。
- 初診時に必要な診察時間
- 診断書の発行と費用の目安
- 通院・再診での確認プロセス
時間や費用を把握して準備することで、安心して診察に臨むことができます。
初診時に必要な診察時間
適応障害の初診では、医師がじっくりと問診を行うため、診察時間は通常よりも長めに設定されます。
一般的に30分から60分程度が目安とされ、症状の経過や生活背景、ストレス要因などを詳しく聞き取ります。
診断は症状とストレスの因果関係を重視するため、詳細な情報が必要だからです。
また、初診では心理検査を実施することもあり、その場合はさらに時間がかかります。
即日で診断が確定するケースもありますが、複雑な場合は数回の診察を経て診断されることも珍しくありません。
初めて受診するときは時間に余裕を持ち、落ち着いて医師に話せる準備をしておくと良いでしょう。
診断書の発行と費用の目安
適応障害と診断され、診断書を発行してもらう場合は、別途費用が必要です。
診断書の費用は医療機関によって異なりますが、一般的には3,000円から5,000円程度が相場です。
会社への提出用、傷病手当金申請用、学校提出用など、用途によって複数の診断書を依頼する場合は、それぞれ費用がかかることがあります。
また、即日発行できる場合もあれば、数日から1週間程度かかることもあります。
特に精神科や心療内科は混み合っていることが多いため、余裕を持って依頼することが大切です。
診断書が必要になりそうな場合は、受診時にあらかじめ医師に相談しておくとスムーズです。
通院・再診での確認プロセス
適応障害の診断は一度で終わることは少なく、再診で経過を確認しながら進められるのが一般的です。
再診は初診よりも短く、通常は10分から20分程度で行われます。
この際、症状の変化やストレス状況の改善、治療効果などを確認します。
診断がまだ確定していない場合は、再診で診断が確定することもあります。
また、休職や傷病手当金の申請に必要な診断書の延長や更新も、このタイミングで行われることが多いです。
通院を重ねることで医師が症状の推移を把握し、より正確な診断と治療方針の決定につながります。
適応障害はストレスの状況によって変動しやすいため、再診での確認は欠かせないプロセスです。
うつ病・不安障害との違い

適応障害はうつ病や不安障害と症状が似ているため、しばしば混同されやすい病気です。
特に「気分の落ち込み」「不安感」「集中力の低下」など共通の症状が見られるため、正確に区別することが重要です。
ここでは、うつ病や不安障害との診断の境界線、症状や原因の違い、そして誤診されやすいケースについて解説します。
- 適応障害とうつ病の診断の境界線
- 不安障害との違い(症状の持続性・原因)
- 誤診されやすいケースと注意点
これらを理解することで、より正しい診断と治療につながります。
適応障害とうつ病の診断の境界線
適応障害とうつ病は症状が重なる部分が多いですが、診断上の大きな違いは「原因」と「持続性」です。
適応障害は特定のストレス要因が引き金となり、その状況に対して不安や抑うつが現れます。
一方、うつ病は特定の原因がなくても抑うつ症状が持続し、日常生活に大きな支障を及ぼします。
また、適応障害ではストレス因子が取り除かれれば症状が軽快する傾向がありますが、うつ病ではそう簡単には改善しません。
このため、発症の経緯やストレス要因との関係を丁寧に確認することが診断の境界線を見極めるポイントになります。
診断基準では「ストレス因子が3か月以内に症状を引き起こし、6か月以上持続しない」場合は適応障害、それ以上長期にわたる場合はうつ病と診断される可能性が高いです。
不安障害との違い(症状の持続性・原因)
不安障害は、過度で持続的な不安や恐怖が中心症状です。
適応障害と異なり、必ずしも明確なストレス要因があるわけではありません。
不安障害では「予期不安」や「回避行動」が顕著で、長期間にわたって症状が続きます。
一方、適応障害は特定のライフイベント(転職、離婚、事故など)がきっかけで症状が出現し、その状況が改善すると回復する傾向があります。
また、不安障害では症状が慢性的に持続するため、治療には長期的なアプローチが必要になることが多いです。
この違いを理解することで、適応障害と不安障害を区別しやすくなります。
症状の持続性と原因の有無が診断上の重要な分岐点です。
誤診されやすいケースと注意点
適応障害は誤診されやすい疾患としても知られています。
特に、ストレス因子がはっきりしている場合でも、症状が重度で長引くと「うつ病」と診断されるケースがあります。
逆に、不安障害の一時的な症状が強く出ている場合に「適応障害」と診断されることもあります。
診断を誤ると、治療方法や休職の扱いが適切でなくなるリスクがあります。
例えば、適応障害であればストレス因子を減らすことが中心ですが、うつ病や不安障害であれば薬物療法や心理療法がより重要になります。
誤診を防ぐためには、症状の出現時期や経過を正確に伝えること、医師が十分に時間をかけて診断を行うことが必要です。
患者側も、自分の状態をメモして持参するなど工夫することで、より正確な診断につながります。
診断後の対応

適応障害の診断を受けた後は、症状の改善や再発予防に向けて適切な対応を行うことが重要です。
治療は薬物療法に限らず、心理療法やカウンセリング、生活環境の調整など多角的に進められます。
また、休職や働き方の工夫などストレス要因を減らす取り組みも欠かせません。
ここでは診断後にとるべき主な対応を3つの視点から解説します。
- 薬物療法の有無
- 心理療法やカウンセリング
- 休職や環境調整によるストレス軽減
医師と相談しながら自分に合った方法を取り入れることで、回復への道を進めやすくなります。
薬物療法の有無
薬物療法は、適応障害の治療で必ずしも必要になるとは限りません。
症状が比較的軽度であれば、環境調整や心理療法のみで改善するケースも多いです。
ただし、不眠や強い不安、抑うつなどが目立つ場合には、抗不安薬や睡眠導入剤、抗うつ薬などが一時的に処方されることがあります。
薬はあくまでも症状を和らげる補助的な役割であり、根本的な治療にはストレス要因への対応が欠かせません。
また、薬の使用には副作用や依存性のリスクもあるため、自己判断での中止や増量は避ける必要があります。
医師の指示に従って適切に使用することが安全で効果的です。
薬物療法を行うかどうかは、症状の程度と生活への影響を考慮して決められます。
心理療法やカウンセリング
心理療法やカウンセリングは、適応障害の治療において中心的な役割を果たします。
特に認知行動療法(CBT)は、不安や落ち込みを強める考え方の癖を修正し、ストレスへの対処法を身につけることに効果があります。
また、カウンセリングでは、患者が抱える悩みやストレスを安心して話せる場を提供し、気持ちの整理をサポートします。
自分の感情を言葉にするだけでも、心理的な負担が軽減されることがあります。
さらに、問題解決能力を高めたり、対人関係のストレスに対処するスキルを学ぶ機会にもなります。
心理療法は薬に頼らないアプローチであるため、副作用の心配が少なく、長期的な回復や再発予防につながります。
医師と連携しながら、継続的に取り組むことが大切です。
休職や環境調整によるストレス軽減
環境調整は適応障害の改善に不可欠です。
職場や学校のストレスが原因であれば、一時的に休職することで心身の負担を軽減できます。
診断書をもとに休職を申請すれば、会社や学校も理解を示しやすくなります。
また、完全な休職に至らなくても、勤務時間の短縮や業務の調整など柔軟な対応を取ることも可能です。
生活環境においても、無理のないスケジュールを組む、家族に協力をお願いするなど工夫が必要です。
ストレスの根本原因を取り除くことが難しい場合でも、環境を調整することで症状は大きく改善する可能性があります。
医師や産業医、カウンセラーと連携しながら、自分に合った環境改善策を見つけていくことが回復への近道です。
診断を受けるべきサイン

適応障害は、ストレスが原因で心身に不調が現れる病気ですが、どのタイミングで医師に相談すべきか迷う人は少なくありません。
症状が一時的なストレス反応にとどまる場合もありますが、長引いたり強まったりする場合は早めの受診が必要です。
ここでは、診断を受けるべき代表的なサインを4つ紹介します。
- 気分の落ち込みや不安が2週間以上続く
- 仕事や学校に行けないほどストレスが強い
- 食欲・睡眠の大きな乱れがある
- 「死にたい」と感じることがある
これらのサインを見逃さず、無理せず医療機関に相談することが回復の第一歩です。
気分の落ち込みや不安が2週間以上続く
気分の落ち込みや強い不安が2週間以上続いている場合は、適応障害を含めた精神疾患の可能性があります。
一時的な気分の変動であれば自然に回復することもありますが、2週間以上持続するのは異常のサインです。
この状態を放置すると、うつ病などより重い疾患に移行するリスクもあります。
「やる気が出ない」「楽しめない」といった感情の変化が続くときは、早めに医師に相談することが大切です。
長引く気分の落ち込みは、心のSOSとして受け止めましょう。
仕事や学校に行けないほどストレスが強い
仕事や学校に行けないほどのストレスを感じている場合も受診を検討すべきです。
適応障害は特定の環境や出来事に強く影響されるため、ストレスが強い状況では日常生活が困難になることがあります。
「出勤しようとすると動悸がする」「学校に行こうとすると涙が出る」といった状態は典型的です。
無理をして通い続けると症状が悪化し、長期休養が必要になる場合もあります。
早期に受診することで、休職や通学サポートなど適切な対策をとることができます。
食欲・睡眠の大きな乱れがある
心の不調は食欲や睡眠といった生活習慣にも表れます。
「眠れない」「夜中に目が覚める」「過食や拒食が続く」といった症状は注意が必要です。
これらは自律神経の乱れによるものであり、体調不良をさらに悪化させます。
睡眠不足や栄養の偏りは回復を妨げ、心身の疲労を増幅させる原因になります。
生活の基本である食事と睡眠が崩れているときは、自己判断せずに専門医に相談することが重要です。
「死にたい」と感じることがある
最も危険なサインが「死にたい」と感じることです。
この思いは適応障害の重症化やうつ病への移行を示すサインであり、放置してはいけません。
具体的な計画がなくても「消えてしまいたい」「いなくなりたい」と感じること自体が危険信号です。
このような気持ちが出てきた場合は、ただちに医療機関や相談窓口に連絡する必要があります。
周囲の人に打ち明けることも命を守る大切な行動です。
命に関わるサインを感じたときは、ためらわず支援を受けましょう。
診断を受ける流れと相談先

適応障害が疑われるとき、どこに相談すればよいか、どんな流れで診断が行われるのかを知っておくことは安心につながります。
適応障害は自己判断が難しいため、専門的なサポートを受けながら進めることが大切です。
医療機関だけでなく、産業医やカウンセラー、自治体の相談窓口など、複数の相談先があります。
ここでは診断を受ける一般的な流れと主な相談先を紹介します。
- 心療内科・精神科を受診する
- カウンセリングや産業医での相談
- 学校・自治体の相談窓口
状況に応じて最適な相談先を選び、早めに支援を受けることが回復の第一歩です。
心療内科・精神科を受診する
心療内科や精神科は、適応障害の正式な診断を受けられる最も一般的な相談先です。
受診の流れは、まず予約を取り、初診で症状や生活状況、ストレス要因について詳しく問診を受けます。
必要に応じて心理検査や身体検査が行われ、DSM-5やICDといった診断基準に基づいて判断されます。
症状が軽度でも、専門医に相談することで「適応障害かどうか」を明確にでき、適切な治療方針を立てられます。
また、診断書の発行も可能で、休職や傷病手当金の申請に必要な場合は早めに依頼するとスムーズです。
「仕事に行けない」「強い不安が続く」といった状態に気づいたら、まずは心療内科や精神科に相談することをおすすめします。
カウンセリングや産業医での相談
カウンセリングや産業医も適応障害の相談先として有効です。
臨床心理士や公認心理師によるカウンセリングでは、安心して話せる場を通じて気持ちを整理し、ストレス対処法を学ぶことができます。
また、会社員の場合は産業医面談を受けられることもあり、仕事に関連したストレス要因について具体的なアドバイスを受けられます。
産業医は就業上の配慮や休職・復職の判断を行う立場にあるため、職場環境の改善にもつながります。
医師による診断と併せてカウンセリングを利用すると、治療効果が高まりやすいのも特徴です。
医療機関と並行して利用することで、より幅広いサポートを得られるでしょう。
学校・自治体の相談窓口
学生や地域住民の場合は、学校や自治体の相談窓口も利用できます。
学校ではスクールカウンセラーや養護教諭が常駐している場合があり、学業や人間関係によるストレスについて相談可能です。
また、自治体の精神保健福祉センターや保健所には、無料や低料金で利用できる相談窓口があります。
匿名で相談できる電話相談やSNS相談も整備されており、誰にも言えない悩みを打ち明けやすい環境です。
自治体窓口では必要に応じて医療機関や支援機関を紹介してもらえるため、受診に踏み出す第一歩として活用できます。
「病院に行くのはハードルが高い」と感じる方は、まず自治体や学校の相談先にアクセスしてみるのも有効です。
適応障害の基礎知識

適応障害は、特定のストレス要因に対して心身がうまく対応できず、生活に支障をきたす状態を指します。
他の精神疾患と異なり、原因が明確である点が特徴です。
診断にはストレス要因と症状の関連性を確認することが不可欠であり、主に問診や心理的背景の把握を通じて判断されます。
また、DSM-5やICD-10といった国際的な診断基準が用いられるため、一定の客観性を持った診断が可能です。
ここでは、適応障害を理解するための基礎知識を3つの観点から整理します。
- ストレス要因と症状の関連性
- 診断の基本は問診と心理社会的背景の確認
- DSM-5やICD-10での診断基準
正しい知識を持つことで、早期の受診や適切な治療につながります。
ストレス要因と症状の関連性
適応障害の大きな特徴は、症状が特定のストレス要因に関連して発症する点です。
例えば、職場の人間関係、家庭のトラブル、転職、引っ越し、試験など、環境の変化や心理的負担が引き金になります。
ストレス要因が発生してから3か月以内に気分の落ち込み、不安、不眠、集中力の低下などが出現するのが一般的です。
症状は一時的なストレス反応に似ていますが、日常生活や仕事に支障を及ぼすレベルで続く場合に適応障害と診断されます。
ストレス要因と症状の関連性を把握することが、他の精神疾患との区別に欠かせないポイントです。
原因がはっきりしているため、治療はストレスへの対処や環境調整に重点が置かれる傾向があります。
診断の基本は問診と心理社会的背景の確認
診断の基本は、医師による問診と心理社会的背景の把握です。
問診では、いつから症状が出始めたか、どのような状況で悪化するのか、ストレス要因が何かを丁寧に聞き取ります。
また、患者の家庭環境や職場環境、対人関係などの背景を把握し、症状との関連を分析します。
心理検査を併用して不安や抑うつの程度を数値化することもありますが、最も重視されるのは本人の生活史やストレス要因の特定です。
このプロセスによって「ただの疲れ」や「一時的な落ち込み」との違いを判断できます。
つまり適応障害の診断は、単なる症状の有無ではなく、生活背景全体を考慮して行われるのが特徴です。
DSM-5やICD-10での診断基準
国際的な診断基準として、DSM-5とICD-10が用いられます。
DSM-5では、ストレス因子が発生して3か月以内に症状が出現し、日常生活に支障を与えることが条件です。
また、ストレス因子が解消された後は6か月以上症状が続かないことも重要な基準となります。
ICD-10でも同様に、特定のライフイベントや環境の変化が症状の直接的な原因であることが重視されます。
さらに、症状が他の精神疾患(うつ病、不安障害、PTSDなど)で説明できない場合に適応障害と診断されます。
これらの診断基準を用いることで、医師は客観的かつ一貫性のある診断を行うことができます。
国際的に共有された基準を活用することは、治療や研究、制度利用の面でも大きな意義があります。
よくある質問(FAQ)

適応障害の診断方法については、多くの方が共通の疑問を抱えます。
特に「検査でわかるのか」「診断にかかる期間」「うつ病との違い」「診断書の有無」「どこで受診すべきか」といった点はよく質問されます。
ここでは代表的な5つの質問に回答し、適応障害の理解を深めるための参考にしていただきます。
Q1. 適応障害は血液検査や脳検査でわかりますか?
適応障害は血液検査や脳検査では直接診断できません。
適応障害はあくまでストレス要因と症状の因果関係から判断される精神疾患です。
そのため、医師は問診や心理検査を中心に診断を行います。
ただし、甲状腺の異常や脳疾患など、似た症状を引き起こす病気を除外するために血液検査や画像検査が行われることはあります。
つまり、これらの検査は「適応障害かどうかを確認するため」ではなく「他の病気を否定するため」に使われます。
正確な診断には、医師への詳細な症状説明が欠かせません。
Q2. 適応障害はどのくらいで診断されますか?
診断までの期間は人によって異なります。
症状が明確でストレス要因が特定できる場合は、初診で診断されることもあります。
しかし、症状が複雑で他の疾患との区別が難しい場合は、数回の通院や経過観察を経て診断が確定することも少なくありません。
一般的には初診から数日~数週間で診断されるケースが多いです。
早めに医師に相談することで、診断と治療の開始をスムーズにできます。
Q3. うつ病と適応障害の診断はどう違う?
うつ病と適応障害は似た症状が多いため、診断の違いが分かりにくい病気です。
適応障害は特定のストレス要因によって発症し、原因が取り除かれれば比較的早く改善する傾向があります。
一方、うつ病は原因が明確でない場合も多く、長期的に抑うつ状態が続きやすいのが特徴です。
診断基準でも「ストレス因子発生から3か月以内に症状が出現し、6か月以内に収束する」のが適応障害とされています。
持続性と原因の明確さが、診断の分かれ目となります。
Q4. 適応障害の診断書はすぐに発行してもらえる?
診断書の即日発行はケースバイケースです。
症状がはっきりしている場合は、初診でそのまま診断書をもらえることもあります。
しかし、医師が経過観察を必要と判断した場合は、数日から数週間の通院を経て発行されることもあります。
会社や学校への提出が必要な場合は、その旨を医師に伝えるとスムーズです。
診断書の費用は3,000〜5,000円程度が目安となります。
Q5. 診断は心療内科と精神科どちらで受ければいい?
心療内科・精神科どちらでも診断は可能です。
心療内科は心身症やストレス関連の症状を幅広く扱い、身体症状を伴う人に適しています。
精神科はうつ病や不安障害を含め、精神疾患全般を対象としており、より専門的な治療を受けたい場合に向いています。
どちらを選ぶか迷った場合は、アクセスのしやすさや医師との相性で決めるのも良いでしょう。
重要なのは早めに専門医に相談することです。
適応障害の診断は専門医に相談を

適応障害はストレスが原因で心身に影響を及ぼす疾患であり、自己判断では見極めが難しいことが多いです。
血液検査や画像検査で直接わかる病気ではないため、問診や心理検査を通じた診断が基本です。
診断を受けることで、休職や環境調整、カウンセリングなどのサポートが受けやすくなります。
気になる症状がある場合は、迷わず心療内科や精神科に相談し、早めに対応することが回復への近道です。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。