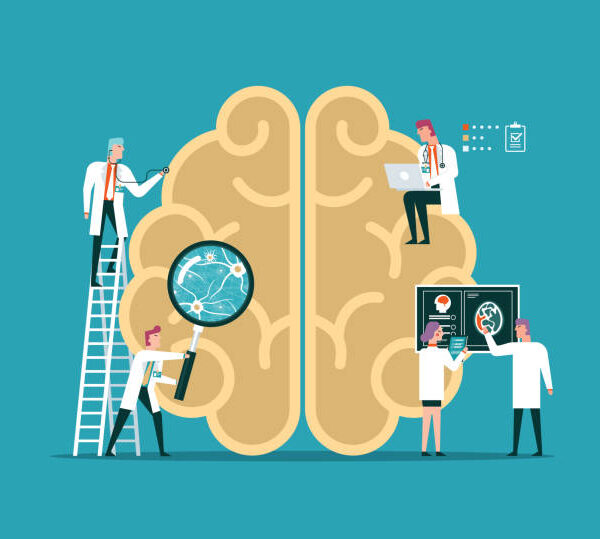「朝になるとどうしても仕事に行けない」「体が動かず会社に行くのがつらい」と感じてしまうことは誰にでも起こり得ます。
過労や睡眠不足だけでなく、うつ病・適応障害・自律神経失調症など精神的な不調が原因で出勤できなくなるケースも少なくありません。
無理をして働き続けると症状が悪化し、取り返しのつかない状況に陥ることもあります。
この記事では、仕事に行けないときの具体的な対処法、休職や診断書の取得方法、傷病手当金などの制度について詳しく解説します。
「甘えではない」と理解し、安心して休養や相談につなげるための第一歩にしてください。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。
仕事に行けないときに考えられる原因

「どうしても仕事に行けない」と感じる背景には、単なる気分の問題ではなく心身の不調や環境要因が関わっていることが多いです。
過労や精神的な病気、人間関係のストレスなど原因はさまざまで、複数が重なって悪化するケースも少なくありません。
ここでは代表的な原因を整理し、それぞれの特徴を解説します。
- 過労や睡眠不足による身体的な疲労
- うつ病・適応障害・自律神経失調症など精神的な不調
- 職場の人間関係や環境要因
- 燃え尽き症候群やモチベーションの低下
- 発達障害やHSP気質が影響する場合
原因を理解することが、正しい対処法を選ぶ第一歩になります。
過労や睡眠不足による身体的な疲労
長時間労働や不規則な勤務が続くと、体の疲労が限界を迎えて出勤できなくなることがあります。
睡眠不足が慢性化すると集中力が低下し、朝起きても体が動かないと感じやすくなります。
一時的な休養で改善することもありますが、無理を続けると慢性疲労症候群などにつながる恐れがあります。
「ただの疲れ」と軽視せず、しっかり休むことが必要です。
うつ病・適応障害・自律神経失調症など精神的な不調
精神的な病気は「出勤できない」状態の大きな原因のひとつです。
うつ病では気分の落ち込みや意欲低下が続き、会社に行く力が出ません。
適応障害は職場環境の変化や人間関係のストレスで症状が現れます。
自律神経失調症では不眠や動悸、めまいなど身体症状が強く出るため、出勤どころか日常生活にも支障をきたします。
精神的な不調は早めの受診と休養が大切です。
職場の人間関係や環境要因
上司や同僚との不和、パワハラ、過度なプレッシャーなど職場環境の問題も「仕事に行けない」大きな原因になります。
人間関係のストレスは身体症状として表れることもあり、頭痛や胃痛などが出勤時に強まるケースもあります。
また、過剰なノルマや責任が重すぎる業務環境も、心身の限界を超えてしまう要因です。
環境要因が大きい場合は配置転換や休職を検討することが有効です。
燃え尽き症候群やモチベーションの低下
真面目に働いてきた人ほど、燃え尽き症候群に陥りやすいといわれます。
長期間ストレスにさらされると意欲が枯渇し、「出勤する意味が見いだせない」と感じるようになります。
これは単なる怠けではなく、心身が疲弊しているサインです。
適切に休養を取り、必要であれば専門家に相談することが回復への近道になります。
発達障害やHSP気質が影響する場合
発達障害やHSP(非常に敏感な気質)を持つ人は、職場の刺激や人間関係のストレスに強く反応してしまうことがあります。
音や人混みに敏感で集中力を保つのが難しい、細かい注意に疲れてしまうなどの理由で出勤が困難になることもあります。
この場合は周囲の理解と環境調整が重要であり、本人が努力で解決できる問題ではありません。
特性を理解した働き方を模索することが必要です。
仕事に行けないときにすぐできる対処法6選

「どうしても会社に行けない」と感じるときは、自分を責めるのではなく具体的な対処法を試すことが大切です。
無理に出勤して心身を壊す前に、できることから取り入れてみましょう。
ここでは、今日から実践できる6つの方法を紹介します。
- 思い切って休む(欠勤連絡の仕方)
- 休養して体調を整える(睡眠・栄養・運動)
- 信頼できる人に気持ちを話す
- セルフケア(呼吸法・瞑想・日記など)
- 仕事の優先順位を見直す
- 転職や部署異動を検討する
一人で抱え込まず、小さな工夫から始めることが回復への第一歩になります。
思い切って休む(欠勤連絡の仕方)
仕事に行けないときは無理に出勤するよりも思い切って休むことが重要です。
欠勤連絡は「体調不良のため本日は休ませていただきます」と簡潔に伝えれば十分です。
無理に理由を細かく説明する必要はなく、できるだけ早めに連絡することが大切です。
安心して休むことで、翌日以降の回復につながります。
休養して体調を整える(睡眠・栄養・運動)
欠勤した日は心身を回復させるための休養時間にあてましょう。
十分な睡眠をとり、栄養バランスのとれた食事を意識します。
体調が許せば軽い散歩やストレッチも効果的です。
規則正しい生活を整えることが、仕事に復帰するための土台になります。
信頼できる人に気持ちを話す
一人で抱え込まず、家族や友人、信頼できる人に気持ちを話すことも大切です。
不安や辛さを言葉にすることで気持ちが軽くなる効果があります。
可能であれば上司や同僚に現状を正直に伝えることで、理解を得やすくなります。
話す相手がいないときは、電話相談やSNS相談窓口を活用するのも有効です。
セルフケア(呼吸法・瞑想・日記など)
緊張や不安が強いときはセルフケアで気持ちを整える工夫をしてみましょう。
深呼吸や瞑想は自律神経を整える効果があり、短時間でも心が落ち着きます。
日記に感情を書き出すのも有効で、頭の中を整理するきっかけになります。
小さな習慣を取り入れるだけでもストレス軽減につながります。
仕事の優先順位を見直す
「仕事が多すぎて動けない」と感じるときは、優先順位を整理することが効果的です。
すぐにやるべきこと、後回しにできることを分けるだけでも気持ちが楽になります。
上司に相談して業務量を調整してもらうのも一つの方法です。
完璧を求めすぎず、まずは最低限できることに集中しましょう。
転職や部署異動を検討する
環境そのものが原因で「仕事に行けない」状態が続くなら、転職や部署異動を検討することも必要です。
職場の人間関係や過度なストレスが原因であれば、休むだけでは根本的な解決にならない場合があります。
転職エージェントやハローワークに相談し、安心して働ける職場を探すことも選択肢の一つです。
無理に今の環境に固執せず、自分に合った働き方を模索することが回復につながります。
医療機関に相談すべきサイン

「仕事に行けない」と感じるとき、どのタイミングで医療機関を受診すべきか迷う人は少なくありません。
一時的な疲労であれば休養で回復することもありますが、一定の症状が続く場合は早めの受診が必要です。
ここでは医療機関への相談を検討すべき代表的なサインを紹介します。
- 気分の落ち込みや不安が2週間以上続く
- 食欲や睡眠の大きな乱れがある
- 「死にたい」と考えることがある
- パニック発作や強い身体症状が出ている
これらに当てはまる場合は、心療内科や精神科など専門医への相談を検討してください。
気分の落ち込みや不安が2週間以上続く
一時的な憂うつ感は誰にでもありますが、2週間以上続く場合はうつ病や適応障害の可能性があります。
「気分が晴れない」「何をしても楽しくない」と感じる状態が続くのは心が限界を迎えているサインです。
放置すると仕事どころか日常生活にも支障をきたすため、早めに医師へ相談することが大切です。
受診に迷うときは、症状や気分の変化をメモして持参すると診断の助けになります。
食欲や睡眠の大きな乱れがある
心の不調は食欲や睡眠に大きな影響を与えます。
食欲が極端に落ちて体重が減る、逆に過食してしまうといった変化は危険なサインです。
また、不眠や過眠など睡眠リズムが崩れると体力や集中力が低下し、さらに悪循環に陥ります。
生活習慣の乱れが続くと心身の回復が難しくなるため、医師に相談して適切な治療を受けることが必要です。
「死にたい」と考えることがある
強いストレスや抑うつ状態が続くと、「死にたい」と考えてしまうことがあります。
このサインは非常に危険であり、一人で抱え込むのは避けなければなりません。
もしそのような気持ちがある場合は、すぐに医療機関へ相談してください。
夜間や休日は自殺防止の電話相談やSNS相談窓口を利用することも可能です。
命を守るためには「早めに声を上げる」ことが何より大切です。
パニック発作や強い身体症状が出ている
心の不調は身体的な症状として現れることもあります。
突然の動悸や息苦しさ、めまい、吐き気などのパニック発作が頻発する場合は受診が必要です。
検査で異常が見つからなくても、自律神経の乱れや不安障害が背景にあることがあります。
身体症状が強く日常生活に支障をきたす場合は、医師の診断を受けることで安心につながります。
心と体の両面をケアすることが回復に向けた第一歩です。
休職という選択肢

「仕事に行けない」と感じる状態が長引く場合、休職を選択することは大切な対処法のひとつです。
診断書があれば会社の制度を利用して休むことができ、心身を整える時間を確保できます。
ここでは休職に関する基本的な流れと、知っておくべきポイントを解説します。
- 診断書があれば休職できる
- 休職中の給与や傷病手当金について
- 復職の流れと注意点
- 休職と退職、どちらを選ぶべきか
正しい知識を持つことで、不安を減らして安心して休職に踏み出せます。
診断書があれば休職できる
多くの会社では医師による診断書の提出があれば休職が認められます。
診断書には「自律神経失調症のため休養が必要」など医学的な根拠が記載されます。
提出先は上司や人事部で、就業規則に従って休職扱いとなります。
診断書があることで欠勤が正当化され、無断欠勤とみなされるリスクを防げます。
まずは医師に休職の希望を伝え、必要な診断書を依頼することが第一歩です。
休職中の給与や傷病手当金について
休職中は給与が支給されないケースが多く、その代わりに健康保険から傷病手当金を受け取れる場合があります。
傷病手当金は標準報酬日額の約3分の2が支給され、最長1年6か月利用できます。
有給休暇を先に消化するケースもあるため、会社の規定を確認しておきましょう。
経済的な不安を減らすためにも、早めに人事や健保組合に申請方法を確認することが重要です。
生活面の支えを得ながら安心して療養に専念できます。
復職の流れと注意点
復職の際には「就労可能」と記載された診断書を提出する必要がある場合があります。
会社によっては産業医や人事担当者との面談を行い、働けるかどうかを確認します。
復職直後は業務量を調整してもらえることもありますが、焦らず段階的に慣らしていくことが大切です。
無理をすると再発のリスクが高まるため、主治医と相談しながらペースを決めましょう。
復職後も定期的に受診を続けると安心です。
休職と退職、どちらを選ぶべきか
「もう仕事を辞めたい」と思うほどつらいとき、休職か退職かの選択に迷う人も少なくありません。
休職は職場復帰を前提とした制度であり、一定の期間休養してから戻ることを目的としています。
一方、退職は完全に職場を離れる決断となり、収入や社会保険の問題が伴います。
焦って決めると後悔につながるため、まずは休職を選び回復を優先するのがおすすめです。
どうしても復職が難しい場合に、転職や退職を検討すると安心です。
仕事に行けないときの生活面での工夫

仕事に行けず休職や欠勤が続くと、心身の不調だけでなく生活面の不安も大きくなります。
経済的な心配や生活リズムの乱れ、人とのつながりが薄れることは回復を妨げる要因になりかねません。
ここでは、生活面でできる具体的な工夫を紹介します。
- 経済的不安を和らげる方法
- 生活リズムを整える工夫
- 家族や友人に協力してもらう
心身を安心させる環境を整えることで、回復のスピードが高まります。
経済的不安を和らげる方法
休職中に大きな負担となるのが収入の減少です。
健康保険の傷病手当金を申請すれば、給与の約3分の2が最長1年6か月支給されます。
また、自治体の生活支援制度や社会福祉協議会の貸付制度を利用できる場合もあります。
経済的不安が強いと心の負担も増すため、早めに制度を調べて手続きを進めましょう。
家計を見直して支出を抑えることも有効です。
生活リズムを整える工夫
休んでいる間は生活が不規則になりやすく、症状の改善を妨げる原因になります。
毎日同じ時間に起きて朝日を浴び、規則正しい食事をとることが基本です。
昼夜逆転を避け、可能であれば軽い運動を取り入れると自律神経が安定しやすくなります。
スマートフォンやパソコンを夜遅くまで使用しないなど、睡眠環境を整える工夫も必要です。
小さな習慣の積み重ねが、復職に向けた準備にもつながります。
家族や友人に協力してもらう
仕事に行けない状況を一人で抱え込むのは危険です。
信頼できる家族や友人に現状を伝え、支援を受けることが心の安定につながります。
買い物や家事をサポートしてもらうだけでも負担が軽くなります。
また、気持ちを聞いてもらうことで孤独感が和らぎます。
周囲の理解と協力を得ることは、安心して回復に専念するための大切な支えです。
仕事に行けないのは甘えではない

「仕事に行けないのは自分が弱いから」「怠けているだけでは」と自分を責めてしまう人は少なくありません。
しかし実際には、心や体が限界を迎えた結果として出勤できなくなっていることがほとんどです。
ここでは「甘えではない」と言える理由を整理して解説します。
- 心身が出すSOSのサイン
- 「休む勇気」が回復につながる
- 同じ経験を持つ人は多い
正しく理解することで、自分を責めずに必要なサポートを受けやすくなります。
心身が出すSOSのサイン
「どうしても会社に行けない」と感じるのは、心身が限界を迎えているサインです。
うつ病や自律神経失調症など精神的な不調は、無理に働き続けることで悪化することがあります。
体が動かない、気力がわかないという状態は怠けではなく、自然な防御反応です。
まずは体からのメッセージを受け止め、休養や相談につなげることが必要です。
「休む勇気」が回復につながる
仕事を休むことに罪悪感を覚える人は多いですが、休むことは回復への大切な一歩です。
無理をして出勤しても成果が出ないどころか、体調を悪化させてしまう可能性があります。
一度立ち止まって休養することで心身のバランスを取り戻し、復職につなげられます。
「休む勇気」を持つことは、長期的に見て自分や会社にとってもプラスになります。
同じ経験を持つ人は多い
「仕事に行けない」と悩むのは自分だけではありません。
厚生労働省の調査でも、精神的な理由で休職や退職を経験する人は年々増えています。
多くの人が同じように悩み、そこから回復して再び働いています。
孤独に感じるかもしれませんが、支援制度や相談窓口も整っているため、安心して頼ってよいのです。
同じ経験を持つ人が多いことを知るだけでも、自分を責める気持ちが和らぎます。
相談・支援先

「仕事に行けない」と悩んでいるとき、一人で抱え込まず外部の相談先を活用することが大切です。
専門機関や公的な窓口を利用すれば、治療や生活支援、就労のサポートを受けることができます。
ここでは代表的な相談・支援先を紹介します。
- 心療内科・精神科
- 会社の産業医や人事窓口
- 自治体や電話・SNS相談窓口
- ハローワークや就労支援サービス
状況に応じて複数を組み合わせて利用することで、安心して回復を目指せます。
心療内科・精神科
心身の不調で仕事に行けないときは、心療内科や精神科を受診することが第一歩です。
うつ病や適応障害、自律神経失調症などの診断を受けることで、医学的な根拠に基づいた治療や診断書の発行が可能になります。
症状が軽い段階でも受診して問題はなく、早めの相談が回復につながります。
まずは近隣のクリニックを調べ、予約してみましょう。
会社の産業医や人事窓口
大企業を中心に、多くの会社には産業医や人事窓口があります。
職場環境が原因で体調を崩している場合、産業医との面談を通じて勤務内容の調整を行うことが可能です。
また、人事部に相談することで休職や制度利用について具体的な案内を受けられます。
職場に関する悩みは、まず社内の仕組みを活用してみましょう。
自治体や電話・SNS相談窓口
「すぐに誰かに話を聞いてほしい」と思ったときは、自治体や公的な相談窓口を利用できます。
こころの健康相談統一ダイヤルや自殺防止の電話相談、SNSを使ったメンタルヘルス支援も広がっています。
匿名で利用できる窓口も多く、気軽に相談できるのが特徴です。
夜間や休日にも対応している場合があるため、緊急時の選択肢として覚えておきましょう。
ハローワークや就労支援サービス
「今の職場で働き続けるのは難しい」と感じる場合は、ハローワークや就労支援サービスを活用するのも一つの方法です。
ハローワークでは職業相談や職業訓練、転職活動の支援を受けられます。
また、地域の就労支援センターでは、心身の不調を抱えながら働く人を対象にしたサポートを提供しています。
無理をして同じ職場にとどまる必要はなく、自分に合った働き方を探すきっかけになります。
よくある質問(FAQ)

Q1. 仕事に行けないのは甘えですか?
いいえ、仕事に行けないのは甘えではありません。
うつ病や適応障害、自律神経失調症など心身の不調が背景にあることが多く、本人の努力不足ではないのです。
無理をすればさらに悪化するため、早めに休養や受診につなげることが重要です。
Q2. 何日くらい休んでもいい?
体調不良での欠勤は数日〜1週間程度であれば診断書不要で認められることもあります。
ただし会社の規定によっては早い段階で診断書を求められる場合もあります。
長引きそうなときは医師に相談し、正しい手続きを踏んで休むことが安心につながります。
Q3. 診断書はすぐにもらえますか?
症状が明らかで休職が必要と判断された場合は初診当日でも発行されることがあります。
一方で、軽度の場合は経過観察を経てから診断書が出されることもあります。
急ぎの場合は「会社に提出が必要」と医師に伝えて相談しましょう。
Q4. 傷病手当金を受け取る方法は?
健康保険組合に申請することで受け取れます。
会社から申請書を受け取り、医師に証明欄を記入してもらう必要があります。
人事や総務を通じて手続きを進めれば、最長1年6か月間の支給を受けられます。
Q5. 復職が不安なときはどうする?
復職に不安があるときは、主治医や産業医に相談することが大切です。
会社によっては時短勤務や業務の調整を行ってくれる場合もあります。
焦らず段階的に復帰し、無理のないペースで働くことが再発予防につながります。
Q6. 退職を選ぶのは間違いですか?
退職を選ぶこと自体は間違いではありません。
ただし体調が不安定なまま退職すると経済的・精神的に大きな負担になる可能性があります。
まずは休職制度や傷病手当金を利用し、冷静に判断するのがおすすめです。
Q7. 家族にどう伝えればいいですか?
家族には「病気による不調で仕事に行けない」と正直に伝えることが大切です。
「医師に休養を勧められた」と説明すれば理解を得やすくなります。
支えをお願いすることで、安心して休養に専念できます。
仕事に行けないときは一人で抱え込まず相談を

仕事に行けないときは、自分を責める必要はありません。
それは心や体が発しているSOSのサインです。
診断書や制度を活用し、医師や相談窓口に頼ることで安心して休養できます。
一人で抱え込まず、周囲に相談することが回復への大切な第一歩です。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。