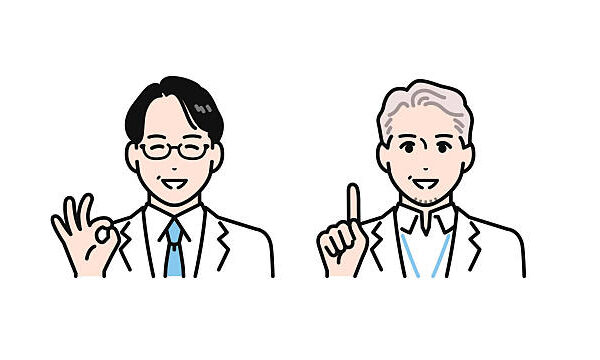診断書は、病気やけがの証明として会社や学校、保険の手続きなどで必要になる大切な書類です。
しかし「受診のときにお願いし忘れてしまった」「後から必要になった」というケースも少なくありません。
では、診断書は後から書いてもらえるのでしょうか?結論から言うと、受診記録が残っていれば多くの医療機関で後日発行が可能です。
ただし、依頼の仕方やタイミング、病院ごとのルールを知らずに申請すると「追加受診が必要」「発行まで時間がかかる」「内容が目的に合わない」といったトラブルに発展することもあります。
本記事では、診断書を後からもらう方法、スムーズに依頼するコツ、注意すべきポイント、費用の目安まで徹底解説します。診断書が必要になったときに慌てないよう、ぜひ参考にしてください。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。
診断書は後から書いてもらえるのか?

診断書は病気やけがの証明として必要になる重要な書類ですが、受診時に依頼を忘れてしまうこともあります。
このとき「診断書は後から書いてもらえるのか?」という疑問を持つ人は少なくありません。
結論から言えば、受診記録が残っていれば多くの医療機関で後日発行が可能です。
ただし、すべてのケースで必ず発行できるわけではなく、医療機関のルールや依頼時期によっては断られることもあります。
ここでは診断書を後からもらえるかどうかについて、押さえておくべき3つのポイントを解説します。
- 医療機関のルール次第で「後日発行」も可能
- 診断書は「受診記録」が残っていれば発行できる
- ただし長期間経過後は発行できない場合もある
これらを理解することで、必要なときにスムーズに診断書を入手できる可能性が高まります。
医療機関のルール次第で「後日発行」も可能
診断書は受診時に依頼するのが基本ですが、実際には医療機関のルール次第で後から発行できる場合があります。
病院やクリニックでは診療録(カルテ)を基に診断書を作成するため、受診記録が残っていれば後日の依頼でも対応が可能です。
ただし、病院によっては「受診日から◯日以内に依頼が必要」など独自の規定を設けていることがあります。
また、担当した医師が休職や異動で不在の場合は、確認作業に時間がかかり即日発行できないこともあります。
そのため、診断書が必要になったらできるだけ早く病院に連絡してルールを確認することが大切です。
診断書は「受診記録」が残っていれば発行できる
診断書を後日発行できるかどうかは、受診記録(カルテ)が残っているかが大きな判断材料になります。
医師は診断書を作成する際、患者の申告だけでなく、診察時の記録や検査結果を根拠として記載します。
そのため、診療内容がしっかり残っていれば、受診日から数日〜数週間経過しても発行が可能です。
一方で、診療記録が不十分な場合や、症状がカルテに明確に記録されていない場合は、追加の受診を求められることがあります。
スムーズに診断書を発行してもらうためには、受診時に医師に具体的な症状や事情をしっかり伝えることも大切です。
ただし長期間経過後は発行できない場合もある
診断書を後から依頼する場合に注意すべきなのは、時間が経ちすぎると発行できなくなる可能性があるという点です。
カルテは医療法で5年間の保存義務がありますが、それを過ぎると廃棄されるケースもあります。
また、数か月以上経過してしまうと「当時の状態を正確に証明できない」として、医師が診断書の発行を断る場合もあります。
さらに、会社や保険会社に提出する際は「受診から一定期間内の診断書のみ有効」とされていることがあり、期限を過ぎると無効になる可能性もあります。
診断書が必要になったらできるだけ早く医療機関に依頼することが、確実に入手するためのポイントです。
診断書を後からもらう際の手続き・もらい方

診断書を後から依頼する場合、必要な手続きや流れを理解しておくことが大切です。
病院ごとに細かなルールは異なりますが、基本的な流れを押さえておけばスムーズに申請できます。
診断書は医師の判断とカルテ記録に基づいて作成されるため、適切な依頼方法を知っておくことが重要です。
ここでは、後から診断書をもらうときに知っておきたい3つのポイントを解説します。
- 電話や窓口で「診断書を希望」と伝える
- 発行には「本人確認」「受診日」情報が必要
- 受診した医師が不在の場合は時間がかかることも
これらを理解して行動することで、診断書をスムーズに受け取ることができるでしょう。
電話や窓口で「診断書を希望」と伝える
診断書を後から依頼する場合、まずは医療機関へ連絡することが基本です。
窓口で直接依頼する方法と、電話で申し込む方法の2つがあります。
電話で依頼する際は「◯月◯日に受診した◯◯です。診断書を発行していただきたい」と具体的に伝えるとスムーズです。
窓口での申し込みの場合も、受付に「診断書を希望します」と明確に伝えることで対応してもらえます。
このときに用途(会社提出用、保険申請用など)を伝えておくと、必要な形式で作成してもらえるため安心です。
発行には「本人確認」「受診日」情報が必要
診断書を依頼する際には、本人確認が必須となります。
運転免許証や保険証などの身分証明書を提示することで、本人であることを証明します。
また、診断書は「いつ受診したか」に基づいて発行されるため、受診日を正確に伝えることが重要です。
カルテ照会のために診察券番号や保険証情報を求められることもあります。
スムーズに依頼を進めるためには、事前に必要書類や情報を確認して準備しておくことが大切です。
受診した医師が不在の場合は時間がかかることも
診断書は実際に診察した医師が署名する必要があるため、医師が不在だとすぐには発行できません。
担当医が休暇や学会などで不在の場合、戻るまで数日〜1週間程度待たなければならないこともあります。
また、別の医師が診断書を作成することは基本的にできないため、時間がかかるのは避けられません。
このため、診断書が必要になったときは、できるだけ早く依頼して余裕を持って受け取り日を確認することが大切です。
急ぎで必要な場合は「いつまでに必要か」を受付に伝えておくと、可能な範囲で対応してもらえることもあります。
診断書をスムーズにもらうためのポイント

診断書は提出先によって必要な内容や形式が異なるため、依頼の仕方によっては発行が遅れたり、内容が不十分で再作成が必要になることがあります。
スムーズに診断書をもらうためには、事前準備と依頼時の工夫が欠かせません。ここでは、診断書をスムーズに発行してもらうために押さえておくべき3つのポイントを解説します。
- 受診時に「診断書が必要」と伝えておく
- 会社や保険会社が求める書式を確認してから依頼する
- 締め切りに余裕を持って準備することが大切
これらを実践することで、診断書の発行をスムーズに進め、余計なトラブルを防ぐことができます。
受診時に「診断書が必要」と伝えておく
診断書を確実に発行してもらうためには、受診時に医師へ診断書が必要であることを伝えるのが最もスムーズです。
診察の段階で「会社に提出するため診断書が必要です」などと伝えておけば、カルテに必要な情報を詳細に記載してもらえます。
後日依頼する場合でも、診療内容が具体的に残っていることで発行がスムーズになります。
逆に、診断書が必要であることを伝えないと、カルテの記録が簡略化されてしまい、再受診が必要になるケースもあります。
受診時に一言伝えるだけで手間を大きく減らせるため、意識しておくと安心です。
会社や保険会社が求める書式を確認してから依頼する
診断書には会社や保険会社独自のフォーマットが存在する場合があります。
たとえば、休職証明書や就業制限証明書など、一般的な診断書では対応できないケースがあります。
提出先から指定の書式がある場合は、その書類を持参して依頼する必要があります。
医師に依頼する際に「このフォーマットに記載してください」と伝えれば、余分な再作成を防ぐことができます。
事前に会社や保険会社へ確認しておくことが、スムーズに診断書を受け取るための大切な準備です。
締め切りに余裕を持って準備することが大切
診断書は即日発行が難しいことが多く、発行までに数日から1週間程度かかるのが一般的です。
そのため、提出期限がある場合は、少なくとも1〜2週間の余裕を持って依頼しておくことが安心です。
期限ぎりぎりに依頼してしまうと、発行が間に合わず提出が遅れてしまうリスクがあります。
また、内容に誤りがあった場合の修正にも時間が必要になるため、余裕を持って行動することが大切です。
「早めに動く」ことが、診断書をスムーズに入手する最大のポイントといえるでしょう。
診断書を後から依頼するときの注意点

診断書は後から依頼しても発行できるケースが多いですが、注意すべき点を理解しておかないとトラブルにつながる可能性があります。
病院やクリニックごとにルールや対応が異なるため、思っていたよりも時間がかかったり、追加の手続きが必要になる場合もあります。
また、診断書は会社や保険提出など正式な手続きに利用されるため、記載内容に誤りがあると受理されないこともあります。
ここでは、診断書を後から依頼する際に特に注意しておきたい3つのポイントを紹介します。
- 発行には数日〜1週間かかることが多い
- 病院によっては「即日発行不可」や「追加受診」が必要なことも
- 保険・会社提出用は記載内容に誤りがないか必ず確認
これらを把握して行動すれば、診断書をスムーズに受け取ることができ安心です。
発行には数日〜1週間かかることが多い
診断書はカルテを確認し、医師が内容を精査したうえで署名する必要があります。
そのため、依頼してすぐに受け取れるケースは少なく、発行までに数日から1週間程度かかるのが一般的です。
特に総合病院など患者数の多い医療機関では、診断書作成が後回しになり、発行までさらに時間を要することもあります。
「明日必要だから今日申請すれば間に合う」と考えていると、予定通りに提出できず困る可能性があります。
余裕を持って依頼することが、スムーズに手続きを進めるための大切なポイントです。
病院によっては「即日発行不可」や「追加受診」が必要なことも
診断書の発行ルールは病院ごとに異なるため注意が必要です。
「即日発行は行っていない」と規定している医療機関も多く、どうしても早く必要な場合でも数日待つことになります。
また、カルテの記録が不十分な場合や症状の経過が明確でない場合は、追加の受診を求められることもあります。
これは診断書が公的な文書であり、医学的根拠に基づいて記載する必要があるためです。
依頼前に医療機関へ確認し、発行条件や必要な受診の有無をチェックしておくと安心です。
保険・会社提出用は記載内容に誤りがないか必ず確認
診断書は会社への欠勤証明や保険金請求などに使用されるため、記載内容の正確さが非常に重要です。
受診日や診断名、休養期間などに誤りがあると、提出先で受理されない可能性があります。
また、提出先によっては「指定の書式」や「必要項目」が決まっている場合もあり、一般的な診断書では不十分なこともあります。
受け取ったらすぐに内容を確認し、もし誤りや不足があれば速やかに医療機関に訂正を依頼しましょう。
診断書は一度提出すると訂正が難しいため、受け取った段階で内容確認を徹底することが大切です。
診断書の費用と支払い方法

診断書は医療行為そのものではなく、文書作成にあたるため費用が発生します。
この費用は保険診療とは異なる扱いとなり、病院やクリニックごとに料金設定がされています。
そのため、同じ内容の診断書でも医療機関によって金額が異なることがあります。
また、支払い方法についても「前払い制」「受け取り時払い」などルールが異なるため注意が必要です。
ここでは、診断書の費用と支払い方法について押さえておきたい3つのポイントを解説します。
- 自由診療扱いとなるため健康保険は使えない
- 費用相場は2,000〜5,000円程度
- 後日依頼の場合でも「前払い制」の病院もある
事前に料金や支払い方法を確認しておくことで、スムーズに診断書を受け取ることができます。
自由診療扱いとなるため健康保険は使えない
診断書の発行は保険診療の対象外となり、自由診療扱いになります。
そのため、健康保険証を提示しても自己負担割合(3割など)は適用されず、全額自己負担となります。
診察料や検査料とは別に、診断書作成費用として独立した料金が設定されています。
病院の掲示板やホームページに「診断書発行料金」が記載されている場合もあるので、事前に確認すると安心です。
保険適用外であることを理解し、追加の出費が発生する点を踏まえて準備しましょう。
費用相場は2,000〜5,000円程度
診断書の料金は医療機関によって異なりますが、一般的な相場は2,000〜5,000円程度です。
簡単な内容(学校提出用や短期間の休養証明など)であれば2,000円前後で発行されるケースが多いです。
一方で、会社提出用や保険申請用のように記載項目が多い診断書は、5,000円以上かかることもあります。
また、診断書の種類(一般診断書・就労証明書・保険金請求用など)によっても料金が変わります。
必要な診断書の種類を確認し、費用の目安を把握してから依頼することが大切です。
後日依頼の場合でも「前払い制」の病院もある
診断書を後日依頼する場合、病院によっては料金を前払いするルールが設けられています。
これは、診断書作成に時間がかかることや、受け取りに来ないトラブルを防ぐためです。
前払い制の場合、窓口で申請時に料金を支払い、後日完成した診断書を受け取る流れになります。
逆に、受け取り時に支払いを行う後払い制の医療機関もあります。
どちらにしても、申請時に「支払い方法」を確認しておくと安心です。
診断書の再発行は可能?

診断書は一度発行されたらそれで終わりというイメージがありますが、紛失や再提出が必要になることもあります。
このとき「診断書の再発行はできるのか?」と疑問を持つ方も多いでしょう。
結論としては、医療機関によって対応が異なるため、必ず再発行できるとは限りません。
再発行を依頼する際は、手数料や対応ルールを事前に確認しておくことが大切です。
ここでは診断書再発行の可否や注意点について、特に重要な3つのポイントを解説します。
- 紛失した場合は「再発行依頼」が可能なこともある
- 医療機関によっては「再発行不可」または「発行手数料」がかかる
- 会社・保険提出用はコピーで済むケースもある
これらを理解することで、診断書を再び必要とする状況に備えることができます。
紛失した場合は「再発行依頼」が可能なこともある
診断書を紛失してしまった場合でも、再発行に応じてもらえるケースがあります。
医療機関はカルテや過去の診断書の控えを一定期間保管しているため、それを基に再発行できるのです。
ただし、全く同じ診断書が再発行されるとは限らず、再度医師の署名や押印が必要になることがあります。
再発行を依頼する場合は、まず受診した医療機関に連絡し、必要な手続きや所要日数を確認しましょう。
急ぎの場合は「提出期限がある」ことを伝えると、優先的に対応してもらえる場合もあります。
医療機関によっては「再発行不可」または「発行手数料」がかかる
診断書の再発行は必ず対応してもらえるわけではなく、再発行自体を受け付けていない医療機関もあります。
また、再発行に対応している場合でも、手数料がかかるのが一般的です。
再発行手数料は1,000〜3,000円程度が相場で、初回発行時と同じ料金を請求されることもあります。
病院側からすると診断書は「新たに作成する文書」と扱われるため、手数料が必要になるのです。
紛失に備えて、最初に発行された診断書はコピーを取ってから提出するのが安心です。
会社・保険提出用はコピーで済むケースもある
診断書を再度提出する必要があっても、必ずしも原本が求められるわけではありません。
会社や保険会社によってはコピーの提出で問題ないケースもあります。
特に、就業証明や短期の欠勤証明などでは、コピーでも十分な証拠として扱われることがあります。
一方で、保険金の請求など重要な手続きでは原本が必須とされることが多いです。
再発行を依頼する前に、提出先に「コピーで良いかどうか」を確認することをおすすめします。
よくある質問(FAQ)

Q1. 診断書を受診日から1ヶ月以上経ってももらえる?
診断書は基本的に受診記録が残っていれば1ヶ月以上経っていても発行可能です。
ただし、時間が経過するほど当時の症状を証明しづらくなるため、医師の判断で追加受診を求められることもあります。
また、会社や保険会社によっては「受診から◯日以内の診断書のみ有効」と規定している場合があります。
利用目的がある場合は、必ず提出先の条件も確認しておきましょう。
Q2. 医師が変わっていても診断書は発行できる?
診断書はカルテに記録が残っていれば別の医師でも発行可能です。
ただし、診療当時の医師が署名するのが基本のため、不在や異動によって対応に時間がかかることもあります。
診療内容が複雑な場合は、担当医以外では発行できないケースもあります。
依頼する際は「診察した医師が不在でも発行できるか」を病院に確認しましょう。
Q3. 会社に提出する診断書と保険請求用は同じもの?
会社提出用と保険請求用の診断書は、用途が異なるため同じものではない場合があります。
会社提出用は欠勤や就労制限の有無を記載することが多く、比較的簡易な内容です。
一方、保険請求用は病名・発症日・治療内容・休養期間など詳細な情報が必要とされます。
同じ診断書で対応できるケースもありますが、提出先が指定する書式がある場合は専用の診断書が必要です。
Q4. 診断書を郵送で受け取ることは可能?
多くの医療機関では郵送対応が可能です。
ただし、本人確認のために事前の申請や署名が必要になることがあります。
郵送費用が別途かかる場合もあるため、依頼時に確認しておきましょう。
急ぎで必要な場合は窓口受け取りの方が確実です。
Q5. 領収書がなくても診断書を依頼できる?
診断書の発行はカルテ記録に基づいて行うため、領収書がなくても依頼可能です。
ただし、受診日や診察券番号を求められることがあるため、手元にある資料を準備しておくとスムーズです。
領収書がある場合は確認が早く進むので、提出できる場合は持参した方が安心です。
診断書は「後から依頼可能」だが注意が必要

診断書は受診時に依頼し忘れても、カルテに記録が残っていれば後から発行できるケースが多いです。
しかし、発行には日数がかかったり、追加受診や手数料が必要になる場合もあるため注意が必要です。
また、提出先の規定によっては一定期間内の診断書でなければ受理されないこともあります。
診断書が必要になる可能性があるときは、受診時にあらかじめ医師へ伝えておくことが一番確実です。
どうしても後から必要になった場合は、できるだけ早めに医療機関へ相談し、スケジュールに余裕を持って依頼することが大切です。