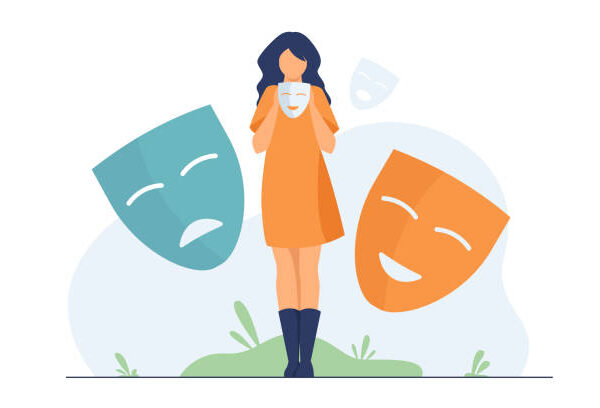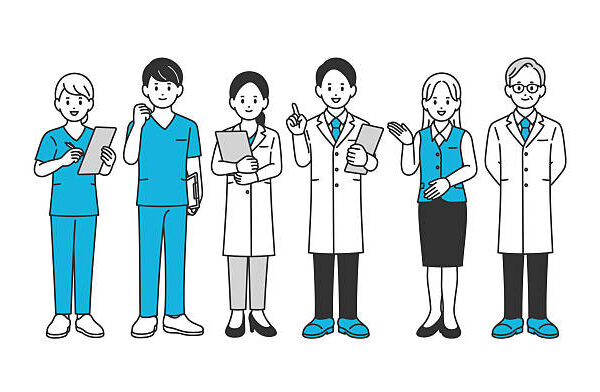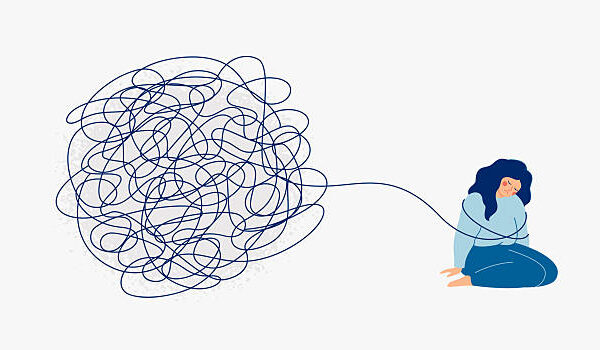傷病手当金は、病気やけがで働けなくなったときに生活を支える重要な制度です。
しかし、実際には申請しても「もらえない」「不支給になる」ケースが少なくありません。
「条件を満たしていなかった」「書類に不備があった」など、理由を正しく理解していないと受給できずに困ってしまうことがあります。
特に退職後の申請や副業収入がある場合、医師の証明が不十分な場合などは注意が必要です。
本記事では、傷病手当金が支給されない代表的なケースとその理由、さらに申請をスムーズに進めるためのポイントを徹底解説します。
「なぜ支給されないのか」を事前に理解しておくことで、不安を減らし、安心して申請手続きを進めることができます。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。
傷病手当金の基本ルールを確認

傷病手当金は病気やけがで働けないときに支給される制度ですが、誰でも自動的にもらえるわけではありません。
支給を受けるためには、一定の条件や手続きを満たす必要があります。
ここでは、傷病手当金を理解するうえで知っておくべき3つの基本ルールを整理します。
- 支給されるための条件(勤務不能・連続3日以上の休業・給与の支払いがない 等)
- 健康保険組合ごとに運用が異なることもある
- 「医師の証明」が不可欠である点
これらを把握しておくことで、申請時の不安やトラブルを防ぐことができます。
支給されるための条件(勤務不能・連続3日以上の休業・給与の支払いがない 等)
傷病手当金を受け取るには、いくつかの支給要件を満たす必要があります。
具体的には、病気やけがによって労務不能の状態にあり、仕事を続けることが難しいことが条件です。
また、仕事を休んだ日が連続して3日以上(待期期間)あり、その後も働けない状態が続いていることが求められます。
さらに、休業中に給与が支払われていないことが条件で、もし給与や手当が支給されている場合は、その分が減額または支給対象外となります。
これらの条件を満たして初めて、傷病手当金の申請が可能になります。
健康保険組合ごとに運用が異なることもある
傷病手当金は全国の健康保険制度で共通の仕組みですが、実際の運用方法や申請手続きは加入している健康保険組合によって異なる場合があります。
たとえば、提出書類のフォーマットや申請の締め切り、支給開始までの所要日数などに違いがあります。
また、細かい解釈や運用ルールも健保組合ごとに判断が異なるため、他の人の体験談が必ずしも当てはまるとは限りません。
そのため、申請を考えている場合は、まず所属する健康保険組合に直接確認することが重要です。
制度の基本は同じでも、実務上の差で不支給になることを防ぐためには、事前の確認が欠かせません。
「医師の証明」が不可欠である点
傷病手当金の申請には、医師が記入する労務不能の証明が必須です。
この証明は、診断書や意見欄の記載として行われ、申請書に医師の署名や押印が必要となります。
医師の証明が不十分であったり、労務不能の期間が明確に記載されていない場合は、不支給となる可能性があります。
また、診療内容と申請内容に食い違いがあると、保険組合から確認や差し戻しが入ることもあります。
スムーズに支給を受けるためには、受診時に「傷病手当金の申請に必要な証明がほしい」と医師に伝えることが大切です。
傷病手当金がもらえない代表的なケース

傷病手当金は生活を支える大切な制度ですが、すべての人が必ず受給できるわけではありません。
支給条件を満たしていない場合や、申請内容に不備がある場合は「もらえない」ケースに該当します。
ここでは、傷病手当金がもらえない代表的なケースを5つに分けて解説します。
- 給与や手当が出ている場合
- 医師の証明が不十分・診断書の記載ミス
- 自己都合退職後に条件を満たさない場合
- 就労とみなされる行為をしている場合
- 休職期間中に他の収入を得ている場合
これらを事前に理解しておくことで、不支給のリスクを避けやすくなります。
給与や手当が出ている場合
傷病手当金の基本条件のひとつに、休業期間中に給与が支払われていないことがあります。
たとえ一部でも給与や休業手当が支給されている場合は、その分が差し引かれるか、場合によっては支給対象外となります。
特に会社独自の休業補償制度がある場合は、傷病手当金が「重複支給」と判断され、不支給となることがあります。
そのため、休業補償と傷病手当金の関係については事前に会社の人事や健保組合に確認しておくことが大切です。
「給与がゼロであること」が原則条件である点を理解しておきましょう。
医師の証明が不十分・診断書の記載ミス
傷病手当金を申請する際には、必ず医師の証明が必要です。
この証明が不十分であったり、診断書や申請書に誤りがある場合は、不支給や差し戻しの対象となります。
例えば「労務不能の期間が明確でない」「病名の記載が不十分」「医師の署名がない」などが典型的な例です。
書類の不備によって支給が遅れることも多く、最悪の場合は支給されないままになることもあります。
申請時には、医師に「傷病手当金用の証明が必要」と明確に伝えることが重要です。
自己都合退職後に条件を満たさない場合
退職後でも傷病手当金を受け取れるケースはありますが、一定の条件を満たしていないと不支給になります。
代表的なのは「退職日までに労務不能であることが証明されていない」場合です。
また、退職前に1年以上の被保険者期間がないと、退職後の申請資格を失います。
さらに、退職日以降に新しい職場や健康保険に加入した場合も、支給対象から外れることがあります。
退職後の申請は条件が厳しいため、早めに制度内容を確認して準備しておくことが大切です。
就労とみなされる行為をしている場合
傷病手当金は働けないことが前提の制度です。
そのため、休職中にアルバイトや副業を行っていると「労務不能ではない」と判断されることがあります。
また、実際に働いていなくても、就労とみなされる行為(内職やフリーランス活動など)が確認されると支給対象外となる可能性があります。
一時的な短時間労働であっても収入があれば減額されることがあるため注意が必要です。
休職中は「完全に働けない状態」であることを証明することが求められます。
休職期間中に他の収入を得ている場合
休職中に給与以外の収入を得ている場合も、支給が制限されることがあります。
たとえば不動産収入や年金収入などがある場合は、就労収入とみなされなくても影響を受ける可能性があります。
また、申請書に収入状況を正しく記載しないと、不支給や返還を求められることもあります。
「副業や一時的な収入でも影響があるのか?」と疑問に思ったら、必ず健保組合に確認しましょう。
透明性を持って申告することが、トラブルを防ぐための最善策です。
退職後の傷病手当金でもらえないケース

傷病手当金は退職後でも一定の条件を満たせば継続して受け取ることが可能です。
しかし、その条件を満たしていないと退職後の申請は認められず、不支給となってしまいます。
特に「退職日に労務不能であるかどうか」「被保険者期間の長さ」「退職後の保険加入状況」が重要なポイントになります。
ここでは、退職後の傷病手当金でもらえない代表的なケースを3つ紹介します。
- 退職日に「働ける」とみなされている場合
- 退職日までに「連続1年以上の被保険者期間」がない場合
- 退職後すぐに別の健康保険へ加入してしまった場合
退職前から申請を検討している方は、これらの条件を必ず確認しておきましょう。
退職日に「働ける」とみなされている場合
退職後に傷病手当金をもらうには、退職日に労務不能であることが絶対条件です。
もし退職日当日に「働ける」と判断されている場合は、退職後の支給対象外となります。
これは、制度が「退職時点で働けない状態の人を保障するもの」であるためです。
そのため、退職時点で診断書に「労務不能」と明記されていることが非常に重要になります。
退職後に支給を受けたい人は、退職日を迎える前に医師へ相談し、証明を確保しておく必要があります。
退職日までに「連続1年以上の被保険者期間」がない場合
退職後に傷病手当金を継続して受け取るためには、退職日までに1年以上の被保険者期間が必要です。
この条件を満たしていない場合は、退職後の支給資格を失うことになります。
たとえば入社して半年で退職した場合や、短期間での転職を繰り返している場合は対象外です。
ただし、前職からの保険加入期間を通算できるケースもあるため、健保組合に確認することが大切です。
退職を検討している場合は、在籍期間が1年以上になってから退職することが望ましいといえます。
退職後すぐに別の健康保険へ加入してしまった場合
退職後に傷病手当金を受け取るには、退職後に新しい健康保険へ加入していないことが条件になります。
すぐに再就職して新しい会社の健康保険に加入すると、前の健康保険からの傷病手当金は打ち切られる仕組みです。
これは、退職後の傷病手当金が「任意継続」や「無職で保険に入っていない人」の救済制度だからです。
もし退職後も支給を受けたい場合は、新しい保険加入のタイミングを考慮する必要があります。
転職予定がある人は、退職前に健保組合へ相談して制度の適用可否を確認するのがおすすめです。
傷病手当金の申請でよくあるトラブル

傷病手当金は制度上の条件を満たしていても、申請の過程でトラブルが発生し、支給が遅れたり不支給となることがあります。
特に多いのは、書類の不備や記載内容の不一致、そして提出期限を守れなかったことによるトラブルです。
これらは事前に注意していれば防げるものが多いため、よくある失敗事例を知っておくことが大切です。
ここでは、傷病手当金の申請でありがちな3つのトラブルを紹介します。
- 書類不備による差し戻し
- 医師・会社・本人の記載内容の食い違い
- 提出期限を過ぎてしまうケース
これらを理解して準備することで、スムーズな受給につながります。
書類不備による差し戻し
傷病手当金の申請で最も多いトラブルは、書類不備による差し戻しです。
申請書に記入漏れがあったり、必要な押印が抜けている場合、保険組合から差し戻されてしまいます。
また、病名や労務不能期間の記載が不明確な診断書も、不備と判断されることがあります。
差し戻しになると再提出に時間がかかり、支給までの期間が延びてしまいます。
申請前に必ず書類をダブルチェックし、不備がないか確認しておくことが重要です。
医師・会社・本人の記載内容の食い違い
申請書は本人・会社・医師の3者が記載する部分があり、それぞれの内容が一致している必要があります。
たとえば、本人が「◯月◯日から休職」と記載しても、会社が異なる日付を記入していると、整合性が取れません。
また、医師が診断書に記載した休養期間と、本人の申請内容が食い違うケースも多いです。
このような矛盾があると、保険組合から確認が入り、支給が遅れる原因になります。
申請前に会社や医師としっかり情報をすり合わせ、同じ内容になるよう注意しましょう。
提出期限を過ぎてしまうケース
傷病手当金の申請には提出期限が設けられており、これを過ぎると受理されない場合があります。
多くの健康保険組合では、支給対象期間が終わってから2年以内に申請しなければなりません。
しかし、会社を経由して提出する必要があるため、本人が余裕を持って準備しないと期限を過ぎるリスクがあります。
また、書類の修正や差し戻し対応に時間を取られ、気づけば期限を超えてしまうケースもあります。
提出期限を守るためには、必要書類を早めに揃え、スケジュールに余裕を持って行動することが大切です。
傷病手当金を確実にもらうためのポイント

傷病手当金は条件を満たしていれば支給される制度ですが、申請の不備や準備不足によって不支給や遅延が起こることもあります。
確実に受け取るためには、申請前の確認と書類の正確な準備が欠かせません。
ここでは、傷病手当金を確実に受け取るために押さえておくべき3つのポイントを紹介します。
- 申請前に会社や健保組合に要件を確認する
- 医師に「労務不能の期間」を正確に記載してもらう
- 提出先ごとに必要書類や締め切りを把握しておく
これらを実践することで、スムーズに申請が進み、支給を確実に受けられる可能性が高まります。
申請前に会社や健保組合に要件を確認する
傷病手当金の制度自体は全国共通ですが、実際の運用は健保組合ごとに異なることがあります。
たとえば申請書の様式や提出期限、必要書類の種類などは組合ごとに異なるケースが少なくありません。
また、会社によっても就業規則で休職や手当のルールが定められている場合があります。
そのため、申請前には必ず会社の人事担当者や健保組合に要件を確認しておきましょう。
事前確認を怠ると、不支給や申請遅延の原因になりやすいため注意が必要です。
医師に「労務不能の期間」を正確に記載してもらう
傷病手当金の申請で最も重要なのは、医師の記載内容です。
特に労務不能の期間が明確でなければ、申請が認められない可能性があります。
医師によっては曖昧な表現をする場合もあるため、「◯月◯日から◯月◯日まで就労不可」と具体的に書いてもらうことが望ましいです。
また、再申請の際に期間がつながるよう、医師にあらかじめ伝えておくとスムーズです。
医師への依頼時には「傷病手当金の申請用」とはっきり伝えることが確実な方法です。
提出先ごとに必要書類や締め切りを把握しておく
傷病手当金は会社・健保組合・本人の三者が関わる手続きであり、それぞれに必要な書類や締め切りがあります。
会社を経由して提出する場合は、本人が余裕を持って書類を準備しなければなりません。
また、健保組合には「支給対象期間終了から2年以内」という期限が設けられています。
提出が遅れると受理されない可能性があるため、締め切りを必ず確認しておくことが重要です。
書類を提出する際にはコピーを控えておくと、万が一のトラブル時に役立ちます。
よくある質問(FAQ)

Q1. 傷病手当金はアルバイトや副業収入があると支給されない?
傷病手当金は労務不能であることが支給条件のため、原則として働ける状態であれば対象外です。
アルバイトや副業を行って収入を得ている場合は「労務不能ではない」と判断され、不支給になる可能性があります。
ただし、過去に行っていた副業収入や不労所得(家賃収入・年金など)は必ずしも不支給理由にはなりません。
判断基準は健康保険組合ごとに異なるため、事前に確認することが大切です。
Q2. 精神疾患による休職でも傷病手当金はもらえる?
うつ病や不安障害など精神疾患による休職であっても、医師の診断により労務不能と証明されれば支給対象になります。
ただし、診断書に労務不能の期間が明確に記載されていない場合は、不支給になる可能性があります。
また、症状が曖昧な場合や就労可能と判断される場合は、支給が認められないケースもあります。
精神疾患の場合は特に、医師に「就労不可であること」を明確に記載してもらうことが重要です。
Q3. 傷病手当金が不支給になった場合、再申請は可能?
傷病手当金が一度不支給と判断されても、条件を満たせば再申請は可能です。
たとえば書類不備や医師の証明不足が原因の場合は、修正して再提出すれば受理されるケースがあります。
ただし、最初の申請時に条件自体を満たしていない場合は、再申請しても認められない可能性が高いです。
不支給理由をしっかり確認し、必要な修正や条件整備を行ったうえで再申請することが大切です。
Q4. 傷病手当金と失業保険は同時にもらえる?
傷病手当金と失業保険は同時に受給できません。
傷病手当金は「働けない人」を対象にしているのに対し、失業保険は「働ける状態の人」を対象にしているためです。
ただし、失業保険の受給期間は延長できるため、まず傷病手当金を受け取り、その後で失業保険を申請することは可能です。
手続きの順番を誤ると損をすることもあるので、ハローワークや健保組合に相談してから進めましょう。
Q5. 傷病手当金は最大でいつまで支給される?
傷病手当金の支給期間は最長1年6か月です。
ただし、この期間は「支給開始日から起算」されるため、途中で仕事に復帰して支給を受けなかった期間も含まれます。
そのため、実際に受け取れる期間は通算で1年6か月以内という点に注意が必要です。
長期的な治療が見込まれる場合は、計画的に申請し、支給期間を有効に活用することが大切です。
傷病手当金は「条件を満たさないともらえない」

傷病手当金は、病気やけがで働けない人を支える大切な制度ですが、条件を満たしていなければ受給できません。
給与が支払われている場合や医師の証明が不十分な場合、退職後の要件を満たさない場合などは不支給の対象となります。
また、申請書の不備や期限切れといった手続き上のミスでも、受給できないケースがあります。
制度を正しく理解し、事前に会社や健保組合に確認することで、不支給のリスクを大幅に減らすことができます。
「傷病手当金は条件を満たさないともらえない」という基本を理解し、早めに準備することが安心につながります。