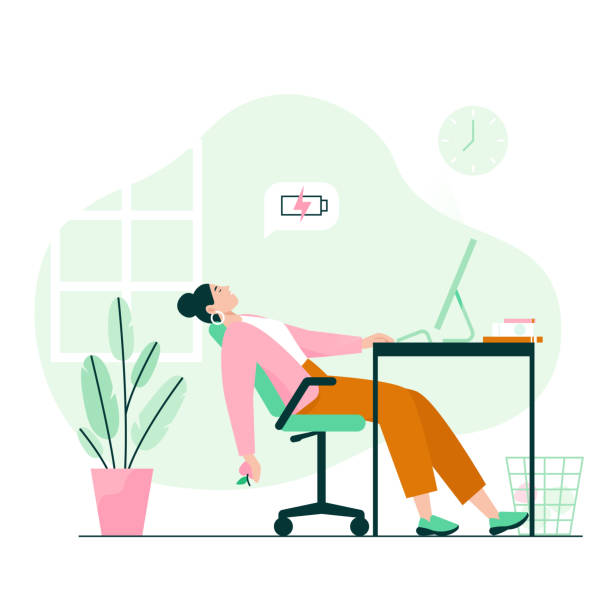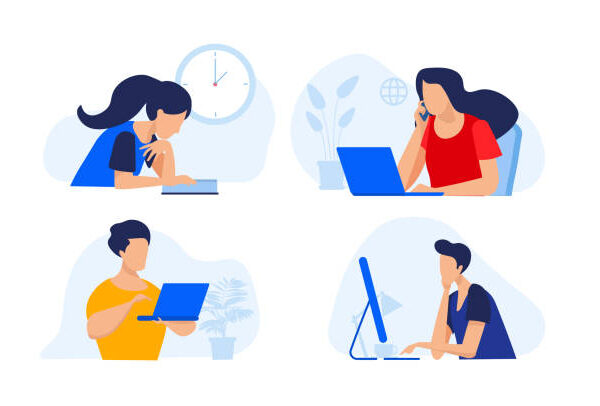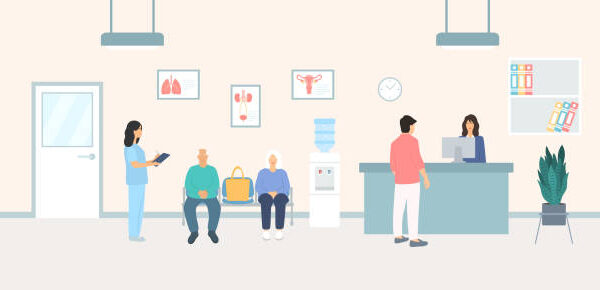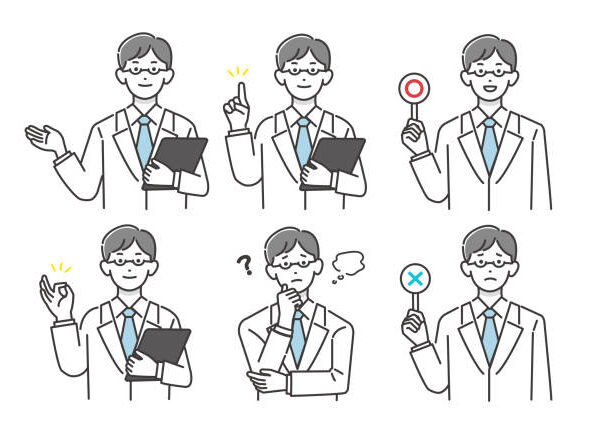「しっかり寝たはずなのに疲れが取れない…」そんな悩みを抱える人は少なくありません。
特に10代・20代・30代・40代といった年代ごとに、原因は大きく異なります。10代では成長期特有の体の変化や生活リズムの乱れ、20代では社会人生活のストレスや不規則な生活、30代では仕事や家庭との両立による疲労、そして40代では更年期や生活習慣病の影響が関与することもあります。
単なる睡眠不足と思って放置してしまうと、自律神経失調症やうつ病、睡眠時無呼吸症候群、慢性疲労症候群といった病気が隠れているケースもあるため注意が必要です。
本記事では、年代別に「寝ても疲れが取れない」原因と考えられる病気、改善方法や受診の目安をわかりやすく解説していきます。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。
寝ても疲れが取れないのはなぜ?

「寝ても疲れが取れない」と感じる背景には、単純な睡眠不足だけでなく、様々な要因が複雑に絡み合っています。
睡眠の質が低下していたり、自律神経の乱れや精神的ストレスが影響している場合もあれば、栄養不足や運動不足といった生活習慣の問題、さらには病気が隠れている可能性も考えられます。以下では代表的な原因を詳しく解説します。
- 睡眠の質の低下(中途覚醒・睡眠時無呼吸症候群など)
- 自律神経の乱れや精神的ストレス
- 栄養不足や運動不足による慢性的な疲労感
- うつ病・甲状腺疾患などの病気が隠れている可能性
それぞれの詳細について確認していきます。
睡眠の質の低下(中途覚醒・睡眠時無呼吸症候群など)
寝ても疲れが取れない大きな原因のひとつが、睡眠の質の低下です。例えば「中途覚醒」が続くと深い眠りに到達できず、体も脳も十分に休まらないまま朝を迎えてしまいます。
また、「睡眠時無呼吸症候群」のように、睡眠中に呼吸が何度も止まる病気では、本人が気づかないまま酸素不足になり、慢性的な疲労感や強い眠気が日中に現れることがあります。
特にいびきを指摘される人や、日中の眠気が強い人は要注意です。こうした睡眠の質の低下は、単なる生活習慣の乱れだけでなく、放置すると高血圧や心疾患のリスクにもつながるため、早期に対処することが重要です。
自律神経の乱れや精神的ストレス
現代人に多い「寝ても疲れが取れない」原因のひとつが、自律神経の乱れです。自律神経は活動時に働く交感神経と、休息時に働く副交感神経からなり、睡眠の質に大きな影響を与えます。
ストレスが続くと交感神経が優位になりやすく、寝ても脳や体がリラックスできず、朝になっても疲れが抜けません。特に仕事や学業、人間関係で強いプレッシャーを感じていると、自律神経のバランスが乱れやすくなります。
さらに、精神的ストレスは浅い眠りや悪夢を招き、回復感のない睡眠につながります。
こうした状態が続くと慢性的な疲労感や抑うつ状態を引き起こすため、適度な休養やリラックス法を取り入れることが必要です。
栄養不足や運動不足による慢性的な疲労感
寝ても疲れが取れない背景には、食生活や運動習慣の乱れも大きく影響します。
栄養面では、エネルギー代謝に関わるビタミンB群、酸素を運ぶ鉄分、そして体を修復するタンパク質が不足すると、体の回復が十分に行われません。
また、運動不足により血流が滞ると、疲労物質が体内に溜まりやすくなり、慢性的な疲労感につながります。特にデスクワーク中心の生活では、軽い運動を取り入れるだけでも血流や代謝が改善し、睡眠の質の向上にもつながります。
逆に過度な運動や不規則な食生活は逆効果となるため、バランスを意識した生活習慣が大切です。
うつ病・甲状腺疾患などの病気が隠れている可能性
生活習慣を整えても「寝ても疲れが取れない」状態が続く場合、病気が隠れている可能性も考えられます。
代表的なのは「うつ病」で、気分の落ち込みや無気力感とともに、睡眠障害や強い倦怠感が出やすくなります。また「甲状腺機能低下症」では、ホルモン分泌の低下によって新陳代謝が落ち、体が常にだるい・重いと感じるようになります。
さらに「慢性疲労症候群」や「心疾患」「糖尿病」なども疲労感の原因となることがあります。
これらは自己判断が難しく、放置すると症状が悪化する恐れがあるため、疲労が長引く場合は早めに内科や心療内科を受診することが大切です。
【年代別】寝ても疲れが取れない原因と特徴

「寝ても疲れが取れない」という悩みは、どの年代にも共通して見られますが、その背景や原因は年代によって大きく異なります。
成長期の10代、社会人生活が本格化する20代、家庭や仕事の両立に追われる30代、そして加齢やホルモンの変化が現れる40代では、それぞれ特有の疲労要因があります。以下では年代別の特徴を詳しく解説します。
- 10代:成長期と生活リズムの乱れ
- 20代:社会人生活・ストレスによる影響
- 30代:家庭・仕事の両立による心身の疲労
- 40代:加齢とホルモン変化の影響
それぞれの詳細について確認していきます。
10代:成長期と生活リズムの乱れ
10代は心身ともに大きく成長する時期であり、エネルギーの消費量も多いため、質の高い睡眠が欠かせません。
しかし、部活動や学業による過労、夜更かしやスマホの長時間利用などで生活リズムが乱れると、寝ても疲れが取れない状態に陥りやすくなります。
特に成長期にはホルモンの分泌が盛んで、体が睡眠を必要としているにもかかわらず、十分な休養が取れないことが慢性的な疲労感を招きます。
また、10代女性に多い鉄欠乏性貧血は、朝のだるさや集中力の低下を引き起こしやすいため注意が必要です。この年代では「ただの寝不足」と軽視せず、生活習慣の改善や栄養バランスの見直しが不可欠です。
20代:社会人生活・ストレスによる影響
20代は学生から社会人へと生活環境が大きく変化する時期であり、仕事や人間関係によるストレス、長時間労働、不規則な生活が疲労の主な原因となります。
特に就職直後は生活リズムが安定せず、夜更かしや食生活の乱れによって睡眠の質が低下しやすくなります。
また、飲み会や外食の機会が増えることでアルコールやカフェインの摂取量が増え、それがかえって疲労感を強める要因になることもあります。
さらに、強いストレスは自律神経を乱し、寝ても脳や体が休まらない状態を作り出します。若さに任せて無理を重ねやすい年代ですが、この時期に疲労を放置すると慢性的な不調や精神的な不安定さを引き起こすため、生活リズムを整えることが重要です。
30代:家庭・仕事の両立による心身の疲労
30代は仕事での責任が重くなる一方で、結婚・出産・育児といった家庭の役割も加わり、心身ともに疲労が蓄積しやすい年代です。
仕事のストレスに加えて、育児や家事による睡眠不足が重なると、たとえ長時間眠っても疲れが抜けにくくなります。
また、この年代から増えてくるのが「睡眠時無呼吸症候群」や「生活習慣病の予備軍」です。体重増加や不規則な生活により、いびきや呼吸の乱れが起きやすくなり、深い眠りを妨げます。さらに、運動不足や栄養の偏りも疲労感を強める要因です。
30代はキャリアや家庭のバランスを取るのが難しい時期ですが、意識的に休養を確保しなければ慢性疲労やメンタル不調に発展するリスクが高まります。
40代:加齢とホルモン変化の影響
40代になると、加齢による体力低下やホルモンバランスの変化が疲労の大きな原因となります。特に女性では更年期に差しかかり、エストロゲンの減少によって不眠やホットフラッシュ、気分の落ち込みが起きやすくなります。
男性もまた、加齢に伴いテストステロンの分泌量が低下し、活力不足や慢性的な疲労感を感じやすくなります。
さらに、高血圧や糖尿病などの生活習慣病が顕在化し始めるのもこの年代の特徴です。これらの病気は睡眠の質を低下させ、体の回復を妨げるため「しっかり寝ても疲れる」という状態を引き起こします。
40代は仕事や家庭の責任がピークに達する時期ですが、体の変化を理解し、生活習慣の見直しや定期的な健康チェックを怠らないことが大切です。
疲れが取れないときに考えられる病気

生活習慣を見直しても「寝ても疲れが取れない」状態が続く場合は、病気が隠れている可能性があります。
特に以下の病気は、慢性的な疲労感や日中の眠気の原因として多く見られます。早期発見・治療につなげるためにも、症状を知っておくことが大切です。
- 睡眠時無呼吸症候群
- 自律神経失調症
- うつ病・不安障害
- 甲状腺機能低下症
- 慢性疲労症候群(ME/CFS)
それぞれの詳細について確認していきます。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が繰り返し止まることで体が酸素不足に陥り、深い眠りが妨げられる病気です。
本人は気づきにくいのですが、家族から「いびきが大きい」「寝ているときに呼吸が止まっている」と指摘されることで発覚することが多いです。
酸素不足の状態が夜間に続くと、翌朝はぐっすり眠ったつもりでも疲れが取れず、強い眠気や頭痛、集中力低下を引き起こします。
放置すると高血圧や心筋梗塞、脳卒中などのリスクを高めるため、早めに睡眠外来での検査が必要です。肥満や加齢、顎の形なども影響するため、生活習慣の見直しと医療的な治療の両立が求められます。
自律神経失調症
自律神経失調症は、交感神経と副交感神経のバランスが崩れることで体の不調が現れる病気です。
主な症状には、慢性的な疲労感、めまい、動悸、頭痛、胃腸の不調などがあります。特にストレスや不規則な生活が続くと、夜になっても交感神経が優位になり、眠りが浅くなるため「寝ても疲れが取れない」と感じやすくなります。
また、女性ではホルモンバランスの変化によって症状が強まることもあります。
自律神経の乱れは検査で明確に診断しにくいため、「不調は気のせい」と誤解されやすいのも特徴です。
しかし、放置すると抑うつ状態や慢性疲労に発展することもあるため、休養、ストレスマネジメント、心療内科での相談が有効です。
うつ病・不安障害
うつ病や不安障害も「寝ても疲れが取れない」代表的な病気です。精神的な落ち込みや不安感に加え、睡眠障害や強い倦怠感が伴うことが多いのが特徴です。
眠りが浅くなる、早朝に目が覚めてしまう、あるいは逆に過眠になるなど、睡眠のリズムが大きく乱れます。その結果、十分に寝ても回復感が得られず、日中に強い疲労感や無気力感が続きます。
さらに、集中力の低下や意欲の減退が生活に大きな影響を与えることも少なくありません。
精神的な症状が背景にあるため、単に生活習慣を改善するだけでは回復が難しく、心療内科や精神科での診断と適切な治療が不可欠です。早期に相談することで症状の悪化を防ぐことができます。
甲状腺機能低下症
甲状腺機能低下症は、甲状腺ホルモンの分泌が不足することで新陳代謝が低下し、全身のだるさや疲れを引き起こす病気です。
症状としては、朝起きても疲れが取れない、寒がりになる、体重が増えやすい、肌が乾燥する、便秘がちになるといったものがあります。
特に女性に多く、更年期と混同されることも少なくありません。軽度の場合は気づかれにくいのですが、進行すると生活に支障をきたすほど強い疲労感が続きます。
血液検査で診断が可能であり、適切な投薬治療によって改善できるため、長引く倦怠感がある場合は内科や内分泌科での受診が推奨されます。
慢性疲労症候群(ME/CFS)
慢性疲労症候群(ME/CFS)は、原因不明の強い疲労感が6か月以上続き、日常生活に大きな支障をきたす病気です。休養を取っても回復せず、軽い運動や作業で症状が悪化するのが特徴です。
また、睡眠の質が低下し、寝ても疲れが全く取れない状態が続きます。
その他にも、集中力や記憶力の低下、筋肉痛、頭痛、微熱など多彩な症状が現れます。精神的な病気と誤解されることもありますが、実際には身体的な要因も関与していると考えられています。
治療法は確立されていないものの、投薬や生活習慣の調整、心理的サポートなどを組み合わせることで症状の軽減が可能です。長期間疲労が続く場合は早めに専門医の診断を受けることが大切です。
日中に出る疲労のサイン

「寝ても疲れが取れない」と感じる場合、日中の体や心の状態に明確なサインが現れることがあります。
単なる寝不足と違い、慢性的な疲労や病気が隠れている場合には、毎日の生活に影響する症状が出やすくなります。以下では代表的なサインを紹介します。
- 朝起きても体が重い
- 日中に強い眠気がある
- 集中力や記憶力の低下
- イライラや気分の落ち込み
それぞれの詳細について確認していきます。
朝起きても体が重い
朝起きても体が重く、だるさが残っている場合は、睡眠の質が低下しているサインです。
通常、深い眠り(ノンレム睡眠)によって体と脳はしっかり休息できるはずですが、夜中に目が覚める中途覚醒や、浅い眠りが続くと疲労が回復しません。
また、睡眠時無呼吸症候群や自律神経の乱れによっても、休んだつもりが十分に回復できない状態が続きます。特に朝起きても疲れが取れない日が連続する場合は、生活習慣の乱れだけでなく病気の兆候の可能性もあるため注意が必要です。
規則正しい睡眠環境を整えることはもちろん、症状が長引く場合には専門の医療機関での相談が勧められます。
日中に強い眠気がある
しっかり眠ったはずなのに日中に強い眠気が襲ってくるのは、疲労が解消されていない大きなサインです。
特に会議中や運転中、静かな環境で急に眠気が強まる場合は、睡眠時無呼吸症候群やナルコレプシーなどの睡眠障害が関与していることもあります。
また、過度なストレスや自律神経の乱れによって眠りの質が浅くなると、日中の活動時に眠気が強まります。単なる昼食後の眠気とは異なり、強い眠気が頻繁に起こる場合は事故や仕事上のミスにもつながりやすく危険です。
改善には生活リズムの安定化が欠かせませんが、症状が続く場合は睡眠外来での検査を受けることが望まれます。
集中力や記憶力の低下
寝ても疲れが取れない状態が続くと、脳の機能にも影響が現れます。その代表的なサインが集中力や記憶力の低下です。
質の良い睡眠は、日中に得た情報を整理・記憶として定着させる役割を持っています。しかし、浅い眠りや中断の多い睡眠が続くと、この機能が十分に働かず、物事を覚えにくくなったり集中が続かなくなったりします。
学生にとっては学習効率の低下、社会人にとっては仕事のパフォーマンス低下に直結するため見過ごせない症状です。
さらに、慢性的な疲労によって脳疲労が進むと、ブレインフォグと呼ばれる思考力の低下にもつながります。単なる「疲れのせい」と片付けず、早めの対策が重要です。
イライラや気分の落ち込み
日中のイライラや気分の落ち込みも、寝ても疲れが取れないときに現れる典型的なサインです。
睡眠不足や浅い眠りが続くと、脳内のセロトニンやドーパミンといった神経伝達物質のバランスが崩れ、感情のコントロールが難しくなります。その結果、些細なことでイライラしたり、気分が落ち込みやすくなります。
特に長期間続く場合は、うつ病や不安障害の初期症状である可能性も否定できません。また、精神的なストレスと肉体的な疲労は相互に影響し合うため、悪循環に陥りやすいのが特徴です。
イライラや落ち込みが続くときには、休養やストレスケアを意識するだけでなく、必要に応じて専門医に相談することが大切です。
改善するためのセルフケアと生活習慣

「寝ても疲れが取れない」状態を改善するには、まず生活習慣を見直し、自分でできるセルフケアを取り入れることが重要です。
睡眠の質を高め、心身のバランスを整えるために、日常生活の中で意識できるポイントはいくつもあります。以下に代表的な改善方法を紹介します。
- 睡眠環境を整える
- 食事・栄養バランスを見直す
- 適度な運動を取り入れる
- ストレスマネジメントを習慣化
それぞれの詳細について確認していきます。
睡眠環境を整える
疲労を回復するためには「質の良い睡眠」が欠かせません。そのためにまず取り組みたいのが、睡眠環境の改善です。寝る直前までスマホやPCを使用すると、ブルーライトの影響で脳が覚醒し、眠りが浅くなります。
就寝の1時間前にはデジタル機器の利用を控え、リラックスできる時間を作ることが大切です。また、寝室の環境も重要で、遮光カーテンを使って外光を遮る、静かな環境を整える、室温を20℃前後に保つなどの工夫が効果的です。
さらに、寝具の硬さや枕の高さも体に合っていないと熟睡を妨げます。小さな改善を積み重ねることで、朝起きたときの回復感が変わり、日中の疲労感も軽減されます。
食事・栄養バランスを見直す
栄養バランスの乱れは「寝ても疲れが取れない」大きな要因のひとつです。エネルギーを作り出すビタミンB群、酸素を運ぶ鉄分、神経や筋肉の働きをサポートするマグネシウムなどが不足すると、体の回復力が低下してしまいます。
特に忙しい人はコンビニ食や外食に偏りがちで、野菜・魚・肉・豆類といった栄養源をバランスよく摂れていないことが多いです。
また、就寝前のアルコールやカフェインは睡眠の質を大きく下げるため控える必要があります。
1日3食を基本とし、血糖値の急上昇を避ける食事法を意識すると、体への負担が減り疲労感が和らぎます。必要に応じてサプリメントを補助的に取り入れるのも有効です。
適度な運動を取り入れる
運動不足は血流を滞らせ、疲労物質の蓄積や代謝の低下を招き、「寝ても疲れが取れない」原因になります。
逆に、適度な運動を取り入れることで血流や酸素供給が改善し、体の回復力が高まります。
特にウォーキングやストレッチといった軽い有酸素運動は、心身をリラックスさせ、副交感神経を優位にする効果があり、睡眠の質向上にもつながります。ポイントは「無理のない範囲」で継続することです。
激しい運動はかえって交感神経を刺激してしまうため逆効果になることもあります。日常生活に15〜30分程度の運動を組み込むだけでも、翌朝の目覚めや日中の疲労感に大きな変化をもたらします。
ストレスマネジメントを習慣化
ストレスは自律神経を乱し、睡眠の質を下げる大きな要因です。そのため、日常的にストレスをコントロールする習慣を持つことが大切です。
具体的には、深呼吸や瞑想、マインドフルネスといったリラクゼーション法が有効です。短時間でも意識的に呼吸を整えることで、緊張状態からリラックスモードへ切り替えることができます。
また、趣味の時間を確保したり、音楽や入浴で心身をリフレッシュさせることも効果的です。
さらに、ストレスを抱え込まずに人に相談することも大切です。こうしたストレスマネジメントを習慣化することで、交感神経と副交感神経のバランスが整い、睡眠の質が向上し、結果的に疲労回復力が高まります。
受診を検討すべきサイン

「寝ても疲れが取れない」状態が長引く場合、生活習慣の乱れだけでなく病気が隠れている可能性があります。
自己判断で放置すると悪化することもあるため、早めの受診が大切です。以下のようなサインがある場合は医療機関への相談を検討しましょう。
- 2週間以上疲れが続く
- 睡眠時間を取っても改善しない
- 強い眠気や頭痛・動悸がある
- 気分の落ち込み・無気力感がある
それぞれの詳細について確認していきます。
2週間以上疲れが続く
通常の疲労は数日休養を取れば改善するものです。しかし、2週間以上にわたり強い疲労感が続く場合は注意が必要です。
慢性疲労症候群やうつ病、甲状腺疾患などの病気が背景にある可能性が高く、単なる寝不足や生活習慣の乱れでは説明できないこともあります。
特に「休日にしっかり休んでも疲れが取れない」「朝から体が重い」という状態が続く場合は、体が出しているSOSサインです。
放置すると仕事や学業、家庭生活にも悪影響が出てしまうため、早めに内科や心療内科を受診することが望まれます。検査によって病気の有無を確認することで、安心感が得られるだけでなく、適切な治療や生活改善の方向性を見出せます。
睡眠時間を取っても改善しない
毎日7〜8時間以上の睡眠を確保しているにもかかわらず、疲労が改善しない場合は、睡眠の質に問題があるか、病気が隠れている可能性があります。
特に、睡眠時無呼吸症候群のように眠っている間に呼吸が止まり、深い眠りに入れないケースでは、本人は気づかずに慢性的な疲労が蓄積していきます。
また、自律神経失調症やうつ病では、十分な睡眠を取っても脳や体が休まらず、倦怠感が続くことがあります。こうした状態を「ただの寝不足」と誤解して放置すると、症状が悪化して生活の質を大きく下げるリスクがあります。
長期的な疲労感がある場合は、睡眠外来や内科での検査を受けることが推奨されます。
強い眠気や頭痛・動悸がある
日中に強い眠気が続いたり、頭痛や動悸を伴う場合は、深刻な睡眠障害や循環器系の病気が関与している可能性があります。
例えば、睡眠時無呼吸症候群では酸素不足が繰り返されるため、脳や心臓に負担がかかり、頭痛や動悸といった症状が現れることがあります。
また、自律神経の乱れや心疾患が原因で動悸や不整脈が起こるケースもあります。強い眠気や頭痛は日常生活のパフォーマンスを著しく下げ、事故や仕事のミスにもつながる危険なサインです。
市販薬やカフェインで一時的にごまかすのではなく、原因を明らかにすることが重要です。早めに内科や循環器科、睡眠外来を受診することで重症化を防ぐことができます。
気分の落ち込み・無気力感がある
疲れが取れない状態に加えて、気分の落ち込みや無気力感が続く場合は、精神的な病気が背景にある可能性があります。
特にうつ病や不安障害では、睡眠障害と強い倦怠感がセットで現れることが多く、心の不調が体の疲労感として表れていることがあります。
「やる気が出ない」「何をしても楽しくない」といった気分の変化が続く場合は、精神的なサインを見逃さないことが重要です。
また、こうした状態を無理に我慢して働き続けると、症状が悪化して回復に時間がかかることも少なくありません。気分の落ち込みや無気力感が2週間以上続く場合は、心療内科や精神科での受診を検討する必要があります。
早期に専門家に相談することで、心身の回復がスムーズになります。
相談先と診療科の選び方

「寝ても疲れが取れない」状態が続くとき、どの診療科を受診すべきか迷う方は多いでしょう。
症状の背景には生活習慣病から睡眠障害、心の不調、ホルモンバランスの乱れまで幅広い要因が考えられるため、適切な診療科を選ぶことが大切です。以下では代表的な相談先を紹介します。
- 内科:生活習慣病や全身疾患のチェック
- 睡眠外来:いびき・無呼吸の検査
- 心療内科・精神科:ストレス・うつ病の可能性
- 婦人科:女性ホルモンの変化が関与する場合
それぞれの詳細について確認していきます。
内科:生活習慣病や全身疾患のチェック
まず最初に相談しやすいのが内科です。内科では、血液検査や心電図、ホルモン検査などを通じて、生活習慣病や全身疾患の有無を調べることができます。
特に、甲状腺機能低下症や糖尿病、高血圧といった疾患は、寝ても疲れが取れない原因となる代表的な病気です。
これらは放置すると深刻な合併症を引き起こす可能性があるため、早期の発見が重要です。症状が漠然としていて原因がわからない場合でも、まずは内科で基本的な検査を受けることで、身体的な異常がないか確認できます。
内科は総合的な入り口として機能するため、初めて受診する際におすすめの診療科です。
睡眠外来:いびき・無呼吸の検査
強い眠気やいびき、睡眠中の呼吸停止を指摘されたことがある人は、睡眠外来を受診するのが適しています。睡眠外来では、ポリソムノグラフィーという精密検査を用いて、睡眠中の脳波や呼吸、心拍数、血中酸素濃度を測定します。
これにより、睡眠時無呼吸症候群や周期性四肢運動障害など、睡眠の質を低下させる病気の有無が明らかになります。睡眠障害は本人が自覚しにくく、生活習慣の工夫だけでは改善が難しいケースも多いため、専門的な検査が欠かせません。
特に「どれだけ寝ても疲れが取れない」「日中に強い眠気がある」という場合は、早めに睡眠外来を受診することで原因解明と治療につながります。
心療内科・精神科:ストレス・うつ病の可能性
寝ても疲れが取れない状態に加え、気分の落ち込みや無気力感、不安感が続く場合は、心療内科や精神科での受診を検討すべきです。ストレスやうつ病、不安障害といった心の病気は、睡眠障害と慢性的な疲労感を引き起こすことが多く、放置すると日常生活に深刻な影響を及ぼします。
心療内科・精神科では、問診や心理テストを通じて心の状態を丁寧に評価し、必要に応じて薬物療法や認知行動療法などを行います。
「ただの疲れ」と思っていても、実際には精神的な要因が大きいこともあるため、心のサインを軽視せず、早めに専門医に相談することが大切です。心療内科は身体と心の両面からアプローチできる点も特徴です。
婦人科:女性ホルモンの変化が関与する場合
特に女性の場合、更年期や月経周期に伴うホルモンバランスの変化が「寝ても疲れが取れない」原因になることがあります。
エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンは、自律神経や睡眠の質に深く関与しており、その分泌量が変動すると不眠や倦怠感、気分の落ち込みが現れやすくなります。
婦人科では、血液検査やホルモン検査を通じて女性ホルモンの状態を確認し、必要に応じてホルモン補充療法や漢方治療を行うことができます。
また、更年期以外でも、若い女性に多い鉄欠乏性貧血やPMS(月経前症候群)が疲労感の原因となることがあります。女性特有の体調変化を考慮するためにも、婦人科での相談は有効な手段です。
よくある質問(FAQ)

Q1. 休日に寝だめすれば疲れは取れる?
休日に長時間寝て「寝だめ」をしようとする人は多いですが、実際には根本的な疲労回復にはつながりにくいとされています。
体には体内時計があり、平日と休日で睡眠リズムが大きく乱れると、かえって自律神経のバランスを崩し、だるさや頭痛を引き起こす原因になります。
特に、昼まで寝てしまうと夜の寝つきが悪くなり、翌週の仕事や学業に影響する「社会的時差ぼけ」が生じます。疲れを取るには休日も平日と同じリズムで起き、軽い昼寝や休養で補うのが理想です。
寝だめではなく「睡眠の質」を高める工夫が、疲労感改善には効果的です。
Q2. 何時間寝ても疲れるのは病気のサイン?
毎日7〜8時間以上寝ているのに疲れが取れない場合、単なる生活習慣の乱れではなく、病気が隠れている可能性があります。代表的なものとして、睡眠時無呼吸症候群や自律神経失調症、うつ病、甲状腺機能低下症、慢性疲労症候群などが挙げられます。
これらの病気では、眠っても深い睡眠に入れない、ホルモンや自律神経の乱れで体が休まらないといった状態が続きます。
「しっかり寝ても疲れる」という症状が2週間以上続く場合は、放置せずに内科や心療内科を受診して原因を明らかにすることが重要です。
Q3. 睡眠時無呼吸症候群はどうやって分かる?
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が止まることで体に酸素不足が起こり、疲労が蓄積する病気です。本人は気づきにくいですが、家族から「いびきが大きい」「寝ているときに呼吸が止まっている」と指摘されるケースが多いです。
診断には、睡眠外来で行うポリソムノグラフィーという検査が有効で、睡眠中の脳波・心拍数・血中酸素濃度などを詳しく測定します。
日中の強い眠気や集中力低下、朝の頭痛も代表的な症状です。疑わしい場合は早めに専門外来を受診することで、CPAP療法などの適切な治療を受けることができます。
Q4. 自律神経失調症と慢性疲労の違いは?
自律神経失調症と慢性疲労症候群は、どちらも「寝ても疲れが取れない」状態を引き起こしますが、原因や特徴が異なります。
自律神経失調症は、ストレスや生活リズムの乱れによって交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、睡眠障害や倦怠感、めまい、動悸など多様な症状が出ます。
一方、慢性疲労症候群(ME/CFS)は原因不明の強い疲労が6か月以上続き、軽い運動でも症状が悪化するのが特徴です。
また、慢性疲労症候群では免疫や神経系の異常も関与していると考えられています。いずれも自己判断が難しいため、症状が長引く場合は医療機関での検査と診断が必要です。
Q5. 何科に相談すればよい?
疲れが長引く場合、まずは内科で全身の健康状態を確認するのが一般的です。血液検査やホルモン検査を通じて、生活習慣病や甲状腺疾患などをチェックできます。
いびきや強い日中の眠気があるなら睡眠外来、気分の落ち込みや不安感を伴うなら心療内科や精神科の受診が適しています。
女性の場合は更年期やPMSの影響も考えられるため、婦人科での相談も有効です。症状によって最適な診療科が異なるため、まずはかかりつけ医や内科で相談し、必要に応じて専門医を紹介してもらうのが安心です。
年代別の特徴を理解し、適切な対応を

「寝ても疲れが取れない」原因は年代によって異なり、10代では成長期の生活リズムや栄養不足、20代では社会人生活のストレス、30代では家庭と仕事の両立、40代では加齢やホルモンバランスの変化が大きく関与します。
生活習慣の改善やセルフケアで解消できる場合もありますが、病気が隠れている可能性もあるため油断は禁物です。
疲労感が長引く場合や日常生活に支障を感じる場合は、早めに医療機関を受診し原因を明らかにすることが重要です。
年代ごとの特徴を理解し、適切な対応を取ることで、健康的な生活と快適な毎日を取り戻すことができます。