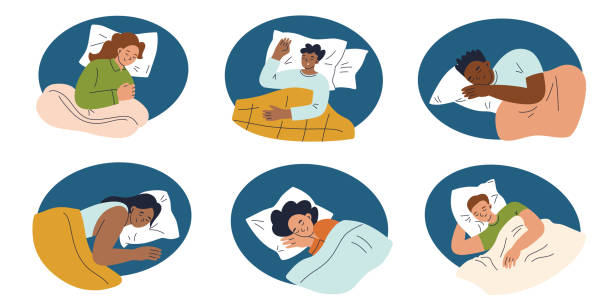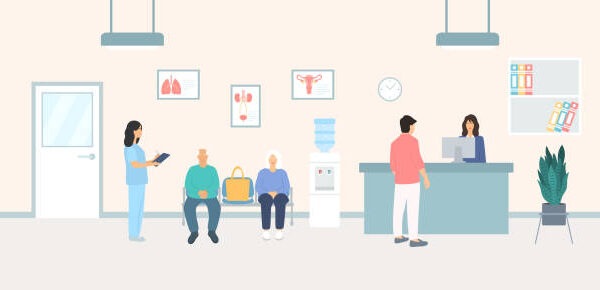「最近、前よりも寝る時間が長くなった」「いくら寝ても眠気が取れない」と感じていませんか?
睡眠時間が長くなるのは、一時的な疲労や生活習慣の乱れといった軽度の要因から、過眠症やうつ病、甲状腺の病気など深刻な疾患まで幅広い原因が考えられます。
特に、長時間睡眠が続く場合は、体質によるものなのか、それとも病気のサインなのかを早めに見極めることが重要です。
本記事では、睡眠時間が長くなる主な原因を「生活習慣」「病気」「年代別要因」など多角的に解説し、セルフチェック方法や改善法、受診の目安まで徹底的に紹介します。原因を正しく知ることで、安心して日常生活を取り戻す一歩につながるでしょう。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。
睡眠時間が長くなる原因とは?

「最近、睡眠時間が長くなった」と感じるとき、その背景にはさまざまな要因が隠れている可能性があります。単なる疲労や生活リズムの乱れだけでなく、ホルモンの変化や季節的要因、さらには病気や心の不調なども関係してきます。
睡眠は心身の健康を支える大切な要素ですが、必要以上に長くなってしまう場合は注意が必要です。ここでは、睡眠時間が長くなる代表的な原因を5つの視点から整理して解説します。まずは以下のリストをご覧ください。
- 一時的な疲労やストレス
- 生活習慣の乱れ(夜更かし・不規則な食事)
- ホルモンバランスの変化(女性・更年期・思春期)
- 季節の影響(冬の睡眠時間増加)
- 病気や心の不調によるもの
それぞれの詳細について確認していきます。
一時的な疲労やストレス
強い疲労や精神的なストレスを抱えると、体は自然と長時間の睡眠を必要とします。
たとえば、過度の仕事や学業による疲れ、強いプレッシャー、人間関係のトラブルなどが続くと、自律神経が乱れやすくなり、回復のために睡眠が長引く傾向があります。
これは「防御反応」ともいえ、体や心を休ませようとする自然な働きです。
多くの場合、一時的なもので、十分な休養やストレス発散によって改善します。ただし、2週間以上続く場合は過眠症やうつ病のサインである可能性があるため注意が必要です。
生活習慣の乱れ(夜更かし・不規則な食事)
夜更かしや朝昼逆転の生活、または不規則な食生活は、体内時計の乱れを引き起こします。
特にスマートフォンやPCのブルーライトを寝る直前まで浴びると、メラトニン分泌が抑制され、睡眠の質が低下し「長時間寝ても疲れが取れない」という状態につながります。
また、夜遅くに食事を取ると消化活動が続き、深い眠りが妨げられます。これらの不規則な習慣は結果的に長時間睡眠を招くことがあります。就寝前のスマホ利用を控え、規則正しい睡眠・食生活を整えることが改善の第一歩となります。
ホルモンバランスの変化(女性・更年期・思春期)
ホルモンバランスの変化も睡眠時間の増加に影響します。女性は月経周期に伴うホルモン変動や妊娠・産後、更年期にエストロゲンやプロゲステロンの変化が起こりやすく、その影響で眠気や過眠が現れることがあります。
思春期の子どもも、体内時計の後退やホルモンの急激な変化によって睡眠が長くなる傾向があります。
また更年期の女性は、ホルモンの減少により睡眠の質が下がり、疲労感から長く眠る必要が出てくることもあります。
こうした変化は自然な現象ですが、強い不調がある場合は婦人科や内科の受診も検討しましょう。
季節の影響(冬の睡眠時間増加)
季節による日照時間の変化も睡眠時間に大きく関わります。冬は日照時間が短く、太陽光を浴びる時間が減ることで体内時計が後ろにずれやすくなります。
また、光不足はセロトニンの分泌を減らし、眠気を強くするメラトニンの分泌を促進します。
その結果「冬になるとつい長く眠ってしまう」という現象が起こります。これは「季節性情動障害(ウィンターブルー)」とも関連し、抑うつ気分や倦怠感を伴うこともあります。
冬場には朝日を意識的に浴び、日中も屋外活動を増やすことで改善が期待できます。
病気や心の不調によるもの
睡眠時間が長くなる背景には、心身の病気が隠れている場合もあります。代表的なものは「うつ病」「過眠症」「甲状腺機能低下症」などで、これらは日中の強い眠気や倦怠感を伴うことが多いです。
また、睡眠時無呼吸症候群のように夜間の睡眠の質が低下しているため、結果的に長く眠らざるを得ないケースもあります。
心の不調としては、不安障害やストレス性疾患も関係します。
こうした場合は自己判断で放置せず、専門の医療機関で検査や診断を受けることが重要です。特に「いくら寝ても疲れが取れない」と感じるときは注意が必要です。
睡眠時間が長いと疑われる病気

「最近寝すぎてしまう」「いくら寝ても眠い」といった症状が続く場合、単なる生活習慣や疲労ではなく病気が隠れている可能性もあります。
長時間睡眠が慢性的に続く場合、心の病気や身体の不調が背景にあることが少なくありません。特に注意したい病気には以下のようなものがあります。
- 過眠症(ナルコレプシー・特発性過眠症)
- うつ病や適応障害
- 自律神経失調症
- 睡眠時無呼吸症候群
- 甲状腺機能低下症などの内科疾患
それぞれの詳細について確認していきます。
過眠症(ナルコレプシー・特発性過眠症)
過眠症は、日中に強い眠気が生じ、十分な睡眠を取っていても居眠りを繰り返してしまう病気です。特に「ナルコレプシー」では突然眠りに落ちる発作や、強い感情に伴う脱力(情動脱力発作)が特徴です。
一方「特発性過眠症」は原因不明ながら慢性的な眠気が続き、長時間の睡眠が必要になる傾向があります。
これらの病気は本人の意思ではコントロールできず、社会生活や学業・仕事に大きな支障を及ぼすため、早期の診断と治療が不可欠です。脳神経内科や睡眠外来での専門的な検査を受けることで適切な対応が可能になります。
うつ病や適応障害
うつ病や適応障害でも、過眠が症状のひとつとして現れることがあります。抑うつ気分や意欲低下だけでなく、エネルギー消耗から回復しようとするために長時間睡眠が必要になるケースが見られます。
特に「朝起きられない」「昼まで寝てしまう」などの症状は典型的です。精神的ストレスや生活環境の変化が引き金になることも多く、単なる疲労や怠けとは区別が必要です。
長引く気分の落ち込みや睡眠異常がある場合は、心療内科や精神科での受診を検討することが大切です。心理的な要因にアプローチする治療と生活環境の改善で、回復が期待できます。
自律神経失調症
自律神経失調症は、交感神経と副交感神経のバランスが乱れることで心身にさまざまな不調をきたす状態です。不眠や動悸と並んで「過眠」も症状のひとつに挙げられます。
自律神経がうまく切り替わらず、体が常に疲れた状態になってしまい、結果として睡眠時間が長くなるのです。
特にストレスの多い人や生活リズムが乱れがちな人に多く見られます。放置すると慢性的な疲労感や精神的な不調を悪化させるため、規則正しい生活やストレスマネジメントが重要です。
症状が強い場合は内科や心療内科での診察を受けることが勧められます。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群は、眠っている間に呼吸が繰り返し止まる病気で、深い睡眠が妨げられるため日中に強い眠気が出るのが特徴です。
本人は「長く寝ているのに疲れが取れない」と感じ、結果的に睡眠時間が長くなることもあります。いびきが大きい、夜間に何度も目が覚める、日中の強い眠気で集中力が落ちるといった症状が見られたら要注意です。
放置すると高血圧や心疾患のリスクも高まるため、専門外来での検査・治療が必要です。CPAP療法などの適切な治療で日中の眠気改善や生活の質向上が期待できます。
甲状腺機能低下症などの内科疾患
甲状腺機能低下症は、甲状腺ホルモンの分泌不足によって新陳代謝が低下し、強い倦怠感や過眠を引き起こす病気です。特に女性に多く、体重増加や冷え、むくみなども併発するのが特徴です。
ほかにも糖尿病、慢性疲労症候群、鉄欠乏性貧血などの内科的な疾患でも過眠が見られることがあります。
これらは生活習慣の乱れだけでは改善せず、血液検査や内科的治療が必要です。長引く眠気や体調不良がある場合は、内科を受診し、ホルモンや血液の状態をチェックすることが早期発見につながります。
睡眠時間が長いのは体質?それとも病気?

「睡眠時間が長いのは単なる体質なのか、それとも病気のサインなのか?」という疑問を持つ人は少なくありません。
実際に、人によって必要な睡眠時間は大きく異なり、健康的な範囲であれば「ロングスリーパー」と呼ばれる体質である可能性もあります。
しかし、日常生活に支障をきたすほど眠気が続く場合には病気の可能性も考えられます。ここでは、体質と病気の違いを見分けるためのポイントを整理します。
- ショートスリーパーとロングスリーパー
- 遺伝や体質による影響
- 体質か病気かを見分けるポイント
それぞれの詳細について確認していきます。
ショートスリーパーとロングスリーパー
人間の睡眠時間には大きな個人差があり、6時間未満でも日中の生活に問題がない「ショートスリーパー」、9時間以上寝ないと疲れが取れない「ロングスリーパー」が存在します。
ロングスリーパーは決して異常ではなく、単に必要とする睡眠時間が長いだけの体質です。
ただし、自分がロングスリーパーなのか病的な過眠なのかを判断するためには、日中の眠気の強さや生活への支障の有無を見極めることが大切です。
もし長時間睡眠にもかかわらず疲労感が取れず、集中力や気分に問題が出る場合は病気を疑う必要があります。
遺伝や体質による影響
睡眠時間の長さは遺伝的要因によってある程度決まっているといわれています。家族にロングスリーパーが多い場合、その体質を受け継いでいる可能性が高いのです。
また、性別や年齢によっても必要な睡眠時間は変わります。例えば思春期の若者は成長に伴い長めの睡眠が必要となり、高齢者は逆に短時間睡眠になる傾向があります。
このように、体質やライフステージによる違いは自然なものであり、健康上のリスクを必ずしも示すものではありません。ただし、長時間睡眠とともに強い倦怠感や気分の落ち込みがある場合は注意が必要です。
体質か病気かを見分けるポイント
「睡眠時間が長い=病気」とは限りませんが、いくつかのチェックポイントで判断が可能です。体質の場合は、長時間寝ても日中にすっきりと目覚め、活動に支障がありません。
一方で病気による過眠の場合、十分に寝ても疲労感が取れず、日中に強い眠気が生じたり、集中力の低下や気分の落ち込みが伴うことが多いのです。
また、睡眠中に呼吸が止まる、強いストレスや抑うつ気分がある、薬の副作用が疑われるなどの場合は、医療機関での検査が推奨されます。「寝すぎかも」と感じたら、体質か病気かを早めに見極めることが健康維持につながります。
年代別にみる睡眠時間が長くなる要因

睡眠時間が長くなる背景には、年齢による体の変化や置かれた環境が大きく関係しています。
成長期の学生や若年層は体の発達や学業のストレス、働き盛り世代は過労や社会的ストレス、高齢者は加齢に伴うホルモン変化や持病の影響など、それぞれの年代で睡眠に影響を与える要因が異なります。
ここでは年代別にその特徴を詳しく解説します。
- 学生・若年層(成長期・学業ストレス・生活リズムの乱れ)
- 働き盛り世代(過労・うつ症状・社会的ストレス)
- 高齢者(ホルモン分泌の変化・持病の影響)
それぞれの詳細について確認していきます。
学生・若年層(成長期・学業ストレス・生活リズムの乱れ)
学生や若年層は成長期にあたり、脳や体の発達のために多くの睡眠を必要とします。特に思春期ではホルモン分泌の影響で自然と夜型になりやすく、昼夜逆転や生活リズムの乱れが生じやすいのも特徴です。
また、受験や学業、人間関係のストレスにより疲労が蓄積し、長時間の睡眠を取らなければ回復できないケースもあります。
若い世代の過眠は必ずしも病気ではなく成長に伴う自然な現象である場合もありますが、日常生活に影響を与えるほど続く場合はストレスや心の不調を疑う必要があります。
働き盛り世代(過労・うつ症状・社会的ストレス)
20代後半から50代の働き盛り世代では、仕事や家庭の責任からくるストレスや過労が長時間の睡眠につながることがあります。慢性的な疲労が蓄積すると体が休養を強く求め、必要以上に眠ってしまうことがあります。
また、この年代ではうつ病や適応障害などのメンタルヘルスの問題も比較的多く、気分の落ち込みや意欲低下とともに過眠が症状として現れることがあります。
さらに、夜遅くまでの残業や不規則な生活習慣、飲酒・カフェイン摂取なども睡眠の質を低下させ、結果的に長時間の睡眠を必要とする要因となります。
高齢者(ホルモン分泌の変化・持病の影響)
高齢者は加齢によって睡眠リズムが変化し、夜間の睡眠が浅くなったり中途覚醒が増える傾向があります。その一方で、昼間に強い眠気を感じやすくなり、トータルの睡眠時間が長くなることがあります。
さらに、メラトニンなど睡眠に関わるホルモンの分泌が減少することも影響します。また、高齢になると糖尿病や心疾患、慢性痛などの持病が睡眠の質を下げ、体力回復のために長時間の睡眠を必要とする場合もあります。
長い睡眠は単なる加齢現象であることも多いですが、過度に日中活動が制限される場合は医師の診察を受けることが大切です。
睡眠時間が長くなったときのセルフチェック

睡眠時間が急に長くなった場合、その背景には一時的な疲労やストレス、体質的な要因、あるいは病気が隠れている可能性があります。
自分の状態を把握するためには、睡眠の質や日中のパフォーマンス、気分の変化などを総合的に確認することが大切です。ここでは、過眠傾向があるときにチェックすべきポイントを整理しました。
- 睡眠の質(熟睡できているか)
- 日中の眠気や集中力低下
- 気分の落ち込みや不安の有無
- 睡眠時間の変化が続く期間
- 睡眠記録(日誌やアプリ)の活用
それぞれの詳細について確認していきます。
睡眠の質(熟睡できているか)
長時間眠っていても「ぐっすり眠れた」と感じられない場合、睡眠の質が低下している可能性があります。
例えば、夜中に何度も目が覚める、夢を頻繁に見る、朝起きたときに疲労感が残るといった症状は、深い睡眠が十分に取れていないサインです。
単純に睡眠時間が長いのではなく、質の低下を補うために体が長く眠ろうとしているケースもあります。睡眠の長さだけでなく、起床後のすっきり感も重要な指標となります。
日中の眠気や集中力低下
過眠のサインとして最もわかりやすいのが、日中の強い眠気や集中力の低下です。
仕事や学業中に眠気が強く、パフォーマンスに支障が出ている場合、単なる寝不足ではなく睡眠障害の可能性があります。
特に、夜しっかり眠っているにもかかわらず日中に眠くなる場合は「過眠症」や「睡眠時無呼吸症候群」などを疑うべきです。眠気の程度や生活への影響を日々観察することが重要です。
気分の落ち込みや不安の有無
長時間の睡眠に加えて、気分の落ち込みや不安感が強くなる場合は、うつ病や適応障害などの精神的要因が関わっている可能性があります。
過眠はうつ症状の一つとして現れることがあり、特に朝起きられない、無気力で一日中横になっているといった状態が続く場合は要注意です。
気分の変化を見逃さず、心の健康と睡眠の関係を意識してセルフチェックを行うことが大切です。
睡眠時間の変化が続く期間
睡眠時間が長くなる現象が一時的なものか、それとも数週間以上続いているかを確認することも重要です。
季節の変化や一時的な疲労であれば数日から1週間程度で改善することが多いですが、2週間以上同じ状態が続く場合は病気の可能性を考えるべきです。
慢性的な過眠は心身に悪影響を及ぼすため、期間を見極めることが早期発見につながります。
睡眠記録(日誌やアプリ)の活用
客観的に自分の睡眠を把握するには、睡眠日誌やスマホアプリを活用するのがおすすめです。
就寝・起床時間、夜中の覚醒回数、日中の眠気などを記録することで、自分では気づかないパターンが見えてきます。
また、医師に相談する際にも具体的な記録があると診断の助けになります。過眠の原因を探るためには、主観的な感覚だけでなくデータの蓄積も役立ちます。
睡眠時間が長いことのデメリット・リスク

「よく眠れるのは健康的」と思われがちですが、必要以上に長く眠ることは必ずしも良いことではありません。特に7〜9時間を超える長時間睡眠が慢性的に続くと、身体や心に様々な悪影響を及ぼすことが研究で明らかになっています。
ここでは、長時間の睡眠による具体的なリスクについて詳しく解説します。
- 生活習慣病(糖尿病・肥満)のリスク
- 心の健康への悪影響(抑うつ・不安の増加)
- 社会生活・仕事・学業への影響
- 睡眠時間と寿命の関係
それぞれの詳細について確認していきます。
生活習慣病(糖尿病・肥満)のリスク
睡眠時間が長すぎる人は、糖尿病や肥満といった生活習慣病のリスクが高まることが複数の研究で報告されています。
長時間の睡眠は、体内時計やホルモンバランスを乱し、インスリンの働きを低下させることが原因と考えられています。
また活動時間が減ることで消費カロリーが低下し、肥満を招きやすくなります。単に「たくさん眠れるから安心」と考えるのではなく、過度の睡眠が健康リスクを高める点を意識することが大切です。
心の健康への悪影響(抑うつ・不安の増加)
長時間の睡眠は、うつ病や不安障害といったメンタルヘルス不調と強く関連しています。
実際に、過眠はうつ病の典型的な症状のひとつとして現れることがあります。
さらに、長く眠ることで日中の活動が減り、達成感や社会的つながりが失われると、気分の落ち込みや不安感が悪化する悪循環に陥りやすくなります。
睡眠時間が長いのに気分がすっきりしない場合は、心の健康を見直す必要があります。
社会生活・仕事・学業への影響
過度に長い睡眠は、社会生活や仕事・学業のパフォーマンス低下につながります。
例えば、朝起きられず遅刻が増える、集中力や記憶力が低下するなど、生活全般に悪影響を及ぼします。さらに、周囲から「怠けている」と誤解されやすく、対人関係にも支障をきたす場合があります。
睡眠は休養のために必要ですが、過剰になれば逆に社会的機能を損なうリスクがあるため注意が必要です。
睡眠時間と寿命の関係
最新の疫学研究では、睡眠時間が極端に短い人と同様に、極端に長い人も死亡リスクが高いことが報告されています。
特に1日10時間以上の睡眠を続けている人は、心血管疾患や脳卒中などのリスクが増加し、寿命が短くなる傾向があるとされています。
つまり「寝すぎ」も「寝不足」と同様に健康に悪影響を及ぼす可能性があるのです。健康寿命を延ばすためには、自分に合った適切な睡眠時間を意識することが大切です。
睡眠時間が長くなるときの改善法

「最近、睡眠時間が長すぎる」と感じたときは、放置せず生活習慣や環境を整えることが大切です。
長時間睡眠の背景には一時的な疲労から病気まで様々な要因がありますが、まずはセルフケアで改善を目指すことができます。ここでは、具体的な改善方法を紹介します。
- 規則正しい生活リズムの確立
- 適度な運動とストレス解消法
- 食生活の見直し(栄養バランス・カフェイン摂取)
- 光と環境の調整(朝日を浴びる・寝室環境)
- 睡眠記録をとって変化を把握
それぞれの詳細について確認していきます。
規則正しい生活リズムの確立
体内時計の乱れは睡眠時間の延長や質の低下を招きます。毎日同じ時間に起床・就寝することで、体内時計が安定し自然な眠りが得られるようになります。
特に朝の起床時間を一定にすることが重要で、休日でも大きくずらさないのがポイントです。
また、寝る前のスマホやPC使用は交感神経を刺激して眠りを妨げるため、リラックスできる習慣を取り入れることが改善に繋がります。
適度な運動とストレス解消法
日中に適度な運動を取り入れることは、睡眠の質を高めるだけでなく、ストレス軽減にも効果的です。
ウォーキングやストレッチなど無理のない運動を継続することで、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が促され、入眠しやすくなります。
また、趣味やリラクゼーションを取り入れることで心身の緊張がほぐれ、長時間の睡眠に頼らずとも疲れを解消できるようになります。
食生活の見直し(栄養バランス・カフェイン摂取)
栄養バランスの乱れや過剰なカフェイン摂取は、睡眠の質を悪化させる原因となります。
朝食をしっかり摂ることで体内時計がリセットされ、適切な睡眠サイクルを維持できます。
夕食は寝る2〜3時間前に済ませ、消化に良い食事を心がけることが大切です。また、カフェインやアルコールは眠りの質を下げるため、午後以降は控えるとより快眠につながります。
光と環境の調整(朝日を浴びる・寝室環境)
人間の体内時計は光によって調整されるため、朝起きたらカーテンを開けて自然光を浴びることが効果的です。
特に朝日を浴びることでセロトニンが活性化し、夜の眠りを促すメラトニンの分泌もスムーズになります。
また、寝室環境も重要で、温度・湿度・照明・寝具を快適に整えることで、長時間寝なくても深い眠りを得られるようになります。
睡眠記録をとって変化を把握
自分の睡眠の状態を客観的に把握するために、日誌やアプリを使って睡眠記録をつけることをおすすめします。
寝た時間・起きた時間・睡眠の質・日中の体調を記録することで、生活習慣や体調の変化との関係が見えやすくなります。
もし長時間睡眠が続き、体調不良や気分の落ち込みが伴う場合は、記録を持参して医師に相談すると診断・治療に役立ちます。
医療機関を受診すべきサイン

「最近よく眠るようになったけど大丈夫かな?」と感じたとき、単なる疲れや生活習慣の乱れであれば自然に改善することもあります。
しかし、睡眠時間の長さが長期的に続いたり、心身に深刻な影響を及ぼしている場合には、医療機関の受診が必要です。以下では、受診を検討すべきサインを具体的に紹介します。
- 2週間以上「眠りすぎ」が続く
- 強い倦怠感や気分の落ち込みを伴う
- 日常生活に支障が出ている
- 睡眠時無呼吸の疑いがある
それぞれの詳細について確認していきます。
2週間以上「眠りすぎ」が続く
一時的な疲労やストレスで睡眠時間が増えるのは自然な反応ですが、2週間以上も長時間の睡眠が続く場合は注意が必要です。
特に、生活リズムを整えても改善しないときは、過眠症やうつ病などの病気が隠れている可能性があります。
睡眠が長引くことで社会生活や仕事、学業に支障をきたす前に、早めに専門医へ相談することが望まれます。
強い倦怠感や気分の落ち込みを伴う
睡眠時間が長いにもかかわらず疲労感が取れなかったり、気分の落ち込みや不安感が強くなる場合、うつ病や自律神経失調症が背景にあることがあります。
単なる「寝すぎ」ではなく、心身からのSOSサインであることも少なくありません。
こうした症状が続く場合には心療内科や精神科での受診を検討しましょう。
日常生活に支障が出ている
長時間睡眠によって朝起きられない、仕事や学校に遅刻してしまう、集中力が低下してミスが増えるといった状況が続く場合は、医療的なサポートが必要です。
生活の質が著しく低下していると、さらにストレスが増え、症状を悪化させる悪循環に陥ることもあります。
生活のリズムが整えられないほどの影響がある場合は、専門的な治療を受けるべきサインです。
睡眠時無呼吸の疑いがある
「いびきが大きい」「呼吸が止まっていると指摘された」「日中の強い眠気がある」といった症状がある場合、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。
この病気は放置すると高血圧や心疾患など深刻な合併症を引き起こす危険性があるため、早期の診断と治療が欠かせません。
特に肥満傾向のある方はリスクが高く、医療機関での検査を受けることをおすすめします。
睡眠改善に役立つサポート・治療法

睡眠時間が長くなりすぎる背景には、心身の不調や生活リズムの乱れ、さらには病気が隠れていることがあります。
そのため、改善には専門的なサポートや適切な治療法を取り入れることが重要です。
以下では、薬物療法から心理的アプローチ、行政や地域の支援、そして家族の理解まで、睡眠改善に役立つ方法を紹介します。
- 薬物療法(抗うつ薬・睡眠薬・内科治療)
- 認知行動療法(睡眠衛生指導)
- 行政や地域の健康相談窓口
- 家族・周囲の理解とサポート
それぞれの詳細について確認していきます。
薬物療法(抗うつ薬・睡眠薬・内科治療)
睡眠の異常がうつ病や不安障害、自律神経の乱れなどによる場合、医師の判断で薬物療法が行われます。
抗うつ薬や抗不安薬は気分の落ち込みや不安を和らげ、結果的に睡眠リズムを安定させる効果があります。また、必要に応じて短期間の睡眠薬が処方されることもあります。
さらに、甲状腺機能低下症や睡眠時無呼吸症候群など内科的な疾患が原因の場合は、その治療を行うことが睡眠改善につながります。
認知行動療法(睡眠衛生指導)
睡眠改善の有効な手段のひとつに認知行動療法があります。
これは、不眠や過眠に影響を与える思考や生活習慣を見直し、より健全な睡眠習慣を身につける方法です。
具体的には「就寝前のスマホ使用を控える」「毎朝同じ時間に起床する」「寝室の環境を快適に整える」など、日常生活の行動パターンを改善することが含まれます。薬に頼らずに根本的な改善を目指す点が特徴です。
行政や地域の健康相談窓口
市区町村の保健センターや地域の健康相談窓口では、睡眠や心身の不調に関する無料相談を受け付けています。
専門の保健師や心理士が対応し、必要に応じて医療機関や支援サービスにつなげてくれることもあります。
また、睡眠に関する講座や健康イベントを開催している自治体もあり、気軽に利用できるサポートのひとつです。医療機関に行く前の初期相談先としても活用できます。
家族・周囲の理解とサポート
睡眠の問題は本人だけでなく、家族や周囲の協力によって改善が早まることがあります。
例えば「無理に起こそうとしない」「生活リズムを一緒に整える」「話を傾聴する」などのサポートが有効です。
睡眠異常は「怠け」や「気の持ちよう」ではなく、心身からのサインであることを理解してもらうことが大切です。家族やパートナーの支えがあることで安心感が生まれ、治療やセルフケアにも前向きに取り組みやすくなります。
よくある質問(FAQ)

Q1. 睡眠時間が長いのは病気ですか?
必ずしも病気とは限りません。成長期や過労後など一時的に睡眠時間が長くなることは自然な反応です。
しかし、2週間以上続いたり、強い倦怠感や気分の落ち込み、日常生活への支障がある場合は病気が隠れている可能性があります。
過眠症、うつ病、自律神経失調症、睡眠時無呼吸症候群などの可能性もあるため、長引く場合は早めの受診が安心です。
Q2. どのくらい寝たら「寝すぎ」と言えますか?
一般的に成人の推奨睡眠時間は7〜9時間です。10時間以上の睡眠が連日続き、しかも疲れが取れない・日中も眠いと感じる場合は「寝すぎ」と考えられます。
ただし、個人差があるため一概には言えません。
ロングスリーパー体質の人も存在するため、睡眠が生活に悪影響を与えているかどうかが判断の基準となります。
Q3. 睡眠時間が長いと寿命が縮むって本当?
複数の研究で「長時間睡眠と寿命の短縮の関連」が報告されています。特に、1日10時間以上の睡眠を続ける人は生活習慣病や心疾患のリスクが高まる傾向があるとされています。
ただしこれは「長時間睡眠そのもの」が原因というよりも、「病気が隠れていて結果的に長時間睡眠になる」ケースが多いと考えられます。
そのため、長い睡眠が続くときは健康状態の確認が重要です。
Q4. 市販のサプリや睡眠改善薬は効果がある?
メラトニンやグリシン、トリプトファンなどのサプリは睡眠リズムや眠りの質を整えるサポートになる場合があります。
ただし「長時間眠りすぎ」の改善に直接的な効果があるとは限りません。また、市販の睡眠改善薬は一時的な不眠に使えることもありますが、長期的に乱用すると逆効果になる場合もあります。
根本原因を改善するためには医師の診断を受けることが望ましいです。
Q5. 何科に相談すればよいですか?
まずは内科で全身の健康チェックを受けるのがおすすめです。甲状腺機能低下症や糖尿病など内科的な病気が隠れていることもあるからです。
精神的な症状(気分の落ち込み、不安)が強い場合は心療内科や精神科、睡眠そのものに問題があると考えられる場合は睡眠外来を受診すると良いでしょう。
迷ったらまずかかりつけ医に相談し、必要に応じて専門医を紹介してもらうのが安心です。
睡眠時間が長くなったら原因を見極めて早めに対応を

睡眠時間が長くなるのは、一時的な疲労や生活習慣の乱れから起こることもあれば、病気のサインである場合もあります。
10時間以上眠っても疲れが取れない、日中も強い眠気がある、気分の落ち込みを伴うなどの症状が続く場合は注意が必要です。
セルフチェックや生活改善を試みつつ、症状が長引くときは早めに医療機関へ相談しましょう。
原因を見極めて適切に対応することで、健康的な睡眠リズムを取り戻し、心身のバランスを保つことができます。