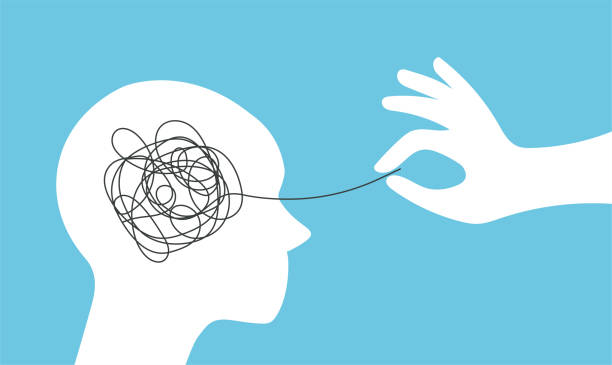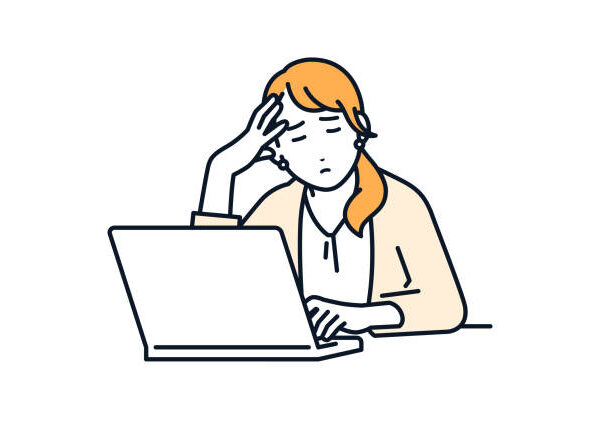「双極性障害は寿命が短い」「突然死のリスクがある」と聞くと、大きな不安を感じる方も少なくありません。
実際に、双極性障害のある人は一般人口と比べて寿命が短いとされ、その背景には自殺リスクの高さや心血管疾患・糖尿病などの合併症、さらに服薬の中断や生活習慣の乱れといった要因が複雑に関わっています。
しかし、これは必ずしも避けられない運命ではなく、適切な治療や生活習慣の工夫によってリスクを減らすことが可能です。
この記事では、双極性障害と寿命が短いと言われる理由や突然死の背景、そして寿命を延ばすために実践できる予防とケアについて詳しく解説します。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。
双極性障害で突然死のリスクが高い理由

双極性障害は、気分の波が大きいだけの病気ではなく、寿命や健康リスクにも深く関わる疾患です。
特に突然死のリスクが高いとされ、その背景には複数の要因が複雑に影響しています。
ここでは「自殺リスクの高さ」「心血管疾患・代謝異常との関係」「薬の副作用や生活習慣の影響」という3つの観点から解説します。
- 自殺リスクの高さ
- 心血管疾患・代謝異常との関係
- 薬の副作用や生活習慣の影響
これらを理解することは、予防やケアの第一歩となります。
自殺リスクの高さ
双極性障害と自殺リスクは切っても切れない関係があります。
うつ状態のときに強い絶望感や無力感を抱くことで、自殺念慮が高まりやすくなります。
さらに、躁状態では衝動性が強まるため、突発的な行動により危険な選択をしてしまうこともあります。
実際に、双極性障害の患者は一般人口に比べて自殺率が数十倍高いとされ、突然死の大きな要因となっています。
このリスクを減らすためには、早期に治療を開始し、周囲がサポート体制を整えることが欠かせません。
心血管疾患・代謝異常との関係
心血管疾患や代謝異常は、双極性障害の患者に多く見られる健康リスクです。
双極性障害では生活リズムの乱れや薬の影響により、肥満・糖尿病・高血圧・高脂血症などが起こりやすいことが報告されています。
これらは心筋梗塞や脳卒中などの重大な病気につながり、突然死のリスクを高める要因となります。
また、慢性的なストレスや睡眠障害も心血管系に負担をかけ、命に関わる合併症の発症リスクを上げます。
定期的な健康診断や生活習慣の改善は、突然死を予防するために非常に重要です。
薬の副作用や生活習慣の影響
薬の副作用や生活習慣も突然死リスクを高める要因として見逃せません。
双極性障害の治療で用いられる気分安定薬や抗精神病薬の中には、体重増加や代謝異常を引き起こすものがあります。
また、過度な飲酒や喫煙、不規則な生活は心血管リスクを増加させる要因です。
薬の効果を最大限に生かすためには、主治医と相談しながら副作用を管理し、生活習慣を整える必要があります。
薬物療法と健康的な生活の両立こそが、突然死を防ぐ大きな鍵となります。
双極性障害の寿命が短いと言われる原因

双極性障害は、気分の波に伴う精神的な苦しみだけでなく、寿命の短縮とも関係があると指摘されています。
研究によれば、双極性障害の方の平均寿命は一般人口よりも短い傾向が見られ、その背景には複数のリスク要因が存在します。
ここでは「自殺や事故死」「合併症」「治療中断や服薬不遵守」「社会的孤立や生活リズムの乱れ」といった代表的な原因を解説します。
- 自殺や事故死のリスク
- 合併症(糖尿病・高血圧・肥満など)による寿命短縮
- 治療中断や服薬不遵守の影響
- 社会的孤立や生活リズムの乱れ
これらの要因を理解することは、寿命を延ばすための予防と対策を考える上で重要です。
自殺や事故死のリスク
双極性障害と自殺リスクの高さは、多くの研究で明らかになっています。
うつ状態では深い絶望感から自殺を考えやすく、躁状態では衝動性の高まりによって危険な行動に走ってしまうことがあります。
また、不眠や極端な気分の変化が集中力を低下させ、事故や不注意による死亡リスクも高めます。
これらは寿命を短くする大きな要因のひとつであり、早期の治療介入や周囲のサポートが不可欠です。
「気分の波は仕方ない」と放置せず、命に関わるリスクとして捉えることが大切です。
合併症(糖尿病・高血圧・肥満など)による寿命短縮
生活習慣病の合併症は、双極性障害の患者に多く見られる寿命短縮の要因です。
薬の副作用や生活リズムの乱れにより、肥満・糖尿病・高血圧・高脂血症などを併発しやすくなります。
これらは心筋梗塞や脳卒中といった致命的な病気につながり、突然死のリスクを高めます。
精神疾患と身体疾患が重なることで治療が難しくなり、全体的な健康状態を悪化させることも問題です。
定期的な健康診断や生活習慣の見直しが、寿命を守るために不可欠です。
治療中断や服薬不遵守の影響
治療中断や服薬不遵守は、双極性障害の寿命を縮める大きなリスクです。
症状が安定したからといって薬を自己判断で中止すると、再発や症状の悪化を招きやすくなります。
また、治療を継続しないことでうつ状態や躁状態が繰り返され、自殺や事故のリスクも高まります。
さらに、治療を中断すると合併症の管理が不十分になり、身体的リスクも増加します。
主治医と相談しながら服薬を継続することが、寿命を延ばすために最も重要な要素のひとつです。
社会的孤立や生活リズムの乱れ
社会的孤立や生活リズムの乱れも寿命短縮の大きな要因です。
双極性障害の症状が周囲に理解されにくいため、人間関係や職場・学業で孤立するケースが少なくありません。
孤立は精神的なストレスを増大させ、自殺リスクを高めるとともに、生活習慣の乱れにもつながります。
不規則な睡眠や食生活、運動不足は合併症のリスクを増加させ、健康寿命を短くする要因となります。
社会的なつながりを維持し、規則正しい生活を意識することが長生きにつながる重要なポイントです。
双極性障害と身体の健康リスク

双極性障害は精神的な病気として知られていますが、実は身体の健康にも大きな影響を与えることが研究で明らかになっています。
気分の波に伴う生活リズムの乱れや薬の副作用、さらにはストレスが、心臓病や生活習慣病などのリスクを高める要因となります。
ここでは「心臓病や脳卒中との関連」「生活習慣病の影響」「喫煙や飲酒など不健康な習慣との関係」について詳しく解説します。
- 心臓病や脳卒中との関連
- 生活習慣病(糖尿病・高血圧・脂質異常症)の影響
- 喫煙・飲酒など不健康な習慣との関係
身体の健康リスクを理解することで、突然死や寿命短縮の予防につなげることができます。
心臓病や脳卒中との関連
双極性障害と心臓病・脳卒中の関連性は、医学的にも注目されています。
双極性障害の方は不眠やストレス負荷が多く、自律神経が乱れやすいため血圧や心拍が不安定になりやすいといわれています。
また、薬の副作用によって体重増加や代謝異常が起こり、それが動脈硬化を進める原因になることもあります。
こうした背景から、心筋梗塞や脳卒中など命に関わる疾患の発症率が高くなり、突然死のリスクが上がるのです。
定期的な心電図検査や血圧測定を受けることは、予防と早期発見のために欠かせません。
生活習慣病(糖尿病・高血圧・脂質異常症)の影響
生活習慣病は、双極性障害と深い関わりがあります。
薬物療法で使われる気分安定薬や抗精神病薬の中には、体重増加や血糖値・脂質の異常を引き起こすものがあり、糖尿病や高血圧、脂質異常症のリスクを高めます。
さらに、生活リズムの乱れや運動不足、不規則な食習慣も加わることで、生活習慣病は進行しやすくなります。
これらの疾患は動脈硬化や心疾患につながり、寿命を縮める大きな要因となります。
食事の見直しや適度な運動、そして定期的な血液検査を続けることが、健康を維持するカギとなります。
喫煙・飲酒など不健康な習慣との関係
喫煙や飲酒といった習慣も、双極性障害の寿命に影響を与える重要な要素です。
ストレスや気分の落ち込みから喫煙や過度な飲酒に頼ってしまう人も少なくありませんが、これらは心血管疾患や肝疾患、がんのリスクを大幅に高めます。
また、アルコールは薬の効果を弱めたり副作用を強める場合があり、症状悪化や治療中断の原因となることもあります。
喫煙も動脈硬化や血管障害を進めるため、突然死のリスクをさらに押し上げます。
生活習慣を見直し、禁煙や節酒を心がけることは、双極性障害と長く向き合う上で非常に重要なステップです。
突然死を防ぐためにできること

双極性障害では、自殺や心疾患、合併症などが原因で突然死のリスクが高いといわれています。
しかし、日常生活や治療の工夫によって、そのリスクを減らすことは十分に可能です。
ここでは「睡眠・食事・運動のバランス」「定期的な健康診断」「主治医との継続的なコミュニケーション」「家族や周囲の理解」という4つの観点から、具体的な予防策を解説します。
- 睡眠・食事・運動のバランスを保つ
- 定期的な健康診断でリスクを把握する
- 主治医との継続的なコミュニケーション
- 家族や周囲にリスクを理解してもらう
日常の小さな積み重ねが、命を守る大きな力になります。
睡眠・食事・運動のバランスを保つ
生活習慣の安定は、突然死のリスクを減らす基本です。
双極性障害の方は気分の波によって生活リズムが乱れやすく、不眠や過眠が心臓や脳に負担をかけます。
また、食生活の乱れは肥満や糖尿病、高血圧を招き、心血管疾患のリスクを高めます。
適度な運動は血流を改善し、ストレス解消にもつながるため欠かせません。
規則正しい睡眠、栄養バランスの取れた食事、無理のない運動習慣を意識することが、突然死予防の第一歩です。
定期的な健康診断でリスクを把握する
定期的な健康診断は、命に関わるリスクを早期に発見するために欠かせません。
双極性障害では、薬の副作用や生活習慣の乱れから糖尿病や高血圧、脂質異常症などを発症しやすくなります。
これらは心筋梗塞や脳卒中につながる重大な病気であり、突然死の引き金になりかねません。
血液検査や心電図検査を定期的に受けることで、問題を早めに把握し、適切な対処が可能になります。
「体調に問題がないから受けなくてもいい」ではなく、予防のために診断を継続する姿勢が大切です。
主治医との継続的なコミュニケーション
主治医との信頼関係は、突然死を防ぐうえで非常に重要です。
薬の副作用や体調の変化を正直に伝えることで、より安全で効果的な治療を受けることができます。
また、「調子が良いから薬をやめたい」と自己判断することは危険で、再発や健康リスクの増加につながります。
定期的に通院し、治療方針や生活習慣について相談することで、安心して長期的に病気と向き合えます。
継続的なコミュニケーションこそが、寿命を延ばすための大切な鍵です。
家族や周囲にリスクを理解してもらう
家族や周囲の理解も、突然死を防ぐ大きな支えになります。
本人が体調の変化に気づきにくいときでも、身近な人が早期に異変を察知できる場合があります。
特に強い気分の波や体調の不調が見られるときに、家族が適切にサポートできる体制を整えておくことが大切です。
また、リスクを共有することで本人が安心して生活でき、孤立を防ぐ効果もあります。
周囲の理解と支援は、病気と長く付き合ううえで欠かせない要素です。
予防と寿命を延ばすためのセルフケア

双極性障害では、突然死や寿命の短縮リスクがあるとされていますが、適切なセルフケアを実践することでそのリスクを大幅に減らすことが可能です。
セルフケアの中心となるのは「薬物療法の継続」「ストレスマネジメント」「サポート体制の活用」の3つです。
これらを日常生活に取り入れることで、再発を防ぎながら心身の健康を守り、安心して長く生活することができます。
- 薬物療法の継続と副作用管理
- ストレスマネジメントと心理療法
- サポートグループや相談機関の活用
ここからは、それぞれのセルフケアの具体的な方法を詳しく解説します。
薬物療法の継続と副作用管理
薬物療法は、双極性障害の治療における最も重要な柱です。
気分安定薬や抗精神病薬は再発を防ぎ、気分の波を安定させる効果があります。
しかし、副作用として体重増加や代謝異常などが起こる場合があるため、医師と相談しながら定期的に血液検査や体調チェックを行うことが欠かせません。
症状が安定しても自己判断で服薬を中断するのは非常に危険で、再発や寿命短縮のリスクにつながります。
薬を正しく服用し、副作用を管理することが、長期的な健康維持に直結します。
ストレスマネジメントと心理療法
ストレスマネジメントは、双極性障害と長く付き合ううえで欠かせないセルフケアです。
深呼吸や瞑想、マインドフルネスを取り入れることで、不安や緊張を和らげる効果があります。
また、心理療法(認知行動療法や心理教育)は、病気の理解を深め、自分の感情や行動をコントロールする力を高めてくれます。
ストレスを放置すると気分の波を悪化させ、再発や身体的リスクにつながるため、日常的なケアが重要です。
小さな工夫を積み重ね、心の安定を保つ習慣を育てることが、寿命を延ばす大きな支えになります。
サポートグループや相談機関の活用
サポートグループや相談機関を活用することは、孤立を防ぎ、再発や突然死リスクを減らすために効果的です。
同じ経験を持つ仲間と気持ちを共有することで安心感が得られ、「自分だけではない」という実感が心の支えになります。
また、家族会や地域の相談窓口、カウンセリングサービスなどを利用することで、専門的なアドバイスやサポートを受けることができます。
社会的なつながりを持ち続けることは、病気の長期的な安定に直結し、寿命を延ばすためにも重要です。
一人で抱え込まず、積極的に支援を利用する姿勢が回復と予防の大きな力となります。
双極性障害と長期的な生活設計

双極性障害は慢性的に経過することが多いため、短期的な治療だけでなく、長期的な生活設計を考えることが大切です。
再発を予防しながら社会生活を維持し、安心できる環境で生活するためには、セルフモニタリングや支援制度、そして家族の理解と協力が不可欠です。
ここでは「再発予防のためのセルフモニタリング」「社会復帰・就労に向けた支援制度の活用」「家族とともに歩む生活設計」の3つの視点から解説します。
- 再発予防のためのセルフモニタリング
- 社会復帰・就労に向けた支援制度の活用
- 家族とともに歩む生活設計
長期的な視点を持つことで、病気に左右されない安定した人生を築きやすくなります。
再発予防のためのセルフモニタリング
セルフモニタリングとは、自分の気分や体調の変化を継続的に観察・記録することです。
双極性障害では、再発の兆候が小さなサインとして現れることが多いため、日記やアプリを使って気分の浮き沈みを記録することが効果的です。
「睡眠時間が短くなっている」「気分が落ち込みやすい」などの変化に早めに気づくことで、主治医と相談しながら迅速に対応できます。
このセルフモニタリングを習慣化することが、再発を防ぎ、長期的に安定した生活を続けるための基盤となります。
無理のない範囲で日常に取り入れることが大切です。
社会復帰・就労に向けた支援制度の活用
社会復帰や就労支援制度を活用することは、双極性障害と共に生きるうえで大きな助けになります。
日本には障害者雇用制度や就労移行支援事業、地域の就労支援センターなど、多様な支援機関があります。
また、職場復帰に向けたリワークプログラムを利用することで、段階的に働く力を取り戻すことも可能です。
就労に関して不安がある場合でも、制度を活用することで安心して社会参加でき、経済的にも安定を得られます。
支援制度を積極的に活用し、自分に合った働き方を見つけることが重要です。
家族とともに歩む生活設計
家族の理解と協力は、双極性障害と長く付き合ううえで欠かせない要素です。
家族が病気の特徴や再発リスクを理解していることで、異変に気づきやすくなり、早めの対応が可能になります。
また、本人が孤立せず安心して生活するための心理的支えにもなります。
生活設計を立てる際には、治療計画だけでなく、家庭内での役割分担や将来の目標について話し合うことも大切です。
「家族と共に歩む」という姿勢が、安定した生活と長期的な安心につながります。
よくある質問(FAQ)

双極性障害と寿命・突然死のリスクについて、多くの方が抱く不安や疑問にお答えします。
正しい情報を知ることで過度な心配を和らげ、前向きに病気と向き合うための助けになります。
Q1. 双極性障害の平均寿命はどのくらい短いのですか?
双極性障害の平均寿命は、一般人口よりも10〜20年短いとする報告があります。
その理由としては、自殺リスクの高さ、生活習慣病や心疾患の合併、薬の副作用による身体リスクが挙げられます。
ただし、これはあくまで統計的なデータであり、全員に当てはまるわけではありません。
適切な治療を続け、生活習慣を整えることで寿命を延ばし、健康に生活することは十分可能です。
数字にとらわれず、予防とケアを重ねることが大切です。
Q2. 突然死はどんな状況で起こりやすいですか?
突然死は、自殺や心疾患、脳血管疾患に関連して起こりやすいとされています。
特に気分の急激な変化により睡眠が極端に減ったり、躁状態で無理を重ねたりすることで心臓や脳に負担がかかります。
また、糖尿病や高血圧などの合併症がある場合は、その影響で心筋梗塞や脳卒中を発症することもあります。
突然死のリスクを減らすためには、定期的な健康診断と治療継続、そして生活習慣の安定が不可欠です。
「無理をしない」ことが最も大切な予防になります。
Q3. 薬の副作用で寿命が縮むことはありますか?
薬の副作用が直接寿命を縮めるわけではありませんが、間接的に健康に影響を与えることはあります。
気分安定薬や抗精神病薬の中には、体重増加や糖代謝異常、脂質異常を引き起こすものがあり、これが心疾患や生活習慣病のリスクを高めます。
しかし、服薬をやめてしまうと再発や自殺リスクが上がるため、治療を中断するのは危険です。
大切なのは副作用を放置せず、主治医と相談しながら適切に管理することです。
定期検査を受けながら薬を継続することが、結果的に寿命を守ることにつながります。
Q4. 自分で寿命を延ばすためにできる生活習慣は?
寿命を延ばす生活習慣は、双極性障害を持つ方に限らず健康維持の基本です。
規則正しい睡眠、栄養バランスの取れた食事、適度な運動を心がけることが、心身の安定に直結します。
また、喫煙や過度な飲酒を避けることも重要であり、これらを続けることで合併症リスクを大幅に下げられます。
ストレスをため込まない工夫や、趣味・リラックス習慣を持つことも再発予防に役立ちます。
生活の小さな積み重ねが、寿命を延ばす大きな力になります。
Q5. 家族はどのようにサポートすればよいですか?
家族のサポートは、双極性障害を持つ方の寿命や生活の質を守るうえで大きな役割を果たします。
無理に励ますのではなく、本人の気分の波を理解し、安心できる環境を整えることが重要です。
再発の兆候に早めに気づき、必要に応じて医療機関へつなぐことも家族の大切な役割です。
また、家族自身がカウンセリングやサポートグループを活用することで、支える側の負担を軽減できます。
「共に歩む姿勢」が、本人の安心と寿命を守る力になります。
双極性障害と寿命を正しく理解し、予防とケアを大切に

双極性障害は寿命が短い・突然死のリスクがあると言われますが、これは決して避けられないものではありません。
その背景には自殺や合併症、生活習慣などさまざまな要因が絡んでいますが、適切な治療と生活改善でリスクを減らすことができます。
重要なのは、数字や不安にとらわれず、できることから予防とケアを積み重ねることです。
治療を継続し、生活習慣を見直し、家族や社会のサポートを受けながら前向きに生活することで、健康で長く生きることは十分に可能です。
双極性障害を正しく理解し、自分らしい生活を守る第一歩を踏み出しましょう。