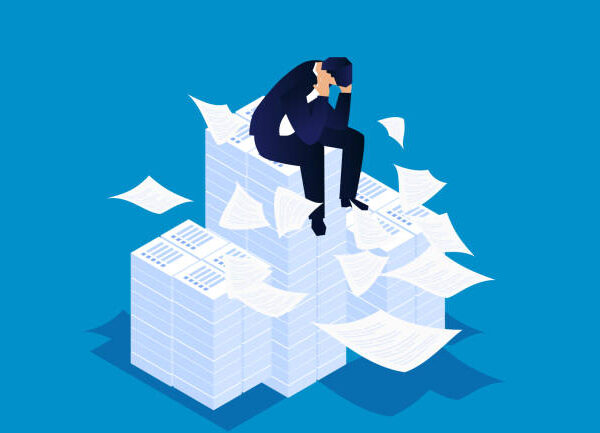「もう疲れた、休職したい」と感じたとき、それは心と体からのSOSです。
無理をして働き続けると、うつ病や適応障害などの精神疾患に進展し、長期的に回復が難しくなるリスクがあります。
一方で「休職は甘えではないか」「会社にどう伝えればいいのか」「診断書や手続きは必要なのか」と悩む方も少なくありません。
本記事では、休職を考えるときに取るべき行動をわかりやすく解説します。
医師の受診から診断書の取得、会社への伝え方、傷病手当金などの経済的支援、そして休職中のセルフケアや相談窓口まで網羅しています。
限界を迎える前に正しい知識を持ち、安心して休養を取るための第一歩として参考にしてください。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。
「休職したい、疲れた」と感じるのはどんなとき?

「休職したい」と思うのは、心や体が限界に近づいているサインです。
日常生活や仕事に支障が出ていても、最初は「気のせい」「もう少し頑張れる」と無理をしてしまう人も多いです。
しかし、以下のような状況が続く場合は、休養や受診を真剣に考える必要があります。
- 朝起きられない・会社に行くのが怖い
- 強い疲労感や眠れない日が続く
- 仕事のミスが増え集中できない
- 涙が止まらない・気分の落ち込みが続く
これらは精神的な疲労やうつ病の初期サインであることも多く、早めの対応が大切です。
朝起きられない・会社に行くのが怖い
朝起きられない、あるいは会社に行くのが怖いと感じることは、休職を検討すべき代表的なサインです。
目覚ましで起きても体が動かない、支度をする気力が出ないなど、身体的にも精神的にも強い負担がかかっています。
また、会社を思い浮かべただけで動悸がする、吐き気がするなどの症状がある場合は注意が必要です。
これは単なる怠けではなく、心身が「これ以上続けると危険」と警告を出している状態です。
無理をして出勤を続けると症状が悪化する可能性があるため、早めに医師に相談することが大切です。
強い疲労感や眠れない日が続く
慢性的な疲労感や不眠も「休職したい」と感じる大きな要因です。
しっかり休んだはずなのに疲れが取れない、夜眠れずに朝を迎えるといった日が続くと、心身が回復する機会を失います。
疲労や睡眠障害は仕事のパフォーマンスを大きく下げるだけでなく、うつ病や適応障害などのリスクを高めます。
特に「眠れないこと」自体が新たなストレスとなり、不安や焦りを悪化させることもあります。
この段階で無理を続けると症状が重くなるため、医療機関への相談や休職を検討することが重要です。
仕事のミスが増え集中できない
集中力の低下やミスの増加は、心が疲れているサインです。
普段はできていた業務がうまくいかない、ケアレスミスが続くと「自分はだめだ」と自己否定の感情が強まります。
こうした悪循環は、さらに集中力を奪い、不安や焦りを助長します。
本人は「気合で何とかしよう」と考えがちですが、心身の限界が近づいている可能性があります。
小さな変化でも長期間続く場合は、早めに休養を検討することが大切です。
涙が止まらない・気分の落ち込みが続く
涙が止まらない、または気分の落ち込みが続くことも、休職を考える重要なサインです。
理由が分からないのに涙が出る、普段楽しめていたことに興味が持てないといった症状は、心のエネルギーが消耗している証拠です。
「気分の浮き沈み」と軽く考えがちですが、これが2週間以上続く場合はうつ病の可能性もあります。
放置すると生活全般に影響が広がり、仕事だけでなく人間関係や日常生活にも支障が出てしまいます。
つらさを抱え込まず、医師や専門機関に相談することが早期回復につながります。
休職を考えるべきサイン

「休職したい」と感じるのは、心身の限界が近いことを示しています。
一時的な疲れや気分の落ち込みであれば休養や休日で回復することもありますが、症状が続く場合は注意が必要です。
ここでは、休職を真剣に検討すべき代表的なサインを紹介します。
- 2週間以上続く心身の不調
- 生活や家事にも支障が出ている
- 通勤・勤務を続けるのが困難
- 「死にたい」と感じる瞬間がある
これらのサインが当てはまる場合、無理をせず医療機関に相談し、休職を視野に入れることが大切です。
2週間以上続く心身の不調
2週間以上、疲労感・気分の落ち込み・不眠・食欲不振などが続いている場合は、休職を考えるべきサインです。
うつ病や適応障害などの精神疾患の診断基準では、症状が2週間以上持続していることが重要なポイントとされています。
「そのうち回復するだろう」と放置すると、さらに悪化して治療が長引く可能性があります。
一時的な不調と慢性的な不調を区別する目安として「2週間ルール」を意識することが大切です。
長く続く心身の不調は、早めに受診して対応することが必要です。
生活や家事にも支障が出ている
生活や家事に支障が出ているときも、休職を検討すべき状態です。
例えば、料理や掃除ができない、食事を取る気力がない、布団から出られないなどの状況です。
これは仕事だけでなく、日常生活全般にエネルギーが不足していることを示しています。
こうした状態で仕事を続ければ、さらに心身を追い込み、悪化するリスクが高まります。
生活に影響が出始めたら、早めに立ち止まり、休養や医療機関での相談を考えることが大切です。
通勤・勤務を続けるのが困難
会社に行こうとすると動悸や吐き気がする、電車に乗るのが怖い、出社しても仕事が手につかないなどの症状がある場合は要注意です。
これは単なる怠けではなく、心身が強いストレスに反応しているサインです。
無理をして通勤を続けると、症状がさらに重くなり長期の休職や入院につながる恐れもあります。
通勤や勤務が困難に感じた時点で、医師に相談し、適切な休養の取り方を検討することが必要です。
「会社に行けない」という状態は、それだけ心身が限界に近い証拠なのです。
「死にたい」と感じる瞬間がある
「死にたい」と感じる瞬間がある場合は、最も深刻なサインです。
これは強い絶望感や希死念慮を意味し、命に関わる危険性があります。
たとえ一瞬でも「いなくなりたい」「消えてしまいたい」と思ったら、それは早急に支援が必要な状態です。
すぐに医師や専門機関へ相談し、一人にならないよう周囲に助けを求めることが重要です。
このサインがあるときは、ためらわず休職を選び、命を守ることを最優先にしてください。
休職をするために取るべき行動

「休職したい、疲れた」と思ったときに重要なのは、感情に任せて突然会社を辞めるのではなく、正しい手順を踏むことです。
休職は会社の制度に基づいて認められるものであり、医師の診断や必要な手続きを進めることで安心して休むことができます。
ここでは休職を実現するために必要な具体的な行動を紹介します。
- まず心療内科・精神科を受診する
- 医師に症状を正直に伝え診断書をもらう
- 会社に休職の意思を伝える(上司・人事)
- 傷病手当金など経済的支援を確認する
順序を守って行動することで、安心して休養に入ることができます。
まず心療内科・精神科を受診する
休職を考えたときの最初のステップは、心療内科や精神科を受診することです。
疲労感や気分の落ち込みが続いている状態は、うつ病や適応障害などの可能性があり、専門的な診断が欠かせません。
医師の診察を受けることで、自分の状態を客観的に把握でき、今後の治療方針や休養の必要性について具体的な判断が得られます。
「ただの疲れかもしれない」と自己判断せず、医師に相談することが心身を守る第一歩です。
早めに受診することで、症状が悪化する前に対応できる可能性が高まります。
医師に症状を正直に伝え診断書をもらう
休職には診断書が必要となるケースが多いため、医師に症状を正直に伝えることが重要です。
「眠れない」「涙が止まらない」「会社に行くのが怖い」など、日常で困っていることを隠さず伝えるようにしましょう。
診断書は会社に休職を申請するための公式な書類となり、制度を利用するうえで不可欠です。
また、診断書を通じて「どのくらいの休養が必要か」「治療の見通しはどうか」といった情報も共有されます。
ためらわず正直に話すことが、適切なサポートを受けるための近道です。
会社に休職の意思を伝える(上司・人事)
会社に休職の意思を伝えることも大切なプロセスです。
診断書をもらったら、直属の上司や人事担当者に提出し、正式に休職を申し出ます。
「迷惑をかけるのでは」とためらう人も多いですが、休職は従業員の権利であり、健康を守るための正当な制度です。
報告の際には診断書とともに「医師から休養が必要と言われた」と伝えるとスムーズです。
無理をして働き続けるよりも、休むことで回復し、長期的には会社にとってもプラスとなります。
傷病手当金など経済的支援を確認する
休職中に不安となるのは収入面です。
そのため、健康保険から支給される傷病手当金などの制度を確認することが重要です。
傷病手当金は、給与の約3分の2が支給される制度で、休職中の生活を支えるために活用できます。
また、会社によっては独自の休職制度や補助が用意されている場合もあるため、人事部に確認しておくと安心です。
経済的な不安を減らすことで、安心して休養と治療に専念できる環境が整います。
診断書と休職の流れ

休職をする際には診断書の提出が必要となるケースがほとんどです。
診断書は医師が「この方は休養が必要である」と医学的に判断した証明書であり、会社が休職を認める根拠となります。
ここでは診断書の発行から会社への提出、休職中の給与や手当、復職時の流れについて解説します。
- 診断書の発行に必要なこと
- 会社に提出する流れ
- 休職中の給与・傷病手当金について
- 復職の際に必要な手続き
全体の流れを知っておくことで、安心して休職に入ることができます。
診断書の発行に必要なこと
診断書の発行には、医師に自分の症状を正直に伝えることが欠かせません。
「眠れない」「食欲がない」「仕事に行くのが怖い」など、日常で困っていることを具体的に説明することが大切です。
医師は診察内容をもとに「うつ病」「適応障害」などと診断し、休職が必要である旨を記載した診断書を作成します。
診断書には休養が必要な期間も記載されるため、どのくらい休めるかの目安となります。
自己判断で無理をするのではなく、医師の判断に従うことが安心して休職するための第一歩です。
会社に提出する流れ
診断書を会社に提出することで、正式に休職が認められます。
一般的には直属の上司や人事部に提出し、その後会社の就業規則に基づいて休職の手続きが進められます。
会社によっては産業医との面談が行われる場合もあります。
診断書があることで「正当な理由による休職」であることが明確になり、会社側も対応しやすくなります。
不安な場合は、提出方法や必要書類について人事担当者に確認しておくと安心です。
休職中の給与・傷病手当金について
休職中は給与が支給されない場合が多いため、生活を支える制度を確認する必要があります。
公的な制度として健康保険から支給される傷病手当金があります。
これは給与の約3分の2が支給される制度で、最長1年6か月受け取ることができます。
また、会社によっては独自の休職手当や福利厚生が用意されていることもあります。
経済的な不安を軽減することで、安心して治療と休養に専念できる環境が整います。
復職の際に必要な手続き
復職をする際には、医師の診断書や復職許可証が必要となることが一般的です。
会社によっては産業医や人事部との面談を経て、職場復帰の可否が判断されます。
また、復職直後は短時間勤務や段階的な職場復帰(リワークプログラム)が用意されている場合もあります。
無理をして元のペースに戻そうとすると再発のリスクが高いため、徐々に慣らしていくことが推奨されます。
復職後も定期的に医師に相談しながら、長期的に安定して働ける環境を整えることが大切です。
「休職は甘えではない」理由

「休職したい」と思っても、「甘えではないか」「自分が弱いだけでは」と不安になる人は少なくありません。
しかし、休職は単なるわがままではなく、医学的にも社会的にも認められた正当な制度です。
ここでは、なぜ休職は甘えではないといえるのか、その理由を解説します。
- 休養は病気の治療の一環
- 放置すると症状が悪化するリスク
- 医師の判断に基づいた正当な制度
- 安心して利用すべき社会的仕組み
自分を責めるのではなく、安心して制度を利用することが回復につながります。
休養は病気の治療の一環
休養は治療の一部であり、決して怠けや甘えではありません。
うつ病や適応障害といった心の病気は、薬だけで治るものではなく、休養によって心身を回復させることが不可欠です。
無理をして働き続けることは、病気を悪化させ、治療を長引かせる原因になります。
休むこと自体が「治療のプロセス」であると理解することが大切です。
医師も必要と判断して休養を勧めているため、安心して休職を選んでよいのです。
放置すると症状が悪化するリスク
放置することのリスクを考えれば、休職はむしろ必要な行動だといえます。
心身の不調を抱えながら働き続けると、うつ病の重症化や長期離職につながる危険があります。
また、不眠や強い疲労が続くことで、生活習慣病や免疫低下など身体的な病気を併発することもあります。
早めに休むことで、短期間の治療や休養で回復できる可能性が高まります。
「頑張り続ける方が危険」だと理解することが、安心して休職を選ぶ後押しになります。
医師の判断に基づいた正当な制度
休職は医師の診断に基づく正当な制度です。
自己判断で「休みたい」と言っているのではなく、医師が「治療のために休養が必要」と判断した結果として診断書が発行されます。
会社もその診断書をもとに正式に休職を認めるため、法律や制度に則った正当な仕組みといえます。
つまり、休職は個人のわがままではなく、医師と会社が認めた正規のプロセスです。
「制度として認められた権利」であることを理解することで、自分を責めずに休むことができます。
安心して利用すべき社会的仕組み
休職は社会的な仕組みとして用意されているものであり、安心して利用してよい制度です。
健康保険の傷病手当金や会社の就業規則などは、従業員が心身の不調を抱えたときに生活や仕事を守るために設けられています。
多くの人が制度を活用して回復し、再び働く力を取り戻しています。
「自分だけが特別ではない」と理解し、社会が用意した仕組みを使うことが回復への近道です。
安心して休職を利用し、しっかりと休養を取ることが、次の一歩を踏み出すための大切な準備となります。
休職中にできるセルフケア

休職中は「何もできない自分」を責めてしまう人もいますが、休むこと自体が治療の一部です。
そのうえで、自分のペースでできるセルフケアを少しずつ取り入れることで、回復を早めることができます。
ここでは休職中に無理なく実践できるセルフケアの方法を紹介します。
- 規則正しい生活リズムを整える
- 睡眠・栄養・運動を意識する
- 感情をノートに書き出す
- オンライン相談やカウンセリングを活用
小さな習慣の積み重ねが、心身の安定につながります。
規則正しい生活リズムを整える
規則正しい生活リズムを整えることは、休職中のセルフケアの基本です。
休んでいると昼夜逆転しやすく、余計に気分が落ち込むことがあります。
毎日同じ時間に起きて朝日を浴びるだけでも、自律神経が整い、心の安定につながります。
完璧にこなす必要はなく、「起きる時間を一定にする」「朝食をとる」といった小さな習慣から始めましょう。
生活のリズムが整うと、自然と気力が回復しやすくなります。
睡眠・栄養・運動を意識する
睡眠・栄養・運動は、心と体の健康を支える3本柱です。
眠れない日が続いた場合は医師に相談し、必要なら睡眠導入剤を使うことも選択肢です。
食事はバランスを意識し、エネルギーを補うことで回復を助けます。
また、軽い散歩やストレッチなど無理のない運動を取り入れると、気分転換や睡眠の質改善につながります。
少しずつ体を動かすことで、回復のサイクルを作ることができます。
感情をノートに書き出す
感情をノートに書き出すことは、不安やストレスを客観視する効果があります。
頭の中で考え続けると不安が増幅しますが、文字にすることで「今自分はこう感じている」と整理できます。
書く内容は「疲れた」「不安だ」といった短い言葉でも構いません。
書き出す習慣を持つことで、自分の気持ちをコントロールしやすくなり、医師やカウンセラーに伝える材料にもなります。
心の整理は回復を後押しする大切なセルフケアです。
オンライン相談やカウンセリングを活用
オンライン相談やカウンセリングを活用することも有効です。
休職中は人とのつながりが減りやすく、孤独感が強まることがあります。
そんなときに、自宅から気軽に相談できるオンラインカウンセリングや電話相談は大きな支えになります。
専門家に話すことで、安心感が得られ、適切なアドバイスを受けることができます。
一人で抱え込まず、外部のサポートを取り入れることが回復への近道になります。
家族や周囲ができるサポート

休職を考えるほど疲れたと感じている人にとって、家族や周囲の存在は大きな支えになります。
しかし「どのように接すればよいか分からない」と悩む方も多いでしょう。
ここでは、家族や周囲ができる具体的なサポートの方法を紹介します。
- 本人の気持ちを否定せず受け止める
- 安心できる生活環境を一緒に整える
- 医療機関や相談窓口につなげる
- 支える側も無理をしない
支える側も完璧を目指す必要はなく、できる範囲で寄り添う姿勢が大切です。
本人の気持ちを否定せず受け止める
本人の気持ちを否定せず受け止めることは、最も大切なサポートのひとつです。
「それくらい大したことない」「もっと頑張れる」といった言葉は、本人をさらに追い込む原因になります。
代わりに「つらいね」「無理しなくていいよ」と共感を示すことで、安心感を与えることができます。
気持ちを理解しようとする姿勢だけでも、孤独感や無力感を和らげる効果があります。
否定ではなく受容が、信頼関係を深める第一歩です。
安心できる生活環境を一緒に整える
安心できる環境を整えることも、家族や周囲ができる重要な支援です。
例えば、静かで落ち着ける空間をつくる、生活リズムを整えるために軽い声掛けをするなどが挙げられます。
安心して過ごせる居場所があることで、心身が少しずつ回復しやすくなります。
また、家族が一緒に過ごすだけでも「一人じゃない」と感じられ、孤独感が和らぎます。
環境づくりは特別なことではなく、小さな工夫の積み重ねが効果を発揮します。
医療機関や相談窓口につなげる
家族や周囲は医療機関や相談窓口につなぐ役割を担うことも大切です。
本人は「迷惑をかけるのでは」と考えて受診をためらうことがあります。
「一緒に行こうか」と提案したり、地域の精神保健福祉センターや電話相談を紹介することが有効です。
専門家につながることで、正しい診断や支援を受けられ、安心して休職や治療に進めます。
無理に勧めるのではなく、寄り添いながら選択肢を示すことがポイントです。
支える側も無理をしない
支える側のセルフケアも忘れてはいけません。家族や周囲が疲れ果ててしまうと、本人を支える余力がなくなってしまいます。
「一人で背負わない」「できることだけをする」と意識することが大切です。
必要に応じてカウンセリングや支援団体を利用するのも良い方法です。
支える人が元気でいることが、結果的に本人の安心にもつながります。
よくある質問(FAQ)

Q1. 診断書がなくても休職できる?
診断書がなくても休職できるかは、会社の規定によって異なります。
一般的に正式な休職制度を利用する場合には、医師の診断書が必要です。
診断書は「病気や不調のため休養が必要」という医学的根拠を示す書類であり、会社が休職を認める判断材料になります。
ただし、短期的な休みや有給休暇で対応できる場合には診断書が不要なこともあります。
制度を正しく利用して安心して休むためには、まず医師に相談し診断書を発行してもらうことが大切です。
Q2. 休職するとクビになる?
休職したからといってすぐに解雇されることはありません。
多くの会社では就業規則で休職制度が定められており、従業員の健康を守るための権利として認められています。
ただし、休職期間が満了しても復職できない場合には退職や解雇につながることもあります。
そのため、休職中は医師と相談しながら回復を目指し、必要に応じて延長や復職準備を進めることが大切です。
会社にとっても従業員に回復してもらうことが利益につながるため、安心して制度を利用してよいのです。
Q3. 休職中はどれくらいの収入がある?
休職中は給与が支給されないケースが多いですが、健康保険の傷病手当金を利用できます。
傷病手当金は、給与の約3分の2が最長1年6か月間支給される制度で、生活を支える重要な仕組みです。
また、会社によっては独自の休職補助や有給休暇の併用が可能な場合もあります。
経済的な不安を軽減するためには、事前に会社の人事部や健康保険組合に確認することが大切です。
制度を理解しておくことで、安心して休養に専念できる環境を整えることができます。
Q4. どのくらい休めるのが一般的?
休職期間は会社の就業規則や医師の診断によって異なります。
多くの企業では3か月から6か月程度が一般的ですが、症状や回復の状況によって延長される場合もあります。
また、休職の延長には再度診断書が必要になるケースが多いため、定期的に受診して医師の指示を受けることが重要です。
「どれくらい休めるか」よりも「どのくらい回復に時間がかかるか」を基準に考えることが大切です。
焦らず、必要な期間しっかり休養することが結果的に早い回復につながります。
Q5. 復職が不安なときはどうすればいい?
復職が不安なときは、一人で悩まず主治医や産業医に相談しましょう。
医師は心身の状態を踏まえて復職可能かどうかを判断し、必要なら短時間勤務やリワークプログラムを提案してくれます。
また、会社の人事部に相談することで段階的な復帰制度を利用できる場合もあります。
「完全に元通りでなければ復職できない」と思う必要はありません。
少しずつ環境に慣れることで不安を減らし、安心して社会復帰につなげることが可能です。
「休職したい」と思ったときは早めに行動を

「休職したい、疲れた」と感じるのは、心と体が限界に近づいているサインです。
診断書をもらって休職することは決して甘えではなく、治療と回復のための正当な選択です。
無理をして働き続けると、症状が悪化して回復に時間がかかる危険性があります。
医師への受診、会社への相談、傷病手当金の申請といったステップを踏むことで、安心して休養を取ることができます。
限界を迎える前に行動することが、健康を守り、再び働ける力を取り戻すための第一歩です。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。