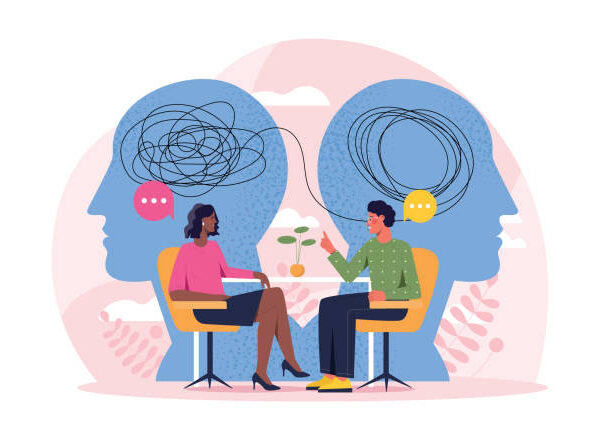うつ病で働けないとき、多くの人が不安に思うのは「給付金はいくらもらえるのか」「どんな手当があるのか」という点です。
実際には、会社員・公務員・自営業など立場によって利用できる制度は異なりますが、代表的なものに傷病手当金や障害年金があります。
本記事では、うつ病のときに受けられる給付金・手当の種類と金額、申請条件や注意点まで詳しく解説します。
「制度が複雑でよく分からない」「生活できるだけの給付があるのか知りたい」という方に役立つ内容です。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。
うつ病で受けられる給付金・手当の全体像

うつ病で働けなくなった場合、生活や治療を支えるために利用できる給付金や手当がいくつも用意されています。
制度は所属する健康保険や年金制度、生活状況によって異なり、受けられる内容や金額にも違いがあります。
代表的なものには、会社員や公務員が受けられる傷病手当金、長期的な症状に対応する障害年金、経済的に困窮した際の生活保護や貸付制度、医療費の自己負担を減らす自立支援医療制度などがあります。
さらに、精神障害者保健福祉手帳を取得すると、交通機関の割引や税制上の優遇といった支援も利用できます。
ここでは、うつ病で利用できる主要な制度を整理して紹介します。
- 傷病手当金(健康保険から支給される手当)
- 障害年金(国民年金・厚生年金からの支給)
- 生活保護・生活福祉資金貸付
- 自立支援医療制度(医療費の軽減)
- 精神障害者保健福祉手帳による優遇
複数の制度を組み合わせて利用することで、安心して療養に専念できる環境を整えることが可能です。
傷病手当金(健康保険から支給される手当)
傷病手当金は、会社員や公務員が加入する健康保険から支給される制度です。
うつ病によって仕事を休み、給与が支給されない場合に申請することで、休職中の生活を支えるためのお金を受け取ることができます。
支給額は、休職前の標準報酬日額の3分の2に相当する金額が、最長1年6か月間支給されます。
この制度は「働けない期間の生活費を保障する」役割があり、経済的な不安を和らげる大きな助けになります。
申請には医師の診断書や会社の証明が必要であり、勤務先や健康保険組合を通じて手続きが行われます。
休職を余儀なくされた場合、まず検討すべき代表的な制度といえます。
障害年金(国民年金・厚生年金からの支給)
障害年金は、うつ病が長期化し、日常生活や就労が著しく制限される場合に受けられる制度です。
国民年金に加入している場合は障害基礎年金、厚生年金に加入している場合は障害厚生年金として支給されます。
等級は1級から3級まであり、重症度によって支給額が変わります。
障害基礎年金の2級は年間約100万円、1級は約120万円が目安で、障害厚生年金はこれに加えて上乗せされます。
申請には医師の診断書、病歴・就労状況等申立書などが必要で、認定には時間がかかる場合があります。
長期的に就労が難しい人にとって、生活を支える重要な制度です。
生活保護・生活福祉資金貸付
生活保護は、生活が著しく困難な人が最低限度の生活を送れるようにするための制度です。
うつ病で働けず、他の給付金や家族の支援だけでは生活できない場合に利用されます。
また、生活保護に至らない場合でも、自治体の社会福祉協議会を通じて生活福祉資金貸付制度を利用できることがあります。
これは、生活を立て直すために必要なお金を低金利、または無利子で借りられる制度です。
いずれも申請には生活状況の確認や審査が必要ですが、どうしても生活が困難な場合の安全網として用意されています。
経済的に追い詰められている場合は、早めに自治体や相談窓口に相談することが大切です。
自立支援医療制度(医療費の軽減)
自立支援医療制度は、精神科や心療内科に通院する人の医療費自己負担を軽減するための制度です。
通常3割負担の医療費が1割に軽減されるケースが多く、通院や薬の費用負担を大きく減らすことができます。
うつ病の治療は長期にわたることが多いため、この制度を利用することで経済的な安心感が得られます。
申請は医師の診断書と申請書を揃え、自治体の窓口で手続きする流れです。
対象となる医療機関や薬局を登録する必要があり、継続的な治療を続けやすくなります。
医療費が心配で治療をためらう人にとって、強力な支援制度といえます。
精神障害者保健福祉手帳による優遇
精神障害者保健福祉手帳は、うつ病を含む精神疾患が一定期間続いている人が取得できる手帳です。
この手帳を持つことで、税制上の控除や公共交通機関の割引、公共料金の減免など、さまざまな優遇が受けられます。
また、就労支援や福祉サービスを利用できるなど、社会生活をサポートする効果があります。
等級は1級から3級まであり、症状の重さによって決まります。
申請には医師の診断書や自治体への申請書が必要ですが、一度取得すると生活上の負担を大きく減らすことができます。
経済的な支援に加え、社会参加の後押しとなる制度です。
傷病手当金の仕組みと支給額

傷病手当金は、うつ病などで長期間働けなくなったときに生活を支えるための重要な制度です。
健康保険に加入している会社員や公務員が対象で、休職中に給与が支給されない場合に利用できます。
支給額は休職前の収入を基に計算され、おおよそ給与の3分の2が支給される仕組みです。
また、支給期間は最長1年6か月と長期にわたって保障されるため、安心して療養に専念できます。
ここでは、傷病手当金を受給するための条件や支給額の計算方法、申請の流れを詳しく解説します。
- 受給できる条件(勤務先を休職・給与がない場合)
- 支給額の計算方法「標準報酬日額×2/3」
- 傷病手当金はいくらもらえる?具体例
- 支給期間(最長1年6か月)と延長可能性
- 会社にバレる?申請の流れと必要書類
制度の仕組みを正しく理解することで、安心して活用できるようになります。
受給できる条件(勤務先を休職・給与がない場合)
傷病手当金を受給するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、健康保険(社会保険)に加入していることが前提です。
そのうえで、①業務外の病気やケガであること、②療養のために働けない状態であること、③連続して3日以上仕事を休んでいること、④給与が支給されていないこと、の4つを満たす必要があります。
うつ病の場合、医師が「労務不能」と診断した場合に対象となります。
会社員や公務員が対象であり、自営業やフリーランスは原則として利用できません。
受給条件を把握することが、申請の第一歩となります。
支給額の計算方法「標準報酬日額×2/3」
傷病手当金の支給額は標準報酬日額×2/3で計算されます。
標準報酬日額とは、休職前の12か月間の標準報酬月額の平均を30日で割った金額です。
その金額に2/3をかけたものが、1日あたりの支給額になります。
例えば、月収30万円の人の場合、標準報酬日額は約1万円となり、その2/3の約6,667円が1日あたり支給されます。
この仕組みによって、休職中でも収入の一部を確保でき、生活の安定につながります。
給与と比べると減額にはなりますが、経済的負担を大きく軽減する役割を果たします。
傷病手当金はいくらもらえる?具体例
実際に傷病手当金はいくらもらえるのかを具体例で見てみましょう。
月収20万円の場合、標準報酬日額は約6,667円、そこから2/3をかけて約4,444円が1日の支給額です。
30日間の休職で約133,000円が支給されます。
月収30万円なら1日あたり約6,667円、30日で約200,000円の支給となります。
このように収入の約3分の2が保障されるため、家計の目安を立てやすくなります。
ただし、実際の金額は社会保険の加入期間や標準報酬月額によって異なるため、加入している健康保険組合に確認することが重要です。
支給期間(最長1年6か月)と延長可能性
傷病手当金は最長で1年6か月(18か月)支給されます。
この期間は連続して支給されるのではなく、支給要件を満たしている日数を合算して計算されます。
そのため、一度復職しても再びうつ病で休職した場合は、同じ病気であれば残りの期間分を受け取れる仕組みです。
ただし、最長期間を超える延長は原則できません。
一部の特例を除き、1年6か月で終了するため、その後は障害年金など別の制度を検討する必要があります。
支給期間を理解し、計画的に生活設計を立てることが大切です。
会社にバレる?申請の流れと必要書類
傷病手当金を申請するには、勤務先と健康保険組合を通じて手続きを行う必要があります。
そのため、会社に申請事実が伝わる点は避けられません。
ただし、具体的な病名や詳細な症状が知られるわけではなく、「労務不能である」という医師の診断書が提出される形です。
申請に必要な書類は、健康保険組合の所定の申請書、医師の証明、事業主の証明などです。
会社を通さずに直接健康保険組合に申請できるケースもありますが、原則は勤務先を経由します。
プライバシーが不安な場合は、主治医や健康保険組合に相談しながら進めることが大切です。
障害年金の仕組みと支給額

障害年金は、うつ病などで長期的に日常生活や就労が制限される場合に受給できる公的制度です。
国民年金や厚生年金に加入している人が対象で、症状の重さに応じて等級が決められ、支給額が変わります。
うつ病は「精神疾患による障害」として認定されることがあり、症状や生活への影響が基準を満たすと受給対象になります。
ただし、申請には医師の診断書や病歴・就労状況申立書などが必要であり、認定が難しいケースも多いため注意が必要です。
ここでは、障害年金の支給額や種類、申請に関する注意点を解説します。
- 等級ごとの支給額(1級・2級・3級)
- 障害基礎年金と障害厚生年金の違い
- 働きながらでももらえる?就労との両立
- 申請の難しさと社会保険労務士に相談するメリット
- 不支給になるケースと注意点
長期的な療養や生活を支える制度として、正しい知識を持つことが大切です。
等級ごとの支給額(1級・2級・3級)
障害年金は症状の程度によって1級から3級に分けられます。
障害基礎年金の場合、1級は年間約97万円×1.25=約122万円、2級は年間約97万円が目安です。
厚生年金加入者はこれに報酬比例の年金が加算され、収入や加入年数によって金額が変わります。
3級は厚生年金加入者のみ対象で、最低保障額は年間約59万円です。
さらに、18歳未満の子どもがいる場合は加算があり、家族の生活を支える役割も担います。
等級によって大きく金額が変わるため、認定基準を理解することが重要です。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
障害基礎年金は国民年金加入者すべてが対象で、全国民共通の制度です。
一方で障害厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金に加入している人が対象となります。
厚生年金は基礎年金に上乗せして支給されるため、受給額が大きくなるのが特徴です。
たとえば同じ2級でも、国民年金加入者は基礎年金のみですが、厚生年金加入者は基礎年金+厚生年金を受け取れます。
そのため、職業や加入している年金制度によって、実際に受け取れる金額に大きな差が出ます。
自分がどちらに該当するかを確認しておくことが大切です。
働きながらでももらえる?就労との両立
「働いていると障害年金はもらえないのでは?」と思う人も多いですが、必ずしもそうではありません。
障害年金は「働けるかどうか」ではなく、「日常生活や労働にどれだけ制限があるか」で判断されます。
そのため、短時間勤務や配慮のある環境で働いている場合でも、生活や就労に制限があれば受給できるケースがあります。
ただし、フルタイム勤務や高収入があると「労働制限がない」と判断され、受給が難しくなることもあります。
就労と年金の両立は可能ですが、ケースによって判断が異なるため、事前に専門家に相談すると安心です。
「働いている=受給不可」とは限らない点を覚えておきましょう。
申請の難しさと社会保険労務士に相談するメリット
障害年金の申請は非常に複雑で、提出書類や診断書の内容が不十分だと不支給になる可能性があります。
特にうつ病の場合、症状が数値化しにくいため、適切に状況を伝えることが難しいのが現状です。
そのため、専門知識を持つ社会保険労務士(社労士)に相談することで、申請の成功率を高められます。
社労士は診断書の記載ポイントや申請書類の準備をサポートしてくれるため、安心して手続きを進められます。
また、不支給になった場合の不服申し立ても支援してもらえることがあります。
初めて申請する人は専門家に相談することを強くおすすめします。
不支給になるケースと注意点
障害年金は申請しても必ず受給できるわけではありません。
よくある不支給のケースとしては、保険料の納付要件を満たしていない、診断書の内容が不十分、症状が軽いと判断される、などがあります。
また、就労状況や日常生活の様子が「制限なし」と見なされると受給が難しくなります。
不支給を避けるためには、病歴や生活の困難さを丁寧に記録し、医師に正確に伝えることが大切です。
さらに、申請から結果が出るまでに数か月かかることも多いため、早めの準備が必要です。
「不支給になりやすいポイント」を知っておくことで、申請の成功率を高められます。
その他の生活支援制度

うつ病で休職や退職を余儀なくされた場合、傷病手当金や障害年金以外にも生活を支えるための制度があります。
代表的なものに生活保護や自立支援医療制度、精神障害者保健福祉手帳による割引や優遇制度があります。
また、失業手当や労災保険といった制度も状況によっては利用できるため、制度を組み合わせて活用することが大切です。
ここでは、うつ病で利用可能なその他の支援制度を詳しく解説します。
- 生活保護を受けられる条件と支給額の目安
- 自立支援医療制度で医療費が軽減される
- 精神障害者保健福祉手帳で得られる割引やサービス
- 失業手当との関係(休職中・退職後の違い)
- 労災保険が適用されるケース
経済的不安を少しでも和らげるために、活用できる制度を知っておくことが重要です。
生活保護を受けられる条件と支給額の目安
生活保護は、収入や資産が生活保護基準を下回っている場合に受けられる制度です。
うつ病で働けず、傷病手当金や障害年金だけでは生活が成り立たない場合に対象となることがあります。
支給額は世帯人数や地域ごとの基準によって異なりますが、最低限度の生活を保障する水準に設定されています。
また、医療扶助が適用されるため、治療費の自己負担がなくなる点も大きな支援です。
申請は市区町村の福祉事務所で行い、生活状況や資産の調査を受ける必要があります。
厳しい審査はありますが、生活が困難な場合の最後のセーフティネットとして活用できます。
自立支援医療制度で医療費が軽減される
自立支援医療制度は、精神科や心療内科に通院する患者の医療費負担を軽減する制度です。
通常3割負担の医療費が原則1割に軽減されるため、通院や薬代の負担が大きく減ります。
うつ病は長期的な治療が必要になることが多く、経済的な支援として非常に有効です。
対象となるのは通院治療に限定されており、医師の診断書を添えて市区町村の窓口に申請します。
医療機関や薬局を指定する必要があるため、事前に確認してから利用することが重要です。
この制度を利用することで、治療を中断せずに継続しやすくなります。
精神障害者保健福祉手帳で得られる割引やサービス
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、さまざまな割引やサービスが受けられます。
等級は1級から3級まであり、症状の重さによって区分されます。
具体的な優遇内容は、税制上の控除、公共交通機関の割引、携帯料金や公共料金の減免、就労支援サービスの利用など多岐にわたります。
また、雇用促進のための制度もあり、手帳を持つことで就労の選択肢が広がる場合もあります。
申請は市区町村の福祉課で行い、医師の診断書が必要です。
生活費や医療費の負担軽減だけでなく、社会参加を支える制度として有効です。
失業手当との関係(休職中・退職後の違い)
失業手当(雇用保険の基本手当)は、退職後に働く意思と能力がある人を対象に支給されます。
そのため、休職中に受け取ることはできません。
一方で、うつ病で退職した場合でも「就労可能」と判断されれば失業手当を受給できます。
ただし、すぐに働ける状態でない場合は「傷病手当金」を優先的に利用し、回復後に失業手当を申請するケースが一般的です。
また、障害年金や生活保護との併用は制限があるため、事前に確認する必要があります。
自分の状況に応じて、どの制度を先に利用するかを検討しましょう。
労災保険が適用されるケース
労災保険は、業務や通勤が原因で病気やケガをした場合に支給される制度です。
うつ病の場合でも、職場の過重労働やハラスメントなどが原因と認定されれば、労災の対象になります。
労災が認められると、療養費の全額支給や休業補償給付(賃金の約8割)、障害補償年金などが受けられます。
認定を受けるには詳細な証拠や医師の診断書、労働環境の記録が必要で、申請が複雑になる場合があります。
そのため、労働基準監督署や専門家に相談しながら手続きを進めることが大切です。
仕事が原因でうつ病を発症した場合には、必ず労災保険の可能性も検討しましょう。
申請の流れと必要書類
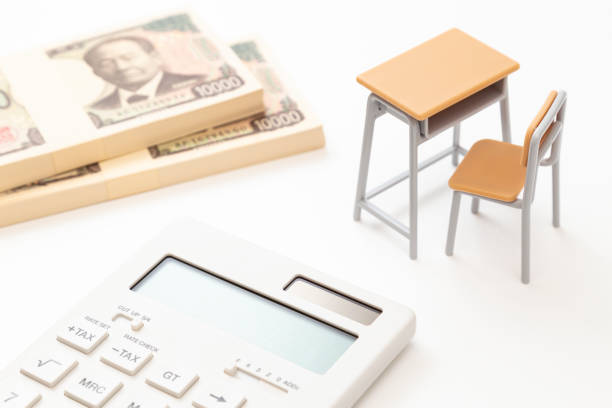
うつ病で給付金や手当を受け取るには、適切な申請手続きを行うことが欠かせません。
制度によって申請先や必要な書類は異なりますが、共通して重要なのは医師の診断書です。
また、会社を通じて提出するものや、年金事務所に直接提出する書類もあります。
申請から支給までには数か月かかることも多いため、早めに準備を始めることが重要です。
ここでは、申請の流れと必要書類、注意点を詳しく解説します。
- 医師の診断書の重要性
- 会社や年金事務所に提出する書類一覧
- 申請から支給までにかかる期間
- 不備や遅延を防ぐための注意点
準備を怠らず正しく申請することで、スムーズに給付を受け取ることができます。
医師の診断書の重要性
医師の診断書は、傷病手当金や障害年金を申請する際に最も重要な書類です。
診断書には、うつ病の症状、労務不能の状態、発症日や治療の経過などが記載されます。
この内容によって受給の可否や等級が判断されるため、正確かつ具体的な記載が求められます。
医師に伝える際は、日常生活で困っている点や就労への影響をできるだけ具体的に説明することが大切です。
「症状が軽く書かれてしまい申請が通らなかった」というケースもあるため、主治医としっかりコミュニケーションを取りましょう。
診断書は制度ごとに専用の様式があるため、申請先の指定用紙を確認する必要があります。
会社や年金事務所に提出する書類一覧
申請に必要な書類は制度によって異なりますが、代表的なものを整理します。
傷病手当金の場合は、健康保険組合の申請書、医師の証明、事業主の証明が必要です。
障害年金の場合は、医師の診断書、病歴・就労状況等申立書、年金請求書、住民票や戸籍謄本などが必要です。
生活保護を申請する場合は、収入や資産を証明する書類、家計簿や銀行通帳の写しが必要となります。
いずれの制度も、本人確認書類(マイナンバーカード・身分証)や印鑑も必須です。
不足があると申請が受理されないため、あらかじめ必要書類をリストアップして揃えておくことが大切です。
申請から支給までにかかる期間
申請から給付金が支給されるまでの期間は制度ごとに異なります。
傷病手当金の場合は、申請から1〜2か月程度で振り込まれるケースが一般的です。
障害年金は審査が厳しく、3〜6か月以上かかることも珍しくありません。
生活保護は申請から2週間〜1か月程度で結果が出るのが目安です。
いずれにしても、支給までには時間がかかるため、早めに申請準備をすることが重要です。
特に障害年金は「遡及請求」が可能な場合もあるため、必要なら専門家に相談すると安心です。
不備や遅延を防ぐための注意点
申請の不備や遅延は非常に多く、結果として給付が受けられないケースもあります。
よくあるのは、診断書の記載が不十分、提出書類の不足、申請内容と医師の記載内容が食い違う、などです。
これを防ぐためには、提出前に書類を必ずチェックし、可能であれば第三者(社労士や相談員)に確認してもらうことがおすすめです。
また、提出期限を過ぎると受給できなくなる場合もあるため、スケジュール管理も重要です。
「一度で完了させる」意識を持って丁寧に準備することが、申請をスムーズに進めるコツです。
事前準備を徹底することで、安心して給付を受け取れる環境を整えましょう。
給付金・手当の併用はできる?

うつ病で利用できる給付金や手当は複数ありますが、同時に受け取れるのかどうかは制度によって異なります。
「傷病手当金と障害年金」「失業手当との関係」「労災保険との重複」「生活保護と他制度の調整」など、ケースごとにルールがあり、知らずに申請すると不支給や返還を求められることもあります。
ここでは、主な制度の併用可否や注意点を整理して解説します。
- 傷病手当金と障害年金の関係
- 失業手当との併用可否
- 労災保険と重複する場合の扱い
- 生活保護と他制度の調整
誤解が多いポイントでもあるため、正しい知識を持って制度を組み合わせることが重要です。
傷病手当金と障害年金の関係
傷病手当金と障害年金は、どちらも「働けない状態」を支える制度ですが、併用の扱いには注意が必要です。
両方を同時に申請することは可能ですが、健康保険組合から支給される傷病手当金は「障害年金を受け取っている場合、その分を差し引いて調整される」仕組みになっています。
つまり、二重に満額をもらえるわけではなく、調整後の金額が支給されます。
例えば、障害年金が月8万円、傷病手当金が月15万円の場合、差額の7万円が支給されるといった形です。
そのため「どちらを優先すべきか」ではなく「両方申請して調整を受ける」流れを理解することが大切です。
併用を検討する場合は、必ず健康保険組合や年金事務所に確認しておきましょう。
失業手当との併用可否
失業手当(雇用保険の基本手当)は、働く意思と能力がある人に支給される制度です。
一方で、傷病手当金や障害年金は「働けない状態」が条件になるため、原則として失業手当との併用はできません。
ただし、失業手当の申請をした後にうつ病が悪化し、すぐに働けないと判断された場合は「傷病手当」に切り替えて受給する仕組みがあります。
逆に、傷病手当金の支給が終了した後に体調が回復し、就職活動が可能になれば失業手当を受け取ることが可能です。
「今の状態は働けるのか働けないのか」で選択が変わるため、申請時にハローワークで相談することが重要です。
制度の仕組みを誤解すると不支給になることもあるので注意しましょう。
労災保険と重複する場合の扱い
労災保険は「仕事や通勤が原因で発症した病気やケガ」に対して適用されます。
うつ病の場合でも、過労やハラスメントが原因と認定されれば対象になります。
労災保険から休業補償給付が支給される場合、同じ期間については傷病手当金は支給されません。
これは「二重給付を避ける」というルールがあるためです。
ただし、障害年金とは併用が可能で、労災による障害補償年金と障害年金を同時に受け取れるケースもあります。
状況によって扱いが異なるため、労働基準監督署や年金事務所に確認しながら手続きを進めることが大切です。
「労災が認められるかどうか」が大きな分岐点となります。
生活保護と他制度の調整
生活保護は「他の制度を利用しても生活できない場合」に適用される制度です。
そのため、傷病手当金や障害年金を受けている場合は、その収入がある前提で生活保護の支給額が調整されます。
例えば、障害年金が月8万円支給されている人が生活保護を申請した場合、生活保護基準との差額が支給される仕組みです。
つまり、他の制度と「併用」するのではなく「調整」される点に注意が必要です。
生活保護は最終的なセーフティネットであり、他の制度を使い切ったうえで申請するのが原則です。
ただし、医療扶助などの支援が受けられるため、経済的に困窮している場合は活用する価値があります。
生活保護を検討する際には、必ず福祉事務所に相談してから判断しましょう。
申請時に注意すべきポイント

うつ病で給付金や手当を申請する際には、制度の条件や仕組みを十分に理解しておく必要があります。
せっかく準備をしても、書類の不備や条件の誤解によって不支給となるケースも少なくありません。
また、申請によって会社に知られる範囲や、受給額が調整・減額される可能性もあります。
さらに、支給が終了した後の生活をどうするかを見据えておくことも重要です。
ここでは、申請時に特に注意しておきたいポイントをまとめます。
- 給付が不支給になるケース
- 給付を受けると会社に知られる?
- 受給額が減額される可能性
- 支給終了後に備える工夫
事前に理解しておくことで、安心して制度を利用できるようになります。
給付が不支給になるケース
給付金や手当は申請すれば必ず受け取れるものではありません。
よくある不支給のケースとしては、健康保険料や年金保険料の未納がある場合や、医師の診断書の内容が不十分で労務不能と判断されない場合です。
また、労災が原因であるにもかかわらず傷病手当金を申請したケースや、勤務先から給与が支給されている場合も対象外になります。
障害年金では「日常生活に著しい制限がある」と認められなければ支給されないため、主治医への症状の伝え方が非常に重要です。
不支給を避けるには、条件を確認し、必要書類を整えたうえで正しく申請することが大切です。
給付を受けると会社に知られる?
傷病手当金を申請する場合は、勤務先の証明が必要となるため、会社に申請事実は伝わります。
ただし、会社に伝わるのは「病気やケガで働けない」という事実であり、必ずしも病名や詳細な診断内容までは知られません。
一方で、障害年金や生活保護の申請は会社を通さず行うため、会社に知られることはありません。
「どこまで知られるのか」を理解しておくことで、不安を軽減できます。
プライバシーが心配な場合は、健康保険組合や医師に事前に相談すると安心です。
申請の仕組みを知ることで、安心して制度を活用できるようになります。
受給額が減額される可能性
制度によっては、他の給付金や収入との関係で減額調整が行われる場合があります。
たとえば、傷病手当金と障害年金を同時に受ける場合は、金額が調整され差額分のみが支給されます。
また、会社から一部給与が支給されている場合、その分が差し引かれることもあります。
生活保護を受給している場合は、障害年金や手当を収入として扱い、保護費が減額される仕組みです。
「もらえると思っていた金額と違った」とならないよう、事前に各制度の調整ルールを確認することが大切です。
必要に応じて専門家に相談して見通しを立てると安心です。
支給終了後に備える工夫
傷病手当金は最長1年6か月、障害年金も更新が必要であり、永続的に保証されるとは限りません。
そのため、支給が終了した後の生活をどう維持するかをあらかじめ考えておくことが重要です。
具体的には、復職やリワークプログラムを利用して社会復帰を目指す、就労支援を活用する、生活費の見直しを行うなどが挙げられます。
また、制度の終了が近づいたら早めに次の制度(障害年金や生活保護など)の申請準備をすることも大切です。
「支給が止まったらどうしよう」と不安になる前に、複数の選択肢を検討しておくことが安心につながります。
支給終了後を見据えた準備が、長期的な生活の安定を支える鍵になります。
よくある質問(FAQ)

Q1. うつ病の給付金はいくらぐらいもらえますか?
うつ病の給付金として代表的なのは「傷病手当金」と「障害年金」です。
傷病手当金は休職前の給与の約3分の2が支給され、1日あたりの金額は「標準報酬日額×2/3」で計算されます。
例えば月収30万円の人であれば、月額約20万円が最長1年6か月支給される計算です。
障害年金は等級によって金額が異なり、2級で年間約97万円(基礎年金の場合)、1級で年間約122万円程度が目安です。
厚生年金に加入している人はこれに報酬比例分が加算されるため、さらに支給額は増えます。
制度によって支給額は変わるため、自分の加入状況を確認することが重要です。
Q2. 傷病手当金と障害年金は同時に受けられますか?
傷病手当金と障害年金は併用自体は可能ですが、そのまま満額が両方支給されるわけではありません。
健康保険組合が傷病手当金を支給する際、障害年金を受け取っている場合はその分が差し引かれます。
例えば傷病手当金の支給額が月15万円で、障害年金が月8万円の場合、差額の7万円が支給される形です。
つまり「併用できるが、調整される」という仕組みになっています。
そのため、どちらかを諦める必要はなく、両方申請することが大切です。
不明点があれば、健康保険組合や年金事務所に確認すると安心です。
Q3. うつ病の手当は会社に知られますか?
傷病手当金を申請する場合は、会社の証明が必要になるため、申請自体は会社に伝わります。
ただし、健康保険組合に提出する医師の診断書の内容がそのまま会社に伝わるわけではありません。
会社が知るのは「労務不能である」という事実であり、病名や詳細な症状が開示されることは基本的にありません。
一方で障害年金や生活保護は会社を通さず申請するため、勤務先に知られることはありません。
プライバシーに配慮されている制度ではありますが、不安な場合は医師や窓口に「どこまで会社に伝わるのか」を確認しておくと安心です。
安心して申請するためにも、情報共有の仕組みを理解しておきましょう。
Q4. 自宅療養中でも手当はもらえますか?
はい、自宅療養中でも手当を受け取ることは可能です。
傷病手当金は「療養のために働けない状態」であれば、自宅で療養していても支給の対象になります。
ただし、医師が「労務不能」と診断していることが前提です。
障害年金についても、日常生活や就労に著しい制限がある場合は、自宅療養中であっても対象となります。
「入院していなければ受給できない」と誤解している人もいますが、自宅療養中でも申請は可能です。
重要なのは、医師の診断書で「就労困難」と示されていることです。
Q5. 受給できない場合の代替制度は?
給付金や手当が不支給になった場合でも、利用できる代替制度はいくつかあります。
代表的なのは生活保護で、最低限度の生活を保障する制度です。
また、自立支援医療制度を利用すれば、通院や薬代の自己負担を大幅に軽減できます。
さらに、精神障害者保健福祉手帳を取得すれば、税控除や公共料金の割引といった優遇を受けられます。
傷病手当金や障害年金が受け取れなかった場合でも、これらの制度を活用することで経済的負担を減らすことが可能です。
困ったときは、必ず自治体の窓口や専門家に相談してみましょう。
うつ病の給付金はいくらかを把握し制度を活用しよう

うつ病で働けなくなったときに頼れる給付金や手当は、傷病手当金や障害年金をはじめとして複数あります。
「いくらもらえるのか」を正しく把握し、自分に適した制度を選ぶことが安心につながります。
また、制度によっては併用や調整が必要になるため、仕組みを理解したうえで申請することが大切です。
さらに、給付金が不支給となった場合でも、生活保護や医療費軽減制度など他の支援が用意されています。
経済的不安を減らすために、複数の制度を上手に活用しながら療養に専念しましょう。
「正しい情報」と「早めの行動」が、生活の安定と回復への第一歩になります。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。