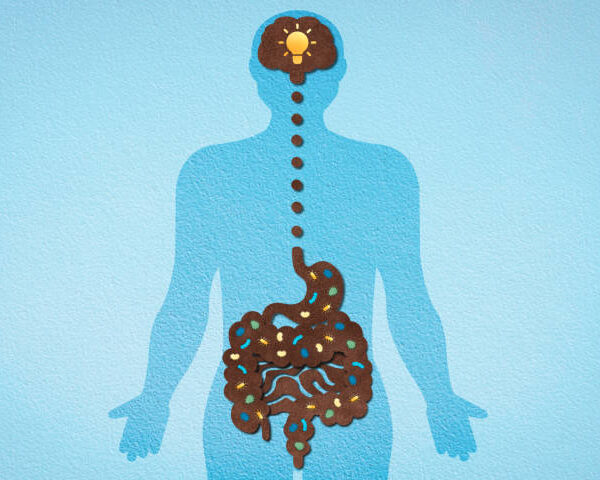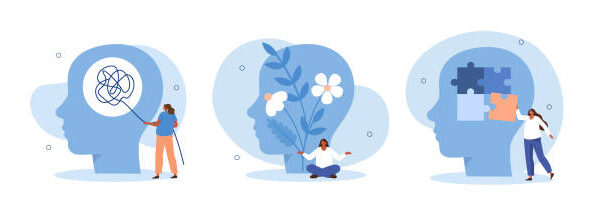「もう何もかもが嫌になる」と感じるとき、人は心身の限界に近づいていることがあります。
一時的なストレスや疲労であれば休養や気分転換で回復することもありますが、気持ちが長く続く場合は病気のサインや心理的な問題が隠れていることも少なくありません。
例えば、うつ病・適応障害・自律神経失調症・燃え尽き症候群などが背景にあることがあり、放置すると悪化するリスクもあります。
また、「何もかもが嫌になる」という心理には、完璧主義・孤独感・承認欲求の不足といった心の背景が関わるケースも多くあります。
本記事では、「何もかも嫌になる」という感情の原因や関係する病気、心理的要因、そして改善に向けたセルフケアや専門家への相談の目安を分かりやすく解説します。
「どうすれば抜け出せるのか」「これは病気なのか」と悩んでいる方に、役立つ情報をお届けします。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。
「何もかもが嫌になる」とはどんな状態?

「何もかもが嫌になる」という感情は、誰にでも一度は訪れる可能性があります。
大きなストレスを抱えたときや、心身が疲れ切っているときに現れやすいものであり、必ずしも病気と直結するわけではありません。
しかし、この状態が長期間続いたり日常生活に支障をきたす場合は、心の不調のサインである可能性もあります。
ここでは「何もかもが嫌になる」と感じるときに考えられる状態を整理します。
- 一時的なストレス反応
- 慢性的な心身の疲労によるもの
- 病気のサインとして現れる場合
- 「何もかもが嫌になる」と口にする心理的背景
自分の状態を理解することが、回復のための第一歩となります。
一時的なストレス反応
強いストレスを受けると、脳や体が過敏に反応し「もう何もかも嫌だ」と感じることがあります。
例えば、仕事や学業で大きな失敗をしたとき、人間関係でトラブルがあったときなど、短期間で強いストレスがかかると、一時的にすべてを投げ出したくなるのです。
この場合、多くは休養をとる、リフレッシュすることで気持ちが落ち着き、自然に回復します。
一過性の反応であれば深刻に捉える必要はありませんが、繰り返す場合には注意が必要です。
「ストレスに対する正常な反応」である一方、放置すると慢性化する恐れもあるため、早めのセルフケアが大切です。
慢性的な心身の疲労によるもの
長期間の疲労が蓄積すると、心も体もエネルギーを消耗し「何もかもが嫌になる」と感じやすくなります。
十分な睡眠が取れない、栄養が偏る、休む時間がないといった生活習慣の乱れが続くと、脳の働きが低下して意欲が失われます。
特に育児や介護、過密な仕事スケジュールの中では、慢性的な疲れが心の不調を引き起こしやすいのです。
「何もやりたくない」「起きるのもつらい」と感じるときは、身体の疲れが限界に達しているサインです。
休息と生活リズムの見直しが回復の第一歩となります。
病気のサインとして現れる場合
「何もかもが嫌になる」という感覚が長期間続く場合、心の病気の症状である可能性があります。
代表的なのはうつ病で、抑うつ気分や無気力感が特徴的です。
また、強いストレス反応で起こる適応障害や、心身のバランスが崩れる自律神経失調症でも、同じように何もかもが嫌に感じられることがあります。
さらに、仕事や育児で過剰な負担を抱えた人が陥る燃え尽き症候群も要注意です。
「休んでも回復しない」「何週間も気分が晴れない」といった場合は、病気の可能性を視野に入れて専門家に相談しましょう。
「何もかもが嫌になる」と口にする心理的背景
「何もかも嫌だ」という言葉には、その人の深い心理が隠れています。
完璧主義で自分を追い込みすぎている人は、少しの失敗で全てが無意味に感じてしまいます。
また、孤独感や人間関係のストレスが背景にある場合、「誰にも分かってもらえない」という気持ちが「すべて嫌」という表現につながります。
承認欲求が満たされないことや、努力が報われない経験も「もう嫌だ」という感情を強めます。
この言葉自体がSOSであることを理解し、本人も周囲も放置せずに向き合うことが重要です。
「何もかもが嫌になる」と関係する病気

「何もかもが嫌になる」という感覚は、一時的なストレス反応として誰にでも起こり得ます。
しかし、気持ちが長期間続いたり、生活に支障をきたす場合は心の病気のサインである可能性が高まります。
ここでは代表的に関連する病気を整理し、それぞれの特徴を解説します。
- うつ病(抑うつ気分・無気力)
- 適応障害(強いストレスに対する反応)
- 自律神経失調症(心身の不調と倦怠感)
- 燃え尽き症候群(仕事や育児での疲弊)
- 不安障害(強い不安や緊張が背景にあるケース)
- 双極性障害(気分の波と無気力感)
該当する症状がある場合は、早めに専門機関への相談を検討しましょう。
うつ病(抑うつ気分・無気力)
うつ病は「何もかも嫌になる」と感じる最も代表的な病気です。
主な特徴は抑うつ気分と無気力で、以前は楽しめたことにも興味を持てなくなります。
朝起きられない、強い倦怠感が続く、集中力が落ちるなど、心と体の両方に症状が現れるのが特徴です。
放置すると日常生活が立ち行かなくなることもあり、重症化する前に治療を受けることが重要です。
抗うつ薬や心理療法による治療で改善が期待できる病気です。
適応障害(強いストレスに対する反応)
適応障害は、仕事や学校、家庭など特定のストレス要因に対して心身が過敏に反応し、不調をきたす病気です。
「職場に行くと気持ちが沈む」「特定の人に会うのが怖い」といった状況依存的な症状が特徴です。
不安や落ち込みだけでなく、不眠や頭痛など身体症状も伴うことがあります。
ストレス源から離れると症状が改善することが多いですが、放置するとうつ病に移行するリスクもあります。
適切な休養や心理的サポートを受けることが回復への第一歩となります。
自律神経失調症(心身の不調と倦怠感)
自律神経失調症は、交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、心身にさまざまな不調を引き起こす状態です。
強い疲労感、めまい、動悸、胃腸の不調など、検査では異常が見つからないのに症状が続くのが特徴です。
この状態では「体がつらいから何もかも嫌だ」と感じやすくなります。
ストレスや生活リズムの乱れが主な原因であり、休養や生活習慣の見直しが重要です。
心療内科での診断や治療により改善が期待できます。
燃え尽き症候群(仕事や育児での疲弊)
燃え尽き症候群は、仕事や育児などに過度なエネルギーを注いだ結果、心身が枯渇してしまう状態です。
「もう頑張れない」「何もしたくない」と感じる典型的な状況で、まさに「何もかもが嫌になる」という表現が当てはまります。
特に真面目で責任感の強い人、看護師や教師など対人援助職、育児中の母親に多く見られます。
症状が進むと抑うつ症状に移行することがあり、早期のケアが必要です。
十分な休養と心理的サポートを得ることが改善のカギとなります。
不安障害(強い不安や緊張が背景にあるケース)
不安障害は、日常生活に支障をきたすほどの強い不安や恐怖が繰り返し現れる病気です。
不安が続くことで、集中できない、眠れない、外出が怖いなどの症状が出ます。
「不安で何も手につかない」「全部嫌になる」という気持ちが強くなることがあります。
不安障害には社交不安障害やパニック障害など複数のタイプがあり、いずれも早期の治療が大切です。
薬物療法や認知行動療法で改善が期待できる病気です。
双極性障害(気分の波と無気力感)
双極性障害は、躁状態(気分が高揚し活動的になる時期)と、うつ状態(気分が落ち込み何もかも嫌になる時期)が交互に現れる病気です。
特にうつ状態のときには、強い無気力感や絶望感が表れ「すべて投げ出したい」と感じることがあります。
一時的に調子が良い時期があっても、再び気分が落ち込むため、本人や周囲が混乱しやすいのが特徴です。
適切な薬物療法や心理的支援により、気分の波を安定させることが可能です。
気分の変動が激しい人は、双極性障害の可能性も考え、専門医に相談することが大切です。
「何もかもが嫌になる」ときの心理背景

「何もかもが嫌になる」という気持ちは、必ずしも病気だけが原因ではありません。
人の心は環境や性格、過去の経験などさまざまな要素に影響されるため、心理的な背景が大きく関わることもあります。
特に強いストレスやプレッシャー、完璧主義、人間関係の問題は、この感情を引き起こしやすい要因です。
ここでは代表的な心理背景を整理します。
- 強いストレスやプレッシャー
- 完璧主義や自己否定感
- 人間関係のトラブルや孤独感
- 承認欲求が満たされない心理
- 過去のトラウマや挫折経験の影響
心理的背景を理解することで、自分の心の状態を客観的に見つめ直す手がかりになります。
強いストレスやプレッシャー
過度なストレスやプレッシャーは「何もかも嫌になる」という感情の大きな原因です。
仕事の納期、受験、家庭での役割など、自分に課せられる負担が大きすぎると心は限界に近づきます。
一時的であれば休息で回復できますが、慢性的に続くと気力を奪い「すべて嫌だ」という感情に直結します。
また、自分で課したハードルが高すぎる場合も同様にストレスを生みます。
ストレスを溜め込みすぎていないかを見直すことが必要です。
完璧主義や自己否定感
完璧主義の人は、少しのミスでも「自分はダメだ」と感じやすく、心が疲弊しやすい傾向があります。
常に完璧を求めて努力しても、その成果を認められないと虚無感に襲われます。
また、失敗をきっかけに自己否定感が強まり「全部投げ出したい」という気持ちに変わります。
自分に厳しすぎると、心に余裕がなくなり「何もかも嫌になる」心理に直結します。
「完璧でなくてもいい」と認めることが予防につながります。
人間関係のトラブルや孤独感
人間関係の問題は、心のエネルギーを大きく消耗させます。
職場や学校でのいじめ、家庭での不和、友人関係のすれ違いなどは、強い孤独感や無力感を生みます。
「誰も自分を理解してくれない」という気持ちは「何もかも嫌になる」という表現につながりやすいのです。
孤立が長引くと、自己価値感の低下にも直結します。
信頼できる人とのつながりを持つことが、心を守る大切な鍵になります。
承認欲求が満たされない心理
人は誰しも承認欲求を持っています。
努力を認められなかったり、存在を肯定されない環境にいると「自分は価値がない」と感じやすくなります。
この気持ちが積み重なると「何をやっても報われない」「何もかも嫌になる」という心理に変わっていきます。
承認欲求が満たされないと、無力感や劣等感が強まり、心のバランスを崩しやすくなります。
小さな成功体験を積み重ねることが、心の回復に役立ちます。
過去のトラウマや挫折経験の影響
過去のトラウマや挫折経験は、心の奥に残り続け「何もかも嫌になる」感情を引き起こす引き金になることがあります。
失敗体験や人間関係での裏切りなどは、新しい挑戦や人付き合いに消極的にさせる要因になります。
また、過去のつらい出来事を思い出すことで、現在の出来事にも「どうせうまくいかない」と感じやすくなります。
この心理は自己肯定感を下げ、前に進む力を奪います。
過去の経験を整理する心理療法などが有効になる場合もあります。
日常生活で見られるサイン

「何もかもが嫌になる」という気持ちは、日常の行動や習慣に具体的な変化として表れることがあります。
それは一時的な疲労や気分の落ち込みに過ぎない場合もありますが、長く続くと心の病気のサインである可能性もあります。
ここでは、生活の中で気づきやすい代表的なサインを紹介します。
- 朝起きられない・会社や学校に行きたくない
- 好きだったことに興味を持てない
- 食欲や睡眠のリズムが乱れる
- 人と会うのが億劫になる
これらのサインに当てはまる場合、早めにセルフケアや専門家への相談を検討することが大切です。
朝起きられない・会社や学校に行きたくない
朝起きることがつらい、あるいは会社や学校に行きたくないと強く感じるのは、心が疲れているサインです。
一時的な疲労であれば休息をとれば回復しますが、何日も続く場合は注意が必要です。
特に「布団から出られない」「行かなければならないのに体が動かない」という状態は、うつ病や適応障害などの病気の兆候である可能性があります。
強い倦怠感は心身からのSOSであり、無理に頑張り続けると悪化することがあります。
「朝起きられないのは怠けではなく症状」と理解することが大切です。
好きだったことに興味を持てない
以前は楽しくできていた趣味や仕事に興味を持てなくなるのも、心の不調のサインです。
これは抑うつ気分の代表的な特徴で、エネルギーが低下し「やりたい」という気持ちが湧いてこなくなります。
音楽を聴いても楽しめない、好きだった食べ物に関心が持てないなど、喜びや快楽を感じにくくなる状態です。
この変化は本人だけでなく、周囲から見ても「最近元気がない」と気づかれることがあります。
楽しめないこと自体が症状であるため、早めの対処が必要です。
食欲や睡眠のリズムが乱れる
食欲や睡眠の乱れは、心と体が限界に近づいているサインです。
食欲が極端に減る、逆に過食気味になるといった変化は、心の不安定さを反映しています。
また、夜眠れない、途中で目が覚める、朝早く目が覚めてしまうなどの不眠もよく見られます。
逆に眠りすぎてしまう過眠傾向も心の不調と関連しています。
食欲と睡眠は心身のバロメーターであり、崩れが続く場合は専門家への相談が勧められます。
人と会うのが億劫になる
以前は普通にできていた人付き合いが億劫になるのもサインの一つです。
友人や同僚との会話を避けたくなる、家族と話すのも負担に感じるといった状態は、心が疲弊している証拠です。
人と会うことでエネルギーを消耗するため「一人になりたい」と思う時間が増えていきます。
孤立が進むとさらに気分が落ち込み「何もかも嫌になる」という悪循環に陥ります。
人とのつながりを断つことはリスクであり、信頼できる相手との交流を少しでも保つことが重要です。
セルフケアでできる対処法

「何もかもが嫌になる」と感じたとき、まず大切なのは心と体を休め、自分をケアすることです。
症状が強い場合や長引く場合は専門家の治療が必要ですが、軽度であればセルフケアで回復をサポートできることもあります。
ここでは、日常生活で取り入れやすいセルフケアの方法を紹介します。
- 睡眠・食事・運動で生活リズムを整える
- ネガティブな情報から距離を取る
- 信頼できる人に気持ちを話す
- リラクゼーションや趣味を取り入れる
- 小さな成功体験を積み重ねる
日々の習慣を少しずつ整えることで、心のバランスを取り戻しやすくなります。
睡眠・食事・運動で生活リズムを整える
生活リズムは心の安定と深く関わっています。
睡眠不足や不規則な食事、運動不足が続くと、自律神経が乱れ「何もかも嫌だ」と感じやすくなります。
夜はなるべく同じ時間に眠り、朝は太陽の光を浴びて体内時計を整えることが大切です。
また、栄養バランスの取れた食事と、散歩や軽いストレッチなど無理のない運動が、心身の回復に役立ちます。
体を整えることが心のケアにつながると意識してみましょう。
ネガティブな情報から距離を取る
SNSやニュースなどから流れるネガティブな情報は、心に大きな負担を与えます。
他人と自分を比べる投稿を見て落ち込んだり、刺激の強い情報に触れて不安が増すことは少なくありません。
「見ない時間」を意識的に作るだけで、心の疲労を減らすことができます。
ポジティブな音楽や本、リラックスできる映像など、自分の心が休まるコンテンツに触れることも効果的です。
情報との距離を整えることが、気持ちを安定させる鍵になります。
信頼できる人に気持ちを話す
気持ちを話すことは、心の負担を軽くする最もシンプルで効果的な方法です。
家族や友人、信頼できる人に「疲れている」「もう嫌だ」と言葉にするだけでも安心感が生まれます。
話すことで気持ちが整理され、解決策が見つかることもあります。
一人で抱え込むと孤独感が強まり悪循環になるため、早めに共有することが大切です。
「誰かに話すことがセルフケア」だと捉えましょう。
リラクゼーションや趣味を取り入れる
リラクゼーションや趣味は、心をリセットする効果があります。
深呼吸や瞑想、アロマテラピー、ヨガなどは自律神経を整え、心を落ち着けるのに役立ちます。
また、音楽を聴く、絵を描く、自然の中を散歩するなど、自分が心地よいと感じる活動を取り入れることも効果的です。
「やらなければならない」ことから一時的に距離を取ることで、エネルギーが回復します。
「自分を癒す時間」を持つことを意識しましょう。
小さな成功体験を積み重ねる
小さな成功体験は自己肯定感を回復させる力になります。
部屋を少し片付ける、短時間でも散歩に出る、簡単な料理を作るなど、できたことに注目しましょう。
「これができた」と感じる体験が、心の回復に大きくつながります。
逆に「できないこと」ばかりに目を向けると、気持ちはますます沈んでしまいます。
小さな達成を積み重ねることが、前向きな気持ちを取り戻す近道です。
医師や専門家に相談すべきサイン

「何もかもが嫌になる」という気持ちは誰にでも起こり得るものですが、一定のラインを超えたときには専門的なサポートが必要になります。
一時的な気分の落ち込みであればセルフケアで回復することもありますが、症状が長引いたり強くなる場合は心の病気が隠れている可能性があります。
ここでは、医師やカウンセラーなど専門家に相談すべき代表的なサインを紹介します。
- 気分の落ち込みが2週間以上続く
- 仕事や学校・家庭生活に支障が出ている
- 強い不安や「消えたい」と思う気持ちがある
- 自分で改善できないと感じる
- 家族や周囲から心配されるレベルになっている
これらのサインを無視せず、早めに相談することで回復のきっかけをつかむことができます。
気分の落ち込みが2週間以上続く
2週間以上気分の落ち込みが続く場合、うつ病や適応障害などの病気の可能性があります。
「たまに落ち込む」程度であれば一時的なものですが、長引く場合は自然回復が難しいことが多いです。
仕事や趣味に意欲がわかない、常に疲れている、涙もろいといった症状が重なっている場合は特に注意が必要です。
早期に治療を受けることで、回復も早くなる傾向があります。
「長引く落ち込みは専門家に相談」を合図にしましょう。
仕事や学校・家庭生活に支障が出ている
生活に支障が出るほどの気分の落ち込みや無気力は、深刻なサインです。
仕事に集中できない、学校に行けない、家事や育児が手につかないなど、日常生活の基本的な活動に影響が出ている場合は早急な対応が必要です。
周囲から見ても「以前と違う」と分かるほど変化があるときは、心が限界に近づいている証拠です。
自分を責めるのではなく「症状が生活に影響している」と冷静に捉え、専門機関に相談することが重要です。
強い不安や「消えたい」と思う気持ちがある
強い不安や「消えたい」「いなくなりたい」という気持ちは、心からの深刻なSOSです。
この状態を放置すると、自分や周囲に危険を及ぼす可能性もあります。
特に夜眠れない、食欲が落ちる、動悸がするなど身体症状を伴う場合は早急な対応が必要です。
こうした気持ちが出てきた時点で、すでにセルフケアだけでの改善は難しい段階にあります。
「消えたいと思ったらすぐ相談」を心に留めておきましょう。
自分で改善できないと感じる
「何をしても改善できない」と感じるときは、専門家に頼るべきサインです。
セルフケアを試しても効果がない、気分転換しても気持ちが晴れないという場合、心のエネルギーが大きく消耗している可能性があります。
自分だけで解決しようとすると、症状が悪化してしまうこともあります。
「これ以上は自分では無理」と感じたときに専門家を頼ることは、決して弱さではなく回復のための行動です。
安心して相談できる環境を探すことが大切です。
家族や周囲から心配されるレベルになっている
家族や友人から心配されるほど気分や行動に変化がある場合、自覚がなくても不調が進んでいる可能性があります。
「最近元気がない」「笑顔が減った」「様子がおかしい」と指摘されることが増えたら注意が必要です。
自分では「大丈夫」と思っていても、客観的に見た周囲の目は正確なことが多いです。
周囲の心配を無視せず、相談を受け入れることが大切です。
「周囲の目は大切なサイン」と捉え、早めに専門家にアクセスしましょう。
子ども・若い世代に見られるケース

「何もかもが嫌になる」という感情は、大人だけでなく子どもや若い世代にも見られます。
思春期や成長過程では心がまだ未熟であるため、ストレスや人間関係の影響を強く受けやすいのです。
特に受験や部活動、SNSなど現代特有の要因が重なることで、強い無気力感や孤独感に陥ることがあります。
ここでは、子どもや若い世代に多く見られる具体的なケースを紹介します。
- 受験や部活動での過度なストレス
- 友人関係・SNSトラブルによる心理的負担
- 親ができる声掛けやサポート
早めに気づいて適切な対応を取ることが、将来の心の健康を守ることにつながります。
受験や部活動での過度なストレス
受験や部活動は、子どもや学生にとって大きなプレッシャーとなります。
学業での成果を求められる受験期や、部活動での大会・試合に向けた厳しい練習は、心身に大きな負担を与えます。
「頑張らなければ」「失敗できない」と自分を追い込みすぎると、エネルギーが枯渇し「何もかも嫌になる」と感じやすくなります。
また、教師や親の期待が重荷になることも少なくありません。
過度なプレッシャーが続く場合は、学習環境や休養の取り方を見直す必要があります。
友人関係・SNSトラブルによる心理的負担
友人関係のもつれやSNSトラブルも、若い世代にとって深刻な心理的ストレスです。
学校でのいじめや仲間外れ、SNSでの誹謗中傷や比較は、自己肯定感を大きく傷つけます。
「自分は必要とされていない」「どこにも居場所がない」という孤独感が「何もかも嫌だ」という感情につながります。
スマートフォンやSNSが生活の一部になっている現代では、逃げ場がないと感じやすいのも特徴です。
情報との距離感を整えることが、心を守る第一歩となります。
親ができる声掛けやサポート
親の関わり方は、子どもや若い世代の心の安定に大きな影響を与えます。
「どうしてできないの」と責めるのではなく、「大変だったね」「よく頑張っているね」と共感する姿勢が重要です。
また、勉強や部活の成果だけでなく、子どもの努力そのものを認めてあげることが安心感につながります。
心配なサインを感じたときには、無理に問い詰めず、安心して話せる環境をつくることが大切です。
親の温かい声掛けやサポートが、子どもにとって「自分は一人ではない」という安心につながります。
よくある質問(FAQ)

Q1. 「何もかも嫌になる」は病気の前触れですか?
「何もかも嫌になる」という感情は、必ずしも病気を意味するわけではありません。
一時的な疲労やストレスで誰にでも起こり得る自然な反応です。
しかし、その状態が2週間以上続く、または日常生活に支障をきたしている場合は、うつ病や適応障害など心の病気の前触れである可能性があります。
特に、食欲や睡眠の変化、強い無気力感を伴う場合は注意が必要です。
早期に気づいて専門家に相談することが、悪化を防ぐために重要です。
Q2. 自分で治すことはできますか?
軽度の場合は、休養を取る、生活リズムを整える、信頼できる人に話すなどのセルフケアで改善できることもあります。
特に睡眠・食事・運動のバランスを見直すことは効果的です。
しかし、強い無気力感や「消えたい」と思う気持ちがある場合は、自分だけで解決しようとするのは危険です。
セルフケアで改善しない場合は、医師やカウンセラーの助けを借りることが必要です。
無理に一人で抱え込まず、早めに専門家を頼ることが大切です。
Q3. 気分が落ち込むのと「うつ病」の違いは?
気分の落ち込みは誰にでもある自然な感情で、数日休めば回復することが多いです。
一方でうつ病は医学的な病気であり、抑うつ気分や無気力が2週間以上持続し、仕事や生活に支障を及ぼします。
また、趣味や好きなことに興味を持てなくなる「興味・喜びの喪失」も大きな特徴です。
単なる気分の落ち込みと区別が難しい場合は、自己判断せず専門家に相談することが大切です。
早期の診断と治療によって回復が期待できます。
Q4. 誰に相談すればいいですか?
まずは信頼できる身近な人に気持ちを話してみましょう。
家族や友人に「疲れている」「何もかも嫌だ」と伝えるだけでも心が軽くなります。
専門的に相談する場合は、心療内科や精神科、またはカウンセラーや公的な相談窓口があります。
最近ではオンラインカウンセリングや電話相談も利用でき、匿名で話せるサービスもあります。
「誰かに話すこと」が改善の第一歩となります。
Q5. 再発を防ぐためにできることは?
再発防止には、無理をせず自分の限界を知ることが大切です。
睡眠・食事・運動など生活習慣を整え、定期的にストレスを発散することが効果的です。
また、小さな成功体験を積み重ねることで自己肯定感を育むことも予防につながります。
再発しやすい人は、ストレスが溜まったときに早めに相談できる環境を整えておくと安心です。
「頑張りすぎない」ことを習慣化するのが最大の予防策です。
「何もかもが嫌になる」は心のSOSに気づくチャンス

「何もかも嫌になる」という感情は、心が限界を迎えているサインかもしれません。
一時的であれば休養やセルフケアで回復できますが、長く続く場合は病気の可能性があります。
大切なのは「自分が弱いから」と責めるのではなく、「心が助けを求めている」と受け止めることです。
一人で抱え込まず、家族や専門家に相談することが早期回復につながります。
SOSに気づくことこそが回復への第一歩です。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。