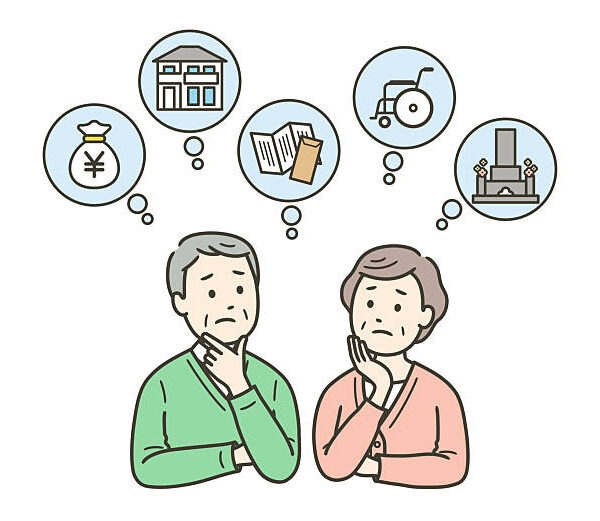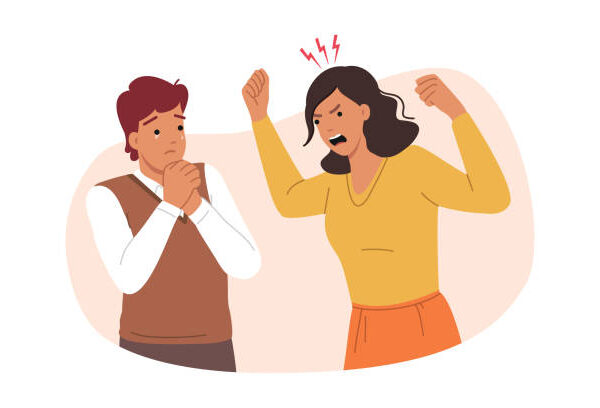双極性障害は、気分の波が大きく「躁状態」と「抑うつ状態」を繰り返す精神疾患です。
日常生活の中で「急にテンションが高くなる」「買い物を衝動的にしてしまう」「ベッドから出られない」といった行動は、双極性障害あるあるとしてよく語られます。
しかし、これらは単なる性格の問題や怠けではなく、病気の特徴的な症状であることを理解する必要があります。
本人はコントロールできず苦しんでいる一方で、周囲からは誤解されやすいのも大きな特徴です。
本記事では、双極性障害に見られる「あるある行動」や誤解されやすい特徴を解説し、正しい理解と支援のあり方を紹介します。
「自分や家族に当てはまるかもしれない」と感じた方にとって、早期の気づきや適切な対応につながる情報をまとめています。
心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。
双極性障害とは?基本知識

双極性障害は、かつて「躁うつ病」と呼ばれていた精神疾患で、気分の波が大きく変動するのが特徴です。
「躁状態」と「抑うつ状態」が交互に訪れ、日常生活や社会生活に深刻な影響を及ぼします。
一見すると単なる気分の浮き沈みに見えるため、周囲から誤解されやすいのも特徴です。
ここでは、双極性障害の定義や他の精神疾患との違い、日本での有病率や発症年齢の傾向を解説します。
- 双極性障害の定義(躁状態と抑うつ状態の繰り返し)
- 統合失調症やうつ病との違い
- 日本での有病率と発症年齢の特徴
基本的な理解を持つことで、「双極性障害あるある」と呼ばれる行動や体験談の背景を正しく捉えることができます。
双極性障害の定義(躁状態と抑うつ状態の繰り返し)
双極性障害とは、気分が異常に高揚する「躁状態」と、気分が極端に落ち込む「抑うつ状態」が繰り返し現れる病気です。
躁状態では、睡眠時間が少なくても活動的に動けたり、多弁になったり、浪費や衝動的な行動が増えるのが特徴です。
一方、抑うつ状態では強い疲労感や無気力感に襲われ、ベッドから出られない、集中できないといった症状が見られます。
これらが周期的に繰り返されるため、本人はもちろん、周囲の人も対応に苦労することが少なくありません。
双極性障害は一時的な気分の変化ではなく、医学的に治療が必要な精神疾患です。
放置すれば社会生活や人間関係に大きな影響を与えるため、早期発見と治療が不可欠です。
統合失調症やうつ病との違い
双極性障害は「気分障害」の一つであり、統合失調症やうつ病とは区別されます。
うつ病は「気分の落ち込み」が中心で、躁状態は現れません。
これに対し、双極性障害では躁状態と抑うつ状態が交互に出現し、気分の変動が大きい点が異なります。
統合失調症は幻覚や妄想といった「現実認識の障害」が主症状であり、双極性障害とは診断基準が異なります。
ただし、抑うつ状態が長く続くと「うつ病」と誤診されることも多いため、正確な診断には専門的な評価が欠かせません。
双極性障害を正しく理解し、他の疾患と区別することが治療方針を決める上で重要です。
日本での有病率と発症年齢の特徴
日本における双極性障害の有病率は、人口の約0.5〜1%と推定されています。
決して稀な病気ではなく、誰でも発症する可能性があります。
発症の多くは10代後半から30代前半にかけて見られ、若い世代に多いのが特徴です。
初期にはうつ病と診断されやすいため、双極性障害と気付かれずに適切な治療が遅れるケースも少なくありません。
また、男女差はほとんどなく、どちらも同じくらいの頻度で発症します。
早期に正しい診断を受けることで、再発予防や生活の安定につながるため、若い世代への啓発が特に重要です。
双極性障害あるある|日常で見られる行動や特徴

双極性障害の特徴は、躁状態と抑うつ状態が繰り返し現れることにあります。
そのため日常生活には特有の「あるある」と呼ばれる行動パターンが見られます。
ここでは、双極性障害に多い日常の「あるある」を詳しく紹介します。
- 躁状態のあるある(多弁・買い物の衝動・睡眠不足でも元気)
- 抑うつ状態のあるある(ベッドから出られない・集中できない)
- 周囲が戸惑うギャップ(昨日まで元気だったのに急に落ち込む)
これらを理解することで、本人や周囲が病気のサインに早く気付けるようになります。
躁状態のあるある(多弁・買い物の衝動・睡眠不足でも元気)
躁状態に入ると、多弁になり会話が止まらなくなるのは典型的な「あるある」です。
次々とアイデアが浮かび、話題が絶えないため、周囲は圧倒されることもあります。
また、衝動的に高額な買い物をしてしまう浪費行動もよく見られます。
さらに、通常なら疲れるはずの睡眠不足でも「平気」と感じ、活動的に動き回ることがあります。
本人は調子が良いと感じていますが、実際には病気の症状であり、その後に抑うつ状態が訪れるリスクを高めています。
躁状態の「元気さ」は魅力的に見える反面、周囲とのトラブルや生活破綻につながる危険を含んでいます。
抑うつ状態のあるある(ベッドから出られない・集中できない)
抑うつ状態では、ベッドから起き上がれないほどの倦怠感や無気力感に襲われることがあります。
どんなに休んでも疲れが取れず、朝起きること自体が大きな負担となります。
また、頭が働かず集中力が低下するため、勉強や仕事に大きな支障が出るのも特徴です。
趣味や好きなことにすら興味を持てなくなり、「何もできない自分」を責めてしまう傾向もあります。
こうした状態は怠けや気分の問題ではなく、双極性障害に伴う抑うつ症状であることを理解することが重要です。
適切な治療や休養によって改善が見込めるため、早めに専門家へ相談することが大切です。
周囲が戸惑うギャップ(昨日まで元気だったのに急に落ち込む)
双極性障害あるあるの一つに、気分の急激な変化によるギャップがあります。
昨日まで非常に元気で活発に過ごしていた人が、翌日にはベッドから出られないほど落ち込むというケースです。
周囲からは「どうしてそんなに変わるのか」と理解しにくく、本人も自分をコントロールできず苦しみます。
このような気分の落差は「二重人格」と誤解されることもありますが、実際には脳の気分調整機能に関連する病気の症状です。
このギャップは人間関係や仕事にも大きな影響を及ぼし、本人を孤立させてしまう原因になることもあります。
周囲が正しい知識を持ち、気分の変化を病気として理解することが、支援や共感につながります。
双極性障害で誤解されやすい「あるある」

双極性障害は、外から見ると一見「性格の問題」や「気分の変化が激しい人」と誤解されやすい病気です。
特に抑うつ状態や躁状態に見られる行動は、周囲から正しく理解されないまま評価されてしまうことがあります。
その結果、本人がさらに孤立したり、支援が遅れて症状が悪化するケースも少なくありません。
ここでは、双極性障害で特に誤解されやすい「あるある」を紹介し、正しい理解のためのポイントを解説します。
- 怠けていると誤解される抑うつ状態
- 明るすぎる態度が「元気すぎる人」と思われる躁状態
- 「二重人格」と混同されやすい誤解
これらの誤解を解消することが、本人の安心と早期治療への第一歩につながります。
怠けていると誤解される抑うつ状態
双極性障害の抑うつ状態は、極端な無気力や倦怠感を伴います。
朝起きられない、仕事や学業に集中できない、外出が難しいといった症状が出やすくなります。
しかし、これらの行動は「怠けている」「やる気がない」と誤解されやすいのが現実です。
本人は動きたくても体と心がついてこず、自責の念に苦しんでいるケースが多く見られます。
抑うつ状態は意志の問題ではなく病気の症状であり、周囲が理解し支援することが不可欠です。
誤解を減らすためには「気持ちの問題ではなく医学的な症状」であることを伝える必要があります。
明るすぎる態度が「元気すぎる人」と思われる躁状態
躁状態では、活動的で社交的、明るすぎる態度が目立つようになります。
多弁になったり、冗談を連発したり、普段よりも積極的に行動するため、周囲からは「元気な人」「ムードメーカー」と見られることがあります。
しかし実際には、これは病気の症状であり、浪費やトラブルにつながる危険を抱えています。
躁状態は本人にとっても快感があり自覚が難しいため、病気と気付かれにくいのも特徴です。
「明るすぎる」行動がただの性格と誤解されると、治療や支援の機会が遅れる可能性があります。
正しく理解することで、早めに症状を見抜き、適切なサポートにつなげられます。
「二重人格」と混同されやすい誤解
双極性障害は、「二重人格」と誤解されることが少なくありません。
躁状態と抑うつ状態の気分の落差が激しいため、周囲からは「全く別の人に見える」と思われてしまうのです。
しかし、双極性障害は解離性同一性障害とは異なり、人格が分裂しているわけではありません。
気分やエネルギーの変動によって、行動や表情が大きく変化しているだけです。
この誤解が続くと「人格が不安定な人」とレッテルを貼られ、本人がさらに傷つくことになります。
正しい知識を広めることで、双極性障害を人格の問題ではなく治療可能な病気として理解できるようになります。
双極性障害の体験談に多い声

双極性障害の当事者の声には、日常生活に直結する具体的な「あるある」が数多く挙げられます。
躁状態では衝動的な行動に走りやすく、抑うつ状態では何もできなくなるといった両極端な経験が繰り返されます。
ここでは、体験談に多く見られる特徴的な声を整理し、具体的な「双極性障害あるある」として紹介します。
- 突然の浪費や衝動買い
- 人間関係のトラブル(言動が極端に変わる)
- 自分でもコントロールできない気分の波
これらの実例を知ることで、当事者の苦悩や生活のリアルさを理解しやすくなります。
突然の浪費や衝動買い
躁状態の「あるある」としてよく挙げられるのが、衝動的な浪費行動です。
普段なら考えないような高額な買い物をしたり、必要のない物を大量に購入してしまうことがあります。
クレジットカードを使いすぎて借金を抱えたり、家計を圧迫するほどの浪費に発展することも少なくありません。
本人はそのとき強い自信や高揚感を感じており、「これは必要だ」と思い込んでしまうため、自覚が難しいのが特徴です。
衝動買いが落ち着いた後に抑うつ状態へ移行すると、自己嫌悪や罪悪感に苦しむケースも多くあります。
このような浪費は「ただの金銭感覚の問題」ではなく、双極性障害の症状として理解することが必要です。
人間関係のトラブル(言動が極端に変わる)
双極性障害の体験談で多く語られるのが、人間関係のトラブルです。
躁状態では自信過剰になり、強気な発言や攻撃的な態度を取ることがあります。
一方で、抑うつ状態になると連絡を絶ったり、必要以上に落ち込んで消極的になるなど、真逆の行動を見せます。
この極端な変化により、周囲は「信用できない人」「気分屋」と感じ、関係が悪化することもあります。
本人も「昨日と言っていることが違う」と言われて悩むことが多く、自分のせいだと責めてしまいます。
しかしこれは性格の問題ではなく、病気による気分の変動が原因であるため、正しい理解が不可欠です。
自分でもコントロールできない気分の波
双極性障害の当事者が最も苦しむのは、気分の波を自分でコントロールできないという点です。
躁状態では気分が高揚し、睡眠を取らなくても活動的に動けるため、本人は「元気になった」と錯覚します。
しかしその後、急激に抑うつ状態に転じ、ベッドから起き上がれないほど落ち込むこともあります。
「また落ち込むのでは」という予期不安が強まり、日常生活の計画や人間関係に大きな支障をきたします。
本人が「頑張ろう」と思ってもどうにもならず、周囲の励ましすら負担になることもあります。
このように、自分の力ではコントロールできない気分の波こそが、双極性障害の最大の特徴であり、理解が求められる部分です。
周囲が気付くためのチェックポイント

双極性障害は本人が自覚しにくく、発症から診断までに時間がかかることが少なくありません。
そのため、家族や同僚、友人といった周囲が小さな変化に気付くことが、早期発見と治療開始の大きな鍵となります。
ここでは、周囲が注意して観察するべきチェックポイントを紹介します。
- 睡眠リズムの乱れに注目する
- テンションの高さと疲れの落差を見る
- 感情の起伏が極端で長期間続くかを観察する
これらを把握しておくことで、単なる性格や一時的な不調との違いに気付きやすくなります。
睡眠リズムの乱れに注目する
双極性障害では睡眠リズムの乱れが顕著に見られます。
躁状態ではほとんど寝なくても活動できる一方、抑うつ状態では長時間寝ても疲れが取れず、一日中ベッドから出られないことがあります。
また、夜更かしや早朝覚醒などの不規則な睡眠パターンが続くのも特徴です。
これらは一時的な不眠や生活習慣の乱れとは異なり、気分の波と連動して現れるのがポイントです。
本人は「たまたま寝られないだけ」と考えることが多いため、周囲が客観的に観察することが重要です。
睡眠リズムの変化は病気のサインとして非常に分かりやすいため、見逃さないことが早期対応につながります。
テンションの高さと疲れの落差を見る
双極性障害では、テンションの高さと疲れの落差が極端に表れます。
躁状態では非常に活動的で、普段以上に明るく積極的な行動を見せることがあります。
ところが数日後には急激にエネルギーが切れたように疲れ果て、抑うつ状態へ移行するケースが多く見られます。
この落差は本人だけでなく、周囲にとっても戸惑いや誤解を招きやすい部分です。
「昨日はあんなに元気だったのに、今日は全く別人のよう」という状況は双極性障害の典型例です。
気分や行動の落差を正しく理解することで、病気の可能性に早く気付くことができます。
感情の起伏が極端で長期間続くかを観察する
感情の起伏が激しく、それが数週間から数か月にわたって続く場合は双極性障害の可能性があります。
躁状態では自信過剰や怒りっぽさが目立ち、抑うつ状態では強い無気力や自己否定が続きます。
一時的な気分の浮き沈みとは異なり、病的なレベルで感情の変動が続くのが特徴です。
周囲からすると「気分屋」や「わがまま」に見えることもありますが、実際には病気による症状です。
この極端な感情の波を観察し記録しておくと、医師が診断する際にも役立ちます。
本人が気付かない場合でも、周囲の冷静な視点が病気の早期発見につながります。
双極性障害あるあると「病気としての理解」

双極性障害あるあるとして語られる行動や特徴は、単なる性格の問題や気分の浮き沈みではありません。
実際には脳の働きや神経伝達物質のバランスが関与する医学的な症状です。
そのため、正しい理解を持たずに放置すると、症状が悪化して社会生活や人間関係に深刻な影響を与える可能性があります。
一方で、医師の診断と適切な治療を受ければ、症状は改善し安定した生活を取り戻すことができます。
ここでは、双極性障害を「病気」として理解するためのポイントを解説します。
- 単なる性格ではなく脳の働きによる症状
- 放置すると悪化し社会生活に支障が出る
- 医師の診断と治療によって改善できる
「あるある」として共感される行動を、正しく医学的に捉えることが回復への第一歩となります。
単なる性格ではなく脳の働きによる症状
双極性障害は性格や気分の問題ではなく、脳の働きによる症状です。
脳内のセロトニンやドーパミンといった神経伝達物質のバランスが崩れることで、気分の波が生じます。
躁状態では過度な自信や活動性、衝動的な行動が出現し、抑うつ状態では無気力や絶望感が強まります。
こうした変化は本人の努力や意思で完全に制御できるものではありません。
周囲が「わがまま」や「怠け」と誤解してしまうことは、本人をさらに追い詰める要因となります。
双極性障害は医学的に治療可能な病気であると理解することが、支援や共感につながります。
放置すると悪化し社会生活に支障が出る
双極性障害を放置すると症状が悪化し、社会生活に深刻な影響を与えます。
躁状態では浪費やトラブル行為が増え、仕事や家庭に問題を引き起こすことがあります。
一方、抑うつ状態が続くと出勤できない、学業に取り組めないといった状況に陥りやすくなります。
症状が長期化すると、失業や人間関係の破綻、経済的困難など二次的な問題が拡大していきます。
さらに、自殺リスクも高まるため、早期対応が非常に重要です。
「様子を見よう」と放置するのではなく、病気として専門家に相談する姿勢が求められます。
医師の診断と治療によって改善できる
双極性障害は適切な診断と治療によって改善が可能です。
医師による問診や診断基準をもとに、気分安定薬や抗精神病薬などの薬物療法が行われます。
また、心理教育や認知行動療法を取り入れることで、気分の変動に対する対処法を学ぶことができます。
家族や周囲の理解を得ながら生活リズムを整えることも、再発予防に有効です。
治療を続けることで、仕事や学業を継続しながら安定した生活を送ることも十分に可能です。
「治らない病気」と悲観せず、早期に専門医へ相談し適切なサポートを受けることが大切です。
双極性障害の治療と対処法

双極性障害は自然に治るものではなく、適切な治療と長期的なサポートが必要な病気です。
治療の基本は薬物療法ですが、それに加えて心理的アプローチや周囲の支援が組み合わされることで安定を目指します。
ここでは、代表的な治療と対処法について整理して解説します。
- 薬物療法(気分安定薬・抗精神病薬)
- 認知行動療法や心理教育の重要性
- 家族・職場の理解と支援
これらをバランス良く取り入れることで、再発を防ぎ、安定した生活を送ることが可能になります。
薬物療法(気分安定薬・抗精神病薬)
双極性障害の治療の中心は薬物療法です。
気分安定薬(リチウム、バルプロ酸など)は、躁状態や抑うつ状態の波を抑え、再発を予防する効果があります。
躁状態が強い場合には抗精神病薬、抑うつ状態が長引く場合には抗うつ薬が補助的に使われることもあります。
ただし、抗うつ薬の単独使用は躁転(うつから躁への切り替わり)を引き起こすリスクがあるため、必ず医師の管理下で使用されます。
薬の効果が出るまでには時間がかかる場合もあり、副作用の管理も重要です。
自己判断で服薬をやめず、医師と相談しながら調整していくことが回復の近道になります。
認知行動療法や心理教育の重要性
薬物療法と並んで重要なのが認知行動療法(CBT)や心理教育です。
認知行動療法では、気分の変動に影響する考え方や行動のパターンを見直し、症状を悪化させない方法を学びます。
心理教育では、患者本人や家族が病気の特徴を正しく理解し、再発兆候に早く気付く力を養うことができます。
「気分の波が来たときにどう対応するか」をあらかじめ知っておくことで、症状の悪化を防ぎやすくなります。
薬だけに頼らず心理的なアプローチを取り入れることが、長期的な安定につながります。
病気への理解を深めることは、本人の自己肯定感を取り戻すうえでも非常に有効です。
家族・職場の理解と支援
双極性障害の治療には、本人だけでなく家族や職場の理解が不可欠です。
躁状態や抑うつ状態の症状は周囲に迷惑をかけることもありますが、それを「性格の問題」とせず、病気として理解する姿勢が重要です。
家族は本人を責めるのではなく、再発兆候に気付いたときに冷静に対応することが求められます。
また、職場では無理のない勤務体系や休養の機会を設けることで、長期的な就労を支えることが可能です。
孤立せず支援を受けながら生活できる環境を整えることが、治療の継続と再発予防につながります。
双極性障害は「一人で戦う病気」ではなく、周囲の支援を受けながら回復を目指す病気なのです。
よくある質問(FAQ)

双極性障害について調べている人の多くが、日常生活に関する「あるある」や症状の違いについて疑問を抱きます。
躁状態や抑うつ状態に見られる行動は一見わかりやすいですが、他の病気や性格との区別が難しいこともあります。
ここでは、よくある疑問に答える形で理解を深めていきます。
- Q1. 双極性障害の「あるある」行動は全員に当てはまりますか?
- Q2. 躁状態とただの「ハイテンション」はどう違うのですか?
- Q3. 双極性障害と境界性パーソナリティ障害の違いは?
- Q4. 家族が気付いた場合、どう接すればよいですか?
- Q5. 双極性障害は治るのですか?
日常に表れる「あるある」を正しく理解することが、誤解を防ぎ、本人や家族の安心につながります。
Q1. 双極性障害の「あるある」行動は全員に当てはまりますか?
双極性障害の「あるある」とされる行動は代表的な特徴ですが、全員に同じように当てはまるわけではありません。
例えば躁状態で浪費に走る人もいれば、仕事に過度に集中して休まないタイプの人もいます。
抑うつ状態においても、動けなくなる人もいれば、気分は落ち込んでいても表面上は普通に振る舞える人もいます。
つまり、「あるある」はあくまで傾向であり、個人差が大きいのが特徴です。
大切なのは「自分や家族の様子が典型例と違っても、病気の可能性を否定しない」ことです。
症状のパターンは人によって異なるため、気になる場合は専門医に相談するのが安心です。
Q2. 躁状態とただの「ハイテンション」はどう違うのですか?
躁状態と単なる「ハイテンション」には明確な違いがあります。
ハイテンションは一時的な気分の高揚であり、十分な睡眠や休養を取れば自然に落ち着きます。
一方、躁状態は脳の働きに異常があり、睡眠をほとんど取らなくても活動し続けたり、衝動的な浪費や攻撃的な言動が続いたりします。
また、躁状態は数日から数週間にわたって継続するため、日常生活や仕事に大きな支障をきたすのが特徴です。
本人には自覚が薄く「自分は元気で調子がいい」と感じやすいため、周囲の客観的な視点が重要です。
単なる気分の盛り上がりと違い、病気として治療が必要であることを理解することが大切です。
Q3. 双極性障害と境界性パーソナリティ障害の違いは?
双極性障害と境界性パーソナリティ障害は混同されやすい病気ですが、根本的に異なります。
双極性障害は脳の働きによる気分の波が中心で、躁状態と抑うつ状態を繰り返します。
一方、境界性パーソナリティ障害は対人関係や自己イメージの不安定さが特徴で、感情が数時間から数日の単位で激しく変わります。
つまり、双極性障害は「長期的な気分の変動」、境界性パーソナリティ障害は「瞬間的で対人関係に影響しやすい感情の波」が特徴です。
診断や治療法も異なるため、誤解せずに区別することが重要です。
正しい診断には専門医の評価が不可欠です。
Q4. 家族が気付いた場合、どう接すればよいですか?
家族が双極性障害のサインに気付いた場合は、責めずに寄り添う姿勢が大切です。
「怠けている」「性格のせい」と決めつけるのではなく、「最近つらそうだね」「一緒に病院に行ってみない?」と声をかけましょう。
本人は自分の行動をコントロールできず苦しんでいるため、共感的に支えることが回復の第一歩です。
また、家族自身もサポートに疲れてしまうことがあるため、カウンセリングや家族会に参加するのも有効です。
孤立せず専門家とつながることで、本人と家族の双方に安心が広がります。
早期のサポートは症状の悪化を防ぎ、回復の可能性を高めます。
Q5. 双極性障害は治るのですか?
双極性障害は完治する病気ではありませんが、適切な治療を続けることで安定した生活を送ることが可能です。
薬物療法で気分の波を抑え、心理療法や生活習慣の改善を組み合わせることで再発を防ぎやすくなります。
また、本人が病気を理解し、家族や職場の支援を得ることで長期的な安定を維持できます。
一度発症すると再発しやすい傾向がありますが、治療によって症状をコントロールし、社会生活を送ることは十分可能です。
「治らないから絶望」というよりも、「治療と支援で安定させられる病気」と捉えることが大切です。
正しい理解と継続的な支援が、本人の未来を大きく変えます。
「あるある」を正しく理解し、共感とサポートにつなげる

双極性障害あるあるとして語られる行動は、一見すると性格の一部や気分の問題に見えることがあります。
しかし、実際には脳の働きに関連する病気の症状であり、本人の努力だけで抑え込むことはできません。
誤解や偏見をなくし、病気として理解することが、本人の安心と回復への近道になります。
また、家族や周囲の共感とサポートがあれば、安定した生活を取り戻すことは十分可能です。
「あるある」を正しく理解し、寄り添う姿勢を持つことが、双極性障害と向き合う最も大切なステップです。